| ���� |
�R�[�h |
�}�^�^�C�g�� |
�����@ |
�����f
�ڔN�� |
�f�[�^ |
��
�� |
2270 |
�ƌv����̍��۔�r |
�H��͐�i���ł͂قړ����A�Z���A��Ô�Ȃǂō����Ƃɓ��� |
2001�N |
�e��SNA |
| 2272 |
�u�����h�u���̐��E�����E���۔�r |
�����炵�����A�s�[�����邽�߂̃u�����h�u�������E�I�ɍ��܂�X���B�n��ʂɂ̓u�����h�u���������Ƃ����������l�A�����Ƃ��Ⴂ���{�l�B |
2025�N |
Ipsos |
| 2272b |
�u������v��`�̍��۔�r |
�����ւ̕s�m�����������Ă��钆�A�u������v��`���e���Ŏ嗬�ɁB���Ƀ^�C�A���`�A�����A���[���b�p�ł̓t�����X�Ȃǂł��������X���������i���{�A�؍���h�C�c�A�C�^���A�͂����ł��Ȃ��j�B |
2025�N |
Ipsos |
| 2273 |
�R���i���s���̏���ω��F�������u�����������v�A�������u�O�o����v |
�}�X�N�ȂǕی���Õi��˗ށA��ނȂǁu�����������v���g�傷��ƂƂ��ɁA�O�H��A�����A�h����A�V����Ȃǁu�O�o����v������ |
2021�N |
�ƌv���� |
| 2275 |
��炵�͌������Ȃ��Ă��邩�H |
���[�}���V���b�N���ɕ�炵�̌��������s�[�N���L������A����}�������A�A�x�m�~�N�X����ʂ��Đ����͂��Ȃ�y�ɂȂ������ |
2019�N |
���{��s |
| 2276 |
��炵�����Z��̍��۔�r |
�]�܂����Z����̎嗬�F���{�E�I�Z�A�j�A�́u�x�O��ˌ��āv�A���Đ�i���́u�c�ɂ̈�ˌ��āv�A��āE�A�W�A�r�㍑�́u�s�s����ˌ��āv�A�쉢�E�A�W�A�V�����́u�s�s���}���V�����v |
2024�N |
Ipsos |
| 2276f |
�e���ŏd������Ă���s���Y�̓��� |
���E�I�ɏd������Ă���s���Y�̓����g�b�v3�́u���Y���l�v�A�u���n�v�A�u�����v�B�����ł́u��̍L���v�A���ł́u������ʃA�N�Z�X�v�A���Ăł́u�v���C�o�V�[�v���d�������B |
2024�N |
Ipsos |
| 2277 |
��v���ɂ�����Z���� |
���E�̏Z����g�b�v3�́A�����s���Y���i�A�����ƒ��A�������B�č��ł͍����ƒ��ƃz�[�����X���A�h�C�c�ł͍����ƒ��A�؍��ł͍����s���Y���i�A���{�ł͍����ŋ����ڗ������Z����B |
2024�N |
Ipsos |
| 2278 |
�����Z��䗦�̍��۔�r |
�v�w1�g���邢�͖�����1�l��1�����Ƃ����Œ��ȉ��̋����Z��ɂ��ē��{�͒Ꮚ���w�ł�2.8���Ɛ��E�̒��ł��Œ���N�ł���u�E�T�M�����v�Ƃ͌����Ȃ��B |
2020�N |
OECD |
| 2280 |
��v�ϋv������̐��ѕ��y������ |
�����{�̉ƒ�ɂ͓d�����i�A��p�ԁA�h�s���i�Ȃǂ����X�ƕ��y���Ă����B |
2007�N |
���t�{��������� |
| 2282 |
��v�ϋv������̕��ώg�p�N�� |
�ϋv������̕��ώg�p�N���͑ϋv���̌����i�Ƃ��Ă̐��n�x�̍��܂肩��A�T���āA�L�т�X�� |
2017�N |
���t�{��������� |
| 2283 |
�Z��̗����ۗL���E�g�C�������̐��� |
���x�������ɋ}���ɕ��y��������g�C���B1965�N�����͓���23��ł����ݎ�莮�g�C�����c���Ă����B |
2008�N |
�Z��E�y�n���v���� |
| 2283d |
�Ɛ��̐��� |
�傫�����������Ƃ�2018�N�ɂ�849���ˁA���̂����ʑ��Ȃ�2���I���p�łȂ��A�����ɂ킽���ĕs�݂ɂȂ��Ă���Ƃ�349���˂ɂ̂ڂ�B |
2018�N |
�Z��E�y�n���v���� |
| 2284 |
�@�B�̎��� |
�@�B�̎����̓o�b�e���[�̎�����1�`2�N�̃X�}�[�g�t�H������20�`25�N�̔�s�@�A�G���x�[�^�[�ɋy�� |
2017�N |
�����}�� |
| 2288 |
�����ӎ��̐��� |
�����ӎ�������҂̔䗦�͕s�ρB�u���̏�v�͊g��X���B�u���v�͏k���X���B |
2012�N |
���t�{���_���� |
| 2290 |
�����ӎ��̍��۔�r |
�������x���u���v�Ǝv���Ă���҂������͓̂��{�����ł͂Ȃ��B�u���v�Ɗ��������Ă��������Ȃ��u���v�̑����������^�̕n�����ł���B |
2000�N |
���E���l�ϒ��� |
| 2293 |
���w�ӎ�������N��ʊ����̐��� |
���w�ӎ�������҂́A�ߔN�A�N��ɂ�炸�����X���B����50��`60�オ�������A70�Έȏオ�ڗ��悤�ɂȂ����B |
2019�N |
���t�{���_���� |
| 2294 |
��\�I�Ȉӎ������Œǂ����n���ӎ��̐��� |
��\�I�Ȋe��ӎ��������猩�����A�����������A���邢�͕n���ƍl����l�̊����͌��葱���Ă��� |
2017�N |
���t�{���_�����A���{�l�̍����������ANHK�AJGSS�ق� |
| 2298 |
���R���Ԃ̉߂����� |
�R���i�̉e���ŊO�o���Ƃ��Ȃ��f��E�R���T�[�g�◷�s������A�x�{�A�e���r�EDVD��C���^�[�l�b�g�ESNS������ |
2022�N |
���t�{���_���� |
| 2300 |
���܂�u�H�����v�ւ̊S |
���W���[����H�����֍���̐����̗͓_�ɂ��Ă̍����ӎ����ω� |
2008�N |
���t�{���_���� |
| 2302 |
�ِ��W�̍��۔�r |
�ِ��Ƃ̌��یo�����Ȃ��҂̔䗦�����ɍ������{�̒j�� |
2005�N |
���t�{ |
| 2304 |
��D�⒆��ɑ���l�����̍��۔�r |
���Ɖ��Ăł́A��D�ɂ��撆��ɂ���A�����̎�̐���F�߂邩�ۂ��̓_�ł܂����������̈ӎ� |
2005�N |
���t�{ |
| 2306 |
�����������~���ɑ����ő�Ȃ��Ɓi�ӎ��̍��۔�r�j |
�u�݂��ɐ����v����Ԃł���̂͐��E���ʁB�u�����v��u�q�͂��������v���d��������A�u�ِ��Ƃ��Ă̖��͂̕ێ��v���d�����鉢�āB |
2005�N |
���t�{ |
| 2307 |
���������̕s���ɂ��Ă̍��۔�r |
�S�ʓI�Ɍ��������̕s�������������{�l�A�傫���č��l�B���ɁA�v�w�̌l�I�ȊW���S�z���ǂ����œ��Ă͑ΏƓI |
2015�N |
���t�{ |
| 2308 |
�����ɂ��Ă̈ӎ��̍��۔�r |
���́u�����Ǝq�ǂ���s���v�Ƃ��A���Ăł́A�u�����ƈ����s���v�Ƃ���X�����ڗ��� |
2005�N |
���t�{ |
| 2309 |
����������x�̍��۔�r |
������ւ̖����x�����E��Ⴂ���{�l�B�r�㍑����v��i���̕��������x���Ⴂ�X�������邪�A���{�l�͊؍��l�ƕ��т��̒��ł����فB |
2024�N |
Ipsos |
| 2310 |
�����X�^�C���̍��۔�r�i�������d���x�j |
�F�l�Ƃ̊O�o�͐��E���ʁA�Z�b�N�X���C�t�͉��ĂŗD�揇�ʂ������A�A�W�A�ł͒Ⴂ�B���{�̓����͐����d���B |
2001�N |
Durex�� |
| 2312 |
�i��ו��̖[���̔N������ |
50�Α�O���ɔN80����x�������ו��̖[���p�x��64�ɂ�30����x�܂Ō��� |
1959�N |
�g��r�F�i1999�j |
| 2314 |
���s���̊e����r |
�u���ꂽ�v���s���̔䗦�����������B��������������Z�b�N�X�̓A�W�A�r�㍑�y�у��V�A�ő����B |
2003�N |
Durex�� |
| 2318 |
���E�e���̃Z�b�N�X�p�x�Ɛ����������x |
�������̖����x�͕K�������Z�b�N�X�p�x�ɔ�Ⴙ���B���{�l�̕p�x��41�J�����ʼn��ʂ̔N45��A�����x�������������ƍʼn��ʁB |
2005�N |
Durex�� |
| 2318r |
���E�e���̃Z�b�N�X�p�x�Ɛ����������x�i��Q�Łj |
2006�N��26�J�������ł̓M���V����ʁA���{�ʼn��ʂ̃Z�b�N�X�p�x�B2011�N��37�J�������ł̓R�����r�A��ʁA�M���V��11�ʁA���{�͂�͂�ʼn��� |
2011�N |
Durex�ЁA�����V�� |
| 2319 |
���E�e���̃Z�b�N�X�p�x�Ɛ������� |
���ۓI�Ɍ���ƃZ�b�N�X�̕p�x�Ɛ������Ԃ͐��̑��֊W |
2006�N |
OECD�AEU�ADurex�� |
| 2320 |
�������Ԕz���̕ω��i1976�N�ȍ~�j |
�����𒆐S�ɓ��{�l�͂��̎l�����I�Ŗ��鎞�Ԃ�ɂ���ł��O���o���邫���R���Ԃ�搉̂���悤�ɕω� |
2006�N |
�Љ����{���� |
| 2321 |
�������Ԃ̑������猩���ݑ�[�N�E�e�����[�N�ɂ�鐶���ω� |
�ݑ�[�N�i�e�����[�N�j�Ŏ�҂͐����s�������A�q��Đ���͈玙���A�����N�͐����E�H���� |
2021�N |
�Љ����{���� |
| 2321d |
����ʼn߂������Ԃ̑����i�N��ʁj |
�R���i���Ŋw�Z��E��Ȃǂւ̊O�o������A����ʼn߂������Ԃ����������{�l�B�������A�R���i���ł��O�o�����܂茸��Ȃ���������ҁB |
2021�N |
�Љ����{���� |
| 2322 |
�������Ԕz���̊e����r |
�j���Ƃ����{�l�̎d�����Ԃ͒����A�܂������͐������Ԃ��Z���A�j���͉Ǝ����ԁA�玙���Ԃ��Z���̂����� |
2001�N |
�Љ����{�����AEU���� |
| 2323 |
�Ǝ����S�̍��۔�r |
�����A����A�|���Ɋւ���Ȃ̕��S�����͓��{�̏ꍇ8�`9���Ɛ��E�̒��ł��ł������B�č����ɓI�ʒu�B |
2002�N |
ISSP |
| 2324 |
���R���Ԃ̒j���i���ɂ��Ă̍��۔�r |
�j���肪�l�̎��R��搉̂��Ă��鍑�̕M���̓C�^���A�B�k���̍��͎��R���Ԃɂ����Ă��j�������B���{�͕����ɋ߂��B |
2006�N |
OECD |
| 2325 |
�����E�H���E�g�̉��̗p���̐������� |
�Z���Ȃ鐇�����ԁA�����Ȃ邨�����E�����Ȃǂ̐g�̉��̗p���̎��ԁi���ɏ����j |
2006�N |
�Љ����{���� |
| 2327 |
���{�l�̍D���ȗ]�ɂ̉߂����������L���O |
�u�e���r�v�A�u����Q�v�A�u�����������̂�H�ׂɁv���D���ȗ]�ɂ̉߂������x�X�g�R |
2007�N |
�m�g�j�������������� |
| 2328 |
��b�E���ۂ������Ă��Ă�����{�l |
�����̕����A�܂��Ⴂ�w�⍂��҂̕�����b�E���ۂ��������A�ߔN�A���{�l�͑S�ʓI�ɉ�b�E���ۂ������Ă��Ă��� |
2005�N |
NHK�����������Ԓ��� |
| 2329 |
����Ȃ����{�l�i�������Ԃ̍��۔�r�j |
����҂������ɂ�������炸�ł��������Ԃ��Z�����{�l�B�ł��悭����̂̓t�����X�l |
2006�N |
OECD |
| 2329a |
����Ȃ����{�l�Q�i�������Ԃ̃A�W�A�����m������r�j |
�@�悭���钆���l�A����Ȃ����{�l�A�A��������Ȃ����{�l�A�C���h�l�A�B���ǂ����ł͓����x�̐������� |
2008�N |
OECD |
| 2329b |
������ꍑ�����L���O�i�g�̉��̗p�����Ԃ̍��۔�r�j |
20�Α�𒆐S�ɏ������������Ɏ��Ԃ�������_�ł͓��{�͐��E��B�؍��A�p�āA�I�����_������ɑ��� |
1990�N |
�m�g�j�������������� |
| 2329d |
����ʂ�����ꎞ�Ԃ̕ω��i�����j |
�g�̉��̗p�����Ԃ͊e����Ƃ������ԉ��B�L�т̒��S�͔Ӎ���ӎY����20�ォ��30��A����������30�ォ��40��փV�t�g |
2011�N |
�Љ����{���� |
| 2330 |
�q�ǂ��̐Q�鎞�ԁi�A�Q�����j |
���{�̎q�ǂ���47������10���ȍ~�A�Q�ƐQ��̂��x���B |
2004�N |
�����V�� |
| 2332 |
�����𒆐S�ɎႢ����قǐ[���Ȑ����̔Y�� |
�Q�s���Ȃǐ����̔Y�݂͎Ⴂ����قǁA���ɏ����Ő[�� |
2015�N |
�������N�E�h�{���� |
| 2332a |
�ꐶ�̊Ԃɑ傫���ڂ�ς�鏗���̐����̑j�Q���� |
�����̑j�Q�����F�j�̏ꍇ��50��܂Łu�d���v�A60��ȏ�́u���N�v�A���̏ꍇ�́u�X�}�z�v���u�玙�v���u�Ǝ��v���u�d���v���u���N�v�ƈꐶ�̊Ԃɑ傫���V�t�g |
2015�N |
�������N�E�h�{���� |
| 2334 |
�c���̗V�сE���m�Â��� |
�c���̗V�т̃g�b�v�R�́u���G�����A�܂莆�A�ʂ�G�A�S�y�V�сv�A�u�܂܂��ƁA�������V�сv�A�u�r�f�I�EDVD������v�B���m�Â��ƃg�b�v�́u���j��̑������A�X�|�[�c�N���u�v |
2013�N |
�m�g�j�������������� |
| 2337 |
�e�̋A��Ԃ̍��۔�r |
���E�̏��s�s�̒��ł���9���`11���ƋA��Ԃ��x���_�Ŗڗ����Ă��铌���̕��e�B�X�E�F�[�f����k���E��C�ł͗[��5���`6���ɕ��e���A���B |
2006�N |
�j�������Q�攒�� |
| 2340 |
��s�s���ɂ�����ʋE�ʊw���v���Ԃ̕ω� |
�ʋΒʊw���Ԃ̓o�u���o�ϊ��ɑ傫�������������A����ȍ~�A�����Ȃ����Z�k���X���ƂȂ����B���ɒʊw�͑�w�̓s�S��A�ȂǂŒZ�k���ڗ��B |
2005�N |
���y��ʏ� |
| 2350 |
�H��x�o�̐��ځi���H�A���H�A�O�H�j |
1985�N�ȍ~�̂P���ѓ����茎���ϐH��x�o�̓����́A���H�i�����H�i�j�������X���A���H�������X���A�ꎞ�L�т��O�H�͒���B�G���Q���W����95�N����23���ʼn����~�܂�B |
2003�N |
�ƌv���� |
| 2355 |
�G���Q���W���̓�߂������� |
�吳�����璷���I�ɒቺ���Ă����G���Q���W���́A���ʐM�v���������������ʂŃ��O�������A2005�N���ɏ㏸�ɓ]�����i�}�^2350���Ɨ��A���e�lj��j |
2016�N |
�ƌv���� |
| 2365 |
�Ɛg���v�w���A�܂���e�Ɠ������Ă��邩�ɂ���ĈقȂ�j���̉Ǝ��p�x |
�����Ɛg�ЂƂ��炵�ł������̕����j�����Ǝ����悭�s���B��������Ε��S�ɂ�鍇�����ʼnƎ����S������Ə������l���Ă����҂͂��� |
2008�N |
����~��i2016�j |
| 2370 |
���{�l�̍s���E�j�����y�эs���H |
���{�l�ɂƂ��Đ����A��݂����A�y�т�����������G�ς͓��ʂ̑��݁B����A�O������`������N���X�}�X��N���X�}�X�P�[�L�̒蒅���������B |
2006�N |
�m�g�j |
| 2375 |
���{�l�̐H��̕ϑJ |
���{�l�̐H��͖��X�V�i�͂����j���珺�a��O���`���x�������̃`���u��A�����Ă���ȍ~�̃e�[�u���̎���ւƕϑJ |
1984�N |
�Ζђ��� |
| 2378 |
�����E�y���ʐH�����ԁE�������Ԃ̍��۔�r |
�H�����ԁA�������Ԃɂ��āA���{�ł͓��j���ł��������A���Ăł́A�ނ���y�j���̕��������A���j���͍ŒZ�̌X�� |
1990�N |
NHK�����������Ԓ����ق� |
| 2380 |
���{�l�̍D���ȗj���E�D���Ȏ��� |
�ł��D���ȗj���́u�y�j���v�A�ł��D���Ȏ��ԑт͖��6������12���܂� |
2007�N |
�m�g�j�������������� |
| 2382 |
�����̎���ω� |
���S�̏ꏊ�́u�����a�@�ցv�A���V�̏ꏊ�́u����瑒�Տ�ցv�A�������@�́A�u�y������Α��ցv�A��̖��́u�l������Ɩ��ցv�Ƒ傫���ω� |
2012�N |
�l�����ԓ��v�A���c���ҁi2012�j |
| 2383 |
���V����`�����l |
�ߏ����Ђ̓�������`���A�݂�ȂŒ����Ă������V�����܂�V�Ђ��܂����̉Ƒ��̒Ǔ��V���ɕω� |
2010�N |
���㑒�V���� |
| 2385 |
���{�l�́h�Ɓh�ӎ��̕ω� |
���̂Ȃ���̂Ȃ��{�q�Ɂu�Ɓv���p�����邱�Ƃ͖��Ӗ��Ƃ����ӎ����x�z�I�ƂȂ�A�u�Ƒ��v�̏d���Ƃ͗����Ɂu�Ɓv�Ƃ����g�g�݂͑��S�̊�@�� |
2008�N |
���{�l�̍��������� |
| 2387 |
�D���Ȃ��炵�����l�̂��߂��i�N��ʃ��[�����f���̏��Łj |
��҂͎����̍D���ȕ�炵�u���A�����N�͐l�̂��߂̕�炵�u���������̂��A�o�������݂ɋ߂Â��A���܂́A�N��傫���k�� |
2013�N |
���{�l�̍��������� |
| 2388 |
���{�l�̂��炵���ԓx�̒������� |
��㒼��́u�����������v����A�u������v�A�����ĉ���������R�ȁu�̂��v�����߂�����֓��{�l�̑ԓx�͕ω� |
2008�N |
���{�l�̍��������� |
| 2390 |
�j�x���ǂ������d������X�� |
�������Ǝv�����Ƃ������ʂ����Ƃ͔������A���̂��������ɉ��������f���d����悤�ɓ��{�l�̑ԓx�������I�ɕω� |
2008�N |
���{�l�̍��������� |
| 2391 |
���Ȕ��f�A��������AKY�̂�����ɏ]���ׂ����i���۔�r�j |
��������ƈقȂ��Ă��������Ǝv���Ύ����������ʂ��i���Ȕ��f�d���j�Ƃ����l�������ەW���B���{�͎��Ȕ��f�ł���������ł��Ȃ��A�ꍇ�ɂ��iKY�d���j�������h |
1993�N |
���v���������� |
| 2392 |
�u�`�������W�v�h���A����Ƃ��u���������v�h�� |
�N����d�˂�Ɓu���������v�h�������Ȃ�B���n��ł͎�҂́u���������v�h�A50�Έȏ�́u�`�������W�v�h�̑������ڗ��� |
2013�N |
���{�l�̍��������� |
| 2395 |
���{�l�Ƃ��Ă̎��M�̋O�� |
�I���A���m�l������Ă���Ǝv���Ă������{�l�́A���x�������Ɏ��M��[�߁A�o�u���O��1980�N��ɂ͔����ȏオ���m�l���D��Ă���ƍl�����B���̌㎩�M�ߏ�͂����ӂ���A�D��Ȃ��̈ӌ������� |
2008�N |
���{�l�̍����������A�m�g�j�������������� |
| 2397 |
�q�ǂ��̍K���A��l�̍K�� |
�q�ǂ��̍K���x�̏㏸�X���Ƃ͑ΏƓI�ɑ�l�̍K���x�͒Ⴂ�܂ܐ��� |
2012�N |
�m�g�j�������������� |
| 2398 |
�ߐH�Z�[���x�i�n���x�̋t�j�̐��� |
�ߐH�Z�ȂǕ��������ւ̏[���x��1990�N��ɂ����㏸�A���̌�A�����B��ґw�̏[���x�̏㏸���ڗ��B�i����n���̐[�����ɂ͋^�╄�����B |
2008�N |
�m�g�j�������������� |
| 2400 |
�����̌��㊴�̐��� |
���������サ�Ă��邩�̈ӎ��́A���x�o�ϐ������Ƃ���ȍ~�̖ڗ������Ⴂ�A�܂��ߔN�u���������v���g��i���߂͏k���j |
2006�N |
���t�{���_���� |
| 2403 |
�����E�c���E���̃����L���O |
�����ɂ���ď��ʂ͈قȂ邪�����A��A�����A�c���A�n�ӁA�ɓ��A�����A�R�{�A���сA�֓������{�l�̖��O�̃x�X�g�e�� |
1998�N |
�������i1998�j |
| 2405 |
���̎q�̖��O�x�X�g�R�̐��ځi1912�N�ȍ~�j |
�ق�10�N���ƂɎ��㐸�_��\�����邩�̂悤�Ɂu���q�v�u���q�v�u�a�q�v�u�b�q�v�u�R���q�v�u�z�q�E�q�q�v�u���v�u����v�̎���ƈڂ肩��� |
2006�N |
�������c���� |
| 2405u |
�č��̏��̎q�̖��O�x�X�g�R�̐��ځi1910�N�ȍ~�j |
���Ă͓��{�̘a�q��K�q�̂悤�Ƀ��A���[����_�����̎q�̖��O�Ƃ��đ����������A���ł̓C�U�x���A�\�t�B�A�A�G�}�A�I�����B�A�Ƃ������ȑO�͂��܂�g���Ȃ��������O���l�C�ɁB |
2022�N |
�č��Љ�ۏ�� |
| 2406 |
��������̏����Ƃ��Đl���A�e�p�A�o�ϗ́A�Ǝ����S�Ȃǂ̉����d�����邩�H |
�j���Ƃ��܂��l���D�悾���A�ِ��Ɣ�r����Ə����͑���̊w���A�E�ƁA�o�ϗ͂��A�j���͑���̗e�p�����d���B�ŋ߂͒j���������̌o�ϗ͂��A�����͉Ǝ��ӗ~�ɉ����j���̗e�p���܂��܂��d������X���B |
2021�N |
�o��������{�����i�Ɛg�Ғ����j |
| 2407 |
�Ɛg�j���̌����ӎv�ƈِ��Ƃ̌��ۏ� |
�唼�͌���������肾���A�����ӎv�̂Ȃ��Ɛg�������i���ɒj�j�B���ۑ���Ȃ��̓Ɛg�j��5���ȏ�A�Ɛg����45���Ƒ����X���B |
2005�N |
�o��������{�����i�Ɛg�Ғ����j |
| 2408 |
��Ǝ�w���L�����A�E�[�}�����`�j���̊��҂Ə����̗\�� |
2�����Ĕn�ԂłȂ��Ɖƌv�������Ȃ��Ƃ̌������炩�A��Ǝ�w���҂̒j�����}�����A��Ǝ�w�\��̏����Ɣ䗦���߂Â��B |
2005�N |
�o��������{�����i�Ɛg�Ғ����j |
| 2409 |
������q��ĂƏ����̐E�Ƃɂ��Ă̈ӎ� |
�q�ǂ������Ă��E�Ƃ𑱂�������悢�Ƃ���p���A�J�u������т��đ������Ă������A�ŋ߁A���] |
2014�N |
���t�{���_���� |
| 2410 |
�u�v�͊O�œ����A�Ȃ͉ƒ�����v�Ƃ����ӎ��̕ω� |
�^���A�����t�]�B�s����蒬�����Ŕ����傫������B |
2004�N |
���t�{���_���� |
| 2411 |
�u�v�͊O�œ����A�Ȃ͉ƒ�����v�Ƃ����ӎ��̍��۔�r |
40�J�����^������������̂�9�J���Ə����h�B�^���̊����Ŋ؍���10�ʁA���{��14�ʂƂ��������l�����������B |
2008�N |
ISSP |
| 2412 |
������E��E�e�����E�n��Ƃ̂������ƍ��܂�Ƒ��̑�� |
�Ƒ�����ԑ���Ƃ���l�����������Ȃ��Ă��Ă��邪�A����́A�E���e�����A�����Ēn��i�ߏ��j�Ƃ̂������������Ă��Ă���̂Ƌt��� |
2003�N |
������������ |
| 2413 |
�Ƒ���e�ʁE�E��E�ߏ��̐l���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̐��� |
������悭�b�����邩�ŃR�~���j�P�[�V�����̒��x�f����ƁA�E��̐l�������āA2000�N��ɓ����ăR�~���j�P�[�V���������܂�X�� |
2010�N |
�m�g�j�������������� |
| 2414 |
�e�Ƃ̓����E�ߋ��̐��� |
���铯���A������ߋ� |
2007�N |
����������b�����A���������I�D�x���� |
| 2420 |
�Ɛg�j���̐e�Ƃ̓����䗦 |
�S�̂Ƃ��Ă͂قډ����̓������i�j7���A��8���j�A�������A10�㏗���͂ЂƂ��炵�A�����N��̓Ɛg�����͓����ւ�180�x�̕ω� |
2005�N |
�o��������{�����i�Ɛg�Ғ����j |
| 2421 |
�e�Ɠ����̖����҂̑ΐl���䐄�� |
�e�Ɠ����̖����҂͑��������A2010�N�ɂ͎�N�w�ł͒j��49.4���A����45.6���ɒB���A�s�N�w�ł����ꂼ��19.9���A12.2���ɒB���Ă���B |
2010�N |
�J���͒����i���ʏW�v�j |
| 2422 |
�e�Ƃ̓����䗦�̍��۔�r |
���āi���ɃI�����_�A�k���j�ŒႭ�A�A�W�A�A�A�t���J�A����Ăō����e�Ƃ̓����䗦�B���{�͂�⍂�����ɑ����B |
2000�N |
���E���l�ϒ��� |
| 2424 |
�Ȃ͕v�̐e����D�悷�ׂ����i���{�E�؍��E��p�E�����j |
���{�Ɗ؍��ł͕v�̐e���D��͏��Ȃ��A��p�⒆���ł͔�r�I�����B |
2006�N |
EASS |
| 2427 |
�ƒ�͌e����B��̏ꏊ���i���۔�r�j |
�ƒ���e����B��̏ꏊ�ƍl����҂̔䗦�ɂ��āA���{�l�͉��ď�����傫�������Ă��邪�A�A�W�A�����̒��ł͒����炢�̈ʒu |
2008�N |
7�������۔�r�����A�����m���l�ύ��۔�r���� |
| 2428 |
�v�w�͈�ԑ�ȑ��k���肩�i���۔�r�j |
�v�w��Y�ݎ��E���k���̑��k����Ƃ��銄���͓��{�l����6���Ƒ��̍���4�����傫�������Ă���A�v�w�W�ٖ̋������ڗ����Ă���B |
2008�N |
�����m���l�ύ��۔�r���� |
| 2429 |
�������Ă��Ȃ��̂ɉƑ����Ǝv���悤�ɂȂ����̂͂���قǑO����ł͂Ȃ� |
�����O�܂ʼnƑ��͈̔͂͐e�ł����������������������A�ߔN�͐e���͒N�ł��������Ă��Ȃ��Ƃ��Ƒ��ƍl������悤�ɂȂ�A���̈Ӗ��ł́A�Ɛ��x����E�p������ |
2013�N |
�S���ƒ듮������ |
| 2430 |
��ɑ��銴��̍������E������ |
��3�ɂ��āA�č��̔��l�͕�e�����ނ������݂��Ƃ��銄���������A���l�͕�e�ɑ��Đe���݂������銄�����傫���̂ƑΏƓI�B���{�ŕč����l�Ǝ��Ă���͍̂��m |
1967�N |
�c���]�F�j�i1971�j |
| 2438 |
�q�ǂ��̂���ƒ�̐����̋ꂵ�� |
�������������̉ƒ�Ŏq�ǂ�������̂Ƃ��Ȃ��̂Ƃł͐����̋ꂵ�������Ȃ����Ă���A���q���̊�{�v���ƂȂ��Ă���B |
2001�N |
����������b���� |
| 2440 |
�q��Ă̐h���̓��e�i���q���̔w�i�j |
�����̋�����q��Ē��̔�p�Ȃnjo�ϓI�ȑ��ʂ��傫���A�����Ɏ��R�Ȏ��Ԃ����ĂȂ��Ȃǎ��Ȏ����ւ̖W���ӎ� |
2008�N |
���t�{���_���� |
| 2441 |
�c������E�ۈ�̍��۔�r |
�c������E�ۈ�T�[�r�X���ǂꂾ���[�����Ă��邩�́A�c���N��قǍ����Ƃɑ傫�ȍ��B0�`2�Ύ��̕ۈ痦�͓��{�̏ꍇ30.6����OECD���ψȉ� |
2014�N |
OECD |
| 2442 |
�ۈ��p�̍��۔�r |
���{��2�`3�Ύ��̕ۈ畉�S�i�ōT���A�����蓖�Ȃǂ�����������p�j�̍�����29�J����8�� |
2004�N |
OECD |
| 2445 |
�v�w�̏����͂ǂ��炪�����H�i���۔�r�j |
���{�͕v�̏������Ȃ̏����������Ă���v�w�̊�����88���Ɛ��E�ꑽ���B���{�Ɏ����œ������������̂̓��L�V�R�A�I�[�X�g���A�A�p���A�h�C�c |
2012�N |
ISSP |
| 2450 |
�j�������҂̔N���Ɩ��������̊��҂̃M���b�v�i���q���v���j |
�����Ȃ���������E�q��Ĕ�p�ɑ��Ď�҂̉҂��͏��Ȃ��Ȃ�A�������̏㏸�⏭�q���̐i�W�ɂނ��т��Ă� |
2003�N |
�R�c���O |
| 2451 |
30�Α�j���̔N���ʍ����E���ۏ� |
�N��300���~�����Ɍ������Ă��邩�ǂ����A�����Ƃ̌��ۂ̔䗦�Ɍ����ȍ� |
2010�N |
���t�{ |
| 2452 |
�N���ɂ�錋���\�� |
�j�̏ꍇ�A�N����200���~�������Ɗi�i�Ɍ����\���͒Ⴍ�Ȃ�B���̏ꍇ�������X�������j�قǂł͂Ȃ��B |
2006�N |
�����J���� |
| 2453 |
�v�͍Ȃ��N��ł���ׂ����i���A�W�A���ؑ䒆��r�j |
�؍��A��p�A�����ł͕v�͍Ȃ��N��ł���ׂ��Ƃ̈ӌ������������{�͂������Ȃ��ӌ������� |
2006�N |
EASS |
| 2454 |
�o���[�̑����i�v�w�N��̐��ځj |
1970�N����2009�N�ɂ����o���[10������24���ցB�܂��ł������N��́u�v3�ΔN��v����u�v�w���N��v�� |
2009�N |
�l�����ԓ��v |
| 2455 |
���������j���̏o��̂��������i�����������A���������j�̕ω� |
����������������A�ŋ߂́A�E���d����ʂ����o������� |
2002�N |
�Љ�ۏ�E�l����茤���� |
| 2456 |
��������ɂ��Ă̐e�̈ӌ��̉e���i���{�E�؍��E��p�E�����j |
�؍��ł͌�����������߂�Ƃ��ɐe�̉e�����傫���B���䒆�͂���قLjႢ���Ȃ��B |
2006�N |
EASS |
| 2458 |
���O���̉ۂɂ��� |
���O���ɂ��ĈȑO�́u�s�v�������h�ł��������A���݂́u�������Ήv���ő��ɕω��B�o�u�����ɂ́u�������ʼnv������ |
2008�N |
�m�g�j�������������� |
| 2459 |
���O���͐����i���۔�r�j |
���������قǂł͂Ȃ������{�����O���ɂ͊��e�ł���A�ł��e�̃C�X���������A���ɔe�Ȓ����E�؍��A�����ĉ��Ă̒��ł͊��e�����Ⴂ�č��E���V�A�������Ƃ��銄�������� |
2013�N |
Pew Research Center |
| 2460 |
��҂̃Z�b�N�X�̌����E�f�[�g�o�����̐��� |
����30�N�ŃZ�b�N�X�̌������}�������i�j�q���Z����10.2������26.6���ցA���q���Z����5.5������30.3���ցj�B�ߔN�́A�j�q�͉����A���q�͑��L�Ƃ��������B |
2005�N |
���{�����狦�� |
| 2462 |
�����҂̃Z�b�N�X�̌����̐��� |
�����o�����Ɋւ���j�����̑傫�ȏk���A�y��2002�N�����Ƃ����e�N��w�ɂ�����㏸����ቺ�ւ̓]�������� |
2005�N |
�Љ�ۏ�E�l����茤���� |
| 2465 |
���H�n�j�q�������Ă���H�i�j���N��ʂ̐��I�S�x�j |
20�Α�O���܂ł̐N�j�q�̃Z�b�N�X���S�E����������2�N�Ԃ�2�{�ɑ��� |
2010�N |
���{�Ƒ��v�拦�� |
| 2466 |
���H�j�q�͂����댻�ꂽ�� |
2000�N����ɑ��H�j�q�����{�ɏo���B�������A�ِ��Ԍ�V�u���̒j�D�ʂ��j�����������D�ʁi���H���q�j�ɕω��B |
2014�N |
���{���Y���{�� |
| 2467 |
���H���q�͂����댻�ꂽ�� |
�ِ��W�ɑ��鏗���̊S���}�ɍ��܂�A�o���[����C�ɔ{�������̂͏��a���I��蕽���ɓ�����1990�N�� |
2018�N |
�l�����ԓ��v�A���{���Y���{�� |
| 2470 |
�y�������Ԃ��������Ă���̂͒N�� |
�Ⴂ����̕����N�����A�܂��e�N��̏����̕����j���y�������Ԃ̒��������� |
2008�N |
�m�g�j�������������� |
| 2472 |
�K���x�̒j�����i���ڂƍ��۔�r�j |
�����̕����j�����K���x�̍�����Ԃ������B���{�����̍K���x�̑Βj�����ߓx�͐��E�����L���O�Ńg�b�v |
2011�N |
���E���l�ϒ����AISSP |
| 2473 |
���ǂ̂Ƃ���K���ɕ�炵�Ă���̂͒j�������i���۔�r�j |
�ǂ������iBetter Life�j�Ƃ����ϓ_����́A�j�D�ʁA���邢�͒j�������ƍl���鍑�����قƂ�ǂ̒��œ��{�Ɗ؍������͏��D�ʂƂ����ӌ������� |
2010�N |
Pew Global Attitudes Project |
| 2475 |
���܂�ς��Ƃ�����j������������������ |
�j�ɐ��܂ꂽ���ƍl����j�������ς�炸�������߂�Ȃ������͂��ĂƈقȂ菗�ɐ��܂�ς�肽���ƍl����҂������h�ɁB���̕����y�����l���𑗂��ƍl���Ă��鏗�������Ⴂ�����Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B |
2008�N |
���{�l�̍��������� |
| 2476 |
���܂�ς��Ƃ�����j�������������������i���۔�r�j |
�����́u���ɐ��܂�ς�肽���v�䗦�͓��{�l�ł͕č��l�Ɠ����悤�ɍ����A�����l�E�؍��l�ł͂Ȃ��Ⴂ�B |
2008�N |
�����m���l�ύ��۔�r���� |
| 2477 |
�~�����̂͒j�̎q�A���̎q�H |
���̎q��~�����Ƃ��鏗�����}���������ߑS�̂Ƃ��Ă��j�̎q��菗�̎q��~����䗦������Ɏ����Ă��� |
2008�N |
���{�l�̍��������� |
| 2478 |
�]�܂����q�ǂ��̒j���\�� |
�o�u�������͂���Œj����菗���̕����]�܂��p�^�[���ɑ傫���ω��B�ŋ߂̓o�����X�u������ |
2015�N |
�o��������{�����i�v�w�����j |
| 2480 |
�X�J�[�g���p���̐��� |
�X�J�[�g�h�͑����h���班���h�ւƑ傫���ω��B1995�N�ɃX�J�[�g���p�Ɣp�Ƃ��t�]�B |
2007�N |
WEB�A�N���X��_�ϑ� |
| 2482 |
�j�炵���E���炵���Ɋւ���ӎ��̍��۔�r |
���{�̍��Z���A���ɏ��q�����́A���炵���A�j�炵���ւ̈ӎ����Ⴂ�B |
2003�N |
���{���N������ |
| 2484 |
�����I�Ȋ���D�ނ̂͂ǂ�ȍ��� |
�����I�ȃt�F�~�j������ł��D���Ȃ͓̂��{�l�A�j���I�Ȋ���ł��D���Ȃ̂̓l�p�[���l�B���̌��N�x�ɂقڔ�� |
2014�N |
Marcinkowska et al�i2014�j |
| 2485 |
���e���`�s��̍��ʃ����L���O |
���e��Î{�p��������݂đ������ł͕č����g�b�v�A�l��������ł͊؍����g�b�v |
2009�N |
��q�M�j�i2010�j |
| 2488 |
�y�b�g�̈��D���E���痦�i���ڂƒj���N��E�Z��ʊ����j |
�y�b�g���痦��3����Ő��ځB�y�b�g���D���Ȃ͎̂Ⴂ���ゾ�����ۂɎ����Ă���̂�40�`50�オ�����B |
2003�N |
���t�{���_���� |
| 2500 |
����y�b�g��ނ̐��� |
�y�b�g��ނ́A���̑����A���̌������ڗ��� |
2003�N |
���t�{���_���� |
| 2510 |
�W���Z��ɂ�����y�b�g����̐���ɂ��Ă̈ӌ��̐��� |
�}���V�����ł��y�b�g���F������ |
2003�N |
���t�{���_���� |
| 2520 |
�y�킪����ƒ�䗦�̍��۔�r�iPISA�����j |
�M�^�[��s�A�m�ȂNJy�킪����ƒ�䗦���ł������̂͊؍���76.6���ł���A�m���E�F�[��73.0��������Ɏ����ł���B���{��66.1���Ƃ܂��������B�k���������Ǝ������ō����X���B |
2022�N |
OECD |
| 2521 |
���p�i������ƒ�䗦�̍��۔�r�iPISA�����j |
�G��⒤���Ȃǔ��p�i�̂���ƒ�͓��{�̏ꍇ37.8����OECD�����ōŒ�B�ł��䗦�������̂̓A�C�X�����h��91.4�ł���A�f���}�[�N��88.8���ł���Ɏ����B |
2022�N |
OECD |
| 2600 |
���{�l���ł��D���Ȃ��́F�Ԃ͍��A�R�͕x�m�R�A�����͂��� |
���{�l���ł��D���Ȃ��̂ւ̉��͊T���Ēቺ���Ă���A�F���D���Ȃ��̂�����قLj�v���Ȃ������ɕω����Ă���Ƃ����悤 |
2007�N |
�m�g�j�������������� |
| 2610 |
��i�a���j���̍d�x |
���ꂢ�A�d���A�߂��炵������̂R�v�f�B�ł��d���_�C�������h�A�����ɍd�����r�[�A�T�t�@�C�A�B |
2008�N |
�����V�� |
| 2640 |
���A���{�̎Љ�ɑ傫�ȉe����^�����o���� |
3�܂ł̕������ʂ̏�ʂ͇@�����{��k�ЁE������ꌴ�����́i55���j�A�A�o�u���o�ςƂ��̕���i41���j�A�B���x�o�ϐ����i40���j�̏� |
2014�N |
�m�g�j�������������� |
| 2642 |
�����ɋN������ۓI�ȏo���������L���O |
�ő�̏o�����͓����{��k�ЁE������1�������́i'11�j�A����ɒn���S�T���������i'95�j�A�č����������e���i'01�j�A��_��k�Ёi'95�j������ |
2018�N |
�����V�� |
| 2650 |
���m�N���̐��E����J���[�̐��E�ցi�X�i�b�v�ʐ^�ƃe���r�j |
1970�N��O���A�X�i�b�v�ʐ^�A�����ăe���r�Ɖ�X�̎��ӂ̓J���[�̐��E�ɕω� |
1990�N |
�x�䌛��Y�i2005�j�A��������� |
| 2655 |
�x���ƂȂ�j�Փ��̕ϑJ |
�����̋x���́A�������ɁA�ߋ�i�G�߂̐ߖځj����V�c�̏j�Փ��i�����̍Փ����܂ށj�ցA�����Đ��A�����̎�v�������p���Ȃ��獑���I�j���������n�C�u���b�h�^�ƂȂ��đ������Ă��� |
2009�N |
�x�䌛��Y�i2013�j |
| 2660 |
���w���j�q�̔��^�̕ω��i���m�������s�n���j |
1960�N��Ɏl���̔_���ł����w�������̓��̓C�K�O�������璷���ւƈ�C�ɕω� |
1967�N |
�c���]�F�j�i1998�j |
| 2670 |
���đ��݂����L���f�B�X�R |
�L���f�B�X�R�͐ԍ�E�V�h�������Ŗ��z�E�R�E�Z�{�A�����ŃE�H�[�^�[�t�����g�̑q�ɊX�ɓW�J�B�o�u�����̏ے��I���݂������ʼnY�̃W�����A�i�����B |
2006�N |
�����V�� |
| 2680 |
�悭�V�ԃQ�[���̍��۔�r |
���Ăł̓g�����v��{�[�h�Q�[����������Ȃ̂ɑ��ē��{�ł̓R���s���[�^�Q�[����M�����u���i�p�`���R�j�������� |
2007�N |
ISSP |
| 2681 |
�M�����u���D���̍��� |
�ł��悭�V�ԃQ�[���Ƃ��āu�M�����u���v���������͓̂��{�l��7.8���i���E34������7�ʁj |
2007�N |
ISSP |
| 2682 |
�M�����u���ˑ��ǂ��^����l�̊��� |
���U��3.6���A�ߋ�1�N��0.8�����M�����u���ˑ��ǂ̋^���B�C�O�Ɣ�r���Ă����� |
2017�N |
�����J���� |
| 2683 |
�M�����u���͋�����邩�i���۔�r�j |
�M�����u�����u�����I�ɋ�����Ȃ��v�Ƃ�����{�l��31���Ɛ��E40�J���̒��ŕ��p�ĂȂǂɎ�����6�Ԗڂɏ��Ȃ��B�t�Ɂu�����I�ɋ������v�͐��E1����38���B�M�����u���Ɋ��e�ȓ��{�l |
2013�N |
Pew Research Center |
| 2700 |
�P�g���C�Ґ��̐��� |
�P�g���C�҂�1990�N��}�g��A�ߔN�������� |
2001�N |
����������b���� |
| 2703 |
�M���x�̍����E�ƁA�Ⴂ�E�Ɓi���۔�r�j |
�M���x�������͈̂�t��Ȋw�ҁA�r�㍑�ŋ��t�A�p�ĂŃ��X�g�������d�B�e���ŐM���x���Ⴂ�̂͐����ƈ�ʁA��i���ł�SNS�̃C���t���G���T�[��L���S�������̐M���x���Ⴂ�B |
2024�N |
Ipsos |
| 2705 |
�����䗦�̍����E�ƁA�Ⴂ�E�Ɓi���E���ς���ѓ��{�Ɛ��E�̔�r�j |
�P�A�E�E����E�E���|�E�Ȃǂ͏����������A���O�E�E�^�]�E�E�ۈ��E�Ȃǂ͒j���������̂����E�I�X���B���E�Ɣ�ׂē��{�̓P�A�E�E����E�̏����䗦�͂���قǍ����Ȃ��A�o�������E�A�Όl�T�[�r�X�E�ł͍����B |
2023�N |
OECD�AILO |
| 2710 |
�����䗦�̐��� |
�����w�Z�����͔������z���A����䗦��15�����B�����H��J���҂�3���܂Œቺ�B |
2007�N |
�e�펑�� |
| 2720 |
���{�l�̈ꐶ�̊e�X�e�[�W�̔Y�݂��� |
�Y�݂��Ƃ͔N��ɂ���ĕω��B���C���̊S���͎Ⴂ�Ƃ��͊w�Ƃ�i�w�A���l����Ǝd���A�����A�q��āA�ƌv�A�����Ē����N����͕a�C���� |
2013�N |
����������b���� |
��
��
��
��
�^
��
��
��
�� |
2740 |
���ƎҐ��E���E�Ґ��̐��ځi�����A�N���j |
1998�N�Ɏ��ƎҐ��̋}���ƂƂ��ɒ����N�𒆐S�Ɏ��E�Ґ����}���A2003�N�ɂ͎��ƎҐ��͑Q���Ȃ��玩�E�Ґ���20�`40�Α�𒆐S�ɋ}�����A5�N�Ԃ�Ɏj��ő����X�V |
2007�N |
�J���͒����A�l�����ԓ��v |
| 2740-2 |
�E�ƕʎ��E�Ґ� |
�x�@�����ł͘A��10�N���E��3���l���B�E�ƕ��ނł͔N���E�ٗp�ی��������҂��ł������A��w�A���Ǝ҂������B |
2007�N |
�x�@�� |
| 2747 |
���E��i�ʎ��E�Ґ��̐��� |
�R���̂Q�͎�݂莩�E�ł���A�K�X���E�A��э~��A�A�����A��э��݂Ƒ����B |
2006�N |
�l�����ԓ��v |
| 2750 |
���N�j���̔z��W�ʎ��E�� |
�j���Ƃ��z��҂̂��Ȃ��҂̕����������E���B�j�͗�����̗��ʎ҂����ς�4�{�̎��E���A���͖����E���ʂ����ς�2�{�ȏ�̎��E���B |
2000�N |
�l�����ԓ��v |
| 2758 |
���E�͖{���ɑ����Ă���̂� |
���E�Ґ��ł͉ߋ��ő��̃��x���������Ă��邪�A���E���ł͐�㒼��Ƃقړ������x���A�W�������E���ł͐�㒼���3����2�̃��x���B |
2010�N |
�l�����ԓ��v�AOECD |
| 2759 |
�j���肪�Ȃ����E����悤�ɂȂ����̂� |
���x�������ȍ~�̎��E�Ґ��̑����͂����ς�j�̑����Ő�߂���悤�ɂȂ������A�j����̏㏸�͐��E�I�X���B�āA�I�[�X�g�����A�Ȃljp�ꌗ�ł͐�s���Ēj���䔽�]�̓��� |
2014�N |
OECD�A�l�����ԓ��v |
| 2760 |
�N��ʎ��E���i�j�q�j�̒������ڂƓ��Ĕ�r |
����ƂƂ��ɕϑJ����N��ʎ��E���̍\���B�ߔN�͒����N�̎��E���̍����\���ɕω����A�č��ȂǂƔ�r���Ă��ۗ������ΏƂ������B |
2003�N |
�l�����ԓ��v |
| 2770 |
���E���̍��۔�r |
98�N�Ɏ��E�Ґ����}���������ߓ��{�̎��E���͐�i������P�ʁA���E101�J������9�ʂƂȂ��� |
2005�N |
WHO |
| 2772 |
���E�e���̒j���ʎ��E�� |
���\�A�����̍ۗ����č����j�����E���B���{�̏������E���͐��E��6�ʁB |
2005�N |
WHO |
| 2773 |
���E�Ƃ��Ƃ̑��ցi���۔�r�j |
�������Ȃ��̂Ɏ��E���������؍��A���������̂Ɏ��E���̒Ⴂ�M���V���Ȃǂ��Ǝ��E�Ƃɂ͑��ւ��Ȃ��B���{�͊؍����l�A���E�������������͏��Ȃ��B |
2019�N |
OECD�AWHO |
| 2773b |
���E�Ƃ��Ƃ̑��ցi�s���{����r�j |
�������Ȃ��̂Ɏ��E���������H�c�A���������̂Ɏ��E���̒Ⴂ���s�ȂǓs���{���ʂɌ��Ă����Ǝ��E�Ƃɂ͑��ւ��Ȃ��B |
2022�N |
�l�����ԓ��v�A����������b���� |
| 2774 |
��v���̎��E���������ځi1901�N�`�j |
���{�̎��E���ō��l��1958�N��25.7�l/10���l�B���E�ō����̓t�����X�A�h�C�c�A���{�A�n���K���[�A���V�A�ƕϑJ�B |
2005�N |
�����J���ȑ� |
| 2774c |
��v���̑��E�����ځi�������v�j |
�������v�ɂ�鍑�۔�r�B���ď����ł͂���30�N�Ɋ�{�I�ɒቺ�X���B���V�A�E���g�r�A�E�؍��ł͈ꎞ���㏸��A21���I�ɓ����Ēቺ�X���B�u���W���͋ߔN�܂ŏ㏸�X�� |
2017�N |
OECD |
| 2775 |
���E�e���̎��E���Ƒ��E���̑��� |
�Љ�X�g���X���A�t���J�A���e���A�����J�ł͑��E���㏸�Ƃނ��т��A���āA�A�W�A�ł͎��E���㏸�Ƃނ��т��B���{�̎��E���͐��E�̒��ł����������E���͐��E�Œᐅ���B |
2002�N |
WHO |
| 2776 |
���E�ɂ�鎀�S�Ґ��̐��� |
���E�ɂ�鎀�S�Ґ��͎��E�Ґ���50����1��600�l�O��B���E�Ґ��ȏ�Ɍo�Ϗɂ��e��������B |
2007�N |
�����J���� |
| 2776a |
���E�e���̑��E�����ځi�x�@���v�j |
���E��Q�҂̐���21���I�ɓ����Ă����ނˊe���Ō����X���B��O�̓W���}�C�J�A���L�V�R�A�؍��ȂǁB |
2011�N |
UNODC |
| 2776d |
��v���ɂ����鑼�E���̒������� |
���{���܂߂���v���ł́A��O����́A���邢�͂����ƒ������j�I�ȑ��E���̒����I�Ȓቺ�X�����F�߂��� |
2000�N�� |
OECD |
| 2777 |
�������Ɨ������̒������� |
�����O���̍����������ɋ߂Â�����ŋ߂̗����� |
2007�N |
�l�����ԓ��v |
| 2778 |
���Ϗ����N��Ƃ��̒j�����̒������� |
�Ӎ����̎w�W�ł��镽�Ϗ����N��́A���A�j�����ꂼ��5.3�A6.7�̏㏸�ƂȂ��Ă���B���̏㏸�X����2000�`2015�N��15�N�Ԃɉ������A���̌㉡���ɓ]�����B |
2021�N |
�l�����ԓ��v |
| 2780 |
���������̐��ڂƌi�C�Ƃ̑��� |
���������������X�������ǂ�Ȃ��A1980�N��ȍ~�ɂȂ��Či�C�Ƃ̑��ւ������A�i�C�̈����ɐ�s���ė��������������������A�i�C�ɐ�s���ė��������̑����������i�Ȃ����������̌����j����悤�ɂȂ����B |
2006�N |
�l�����ԓ��v�AGDP���v |
| 2781 |
�j���������x�����Ă��鍑���قǓ������ɑ��鋖�e�x������ |
�j�������x���⓯�������e�x�������͖̂k���A�Ⴂ�͓̂쉢�A�����A�r�㍑�B��v���͂��̒��ԁB���{��OECD�����̒��ł͒�߁B |
2014�N |
OECD |
| 2782 |
���E�E�������E�����̋��e�x�̐��ڂƒj���E�N��ʋ��e�x |
���E��F�߂�ӌ��͑����Ă��Ȃ����A�������E�����ɂ��Ă͔F�߂�l�������Ă���B |
2005�N |
���E���l�ϒ��� |
| 2783 |
���������e�x�̍��۔�r |
���e�x�ō��̓I�����_�A�Œ�̓G�W�v�g�A���{�͒��ʁB�v���e�X�^���g�n���[���b�p���J�\���b�N�n���[���b�p������āE�A�W�A���C�X�������̏��B |
2000�N |
���E���l�ϒ��� |
| 2783a |
���������e�x�̎�v������ |
���������e�x�͐��E�œ�ɉ��̕����B���ĂƂ��̉e�����Ă��鍑�ł͂܂��܂����e�ƂȂ����ŋ��\�A����r�㍑�ł͗��₩�B |
2017�N�� |
���E���l�ϒ��� |
| 2784 |
���E���e�x�̍��۔�r�i58�J���j |
���E�ɑ��鋖�e�x�̍����I�����_�A�t�����X�A�X�E�F�[�f���B���e�x�̒Ⴂ�o���O���f�V���A�C���h�l�V�A�B���Љ��`���������Ǝ��ۂ̎��E���Ƒ��ցB |
2000�N |
���E���l�ϒ����AWHO |
| 2785 |
���C�͋�����邩�i�s�ϋ��e�x�̍��۔�r�j |
���C�E�s�ς̋��e�x���ł������̂̓t�����X�l�B���{�l��39������9�ʂƔ�r�I���e�ȍ����B�C�X�������͕s���e |
2013�N |
Pew Global Attitudes Project |
| 2787 |
�ϗ���̋��e�x�i��v���̔�r�j |
�E�ŁA�d�G�A���邢�͓������A���E�Ȃǂɑ���ϗ���̋��e�x�͍��ɂ��傫�����ƂȂ�B |
2005�N |
���E���l�ϒ��� |
| 2787d |
�ϗ��I�ȋ��e�x�̎�v����r�i�s���[���T�[�`�Z���^�[�����j |
�T���ĉp�ƕ��Ɏ����ō������O���A�����A�������A�s�ρA��D�A�D�P����A�M�����u���A�����ւ̓��{�l�̗ϗ��I���e�x |
2013�N |
Pew Research Center |
| 2787h |
�ϗ���̋��e�x�i�e�����z�Ɠ��{�̓����j |
���E�����u���v�֘A�̗ϗ������B���{�l�ɂƂ��ėϗ���̋��e�x����������́u���v�Ɓu���v�A�Ⴂ����́u�\�́v�Ɓu���[���v |
2019�N |
���E���l�ϒ��� |
| 2785a |
�����̗ǂ����E�������i�̊������Ɣƍߗ��Ƃ̑��ցj |
���{�͔ƍ߂����Ȃ����ł���̂ɍ����͎������ǂ��Ƃ͊����Ă��Ȃ��B�ƍ߂̏��Ȃ���i���ł͑̊������Ɣƍߗ��̑��֓x�͒Ⴂ |
2016�N |
OECD |
| 2785d |
�̊������̃W�F���_�[�M���b�v |
���������ɖ铹�̕s���������鍑�̓I�[�X�g���A�A�j���[�W�[�����h�Œj���M���b�v��4���߂��B�t�ɒj���������Ȃ͉̂p���A�I�[�X�g���A�B���{�͒��ԓI�ʒu�ŃM���b�v�͖�2���B |
2020�N |
OECD |
| 2786 |
�ƍߗ��̐��� |
�x�@���v�ł͂Ȃ������ɑ��钲������ƍߔ�Q���̐��ڂ�����Ɣƍ߂͑S�̂Ƃ��Č����X���B�����ߔN�͎��]�ԓD�_��u�������Ȃǂ������͂��߂Ă���͗l |
2012�N |
�@���Ȗ@������������ |
| 2788 |
�ƍߗ��̍��۔�r�iOECD�����j |
�ƍߔ�Q�Ҕ䗦���猩�����{�̔ƍߗ��͐�i�����Œ� |
2005�N |
OECD |
| 2788c |
��Ȕƍ߂̔�Q�җ��i��OECD��r�j |
�ƍߔ�Q�җ��́A���]�ԓD�_5.1���A����Ҕ�Q1.9���A�����ɑ��鐫�ƍ�1.3���A�ԏ�r�炵1.1���Ƒ����Ă���BOECD���ςƔ�r���đ����͎̂��]�ԁE�I�[�g�o�C�D�_�����ł���A����ȊO�͉�����Ă���B |
2005�N |
OECD Factbook |
| 2788d |
�����A�\�s�E�����A���ƍ߂ɂ��Ă̍��۔�r |
26�J�����A�����ł̓��L�V�R�A�\�s�E�����ł̓A�C�X�����h�A���ƍ߂ł̓A�C�������h���g�b�v�B�O2�҂ł͓��{�͍ʼn��ʁA���ƍ߂ł͉�����8�ʁB |
2005�N |
OECD Factbook |
| 2788e |
����Ҕ�Q�ɂ��Ă̍��۔�r |
��Q���g�b�v�̓M���V����24.7���B���{��1.9����OECD����10.4���������A�e���̒��ōŒ�̔�Q���B |
2005�N |
OECD Factbook |
| 2788f |
���E�E�����d�ɂ��Ă̍��۔�r |
�T���ĒႢOECD�����̉��E���B�M���V���A���L�V�R�A�n���K���[�A�|�[�����h�Ȃǂ͗�O�B��i���̒��ł̓t�����X����⍂���A���{�͑��ΓI�ɒႢ�B |
2005�N |
OECD Factbook |
| 2788g |
�D�_���������E���Ȃ��� |
���{�͓D�_�̏��Ȃ����B�D�_�������Ǝ�������ό��q���M���Ă���C�^���A�����͓D�_�����Ȃ��B |
2005�N |
OECD Factbook |
| 2789 |
�����䗦�̍��۔�r |
�����䗦�͑����̍��łP���ȉ��B�č��͍ł������A9�����z���Ă���B���{����r�I�������ɑ�����B |
2007�N |
ICPS |
| 2789c |
���C�v��Q�̏� |
30�㏗���̃��C�v��Q�o������12.1���Ə����S�̂�7.3����傫�����邱�Ƃ��烌�C�v��Q�͂��Ă�葽���Ȃ����Ɛ��肳��� |
2008�N |
���t�{ |
| 2789f |
�X�g�[�J�[��Q�̏� |
�����̖�1���i30�㏗���͖�2���j�A�j����4�����X�g�[�J�[��Q���o���B���̊댯��������������3���i30�㏗����7.7���j�ɒB�� |
2014�N |
���t�{ |
| 2790 |
�z��҂���̖\�͔�Q�iDV�A�h���X�e�B�b�N�E�o�C�I�����X�j�o���� |
���Ɋ��������̂R���̂P���v����\�͓I�s�ׂ����o�� |
2005�N |
���t�{ |
| 2792 |
���l����̖\�͔�Q�o���� |
�Ⴂ�Ƃ��ɗ��l����\�͓I�s�ׂ���������14���A�Ⴂ�����قǔ�Q�������i20�Α��23���j |
2005�N |
���t�{ |
| 2792b |
�h���X�e�B�b�N�E�o�C�I�����X�o�����̍��۔�r |
�v�Ȃǂ���g�̓I�E���I�\�͂����o���̂��鏗���̓G�`�I�s�A�n����70.9��������{�s�s��15.4���܂ő傫�ȕ� |
2000
�`04�N |
WHO |
| 2792d |
�h���X�e�B�b�N�E�o�C�I�����X�o�����̐�i����r |
���{��DV�͐�i���̒��ł���r�I���Ȃ��� |
2000
�`08�N |
���A |
| 2792j |
�h���X�e�B�b�N�E�o�C�I�����X�̐��E�����L���O |
���{�l�����̉ߋ�12�J��DV�o������OECD38������23�ʂ�3.0���Ə��Ȃ����BOECD�g�b�v�̓R�����r�A��10.0���B��OECD�g�b�v�̓C���h��15.9���B�����A�؍��͂��ꂼ��5.9���A8.8���Ƃ��Ȃ葽���B |
2018�N |
OECD Society at a Glance |
| 2793 |
�ƍߎ҂Ɣ�Q�҂Ƃ̊W�i�ƍߎ�ޕʁj |
�E�l�Ə��Q�́A�e���y�іʎ��̂���҂ɑ��āA���Y�Ƌy�ѐ��ƍ߂́A�ʎ��̂Ȃ��҂ɑ��ĔƂ����ꍇ�������B |
2005�N |
�ƍߔ��� |
| 2793c |
���Ăɂ����鑼�E�̔�Q�҂Ɖ��Q�҂̊W |
���{�Ɠ����悤�ɉ��Ăɂ����Ă����E�̉��Q�҂͕v�w��e���������B���ɏ����͕v�⌳�v�ɎE����銄����4���ȏ�ƍ��� |
2008�N |
Small Arms Survey�AUNECE |
| 2794 |
�O���l�ƍ߂̐��� |
1980�N��㔼�����P�̃s�[�N93�N�ɂ����ĊO���l�ƍߋ}���A2004�N�ɂ͑�Q�̃s�[�N�B�O���l�ƍߔ䗦��2���B���Ђł͒������ő��B |
2006�N |
�ƍߔ����� |
| 2795 |
�������ڂȂǂɂ���ȋ��z���\���� |
L&G�ɂ��u�~�V�v���\�����͖L�c���������i1987�N�j�A�S�����t�����i2002�N�j�Ɏ����W���K�� |
2009�N |
�����V�� |
| 2795b |
��Ȍl��o���� |
�l��o�����̗��o�l���Ƃ��ẮA����{�����864���l���ł������A�\�t�g�o���N��KDDI�̎�����450���l���x�ő����B |
2009�N |
�����V�� |
| 2795c |
��ȍ��z�������� |
2011�N5���Ɍx����Љc�Ə��i����s�j����D��ꂽ6��400���~�͂���܂ł̋��������ɂ�����j��ō��z |
2011�N |
�����V���E�����V�� |
| 2795d |
��Ȗ����ʏP������ |
�����ʏP�������̂�����Q�҂������̂�2001�N�̑�㋳���t���r�c���̎����P��������2008�N�̓����E�H�t���̒ʍs�l�P������ |
2014�N |
�����V���E�����V�� |
| 2796 |
�Љ�ۏዋ�t��̑���������̐��� |
�Љ�ۏዋ�t�̑���������͂���܂ʼn����̎����Ƌ}�㏸�̎��������݂ɖK���`�ŏ㏸���Ă����_�ɑ傫�ȓ��� |
2004�N |
�Љ�ۏ�E�l����茤���� |
| 2798 |
�Љ�ۏዋ�t��̍��۔�r�iOECD�����j |
�Љ�ۏ�̃��x�����Ⴂ�_���ڗ����{�B���[���b�p�͎Љ�ۏ�卑�������B |
2003�N |
OECD |
| 2799 |
�Љ�ۏ�Ɋւ��鐭�{�ӔC�ɂ��āi���۔�r�j |
���{�͕č��⑼�̃A�W�A�����ƕ���ŎЉ�ۏ�ɑ��鐭�{�ӔC�̏d���x�����ΓI�ɒႢ�B����Ґ����ێ��ƈ�Ë����Ɋւ��Ă͎��͋~�Ϗd���x���E��B |
2006�N |
ISSP |
| 2800 |
�n��ԎЉ�ۏ�ړ]�i���m���Ƒ啪���j |
��N�����獂��ւ̎Љ�ۏ�ړ] |
1999�N�x |
�����o�όv�Z |
| 2900 |
���I�N���E�Љ�ۏ�̋��t�����E���S���@�ɑ��鍑���ӎ� |
�]�܂������I�N���̋��t�����ɂ��Ă͍����́u��T�Ɍ����Ȃ��v�ƍl���Ă���B�܂��Љ�ۏ�̋��t�����ɂ��Ắu�ێ��v���u�����v������B |
2001�N�A
2004�N |
���������I�D�x�������i���t�{�j |
| 2910 |
�Љ�ۏᐧ�x�̋��t�ƕ��S�̐���ʊi�� |
��N�w�̋��t���͒Ⴍ�A���S���͍������Ƃ��N���s�M�̍��{�v���ƂȂ��Ă���B |
2005�N |
��ؘj�i2005�j |
| 2920 |
�N�����߂��鐢��Ԃ̈ӎ��M���b�v |
�N�����߂���ӎ��͒P�ɔN��Ƃ�����莞��o���̍��������炷����Ԃ̈ӎ��̍��ɂ���đ傫���قȂ��Ă��� |
2003�N |
�c�������� |
| 2923 |
�q�ǂ��D�悩����җD�悩�F����̗D�揇�� |
�q�ǂ����������܂ňȏ�ɗD�悷�ׂ��Ƃ����ӌ������܂�Ȃ��A�Ⴂ����قǎq�ǂ��D��̈ӎ��������B�������A����S���ꍇ������������50��͍�����D��̈ӎ�������w���������B |
2018�N |
���{�l�̍��������� |
| 2925 |
���炢�炷���҂��� |
�����N�ɑ���20�Α�A30�Α�̎�N�w�́u���炢��v������ |
2008�N |
���{�l�̍��������� |
| 2927 |
���I�ȑ��݂�͂�M�����҂������Ă��� |
�u���̐��v��u��Ձv��u�����E���ӂ��̗́v��M�����҂������Ă���B�����A������M���Ȃ����N�w�������Ă���B |
2008�N |
�m�g�j�������������� |
| 2950 |
�����ی쐢�ѐ��ƕی엦�̐��� |
�ߔN�A�����ی쐢�ѐ����ی엦���㏸ |
2005�N�x |
�����J���ȁA�Аl�� |
| 2955 |
�H���E�ߗ��E��Âɍ����Ă��鐢�� |
�o�ϓI���R�ʼnߋ���N�ԂɐH���A�ߗ��������Ȃ��������Ƃ̂��鐢�т́A���ꂼ��15.6���A20.5���B���N�łȂ��̂Ɉ�Ë@�ւɍs���Ȃ��������т�2.0���i���̂��������͌o�ϓI���R�j |
2007�N |
�Љ�ۏ�E�l����茤���� |
| 2970 |
�z�[�����X�l�� |
�z�[�����X�͂R��s�s�i����23��A���s�A���É��s�j�ɑ������A�S�̂Ƃ���2��5��300�l('03)����1��8��500�l('07)�ւƌ� |
2007�N |
�����J���� |
| 2972 |
�z�[�����X�䗦�̍��۔�r |
�H�����L�n�ŕ�炷�z�[�����X�̐l���͕č����l��10���l������75.5�l�ł���̂ɑ��A���{��2.5�l��30����1�B |
2023�N |
Our World in Data |
| 2975 |
�ǓƊ�������Ă���l�̊��� |
30�㖢���j���������Ƃ������u�����E��Ɂv�ǓƂ������Ă���i15�`16���j�B�����N�����҂ɂ��ď����̌ǓƊ��͒ቺ���邪�j���̌ǓƊ��͂Ȃ��������B |
2021�N |
���t���[ |
| 2980 |
��Q�҂Ƃ̂ӂꂠ���̐��� |
��Q�҂Ƙb������菕�������肷��@��͑����Ă��Ă��� |
2012�N |
���t�{���_���� |
| 2990 |
�Љ�v���ӎ��̍��܂� |
�Љ�ɖ𗧂������Ƃ����l�������I�ɑ�������X���B�Z���I�ɂ͍D���̕����ɒ����B |
2008�N |
���t�{���_���� |
| 2992 |
�Љ���ӎ��̏����� |
���̒��̂��߂ɂȂ�d�����������l�͑����Ă��邪�A�����]���ɂ��Ă܂Ő��̒��̂��߂ɂȂ鐶���ɂ͌X�ł��Ȃ��Ƃ����ӎ������� |
2008�N |
�m�g�j�������������� |
| 2994 |
����ɂȂ�l�����邩�i�Љ�I�����j�̍��۔�r |
���{�͒����E�؍��ƂƂ��ɗ����l�����ΓI�ɏ��Ȃ����̕��ނɂ͂��� |
2008�N |
OECD Factbook |
| 2995 |
����҂ɂƂ��ė����l�͂��邩�i����҂̌Ǘ��j�̍��۔�r |
�Љ�I�Ǘ��͍���w�œ��ɐ[���Ȃ̂���ʌX�������A���{�͓��ɂ��������N����傫�����ł͂Ȃ��A����w�̌Ǘ��͐�i�����ϒ��x�B |
2018�N |
OECD |
| 2996 |
�ЂƏ����i�Љ�I�����j�̍��۔�r |
�����Ă��錩�m��ʎ҂������������{�l�̔䗦��22.7���Ő��E38�J�����ʼn��ʁB�ŏ�ʂɂ́A�J�i�_�A�č��A�I�[�X�g�����A�Ȃljp�ꌗ������6���ȏ�ŕ��ԁB |
2008�N |
OECD Factbook |
| 2998 |
��x���̍s�����̍��۔�r |
�ߋ�1�N�Ԃɓ�x���̍s�����Ƃ����҂̔䗦�͓��{��8���ƍŒ�B�C���h�A�C���h�l�V�A�A�^�C�ȂǓr�㍑�ł�50������̂ɑ��āA�����̉��Đ�i���ł͂�������20����B |
2025�N |
Ipsos |
| 3000 |
�{�����e�B�A�����җ��̐��� |
�{�����e�B�A�Q�����ɖڗ������㏸�͂Ȃ� |
2006�N |
�Љ����{���� |
| 3001 |
�s���{���ʂ̃{�����e�B�A�����җ� |
�ł��{�����e�B�A������������Ȃ̂͒���A�ł��s�����Ȃ͉̂���B�l���K�͂̑傫�Ȓn��قǕs�����ł��邪�������n��ł������Ƃ͌���Ȃ��B |
2006�N |
�Љ����{���� |
| 3002 |
�{�����e�B�A�ɂ��Ă̍��۔�r |
���{�̃{�����e�B�A�������͒��ʁA���K��t�͔��ɏ��Ȃ��B |
2008�N |
OECD Factbook |
| 3003 |
OECD�����ɂ�����{�����e�B�A�����җ� |
�č��A�X�E�F�[�f���A�I�����_�A�؍��Ȃǂō������{�A�h�C�c�A�t�����X�ȂǂŒႢ�{�����e�B�A�����җ� |
2000�N |
OECD |
| 3005 |
�{�����e�B�A�������Ԃ̍��۔�r |
�{�����e�B�A�����Ɋ����������Ԃ̒������猩��Ɠ��{��؍��ł̓{�����e�B�A�͍��Â��Ă��炸�A���āA���ɕč��A�J�i�_�ł̓{�����e�B�A��������ł���B |
2006�N |
�Љ����{���� |
| 3010 |
�{�����e�B�A�̉��l�Ɗ�t�̊����i���۔�r�j |
���{�̃{�����e�B�A�����̗ʓI�ȃ��x���͒Ⴂ���A����ȏ�ɋ��K��t�͏������B |
2004�N |
�R�����l�i2007�j |
| 3020 |
�s���{����NPO�@�l�F�ؐ� |
�S����NPO�@�l���F������������ |
2007�N |
���t�{���������� |
| 3070 |
���{�̎Љ�|����ʂ̉��P�E�����̍����ӎ� |
�e�����̎Љ�̏����X�Ɣ��f |
2008�N |
���t�{���_���� |
�J
�� |
3080 |
���Ɨ��̐��ځi���{�Ǝ�v���j |
���{�̎��Ɨ���5���O��ƈȑO�Ɣ�ׂ�Ə㏸���A�ቺ���ڗ��ĉp�Ɠ������ƂȂ������A�ߔN�ቺ���A���萫�̓����͕ێ� |
2007�N |
�����ȓ��v�ǁAWDI�AILO |
| 3083 |
��҂̍������Ɨ��i�N��ʂ̎��Ɨ����ځj |
��҂̎��Ɨ��͑S�̖̂�2�{�ŁA�s�[�N����10���������A���݂�6.3���ƒቺ���A�ΑS�̔{�����ቺ�X�� |
2014�N |
�J���͒��� |
| 3085 |
���Ɨ��̐��ڂƌٗp��ɑ��鍑���ӎ� |
���ۂ̌ٗp����ٗp�E�J�������ɑ��鍑���ӎ��͔ߊϓI�B�����j���[�X����`����p���ƌٗp���x�̏_��̗������e�����Ă���ƍl������ |
2016�N |
�J���͒����A���t�{���_���� |
| 3090 |
���Ɨ��̍����ƒn��i���ɂ��Ă̍��۔�r |
���{�̎��Ɨ��͐������̒Ⴂ���A�n��i���������ɔ�ׂ�Ώ����� |
2004�N |
OECD |
| 3094 |
��v���ɂ����鎸�Ɨ��̒n��i���̐��� |
���{�����łȂ����Ď�v���ł������ނˎ��Ɨ��̒n��i���͏k���X���ł���A�v���Ƃ��ẮA�T�[�r�X�o�ω��Ƃ�����i�����ʂ̌o�ύ\���ω��̉\���������B |
2021�N |
OECD |
| 3100 |
�J�����Ԃ̐��ځi�e����r�j |
�J�����ԓ��ċt�]�A�ċt�] |
2006�N |
OECD |
| 3120 |
�J�����Ԃ̒������ځi���{�A�p���E�č��j |
19���I�����̉p�āA���{�ł���O�́A�N��3000���Ԃ�傫�������Ă����B |
2004�N |
������ |
| 3123 |
�����ԘJ���̐��� |
�����ԘJ���͌����X���B�����ԘJ���̂���49�`59���Ԃ̕���60���Ԉȏ�����傫�������B |
2012�N |
�J���͒��� |
| 3125 |
�����ԘJ���Ҕ䗦�i���ځA�E�ƁA�j���N��j |
����10���Ԉȏ�̒����ԘJ���҂͋ߔN�����X���B���ɁA�j���̔̔��E�E�T�[�r�X�E��30�Α�łS�����Ă���B |
2005�N |
�m�g�j�����������Ԓ��� |
| 3130 |
�����ԘJ���Ҕ䗦�̍��۔�r |
���Đ�i���Ƃ̔�r�ōł��������{�̒����ԘJ���ҁB���̑��A�p�ꌗ�����Œ����ԘJ���҂������B |
2000�N |
������������ |
| 3132 |
�j���ʘJ�����ԕ��z�̍��۔�r |
�J�����ԕ��z�Z��3�^�C�v�A���z�̏W���E���U��3�^�C�v�ɕ�����Ɠ��{�͒����ԁE���ԕ��z�^�ɑ����@ |
2005�N |
OECD |
| 3135 |
�J�����Y���ƔN�ԘJ�����Ԃ̑��ցi���E�e����r�j |
���ԓ������GDP�̑傫���J�����Y���̍������قǔN�ԘJ�����Ԃ͒Z���B���������{���܂ޓ��A�W�A������č��A�A�C�������h�͐��Y���̊��ɂ悭�����̂ɑ��A��ď�����h�C�c�A�f���}�[�N�Ȃǂ͐��Y���ȏ�ɘJ�����Ԃ��Z���B |
2017�N |
Our World in Data |
| 3137 |
�J�����Ԃƌ��N��� |
60���Ԉȏ�̒����ԘJ���͖��炩�Ɍ��N������������B����A���N��Ԃɕs���������j���J���҂͒Z���ԘJ����I������X��������B |
2011�N |
�Љ����{���� |
| 3140 |
�Ǘ��E�����䗦�̍��۔�r |
�Ⴂ���{�̊Ǘ��E�̏����䗦 |
2011�N |
�f�[�^�u�b�N���ۘJ����r |
| 3142 |
���{�̊Ǘ��E�F�l�I�����Ə����䗦�̐��� |
�Ǘ��E�̊�����1980�N�̃s�[�N�ɂ�4.7���ł�������30�N���2010�N�ɂ�2.4���ɂ܂ʼn����B�����䗦�͐��܂��Ȃ��ɂ�3��������������2010�N�ɂ�14.0���܂ŏ㏸ |
2010�N |
�������� |
| 3150 |
�J���͕s���E�J���͉ߏ�̏��� |
2004�N����J���͉ߏ肩��J���͕s���ɓ]���p�[�g�^�C�}�[��萳�Ј��̕s�����x����ɓ]���������ŋ߂͑S�̂Ƃ��ĉߏ�̕��ւƌ������Ă���B |
2008�N |
�����J���� |
| 3160 |
�A�E���藦�̐��ځi�呲�j |
��������A�E���藦�̏B�������N�x�O���Ɋ�Ƃ͂��Ȃ������o���Ă���̂�GDP���������Ɍ�����o�Ϗ�قǂ̈����Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B |
2009�N |
�����J���ȁE�����Ȋw�� |
| 3161 |
�A�E���藦�̒n��ʂ̐��ځi�呲�j |
�e�n��ŏA�E���藦�B���É��o�ό����܂ޒ����ł͓��肪�x���Ƃ��������B���藦�A�A�E���́A�n�捷�k���A�S���ώ����̌X���B |
2015�N |
�����J���ȁA�����Ȋw�� |
| 3165 |
�w��ʏA�E�Ґ�����ё�w���A�E���̐��� |
�A�E�Ґ����ł������w����1965�N�ɒ������獂���ցA�܂�1998�N�ɍ�������呲�ɃV�t�g�����B�呲�A�E�����ŋߋ}���ቺ |
2010�N |
�����Ȋw�� |
| 3170 |
�����E�����E�呲�ʂ̂R�N�ȓ����E�� |
�����̂V���A�����̂T���A�呲�̂R�����A�A�E��R�N�ȓ��ɋߐ�����߂Ă��܂��X�����u���O�ގЁv�ƌĂ� |
2009�N |
�����J���� |
| 3176 |
�A�E�����̌��ʁA��]�����Ђɓ��ꂽ�� |
���u�]�̉�Ђɓ��ꂽ�Ƃ���V���Ј��̊����͍Œ��51������㏸�𑱂�8�����z�� |
2018�N |
���{���Y���{�� |
| 3180 |
�V���Ј��̓��Г��@�̐��ځi�u�A�Ёv����u�A�E�v�ցj |
�V���Ј��̉�БI�@�́A�u��Ёv�Ɏ䂩��āi��Ђ̏������Ȃǁj����u�E�v�Ɏ䂩��āi�\�͂�����Ȃǁj�ɑ傫���ω� |
2009�N |
���{���Y���{�� |
| 3184 |
�V���Ј��̃L�����A�ӎ��i�ꐶ�Ј����Ɨ����j |
�ꐶ��Ђɋ߂�Ƃ����V���Ј��������h�ƂȂ�Ɨ��u���̎�҂�1����Ɍ��� |
2010�N |
���{���Y���{�� |
| 3188 |
���Ђ�������ɂ͎В��ɂ܂łȂ肽���� |
��2�������В��u���̐V���Ј�������10���p�[�Z���g�B�В����d���A�d����蕔�����]�� |
2017�N |
���{���Y���{�� |
| 3200 |
�p�[�g�^�C���J���҂̔䗦���ځi�e����r�j |
���{�̃p�[�g�䗦�͒j���Ƃ��I�����_�Ɏ��������䗦 |
2005�N |
OECD |
| 3210 |
���I�p�[�g�^�C���J���҂̊��� |
���{�̃p�[�g�䗦�͊e���Ɠ��l�ɏ㏸���Ă������A���I�p�[�g�̔䗦�͉�����������C���B���ۓI�ɂ����ʐ��� |
2014�N |
�J���͒����AOECD |
| 3240 |
���K�ٗp�҂ƔK�ٗp�҂̐��� |
������K�ٗp�ҁA���鐳�K�ٗp�� |
2008�N |
�J���͒��� |
| 3242 |
�����Ă���K�ٗp�҂̐��� |
�K�ٗp�҂̑����͈ȑO�ɂ������č���҂ɂ���Đ�߂���悤�ɂȂ��Ă���B��N�̔K�ٗp�҂�2000�N��㔼����ނ��댸���ɓ]���Ă��� |
2017�N |
�J���͒��� |
| 3250 |
�K�J���Ҕ䗦�i�p�[�g�E�A���o�C�g�E�h���E�_�̔䗦�j�̐��ځi�j���N��ʁj |
�j���Ƃ���N�w�ő��������K�Ј� |
2008�N |
�J���͒��� |
| 3256 |
���K�E�K�ʂ̖����� |
���K�A�Ǝ҂ƔK�A�Ǝ҂̖������̍��������Ƃ��傫���̂͒j��30�Α�ł���A���K��30.7���A�K��75.6�� |
2010�N |
�����J���� |
| 3260 |
���Ј����݂̐E���ɏ]������Ј��̊��� |
���Ј����݂̐E���ɏ]������p�[�g���̑��̔Ј������� |
2006�N |
�����J���� |
| 3262 |
�ŋ߂̐E��̕ω� |
��Ԗڗ��̂́u�d���̏o����l�ƁA�����łȂ��l�Ƃ̍����߂��悤�ɂȂ����v�̂Ɓu��Ђ��^�������̂łȂ��Ȃ����v���� |
2018�N |
�J�������E���C�@�\ |
| 3264 |
�E��̂����߁E�p���n����Q���i�����ʁj |
�N��ʁA�ٗp�`�ԕʁA��ƋK�͕ʂȂǂ̑����ʂ̌��ʂ�����ƁA�ǂ�ȐE��ł������߁E�p���n���̔�Q�͔������Ă���Ƃ����X�������� |
2014�N |
�J�������E���C�@�\ |
| 3265 |
�E��łǂ�ȁu�����߁v��u�p���n���v���N�����Ă��邩 |
�����Ƃ������̂́u�{��ꂽ��A�\�����͂��ꂽ�v�i14.8���j�ł���A����Ɏ����ő����̂́u�d���������ŕK�v�������炦�Ȃ��v�A�u�����ɂ��ẲA����\���L�߂�ꂽ�v |
2014�N |
�J�������E���C�@�\ |
| 3267 |
�p���n���̍��۔�r |
���{�̃p���n���䗦��25.3���Ɛ��E37��������4�ʂł���A��v��i���iG7�j�̒��ł͍ł����� |
2015�N |
ISSP |
| 3270 |
�E��̃X�g���X�̏� |
����҂������j���e�N��w�Ŕ����ȏオ�����X�g���X�������Ă���B���ɒj��30�`40�Α�̃X�g���X�͖ڗ��B���̏\�N�Ԃł͂ނ���X�g���X��⌸��B |
2007�N |
�����J���� |
| 3273 |
�W���u�X�g���C���̊e����r�iOECD�����j |
�d����ْ̋��E���S�i�W���u�X�g���C���j���傫�ȓ��{�B������OECD�����̈�ʂ̌X���Ɠ��l�A�d����̊������͉��P�̕����B |
2015�N |
OECD |
| 3274 |
�d���̃X�g���X�̍��۔�r |
�d���̃X�g���X���J�̒��x�ɂ��Ă͓��{�̐E��͌b�܂�Ă��� |
2005�N |
OECD |
| 3276 |
���{�͎d���̃X�g���X���������� |
���{�l�͑������X�g���X�̑����l�Ə��Ȃ��l�����ɕ������Ă���̂ŁA�X�g���X�̂���l�̎����ɂ���āA���{�̓X�g���X�̑������Ƃ����Ȃ����Ƃ��咣�ł��錋�ʂ������� |
2005�N |
ISSP |
| 3277 |
���₷�������E���ɂ������� |
�����ԘJ�������5�ʂ͊؍��A�h�~�j�J���a���A��p�A�t�B���s���A���{�B�����������̍��ł͎d���̔��͂���قǂłȂ��B�J���͒����Ȃ����t�����X�l�͔��Ă���B |
2005�N |
ISSP |
| 3280 |
��v���ɂ����钷���ԘJ���Ǝd���̃X�g���X�̐��� |
���n��ω��̍��۔�r���猩��Ɠ��{�͒����ԘJ���������Ă���̂Ɏd���̃X�g���X�������Ă�������������яオ��B�ߘJ���͒����ԘJ�������̂����ɂ͂ł��Ȃ����낤 |
2015�N |
ISSP |
| 3282 |
�����ԘJ���Ǝd���̃X�g���X�Ƃ̑��� |
��v��i���̒��ł͍ł������ԘJ���������A�d���̃X�g���X���傫�����{ |
2015�N |
ISSP |
| 3290 |
�J���ЊQ���S�Ґ��̐��� |
�J�Ў��͍��x��������6000�l�䂩�猸�葱��2015�N����͂���1000�l��������Ă���B |
2017�N |
�����J���� |
| 3300 |
�J�����Ԃ̑����ւ̃t���^�C�}�[�E�p�[�g�^�C�}�[�ʗv������ |
���ϘJ�����ԑ����Ɋւ��ߔN�̓p�[�g�䗦�㏸�v�����d�v�ƂȂ� |
2007�N |
�����ΘJ���v���� |
| 3320 |
�N��ʕ��ϋΑ��N���̍��۔�r�i���{�̒����ٗp�j |
�j�q�s�N�w�܂łŐ������Ă��������ٗp�B����ґw�A�����w�ł͕K���������Ă͂܂�Ȃ��B |
1991�N |
OECD |
| 3324 |
��l��������������̐��ځi���{�y�ю�v���j |
���Ăł�30�N��3�`4���L�т��������������{�ł̓o�u������ȍ~�قډ����̐��ځB���x�������̍����L�сA���萬�����̉��ĕ��݂̐L�тƑΏƓI�B |
2023�N |
OECD�A��J���� |
| 3326 |
�E��ʂ̔N���Ƃ��̕ω� |
�����̐E���300�`500���~�B���N���͈�t�A��w�����A�L�ҁA�q��@���c�m�B�ꕔ�̐E��������ĔN���͌����X�� |
2011�N |
�J���o�ϔ��� |
| 3328 |
��N�ސE���̐��� |
�呲�z���C�g�J���[�̑ސE���̓s�[�N�������3�����B��N�ΘJ�҂⍂���u���[�J���[�ȂǂƂ̏����i���͏k���B |
2007�N |
�A�J������������ |
| 3330 |
�N��ʒ����J�[�u�̍��۔�r�i���{�̔N�������j |
�z���C�g�J���[�ł͊e���ň�ʓI�ȔN�����������{�ł̓u���[�J���[�ł��������Ă����B�����͐������Ă��Ȃ��B |
1995�N
�O�� |
�d�b |
| 3333 |
�N�������̍��۔�r |
�����̂n�d�b�c�����ŔN�������͂Ȃ��x�z�I�B�N���ɂ������A�b�v���͍���������؍��A�g���R�A���{�A�h�C�c�̏� |
2015�N |
OECD |
| 3335 |
�N�������̔N��ʎx�����̐��� |
��҂̔N�������x�������܂�A��҂ƒ����N�̔N�������x�������t�] |
2016�N |
�J�������E���C�@�\�A���{���Y���{�� |
| 3340 |
�����J�[�u�̃t���b�g�� |
�N��ʒ����J�[�u�̌������̒���1990�N�ȍ~��V���̐����Ƀt���b�g���i�W |
2004�N |
�J���o�ϔ��� |
| 3342 |
�Œ�����̍��۔�r |
��i�����ł��Ⴂ���{�̍Œ�������x�� |
2006�N |
OECD |
| 3343 |
��v���̍Œ���������̐��� |
���{�̓����͇@�Œ����x���̒Ⴓ�A�A���N�̈��萫�A�B�����I�ȏ㏸�X�� |
2011�N |
OECD |
| 3344 |
�p�[�g�^�C�������̍��۔�r |
�t���^�C�������Ɣ�r���Đ�i�����ł��Ⴂ���{�̃p�[�g�^�C�������̐��� |
2003�N |
OECD |
| 3346 |
�����E���^�i���̍��۔�r |
�t���^�C���x�[�X�̋��^���z�̊i���Ɋւ��Ă͓��{�̏ꍇ���m�ȓ������Ȃ����ʐ��� |
2007�N |
OECD |
| 3348 |
�K�͕ʒ����i���̍��۔�r |
���{�͒�����ƂƑ��Ƃ̋K�͕ʒ����i�����傫�����̍��ł���B���B�ł͒�����Ƃ����ƕ��݂̒����̍��������B |
2013�N |
�f�[�^�u�b�N���ۘJ����r |
| 3350 |
�j�������i���̐��ځi���۔�r�j |
�S���E�I�ɒj�������i���͏k���X���A���������{�A�؍��͂Ȃ��j�������i���� |
2004�N |
OECD |
| 3351 |
�j���ʒ����i���̔N��X�p�^�[���i���۔�r�j |
�N��ɂ��j�������i���̕ω��p�^�[���́A����ɂ��@�i���g��A�A�t���J�[�u�A�B�i���k���ɕ�����A�܂���ƊԊi�����傫���P�[�X�A�������P�[�X�Ȃǂ��܂��܁B���{�͍��Ƃ�قNJi�����傪�����B |
2010�N�㔼�� |
OECD |
| 3352 |
�q�ǂ��̗L���ɂ��j�������i���̈Ⴂ�i���۔�r�j |
�j�������i���͎q�ǂ��̂���J���҂̕����傫���A��e�ł��邱�Ƃ��������̂�OECD�������ʁB���������{�̎q�ǂ��̂��鏗���̒����M���b�v�͐��E1�傫���B |
2010�N |
OECD�i2012�j |
| 3355 |
�����E���^�����Ō��߂邩 |
���ʎ�`�̗v�f�͏������Ȃ������A�N��E�Α��E�w���̗v�f���������Ȃ�A�E��E�E���̃E�G�C�g�����܂��Ă��Ă��� |
2009�N |
�����J���� |
| 3357 |
��Ƃ��x�o���鋳��P����̐��� |
��Ƃ��A�Ǝ҂̂��߂Ɏx�o���鋳��P����͒����ቺ�X�� |
2011�N |
�A�J������������ |
| 3360 |
��Ƃ���݂��������p�̐������ |
��ƂɂƂ��ď����͉Ƒ��A�Α��N���A�c�Ƃ̖�肩�犈�p���ɂ����Ƃ��Ă���B�E��̒j����ڋq���A���̗͂����ɂ��Ă͒�����Ƃ͗]����Ƃ��Ă��Ȃ��B |
2006�N |
�����J���� |
| 3400 |
�E�ƕʗj���ʎd�����Ԃ̐��� |
�y���d���͐E�Ƃɂ��傫�ȍ� |
2005�N |
NHK�����������Ԓ��� |
| 3450 |
�t���[�^�[���E�j�[�g���̐��� |
10�N�ԂŔ{�������t���[�^�[���i�����J���Ȓ�`200���l��A���t�{��`400���l��j�A20��㔼�`30��O���̃t���[�^�[�}���Ŗ�肪�[�����B�����C�̂Ȃ��j�[�g�������B |
2007�N |
���t�{�A�����J���� |
| 3460 |
�j�[�g�i��N���Ǝҁj�̒������� |
1990�N��㔼�ɔ�A�ƁE�E�E��Ǝ��E��ʊw�̎�҂������ɑ��� |
2005�N |
�������� |
| 3470 |
�N��ʃt���[�^�[���E�j�[�g���̐��� |
�t���[�^�[�A�j�[�g�Ƃ��A24�܂ł̑O����N�w���25�Έȏ�̌����N�w�̑������ڗ����Ă�����͐[���� |
2007�N |
�J���o�ϔ��� |
| 3490 |
��ɉ����Ă���J���s��i���۔�r�j |
�X�L�������ʂɍ��X�L���i�Ǘ��Ɛ��E�Z�p�j�ƒ�X�L���i�T�[�r�X�E�̔��ƒP���J���j���������A����ȊO�̒��X�L������������Ƃ�����ʌX�����F�߂��� |
2015�N |
OECD |
| 3500 |
���i�E�Ƃ��猩���Љ�o�ς̕ω� |
������ʂ����i�E�ƁA�P�A�̎���̓��� |
2005�N |
�������� |
| 3520 |
�Z�[���X�}���̎��i�c�ƐE�̒������ځj |
���x���������߂��ċ}���������c�ƐE��2000�N���s�[�N�ɑ傫����������X���B�����v���͑������œ����������ʍ������A�l�b�g�Љ�̐i�W�A�����Ă`�h�̔��B |
2015�N |
�������� |
| 3550 |
���e�t�Ɣ��e�t�̐��ڂƓs���{���ʔ��e�t���x |
����30�N�͗��e�t�͌����A���e�t�͔{���Ɠ��{�l�����̂������x���ڗ��悤�� |
2005�N |
�����J���� |
| 3570 |
���̘J���������E�� |
���̘J���䗦�́A�_�ы��Ƃōł������A���݁E�����֘A�A�����ăT�[�r�X�֘A�̐E�킪����Ɏ����ł���B����A���ʐM�A�����A�o�c�A�Ǘ��Ȃǂ̐E�Ƃł͓��̘J���̔䗦�͒Ⴍ�Ȃ��Ă���B |
2023�N |
OECD |
| 3572 |
���̘J�����������E���Ȃ����iOECD��r�j |
���̘J���͑S�̓I�Ɍ�����邪�A��v��i���̒��ł͕č��̓��̘J���䗦��43.1���ƍł������A���{��24.7���ƍł��Ⴍ�Ȃ��Ă���B |
2023�N |
OECD |
| 3597 |
�Z�p�Ґ��̐��� |
2000�N�܂ŋ}�������Z�p�҂͂��̌㌸���B�ł������Z�p�҂͎��㒪���ɑΉ����A�@�����Z�p�ҁA�A���z��y�؋Z�p�ҁA�B����E�ʐM�Z�p�҂ƕω����Ă��Ă��� |
2010�N |
�������� |
| 3600 |
�Ɨ��Z�p�҂̐��� |
�������鎩�c�ƋZ�p�� |
2000�N |
�������� |
| �Z3601�`99��3979�̌�Ɍf�� |
| 3700 |
�d���Ɋւ��d�v���ڂɂ��Ă̈ӎ��ω� |
�����d���������d���A�y�ё��l�ȑ��ʂւ̔z���� |
2005�N |
���������I�D�x�����i���t�{�j |
| 3710 |
�ǂ̂悤�Ȏd�������z�I���Ǝv���� |
�u���z�̎d���v�̗D�揇�ʂ́A�h����������������Ƃ̃o�����X���y��������含�����N���E�̈��聄���̂��߁��������h |
2022�N |
���t�{���_���� |
| 3720 |
�����ړI |
�����S�̂Ƃ��ĎЉ�ɖ𗧂d���ւ̎u�����܂�B��҂ł́A2000�N������A�u�\�͂����߂��d���v�ւ̖��S���Ɓu�y�����d���v�ւ̌X�����܂� |
2014�N |
���t�{���_�����A���{���Y���{�� |
| 3770 |
�E��̒����N�ɑ���N��ʂ̍��۔�r |
�E��ɂ����钆���N�ւ̔N��ʂ͓��{�̏ꍇ28���ƃh�C�c�ƕ���ŏ��Ȃ��i��v12��������40���j�B�N��ʂ��ł������̂͊؍���61���B |
2022�N |
OECD |
| 3790 |
��Ƃɂ�����I�g�ٗp�̏� |
�I�g�ٗp������킷50��̌p���ٗp���͂Ȃ������Ƒ��Ƃ𒆐S�ɍ������A40��ȉ��ł͒�����Ƃ���Ƃ̒Ⴂ�p���ٗp���ɋ}���ɋ߂Â��X�� |
2016�N |
OECD�A�����Z���T�X |
| 3800 |
�I�g�ٗp�ɂ��Ă̊�ƈӌ� |
93�N�܂ŏI�g�ٗp���d������X���A����ȍ~�傫�������� |
2002�N |
�ٗp�Ǘ����� |
| 3804 |
�I�g�ٗp�u�����]�E�u�����i���۔�r�j |
���{�̎�҂͉��ď����̎�҂Ɣ�I�g�ٗp�^�̈ӎ��������A�܂����������ӎ��̎�҂������Ă���_���ڗ����Ă���B |
2008�N |
���E�N�ӎ����� |
| 3810 |
�J���^���i�J���g���E�J�����c�j�̐��� |
��シ��50���A���x�������ɂR���̂P�������J���g���g�D�������̌�ቺ�𑱂��A����2003�N����Q����� |
2005�N |
�����J���� |
| 3814 |
������v�c�̕ʒP�ʘJ���g���̑g���������� |
���]�ȂǍ��x�������̘J���S�c�̂́A1990�N�ォ��A�����S�ɘJ����������ꂳ�ꂽ���A�X�����c���������ĉe���͓ڍ� |
2005�N |
�����J���� |
| 3817 |
�J���g���g�D���̍��۔�r |
�k���ō����J���g���g�D���B�e���ŘJ���g���g�D���ቺ�X���B |
2005�N |
�J�������E���C�@�\ |
| 3820 |
�O���l�J���Ґ��̐��� |
�N�X�����X�������ǂ��Ă���O���l�J���Ґ� |
2006�N |
�����J���� |
| 3830 |
���O���̊O���l�J���� |
���O���̒��ł͓��{�̊O���l�J���҂̔䗦�͍ۗ����ĒႢ�̂����� |
2000�N |
�f�[�^�u�b�N���ۘJ����r |
| 3835 |
���Ď�v���̊O���l�J���҂̍��ЁE�o�g�n |
�g���R�l�̑����h�C�c�A�����b�R�l�̑����C�^���A�ȂǁA�ǂ̍�����̊O���l�J���҂��������͍��ɂ���ėl�X |
2002�N |
OECD |
| 3840 |
���w��l�ނ̍��ۗ��� |
�č��A�J�i�_�ł͓r�㍑���w��l�ނ����p�B���̑�OECD�����ł����w��l�ނ̍��ۗ����������B�������Ⴂ���{�A�؍��B |
2000�N |
OECD |
��
��
�^
��
�� |
3850 |
���t���̐��ځi�����y�і����N�l��������j |
�����N�l��100�l�����苳�t���i�m���t���܂ށj�͑����X���������Ă���A70�N��3.1�l����2000�N��6.1�l�ւƔ{�� |
2000�N |
�������� |
| 3852 |
���w�Z���t�̒j���䗦�̍��۔�r |
��i�����̒��ł͓��{�̏������t�䗦�͍Œ�x�� |
2006�N |
OECD |
| 3853 |
�c�t���E���w�Z�E���w���Z�E��w�̋����̏����䗦�Ɋւ��鍑�۔�r |
�c�t���A���w�Z�A���w�E���Z�A��w�Ƃ���Ƌ����̏����䗦���Ⴍ�Ȃ钆�ŁA���ʂ̍����傫���Ȃ�B���{�͑�w�⒆���ŏ����䗦�ʼn��ʁB |
2019�N |
OECD |
| 3854 |
���̎������i���w���E�ی�ҁE�w���S�C�j |
�ł������I���Ǝv����ʏ�̎������͏��w����55���A�ی�҂�4����3�A����҂ł���w���S�C�ł�87�� |
2006�N |
���{�X�|�[�c�U���Z���^�[ |
| 3855 |
�w�Z�ɂ�����̔��̌��� |
�w�Z�̐搶����̑̔������҂̔䗦�͍��Z���̏ꍇ1982�N��4������2002�N��1���ւƋ}�� |
2002�N |
�m�g�j�������������� |
| 3856 |
�y�����w�Z���� |
�����Z���̈ӎ��ł́A�w�Z�͈�w�y�����Ȃ�A�S�C�̐搶����������̂��Ƃ���w�������Ă��炦��ɂȂ����B |
2012�N |
�m�g�j�������������� |
| 3857 |
���升�i�Ґ����Z�����L���O |
���3�ʂ͗���i���s�j�A�V���i����j�A���厛�w���i�ޗǁj�B�����{�A���ɋߋE���̍��Z�̍��i�Ґ������� |
2017�N |
�T���f�[���� |
| 3858 |
���升�i�Ґ����Z�����L���O |
�����̊J�����Z��168�l�ō�N���l��1�ʁA2�ʂ͕��ɂ̓卂�Z�A��3�ʂ͓����̒}�g��t�����B |
2010�N |
�T���f�[���� |
| 3860 |
���升�i�Ґ����Z�����L���O�̐��� |
�������Z�̖��i�ƍ������A���Ɍ������Z�̃����L���O�ቺ���ڗ��B�ʍ��Z�̕���������B |
2005�N |
���J�i1995�j�A�T���f�[���� |
| 3860c |
��v�����升�i�Ґ����Z�����L���O�i�k��E���k��E���É���E���E���E�ꋴ��E���H��E��t��E�_�ˑ�E�����j |
����A����ȊO�̎�v������w�̍��i�Ґ����Z�����L���O�ł͓��k��̐����̂悤�ɒn���g�b�v�i�w�Z����ʂ����߂� |
2018�N |
�T������ |
| 3860e |
����c��E�c����e�w�����i�Ґ���ʍ��Z�����L���O |
����c��e�w���̍��i�g�b�v���Z�͉ߔ����̊w���ŊJ���A�Ó삾���A�c����̏ꍇ�͂��ׂĂ̊w���ňقȂ鍂�Z |
2018�N |
�T������ |
| 3861 |
���ƃg�b�v�̏o�g���Z�����L���O |
���3�ʂ́A�c���`�m���Z�i�_�ސ�j�A�C�Q�ٍ��Z�i�����j�A���z���Z�i�����j |
2016�N |
�T�����m�o�� |
| 3861a |
�����Y�a���Z�Ɠs������J���Z�̎�v��w���i�Ґ� |
�s������J���Z�Ɣ�r���Ă�����̂ق��ɋ���A���k��Ȃǎ�v������w�ɕ��L�����i�҂��o���Ă��錧���Y�a���Z |
2019�N |
�T���f�[���� |
| 3862 |
��w������֓x�����L���O |
�ł���������������̂����嗝�V�B����Ɉ�Ȍn4��w�������A���̎��ɁA���Ȍn�̓��啶�T�E�U�A���Ȍn�̓��嗝�T�A��Ȍn7��w�ƂȂ��Ă���B |
2013�N |
�T������MOOK��w�����L���O |
| 3864 |
���{�̎�v��w�i���ƗݐϏA�E�Ґ������L���O�j |
��v��Ƃɑ����̐l�ނ𑗂荞��ł����w�Ƃ��Ă͑���c�A�c�����c�[�g�b�v�B����ɖ����A���u�ЁA����A���傪���� |
2017�N |
�T���_�C�������h |
| 3865 |
���ƏA�E����w�����L���O |
�L����w�̑��A�H�Ȍn��w�A�S�N�����q��̑��ƏA�E���̍������ڗ��B |
2007�N |
�G�R�m�~�X�g |
| 3866 |
��w�����L���O�F���ƌ������������i�Ґ� |
���Ă̍������������ɓ����鍑�ƌ����������T�퍇�i�҂ɂ͓��呲�����|�I�ɑ��� |
2009�N |
�T������MOOK��w�����L���O |
| 3867 |
��w�����L���O�F�i�@�������i�Ґ��E���i�� |
���i�Ґ����3�ʂ́A����A������A�c����B���i�����3�ʂ́A�c����A�ꋴ��A���� |
2010�N |
�@���Ȍ��\���� |
| 3868 |
��w�����L���O�F���F��v�m�E�ꋉ���z�m�̍��Ǝ������i�Ґ� |
���F��v�m�������i�Ґ����3�ʂ́A�c����A����A������B�ꋉ���z�m�������i�Ґ����3�ʂ́A����A�������ȑ�A����B |
2009�N |
�T������MOOK��w�����L���O |
| 3868a |
��w�����L���O�F���q���E���h���E�x�@���A�E�Ґ� |
���q���A���h���A�x�@���ɂȂ�҂��ł�������w�́A���ꂼ��A���{��w�A���m�ڑ�w�A���{��w |
2012�N |
�T�����m�o�� |
| 3868c |
��w�����L���O�F�w���� |
�w�����g�b�v�͓��{��w7���l�A2�ʂ͑���c��w5���l�A3�ʂ͗����ّ�w3��5��l |
2016�N |
�T�����m�o�� |
| 3868d |
��w�����L���O�F���q�w���� |
�g�b�v�͓���2.1���l�ő���1.6���l�A������1.2���l�������B������A�����w�@��A��q��͉ߔ��������q�B������͐l���A�����Ƃ��ɒႭ�A���ɓ����2����� |
2017�N |
��w�����L���O�iAERA���b�N�j |
| 3868e |
��w�����L���O�F�O���l���w���� |
�O���l���w����������w�̃g�b�v3�́A����c��A����A�����كA�W�A�����m��i���{��ʉȂȂǂŊO���l���w�����W�߂�����w�������j |
2017�N |
���{�w���x���@�\ |
| 3869 |
��w�}���ّ����������L���O |
�������̑�����w�g�b�v3�́A����A����A����B�����͒����~�ςɂ�葠�����������B |
2008�N�x |
�T������MOOK��w�����L���O |
| 3870 |
���ϊw���K�͂̍��۔�r�i�����w�Z�j |
���{�́A34�l�Ɖ��ď�����10�l��`20�l��O���ł���̂Ɣ�ׂ�ƁA�N���X�l���������B |
2003�N |
OECD |
| 3870f |
���t1�l�����萶�k���̍��۔�r�i�����w�Z�j |
���{�̏��w�Z�͋��t1�l������̐��k��15.9�l�Ɗw���K�͂��傫�����ɂ���قǑ����Ȃ��iOECD���ς�14.5�l�j |
2019�N |
OECD |
| 3871 |
�����̃_�C�o�[�V�e�B���C�Q�����i���۔�r�j |
�������E��������ł̎��ƂȂNj��t�̃_�C�o�[�V�e�B���C�ւ̎Q�����͓��{��10����ƒႢ�i�č��A�J�i�_�Ȃǂ�4���ȏ�j |
2018�N |
OECD |
| 3872 |
�����̎��Ǝ��Ԃ̍��۔�r�i���w�Z�j |
���{�́A535���Ԃł���A�n�d�b�c�����̒��ōł����Ȃ��B�č��̎��Ǝ��Ԃ̔����ȉ��B |
2003�N |
OECD |
| 3874 |
�����̋��^�����̍��۔�r�i���w�Z�j |
���{�̋����̋��^�����́A�P�l������f�c�o������1.60�{�ƁA�n�d�b�c�����̒��ł́A��U�ʂ̍������� |
2003�N |
OECD |
| 3875 |
���t�E�Z���̊w�O�Ƃ̊ւ��i���۔�r�j |
���{�̊w�Z�ł́A���番��ȊO�̊����ւ̋��t�̊S�͒Ⴂ���A�Z���̊w�O�Ƃ̎����I�Ȋւ��͑傫���B |
2018�N |
OECD |
| 3876 |
���{�̐搶�͐��Ԓm�炸�� |
���{�̒��w�Z���t�̋��t�ȊO�̌o���N����1.5�N�Ɛ��E�ꏭ�Ȃ��iOECD�����𒆐S�Ƃ����Ώۍ��E�n��̕��ς�6.5�N�j |
2013�N |
OECD |
| 3877 |
���t�������Ă���e��Ɩ��̕��S���i���w�Z�j |
�u�ʒm�\�̍쐬�v�A�u���k�̖��s���ւ̑Ή��v�A�u�ی�҂���̋��ւ̑Ή��v�����w�Z���t��3�啉�S |
2014�N |
�����Ȋw�� |
| 3879 |
���t�Ƃ��Ă̖����ƌ���̍��۔�r |
���{�̒��w�Z�̐搶�́A���t�̎d���ɖ������Ă��Ȃ����A���t�ɂȂ������Ƃ���������Ă��Ȃ� |
2013�N |
OECD |
| 3880 |
�����l�����������k�̊w�Z�]�������L���O�iPISA�����j |
�u�w�Z�Ȃ�Ď��Ԃ̖��ʁv�ƍl���鐶�k���ł����Ȃ����{�B���̑��̍��ڂ��܂ߓ��{�̐��k�̏����l���������w�Z�ւ̃v���X�]���͎�v��i���g�b�v�B |
2022�N |
OECD |
| 3882 |
�w�Z����Ɖƒ닳��̕��S�ӎ��i���۔�r�j |
���{�ł͊w�Z����ɑ��u�����ߑΏ��v�ւ̊��҂���������ŁA�u�L�����A�w���v��u�f�W�^�����e���V�[�v�ւ̊��҂͊C�O�Ɣ�גႢ�B��i���ō����u�����ߑΏ��v���ҁA�r�㍑�ō����u�Љ�I�X�L���w���v���ҁB |
2024�N |
Ipsos |
| 3884 |
�D���Ȏ��ƉȖڂ̒j���W�F���_�[�� |
���w����j�͒j�q�D���A�O����╶�w�A�|�p�͏��q�D���ƍD���ȋ��Ȃɂ͒j���ɂ��Ⴂ�����邪�A���������W�F���_�[���͐��E�I�ɏk�܂�X�� |
2025�N |
Ipsos |
| 3886 |
�Ό�����̍��۔�r |
�����I�E�C�f�I���M�[�I�ȃo�C�A�X�������̑傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă��鍑�́A�|�[�����h�A�č��A�n���K���[�A�؍��A�}���[�V�A�Ȃǂł��邪�A���{�͂��������Ό����炪����قǐ[���łȂ��B |
2025�N |
Ipsos |
| 3900 |
�呲���Ɨ��̐��� |
�呲�Ҏ��Ɨ��͑��ΓI�ɏ㏸�A�u���߂���E�Ƃ̐��ځv�ƘA�� |
2007�N |
�����A�J���͒��� |
| 3905 |
�呲���Ɨ��̍������Ɨ��ɑ���{���̐��ځi���۔�r�j |
�؍���C�^���A�ł͑呲���Ɨ����������Ɨ�������N���B��ʂɑ呲���Ɨ��͑��ΓI�ɏ㏸�X���B�č��A�h�C�c�͒�ʈ���B |
2008�N |
OECD |
| 3915 |
�����H���P�����m���ő������ւ̋O�� |
�����̉H���P����i�A�̑�R�N��15�����l�̋L�^��27�N�Ԃ�ɓh��ւ�����P��1�ʂƂȂ�1434����B�� |
2019�N |
�����V���ق� |
| 3916 |
�����E�̏��i�N����L���O�F���䑏�����m�̐V�L�^ |
���w�����m�̒��ł����䑏�����i�̎��i���i�N���v������㎵�i�܂ł̓��B���Ԃ͉������O��i���čő��E�ŒZ�L�^������ |
2018�N |
�����V�� |
| 3919 |
���{�l�̍D���Ȋy�탉���L���O |
�s�A�m���s����1�ʁB�t�H�[�N�u�[�������ƂȂ�1983�N��4�����z��2�ʂ������M�^�[��2007�N�ɂ�10�����9�ʂɌ�ށB |
2007�N |
�m�g�j�������������� |
| 3920 |
���吶�����q����l���i��O�E���j |
1�ʁ`2�ʂ́A��O�i1938�j�͐��������A�Q�[�e�A���i1963�j�̓V�����@�C�c�@�[�A�}���N�X |
1963�N |
�ߌ��r�� |
| 3922 |
�������\����Ǝv�����j��̐l�� |
�������Ńg�b�v�ƂȂ����̂�4�l�B���Ȃ킿�ȖA�����A�É��́u����ƍN�v�A�A���m�A����́u�D�c�M���v�A�R�`�ƐV���́u�㐙���M�v�A���m�ƒ���́u��{���n�v�B |
2022�N |
�\�j�[���� |
| 3925 |
���{�l�̍D���ȉ��y�ƁE��ƁE��ƁE���j�l���̃x�X�g�e�� |
���R���ʂɂ��Ή��y�Ƃł̓��[�c�A���g�A��Ƃł̓S�b�z�A��Ƃł͎i�n�ɑ��Y�A���j��̐l���ł͐D�c�M������Ԑl�C�B |
2007�N |
�m�g�j�������������� |
| 3926 |
���{�l�̐S�Ɏc������ƁE�V���x�X�g�e�� |
20���I�̐l�C��ƃg�b�v3�͎i�n�ɑ��Y�A���{�����A�Ėڟ��B�����̐l�C��ƃg�b�v3�͓���\��A����t���A�r��ˏ��B�ŋ߂͉f�������ꂽ��ƁA������Ƃ��l�C�B |
2020�N |
�����V�� |
| 3927 |
���Z�E��w�E��w�@�i�w���̐��� |
5���ȉ����������Z�i�w����1974�N��9�����ɁB��w�i�w����1976�N��39�����s�[�N�ɑQ���A1990�N��ȍ~�ēx�㏸�A����5�����B |
2007�N |
�����Ȋw�� |
| 3928 |
��w�i�w���̍��۔�r |
���{�A�č��A�p����5�`6���̐����A�t�����X�A�h�C�c�͖�4���B�؍���8���ȏ�Ɠ��ʍ��������ɏ㏸�B |
2007�N |
�f�[�^�u�b�N���ۘJ����r |
| 3928a |
��w�ފw���i���ޗ��j�̍��۔�r |
���E�ōł��Ⴂ���{�̑�w�ފw���i10���j�B�������̓C�^���A�A�č���50����Ɖߔ������ފw�B |
2005�N |
OECD |
| 3929 |
�呲�䗦�i��N�w�ƒ����N�w�j�̍��۔�r |
�ߔ����̎�҂���w���Ȃ̂͊؍��A�J�i�_�A���V�A�A���{�̂݁B���i���Ɋ؍��j�ł͌o�ϐ����ɔ����đ呲�䗦���傫���g��B |
2008�N |
OECD |
| 3929a |
�呲�����̑��ΐ����ɂ��Ă̍��۔�r |
���{�͊؍��قǂł͂Ȃ����j�̑呲�̑��Ώ����͐��E�Ɣ�r����ƒႢ�B���{�̑呲�����̑��Ώ����͒j�ɔ�����B |
2009�N |
OECD |
| 3930 |
��v���̕��ϏA�w�N�� |
���ϏA�w�N�����E��͕č��A�Q�ʂ̓m���E�F�C�A���{�͐�i����12�ʁA�؍��͑�7�ʂƓ��{�������Ă���B |
2000�N |
Barro=Lee�i2000�j |
| 3932 |
���{�ƃ��[���b�p�̎������i19���I�㔼�j |
�]�ˎ��ォ�疾���ɂ����Ă̓��{�̎����������E�̒��ł����������Ƃ����̂̓E�\�B���Ȃ��Ƃ����������{�ł͒n�捷�A�j�������傫���A���ς��ăv���C�Z����t�����X�ȂǂƔ�r����Ɩ��炩�ɒႩ�����B |
1900�N |
�����o�ϓ��v |
| 3933 |
�m�[�x���܁i���R�Ȋw����j�̍��ʃ����L���O |
�č����R�܂����v����222�l�Ƒ�Q�ʂ̉p��74�l��傫�������Ă���B���{��9�l�B |
2006�N |
�Ȋw�Z�p���� |
| 3934 |
���{�l�m�[�x����҂̏o�g���Z�E�o�g��w |
���{�l�m�[�x����҂̏o�g���Z�͓����ȊO�̌������Z���قƂ�ǁA�o�g��w�͂��ׂč�����w |
2016�N |
�T���G�R�m�~�X�g |
| 3934d |
�m�[�x�����w��҂̒j���ʁE�n��ʐ��� |
20���I�ȍ~�̎�҂̒������ڂ́A�����䗦�̊g��A�A�W�A�E�A�t���J�䗦�̊g��ƒj�����S�A���[���b�p���S��E���A���l�����i�� |
2024�N |
OECD |
| 3935 |
�Ȋw�Z�p���e���V�[�i����x�j�̊e����r |
�Ȋw�Z�p��b�T�O�̗���x�œ��{�͐��E��13�ʁA�d�t���ς��Ⴍ�A�[���Ȏ��� |
2002�N |
�Ȋw�Z�p���� |
| 3936 |
���E�ꓪ���������{�l�iOECD�̐��l�X�L�������j |
���l�̃X�L���i�Z�\�j������킷�lj�́i���e���V�[�j�Ɛ��I�v�l�́i�j���[�����V�[�j�̃e�X�g�̓��{�̌��ʂ͂�������Q��24�������g�b�v |
2011�N |
OECD |
| 3936a |
�m�͊i���̏����ȓ��{�l�iOECD�̐��l�X�L�������F���_���z�j |
���{�͕��ϓ��_�����E�ꍂ������łȂ��A���_���z���lj�͂ł͊i�������E�ꏬ���� |
2011�N |
OECD |
| 3936d |
�m�̓g�b�v�N���X�̓��{�l�iOECD�̐��l�X�L�������j |
�O��2011�N�قǂł͂Ȃ����k���ƕ��ѓ��A�W�A�ł͗B����{���m�͂Ő��E�g�b�v�N���X�ł��邱�Ƃ������ꂽ�B�V�����Ƃ��Ĉږ����������m�͔�r�ł͖k�������{�����Ȃ�������B |
2022�N |
OECD |
| 3936g |
�m�͊i���̏��������E�傫�����iOECD�̐��l�X�L�������j |
���{�͓lj�́A���I�v�l�́A�������͂̂�����ł���x�����������E�ŏ��ł���m�͊i�����������B�������A�ږ�����������r�ł͖k�������̕�����x�����������Ȃ��B |
2022�N |
OECD |
| 3937 |
�q�ǂ��Ƒ�l�̒m�͑��� |
���{��k�������͎q�ǂ�����l�̒m�͂̕��������A�؍���쉢�����͎q�ǂ�����l�̒m�͂̕����Ⴂ |
2012�N |
OECD |
| 3938 |
���l�X�L���̍��۔�r�F��҂ƒ����N�̐���i�� |
��҂������N���A�lj�́A���I�v�l�͂œ��{�l�����E��i��҂̐��I�v�l�͂��I�����_�A�t�B�������h�Ɏ������E3�ʂȂ̂������j |
2011�N |
OECD |
| 3938b |
���J�����g����i���l�w�K�j�ɂ�����W�F���_�[�M���b�v�̍��۔�r |
���J�����g���炪�ᒲ�ȍ��́A�����̎Q�������j�����Ⴂ�X���B���{��OECD�����̒��ŏ����̎Q�������g���R�Ɏ����ő傫���j����������Ă���B |
2017�N |
OECD |
| 3939 |
�Љ�K���͌Œ�I���iOECD�̐��l�X�L�������F���e�̊w���̉e���x�j |
���e�̊w���ɂ��m�͊i���ŊK���ԗ������𑪂�Ƃ���ƁA�K�����g�b�v3�͕č��A�h�C�c�A�t�����X�A�������g�b�v3�̓L�v���X�A���{�A�G�X�g�j�A |
2011�N |
OECD |
| 3939d |
�Љ�K���͌Œ�I���iOECD��PISA�����F�e�̒n�ʂ̉e���x�j |
���{�͐e�̎Љ�I�n�ʂ��q���̐��тɉe��������x���������B�t�����X�A�č��A�����Ȃǂ͑傫���e�����A��Ăł͗T���Ȑe�̎q�̂ݐ��т��ǂ� |
2015�N |
OECD |
| 3940 |
�w�͂̍��۔�r�iOECD��PISA�����j |
���{��15�Ύ����̊w�͂͐��E57�J�����A�Ȋw��6�ʁA�lj�͂�15�ʁA���w��10�ʁB�O���葍�ĂŒቺ�B |
2006�N |
OECD |
| 3940f |
�w�͂̍��۔�r�iPISA�e�X�g�̐��у��x���Ɛ��ь���x�j |
���A�W�A�����ō����w�́B�h�C�c�A�|�[�����h�A�|���g�K���ȂǏ��q���̐i���قǐ��т̏㏸�x���傫���Ƃ����X�������邪�A���{��؍��́A���q���ɂ�������炸���ђ�� |
2015�N |
OECD |
| 3941 |
�Ȋw���_�̕��U�i�w�͊i���j�̍��۔�r |
���{�̓h�C�c�A�I�����_�Ɏ����Ŋw�Z�Ԃ̊w�͍����傫���B�Ȋw�̊w�͐��E��̃t�B�������h�͊w�Z�Ԃ̊w�͍��قƂ�ǂȂ��B |
2006�N |
OECD |
| 3941a |
�lj�͓��_�̕��U�i�w�͊i���j�̍��۔�r |
���{�̓h�C�c�A�C�^���A�Ɏ����Ŋw�Z�Ԃ̊w�͍����傫���B�lj�͂̊w�͐��E��̒����͊w�Z���̊w�͍�����ԏ������B |
2018�N |
OECD |
| 3941b |
�ږ����ǂ����ňقȂ�lj�̓e�X�g�̐��сiPISA�����j |
�k�������A�h�C�c�ňږ����k�̐��ђႭ�A�V���K�|�[���Ȃǂł͈ږ����k�̕������я�ʁB���{�̓lj�̓����L���O��15�ʂ���ږ���������20�ʂɒቺ�A�h�C�c��20�ʂ���9�ʂɏ㏸ |
2018�N |
OECD |
| 3941d |
�u�����v�Ɓu�ӌ��v����ʂł��邩�iPISA�����j |
�����ƈӌ�����ʂł��邩�̖�ւ̐������͓��{��5�����48����OECD�����̒���16�ʁB�č���69���ōō��A�؍���26���ōŒ�B |
2018�N |
OECD |
| 3941h |
���������[���ւ̑Ή��\�́iPISA�����j |
���\���̓d�q���[���i�t�B�b�V���O���[���j�ɖ��h���Ȋ؍��̍��Z���A�K�[�h�̌������{�̍��Z���B |
2018�N |
OECD |
| 3942 |
�w�������̍��۔�r�iPISA�����j |
���{�͐��E��w���������ۂ���Ă��鍑�i�w������͂قlj����j�B��ʂɐ�i���ł͑����������k�������B |
2009�N |
OECD |
| 3942a |
�t��W�̍��۔�r�iPISA�����j |
���k�ɊȒP�ɂ͎�������L�ׂȂ����{�̋��t�B���`��؍��ɂ������X���B |
2009�N |
OECD |
| 3942c |
�f�W�^���lj�͂ƃv�����g�lj�͂̍��۔�r�iPISA�����j |
�f�W�^���lj�͂̍��ۃ����L���O�͊؍�1�ʁA���{4�ʁB�f�W�^���lj�͂��v�����g�lj�͂�������x�ɂ��Ẵ����L���O�ł͓��{��9�ʂƒႢ�B |
2009�N |
OECD |
| 3942d |
���Z���̃C���^�[�l�b�g���p���̍��۔�r |
���{�̐��k�̉ƒ�ł̃C���^�[�l�b�g���p����45�J����36�ʂƒႭ�Ȃ��Ă���A�w�Z�ł̗��p����39�ʂƂ���ɒႢ�B |
2009�N |
OECD |
| 3942e |
�Ǐ����鐶�k�̒j�����i���۔�r�j |
���{���܂ߐ�i���ŒႢ�Ǐ����B���E�I�ɓǏ������q���k���L�̊y���݂ƂȂ��Ă���X���̒��A�������̓��ؒ��ł͒j�q�̓Ǐ��������ΓI�ɍ����B |
2009�N |
OECD |
| 3942g |
�w�̓e�X�g���ϓ_�ւ̈ږ����k�̉e���iPISA�����j |
�V���K�|�[���A�A���u���A���Ȃǂ̗�O�������A�����̍��ňږ����k�̐��т͕��ϓ_��������X���B���Ƀh�C�c�ŗ������傫�� |
2015�N |
OECD |
| 3942i |
���Z���̐��������x�̍��۔�r�iPISA�����j |
���{�̍��Z���̐��������x�͑��̓��A�W�A�����Ɠ����悤�ɐ��E�̒��ŒႢ���x���B���������A�W�A�ł͖����x�̒j�q�D�ʓx�͉��ĂȂǂƔ�r���ĒႭ�A���ł����{�͖����x���B�ꏗ�q�D�� |
2015�N |
OECD |
| 3942j |
���{�قǏ��q�����̐��������x���j�q�ɔ�ׂč������͂Ȃ��iPISA�����j |
���q�����͒j�q��萶�������x���Ⴂ�̂����E�̑吨�ł���̂ɁA���{�����͏��q�����̕��������x������ |
2015�N |
OECD |
| 3942k |
�����߂̍��۔�r�iPISA�����j |
��v��i���̒��ʼnp���Ɏ����ł����߂̑������{�B���E54�J���̒��ł�19�ʂƓ��ɑ����킯�ł͂Ȃ����u���Â��܂킷�v�Ƃ��������߂ɂ��Ă͐��E��3�ʂƖڗ����đ����Ȃ��Ă���B |
2015�N |
OECD |
| 3942m |
�����߂��₷���̂́u�ł���q�v���u�ł��Ȃ��q�v���iPISA�����j |
���āE�����ł͐��т̈������k�̕��������߂��₷���̂ɑ��ē��{�ł͐��т̗ǂ����k�̕��������߂��₷�����ʂ����� |
2015�N |
OECD |
| 3942o |
���Z���̃l�b�g���ł͑S���E�I�iPISA�����j |
���E�̂قƂ�ǂ̍��Ŏ������k�̃C���^�[�l�b�g���p���Ԃ�2���Ԃ�傫���z���l�b�g���ł̌X���B�������͓��{��90���Ȃǔ�r�I�Ǐ�y�� |
2015�N |
OECD |
| 3942t |
���Z���̃A���o�C�g�̍��۔�r�iPISA�����j |
���Z1�N�����w�Z�̊O�Ŏ����̓�����d�������Ă��邩�ɂ��Ă͍��ɂ��6���`38���Ƃ����傫�ȈႢ�BOECD����23���ɑ����{�Ȃǎ�������1���O��Ɗw�O�d���͂��Ȃ��X�� |
2015�N |
OECD |
| 3943 |
���w���̏h������鎞�Ԃƃe���r�E�r�f�I�����鎞�ԁi���۔�r�j |
���{�̒��w���́A�S�T�J�����A�h������鎞�Ԃ��ł����Ȃ��A�e���r�E�r�f�I�����鎞�Ԃ��ł������B |
2003�N |
�����Ȋw�� |
| 3944 |
�݊w���̊w�Ǝ��Ԃ̐��� |
���������w�Z�E���Z�̏T�x�Q�����̉e���͊w�Ǝ��ԑ��v�ɂ͂�����Ă��Ȃ��B��w�̃��W���[�����h������̔��]�ɂ��w�Ǝ��ԑ����ڗ����Ă���B |
2006�N |
�Љ����{���� |
| 3945 |
�b�荑�̒n����̈ʒu�̑�w���E���Z���듚�� |
�C���N�̈ʒu�m��Ȃ���w���T���i���{�n���w����j |
2008�N |
���{�n���w�� |
| 3946 |
�s���{���̈ʒu�ɂ��Ă̏��w������ |
�듚����P�ʂ͋{��A��������P�ʂ͖k�C�� |
2007�N |
�����V�� |
| 3947 |
�撣�艮���̂�т艮���i�����Z���ӎ��̐��ځj |
�ڗ����đ�����l���̂�т�u�� |
2002�N |
�m�g�j�������������� |
| 3947a |
�����E���k�̃C���C���x�̐��� |
�o�u�����Ȍ�A�����Z���̃C���C���x�͒ቺ�X���B���w���̃C���C���x�͂� |
2014�N |
�m�g�j���������������A���t�{�� |
| 3947f |
���w���E���w���̂Ȃ肽���E�� |
�Ȃ肽���E�Ə��2�ʁF���w���́A�j�q�ł́A�X�|�[�c�I��A��t�A���q�ł́A�p�e�B�V�G�A�ۈ�m�B���w���́A�j�q�ł́A�X�|�[�c�I��A�������A���q�ł͕ۈ�m�A�Ō�t |
2014�N |
���t�{ |
| 3948 |
�w�K�m�ƕ�K�i���w���j |
��s�s�قǏm�ɒʂ��q�������A��K�����{���Ă���w�Z�͋t�ɏ��Ȃ��B�n�����ł͏m�͏��Ȃ���K�������B�m�ł���s�s�قǕ�K�m���i�w�m�������B |
2007�N |
�����Ȋw�� |
| 3950 |
�w�Z�����̑�GDP��i���۔�r�j |
�����؍��̎��I�����A�Ⴂ���{�̋����䗦�B |
2004�N |
OECD |
| 3952 |
�����̂��Ƃ킴�����L���O |
�������g�������Ƃ킴�ōł������̂͌���22���A���ɑ����̂͋���17���ł���A���⋍�����{�l�̐�����Ȃ��݂��[�����Ƃ�������B���̂ق��A�L�A�ՁA�ցA�n�Ȃǂ��������A�F��0���ł���A�F�͋��P����A���������肷��ɂ͋��낵�����݂�����̂��낤�B |
2000�N |
��g���Ƃ킴���T |
| 3953 |
�Ⴆ���I�m������u���Ƃ킴�v�����L���O |
�g�b�v5�́A�u�S���͈ꌩ�ɔ@�����v�A�u���͋��Ȃ�v�A�u��e��ǂ��҂͈�e���������v�A�u�O���V��v�A�u�o���ς���ΎR�ƂȂ�v�B�]�˒����ȗ��̂��̂��قƂ�ǁB |
2017�N |
goo�����L���O |
| 3954 |
���k�J�ǂ̍��۔�r |
�Ǐ��̂�����ȕč��A�Ǐ����Ȃ��t�����X�ȂǓ쉢�����B�K�[�f�j���O�ɗ]�荷�͂Ȃ����h�C�c����₳���� |
2011�N |
Harmonised European Time Use Survey �ق� |
| 3955 |
�J�^�J�i��̍�������x |
�J�^�J�i����u������v�Ƃ����҂̓X�g���X��94.7������G���t�H�[�X�����g�i�@���s�j��4.6���܂ő傫�ȕ��B�J�^�J�i��̍�������x��5�N�Ԃő傫���㏸�B |
2007�N�x |
������ |
| 3955d |
�d�q���З��p���̐��� |
�d�q���Ђ̗��p�҂��������A2023�N�x�ɂ͓Ǐ�����l��48.4���Ɩ����d�q���Ђ̗��p�̕�������葽���Ɖi20�`30��ł�56�`59���j�B |
2023�N�x |
������ |
| 3956 |
�����̓Ǐ��� |
������46.1���͂P�J���Ɉ�����{�i�G���A�}���K�������j��ǂ�ł��Ȃ��B1�`2���ǂ�ł���҂�36.1���ł���B |
2008�N�x |
������ |
| 3956a |
�ƒ�̑������̍��۔�r |
���ύ����ő��̓A�C�X�����h181���A�ŏ��̓t�B���s��19���A���{��75����38�J����26�ʂƑ����Ȃ��B�������ƓǏ����͔��B�ĊO�Ⴂ�t�����X�̓Ǐ����B |
2009�N |
ISSP |
| 3956f |
�ƒ�̑������̍��۔�r�iPISA�����j |
���{�͕���170����OECD����34�J���̒���13�ʁA�Ώۍ��S��65�������ł�14�ʂƔ�r�I�������������B���3�ʂ̓��N�Z���u���N�A�؍��A�n���K���[�̏� |
2012�N |
OECD |
| 3957 |
�V����ǂ܂Ȃ��Ȃ������{�l |
�s�N���ǂ�ł����V�������͍���҂��ǂރ��f�B�A�ɑ傫���ω� |
2005�N |
�m�g�j�����������Ԓ��� |
| 3957d |
�V��������Ō����ߍw�ǂ��Ă���l�̊��� |
�V���������߂łƂ��Ă���l��2008�N�x��88.6������2020�N�x�ɂ�61.3���ւƒቺ�B����30���32.9���A40���43.1���ɂ܂Œቺ |
2020�N�x |
�V���ʐM������ |
| 3958 |
�����V���̓ǎҗ����۔�r |
�ǎҗ��F���{92���A�A�C�X�����h96���A�h�C�c71���A�č�45���A�t�����X44���A�p��33���ƕ����傫�� |
2008�N |
OECD |
| 3959 |
�V���w�Ǖ����ƃW���[�i���X�g�l���i���۔�r�j |
�w�Ǖ����ł͓��{1�ʁA�č�2�ʁA�h�C�c3�ʁB�W���[�i���X�g�l���ł͕č�1�ʁA���{2�ʁA�h�C�c3�ʁB |
2008�N |
OECD |
| 3959d |
�e���r����̐����F�������Ԃ̒������� |
2�̃s�[�N�����e���r����B�����I�ɓ����ăl�b�g�ɉ����ꍂ��̗v�f�������ƃe���r�������Ԃ͔����B����ɂ��x�����Ȃ���70�N�ɋy�ԃe���r����͏I������������B |
2020�N |
�m�g�j�����������Ԓ��� |
| 3960 |
�P�������蕽�σ��f�B�A���p���ԁF�e���r�E�V���E�C���^�[�l�b�g |
�C���^�[�l�b�g�̗��p���Ԃ��A���߂āA�V����ǂގ��Ԃ��������B |
2004�N |
������ |
| 3960d |
�P�������蕽�σ��f�B�A���p���ԁF�e���r�ƃC���^�[�l�b�g�i�N��ʁj |
����҂̃e���r�ˑ����������ŁA�Ⴂ����ł�2010�N�㏉�߂���l�b�g���p���Ԃ��e���r�������Ԃ�����A���ł�2�{�ȏ�i��҂̃e���r����j |
2019�N |
������ |
| 3961 |
��Ƃ��Ẵe���r�E�V���E�C���^�[�l�b�g |
�Ⴂ����𒆐S�ɐV������C���^�[�l�b�g�֏���傫���V�t�g�A���p�x���t�] |
2008�N�x |
������ |
| 3961d |
��Ƃ��Č������Ȃ����f�B�A�́H |
�V���ƃC���^�[�l�b�g�̊����́A���ꂼ��A2008�N��59��vs29������2020�N��38��vs53���ւƑ�t�]�B�V���A�e���r�͍���Ҍ������f�B�A�ɕω��B |
2020�N |
�V���ʐM������ |
| 3961j |
����ɂ���đ傫���قȂ���m�F��i�F�l�b�g��M���邩�e���r�E�V����M���邩 |
���N�`���ɂ��Ă̕s�m���ȏ���f�}�������������l��55���ɏ�邪�A����ɂ��Ă̐��������̊m�F��i�͎Ⴂ����́u�l�b�g�v�A���N�w�́u�e���r�E�V���v�Ƒ傫�ȃM���b�v |
2021�N |
�V���ʐM������ |
| 3961m |
�N��ɂ���ď��郁�f�B�A���ǂ̂悤�ɈႤ���ɂ��Ă̍��۔�r |
�u��ґw��SNS�Ȃǃl�b�g�n���f�B�A�A���N�w�͐V���A�e���r�Ƃ������������f�B�A���傽���v�����E�I�X���B���{�̓e���r���܂����͂�ۂ��A�č��A�J�i�_�͍���w�܂Ńl�b�g�X�Ƃ����������B |
2017�N�� |
���E���l�ϒ��� |
| 3962 |
��Ƃ��Ẵe���r�E�V���E�g�ѓd�b�̍��۔�r |
��Ƃ��Ă̗��p���͂ǂ̍����e���r�A�V���A�C���^�[�l�b�g�̏��B�e���r�͊T���ė��p�����������V���A�C���^�[�l�b�g�͍��ɂ��傫�ȍ��B |
2005
�`06�N |
���E���l�ϒ��� |
| 3963 |
�V���E�G���ɑ��鍑���̐M���x�i���۔�r�j |
���{�l�̐V���E�G���ւ̐M���x�͐�i���̒��Ńg�b�v�B���ɐ��{�ւ̐M���x�Ƃ̑��Δ{����2.5�{�Ƌɒ[�ɍ��� |
2005�N |
���E���l�ϒ��� |
| 3963b |
�č��ɂ�����}�X���f�B�A�M���x |
�č��ł̓}�X���f�B�A�̐M���x���S�̓I�ɒቺ���钆�œ��ɋ��a�}�x���w����̐M���x�������ɒቺ�B���a�}�x���w�͖���}�x���w���M���Ȃ�Fox News�����M���Ȃ��B |
2025�N |
Gallup�APew Research Center |
| 3964 |
�l�C�e���r�ԑg�x�X�g�e�� |
2010�N�x�̎����o����1�ʂ́uNHK�j���[�X7�v�A�����Җ�����1�ʂ̓e�����́u�����������̂��I�r�㏲�̊w�ׂ�j���[�X�v |
2010�N |
�m�g�j�������������� |
| 3964a |
��㍂�������e���r�ԑg |
���1�ʂ́A1963.12.31�����̑�14��m�g�j�g���̍���i81.4���j�ł���A�����1964�N�̓����I�����s�b�N�A2002�N�̃T�b�J�[�v�t��60����㔼�ő��� |
2002�N |
�����V�� |
| 3964d |
�m�g�j�e���r�ԑg�̒j����N��ʎ����� |
���̘A���e���r�����A��̓h���}�A�j���[�X7�̂�����̔ԑg�ł�����w����Ȏ����ҁi�j60��ȏ�A��50��ȏ��10���ȏ�̍����������j |
2019�N |
�m�g�j�������������� |
| 3965 |
�m�g�j���̘A���e���r�������ώ������̔N�x�ʐ��� |
1983�N�x�u������v�̕��ώ�����52.6�����s�[�N�ɒ����ᗎ�X�� |
2005�N |
�x�䌛��Y�i2006�j |
| 3967 |
NHK��̓h���}�̕��ώ������̐��� |
�ō��̕��ώ��������L�^�����̂�1987�N���f�̓n�ӌ��剉�u�Ɗᗳ���@�v�i39.7���j�A2006�N�u�������ҁv��20.9�� |
2007�N |
�����V�� |
| 3967a |
�m�g�j�g���̍���̕��ώ��������� |
1963�N�i��14��j��81.4���ōō��B1980�N��㔼��70���䂩��50���O��ɋ}�����A���̌�A2005�N�O��܂ł�40���O��ɑQ���B�ŋ߂͂�╜�� |
2013�N |
NHK�N�� |
| 3967d |
�u�Γ_�v�o���҂̕ϑJ |
�ԑg���͂��܂���1965�N�����̎i��҂͒k�u�A��엘�����o�[�͉~�y�A�̊ہA���s�y�A���V�A���������B |
2022�N |
�����V�� |
| 3968 |
��ʎG�����s���������L���O |
�u�T�����t�v��80�������ő��A����ɁA�u�T���V���v�A�u�T������v�A�������u���|�t�H�v�������B |
2007�N |
���{�G������ |
| 3969 |
�R�~�b�N�����s���������L���O |
���N�����R�~�b�N���u�T�����N�W�����v�v���ő��A����Ɂu�T�����N�}�K�W���v�A���������u���Ⴈ�v�A�u�����O�}�K�W���v�A�u�T�������O�W�����v�v�������B |
2007�N |
���{�G������ |
| 3969a |
�����t�@�b�V�������ǎ҃��f����w�����L���O |
�o��l���g�b�v�͐R�w�@��i244�l�j�A���q�吶�l���ɐ�߂�o��䗦�̃g�b�v�͐_�ˏ������q�w�@��i7.2���j |
2010�N |
�T������MOOK��w�����L���O |
| 3969b |
�T�����̓ǎґw |
�����N�w���ǂޏT������A���t�A�V���A�����A�|�X�g�i����A�|�X�g�͒j�������j�B����30��ȏオ�ǂޏ����T�����B��Ҍ������j�����Ə������ɕ������B20��`50�オ�ǂރr�W�l�X���B |
2013�N |
�����V�� |
| 3969e |
�R�~�b�N���̓ǎґw |
10��ɋ������N�W�����v�A20�オ�������N�}�K�W���A���N�T���f�[�A30�`40�オ�������[�j���O |
2013�N |
�����V�� |
| 3969h |
�T�������Ƃ̓Ǐ��� |
�T�����Ǐ����g�b�v�͈�ʎ��ł͏T�����t��12���A�������ł͏������g��13���A�r�W�l�X���ł͓��o�r�W�l�X��4���A�R�~�b�N���ł͏T�����N�W�����v��7�� |
2018�N |
�����V�� |
| 3969k |
�T�����ǎґw�F��40�N�Ԃ̕ϑJ |
�T�����̓ǎ҂͑���������w�Ő�߂��Ă��邪�A�����╶�t�͂��Ƃ��炻���ł���̂ɑ��A�����|�X�g�͂��ẴT�����[�}���ǎґw������������߁B |
2019�N |
�m�g�j���������������A�����V�� |
| 3970 |
�V���e���S�ʍL���y�[�W�䗦 |
�S�ʍL���y�[�W�䗦�͎�v����3���`3��5���ɂ��B����B�X���������]�܂��B |
2005�N |
�{��T |
| 3971 |
�@���Ƃ̐l������ |
�������������@���Ƃ̐l����1995�N�̃I�E���^���������ȗ���� |
2005�N |
�������� |
| 3971a |
�@���S�̂Q���� |
����҂𒆐S�ɐM�������A���̐���M���Ă���50�N�O�Ƃ͈قȂ�A����l�͐M�S�͔����Ȃ�������҂𒆐S�ɂ��̐���M������̂͑����� |
2008�N |
���{�l�̍��������� |
| 3971b |
�@����M�̂����ʼn���M���Ă��邩 |
�_������E�o�T�̋�����M������̂͏��Ȃ��Ȃ�A��Ղ₠�̐��A�����E���ӂ��̗͂�M������̂͑��� |
2008�N |
�m�g�j�������������� |
| 3971c |
���{�l�ɂƂ��Ă̐_�̑��݊��i���ڂƔN��ʂ̈Ⴂ�j |
�_��M����҂͌����Ă��Ȃ��B���{�̔N��͐_��]��M�����A��҂��ނ���M�S�Ԃ����Ƃ����s�v�c�B |
2019�N |
���E���l�ϒ��� |
| 3971d |
���@�������@���S�͑�ɂ�����{�l |
�M�������Ă���҂͑����Ȃ����唼���@���I�ȐS���ɂ��Ă���̂����{�l�̓��� |
2013�N |
���v���������� |
| 3971e |
���{�l�̏@���S�̐��� |
�@���S�͂�␊���ė��Ă��邪�A�u�M��M�S�v�Ƃ������u�@���I�Ȃ�����v���d������Ƃ������{�l�̍l�����͕s�ρB��҂̏@���S�̓o�u�����Ɍ��� |
2016�N |
���v�����������A���{���Y���{�� |
| 3971h |
�_�⎀��̐��E��M����҂̊����̐��� |
������ނ̒������ʂɂ��ΐ_�i���j��M����҂̊����͔g�ł��Ȃ���قډ����A����̐��E�i���̐��j�͒����ɂ���Ă͑����X�� |
2019�N |
���E���l�ϒ����A���{�l�̍����������A���{�l�̈ӎ������AISSP���� |
| 3972 |
���w�q�̑����_�Е��t�x�X�g10�̕ϑJ |
1980�N��ȍ~�A���j�̂����[���Ȃ������s�s�̂ǐ^�Ɉʒu���閾���_�{�ւ̎Q�q�q�����w�x�X�g���� |
2007�N |
�x�䌛��Y�i2006�j�A�x�@�� |
| 3973 |
�S���̐_�АM�� |
�S��8���Ђ���_�ЁB�n��ʎА��ł͐V�����g�b�v�A���ɁA����������Ɏ����B�M�Ƃ��Ă͔����M���ł������A�ɐ��M�A�V�_�M������Ɏ����B |
1995�N |
�����V�� |
| 3974 |
�_�ЁE���t�A�s�y�n���ւ̐����O�����̐l�o |
40���l�ȏ�̐l�o�̂���_�Е��t�͑S����50�߂����邪�A�l�o���������ƂŖڗ����Ă���̂́A�����{�ł͖����_�{�A���c�R�A����t�A�����{�ł͕�����ׁA�Z�g��� |
2009�N |
�x�@�� |
| 3975 |
�����_�А푈�ʍ��J�Ґ� |
�����_�Ђɍ��J�҂͖����ېV�̎u�m�ɂ͂��܂��Q�����E����v�ҁi��Ƃ��܂ށj�܂�246���l |
2004�N |
�����V�� |
| 3976 |
��ڕʃX�|�[�c�l���i���{�l���Ǝ��{���j |
�X�|�[�c�l����������ڂ́A�E�H�[�L���O�A�{�E�����O�A���j�A�S���t�A�o�h�~���g���A�싅�A�T�b�J�[�A�싅�i����܂ށj�̏� |
2004�N |
�X�|�[�c���� |
| 3976e |
�j���N��ʃX�|�[�c�s���җ� |
�ቺ���Ă����X�|�[�c�s���җ����e�N��ŏ㏸�ɓ]���� |
2016�N |
�Љ����{���� |
| 3976a |
���{�l�̍s���X�|�[�c�E�����L���O |
�����̂͑S�̂ł̓E�H�[�L���O�A�{�E�����O�A���j�A�W���A10��j�q�ł̓T�b�J�[�A�싅�A���j�A�{�E�����O |
2011�N |
�Љ����{���� |
| 3976c |
���{�l�̊ϐ�X�|�[�c�E�����L���O |
�{�݊ϐ�ł̓v���싅�A���̑��̖싅�AJ���[�O�A�e���r�ϐ�ł́A�v���싅�B�t�B�M���A�X�P�[�g�A���Z�싅�̏��B�e���r�ϐ�Ƃ������{�݊ϐ킪�������J���[�O�E�T�b�J�[ |
2010�N |
�X�|�[�c���� |
| 3976g |
�ł��D���ȃX�|�[�c�I��g�b�v10 |
�ł��D���ȃX�|�[�c�I��P�ʂ̍��̓C�`���[��������߂Ă������A2014�N�͐�c�^���������I��ł͂��߂ĂP�ʂƂȂ��� |
2014�N |
���������� |
| 3976h |
���{�l�̍D���ȃv���X�|�[�c |
�����I�ɒቺ�X���ɂ���v���싅�Ə㏸�X���ɂ���v���T�b�J�[�Ƃ̍����k�܂����B�告�o�̓v���싅������l�C����傫����� |
2015�N |
���������� |
| 3977 |
�v���X�|�[�c�ϋq������ |
�싅�A�T�b�J�[�A���o���ϋq�������x�X�g�R�B���c���Z�͋����A���ցA�������n�̏��B |
2004�N |
�X�|�[�c���� |
| 3977a |
���{�l�̍D���ȃv���싅�`�[�� |
�l�C�x��ʂ͓ǔ��W���C�A���c�A2�ʂ͍�_�^�C�K�[�X�A3�ʂ͕����\�t�g�o���N�z�[�N�X�B�ߋE�ł͍�_�^�C�K�[�X�̐l�C�����|�I�B |
2007�N |
�m�g�j�������������� |
| 3978 |
�v���싅���l��i�C�^�[�̃e���r�������̐��� |
�싅�E���l�펋�����A�����ᗎ�X���ɂ���A�ŋߓ��ɒቺ |
2006�N |
�W���p���A���}�i�b�N |
| 3978a |
�C�`���[�̔N�x�ʈ��Łi�q�b�g�j���̐��� |
�僊�[�O�j��A�O�l������9�N�A��200�{���ł�B�� |
2009�N |
�����V���� |
| 3978c |
��J�ĕ��I��̔N�x�ʒ��Ŗ{���̐��� |
�N�ɓ��{�n�������2�{�ȏ�̃z�[�����������W���[�ŕ����Ă����J�ĕ��I��B2023�N�ɂ�MLB�̖{�ۑʼn��ɋP�����B����ɓ�ۑŁA�O�ۑł̖��͂��������Ȃ��B |
2024�N |
�X�|�[�c�i�r |
| 3978e |
���{�l�僊�[�K�[�F�N��̐��� |
�c�����哊�肪�đ僊�[�O�̃����L�[�X�ƌ��_����z�͑��z�ł��N�_���Z�ł��ߋ��ő� |
2014�N |
�����V���ق� |
| 3978h |
���Ȃ��ݑI��̏��q�e�j�X���E�����L���O�̕ϑJ |
�S�ăI�[�v���ɑ����S���I�[�v���ŗD���������Ȃ��ݑI�肪�A�W�A�����̐��E�����L���O1�ʂ��m�� |
2019�N |
WTA |
| 3979 |
�T�b�J�[�E���[���h�J�b�v�i�v�t�j���уf�[�^ |
�D��5��̃u���W�����g�b�v�A4��̃C�^���A�A3��̃h�C�c�������Ă���B�O��̓g���R�A�؍��ƃA�W�A�������߂ď�ʐi�o����������͌����g�[�i�����g�ɂ��c�ꂸ�B |
2006�N |
�e�h�e�` |
| 3979f |
�T�b�J�[�E���[���h�J�b�v�i�v�t�j���{��\�̐��ѐ��� |
2014�N�u���W�����͎c�O�Ȃ���Q�s�P�����łP�����[�O�s�ށB����܂ł̍ō����т̓x�X�g16 |
2014�N |
�����V�� |
| 3979h |
�T�b�J�[�E���[���h�J�b�v�i�v�t�j���{��\�̔N��E�o�g�E����ꏊ |
���[���h�J�b�v�E���V�A���̓��{��\�I��̓����͕��ϔN������A���[�X�o�g�ҁA�C�O�g�������_ |
2018�N |
�����V�� |
| 3979a |
2006�N���[���h�J�b�v�i�v�t�j�h�C�c���o�ꍑ�̃T�b�J�[�֘A�w�W |
���{��FIFA�����L���O�̓u���W����1�ʂɎ���17�ʂƂȂ��Ă���A�N���A�`�A��24�ʁA�I�[�X�g�����A��44�ʂ𗽂��ł���B |
2006�N |
FIFA�A�����V�� |
| 3979b |
2011�N���q�v�t�h�C�c���Ȃł����W���p���̐g�� |
���{��\�u�Ȃł����W���p���v�̐g���͕č��I���h�C�c�I��Ɣ�r���Ă��Ȃ�Ⴉ���� |
2011�N |
�e���T�b�J�[����g�o�� |
| 3610 |
�����I�����s�b�N�Ŋy���݂ȋ��Z |
�����I�����s�b�N�ł̊��҂��傫�����Z�g�b�v3�͐��j�i���j�j�A����i�}���\���j�A�̑��B��N����2�ʂ�3�ʂ��t�]�B |
2019�N |
���������� |
| 3612 |
�e���ŊS�̍����I�����s�b�N���Z |
2024�p���ܗ֒��O�̒����ɂ��ƁA���[���b�p�ł͗��㋣�Z�ւ̊S�������i���{�����������j�A��Ăł̓T�b�J�[�ւ̊S�������B�����ł͑싅�A�؍��ł̓A�[�`�F���[�A�}���[�n�����ł̓o�h�~���g�����S�x�g�b�v�B |
2024�N |
Ipsos |
| 3620 |
���E�e���̉j����҂̊��� |
�j����҂��ł��������̓X�E�F�[�f���i95.1���j�ł���A�I�����_�A�m���E�F�[������Ɏ����B���{��62.5���A38�ʂƂ��������Ȃ��B�ł����Ȃ��̂̓������_��14.7���B�w�Z����Ƃ̑��ւ��傫���B |
2019�N |
OECD |
| 3680 |
���O�r�[W�t���{���ɂ�������{��\�I��Ƒΐ푊��̐g���E�̏d�� |
�C�O�o�g�I��������������{��\�I����S�̂Ƃ��đ傫���Ȃ����Ƃ͂����A�Ȃ��A�C�O�̑�\�I��Ƃ͑̊i�������݂��Ă��� |
2019�N |
World Rugby |
| 3980 |
�I�����s�b�N�E���_�����i�����_�����j�̐��� |
�A�e�l�E�I�����s�b�N�ŋ����_�����ߋ��ő��^�C�A���_�������ߋ��ō� |
2004�N |
�V�� |
| 3981 |
�I�����s�b�N���_�����ƌo�ϋK�͂Ƃ̑��� |
�l�����_�����͌o�ϋK�́i�l���K�́~��l������GDP�j�ɔ�Ⴗ��B�o�ϋK�͂̊��ɏ��Ȃ����{�̃��_���� |
2016�N |
sports-reference.com�AYahoo |
| 3982 |
�I�����s�b�N���Q���̍����E�I�萔�̐��� |
1896�N��P��A�e�l����Q�����E�n�搔�A�I�萔�Ƃ��Ɋg��̈�r�����ǂ��Ă����B�����I��䗦�̏㏸���ڗ��� |
2008�N |
IOC |
| 3983r |
�p���I�����s�b�N�e���l�����_���� |
�e���̊l���������_����
�@�Q�l�F���{���_���������@�O�����e�����_�����@�O�X�I���e�����_���� |
2024�N |
���t�[�ق� |
| 3983t |
�����I�����s�b�N�e���l�����_���� |
�e���̊l���������_����
�@�Q�l�F���{���_���������@�O�I���e�����_�����@�O�X���h���e�����_���� |
2021�N |
���t�[�ق� |
| 3983v |
���I�f�W���l�C���I�����s�b�N�e���l�����_���� |
�e���̊l���������_����
�@�Q�l�F���{���_���������@�O���h���e�����_�����@�O�X��k���e�����_���� |
2016�N |
�e�� |
| 3983z |
�����h���I�����s�b�N�e���l�����_���� |
�e���̊l���������_����
�@�Q�l�F���{���_���������@�O��k���e�����_�����@�O�X��A�e�l�e�����_���� |
2012�N |
�e�� |
| 3984 |
�k���I�����s�b�N�e���l�����_���� |
�e���̊l���������_����
�@�Q�l�F���{���_���������@�O��A�e�l�e�����_���� |
2008�N |
�V�� |
| 3985 |
�A�e�l�I�����s�b�N�e���l�����_���� |
���{�̋����_���͕č��A�����A���V�A�A�I�[�X�g���A�Ɏ�����T�ʁA���_�������̓h�C�c�Ɏ�����U�� |
2004�N |
�V�� |
| 3986 |
�~�G�I�����s�b�N�e�����_���l�����̐��� |
�h�C�c�A�č���1�`2�ʂň���B�J�i�_�㏸�B�����A�؍������i���钆�A���{��98�N�������10�ȍ~�ӂ��Ȃ��B |
2006�N |
�����V�� |
| 3987 |
�~�G�I�����s�b�N�ɂ�������{�̃��_�����i���⓺���_���j |
����܂ł̃��_���l�����Ƃ��ẮA98�N����~�G�ܗւ����T�A���v10�ōő��B |
2006�N |
�����V�� |
| 3987t |
�~���m�E�R���e�B�i�~�G�ܗւ̊e�����_���� |
�֘A�}�^�F�~�G�ܗւł̂���܂ł̓��{�̃��_�����A�O���k���~�G�ܗ֊e�����_���� |
2026�N |
���t�[ |
| 3987s |
�k���~�G�ܗւ̊e�����_���� |
�֘A�}�^�F�~�G�ܗւł̂���܂ł̓��{�̃��_�����A�O���s�����`�����~�G�ܗ֊e�����_���� |
2022�N |
���t�[ |
| 3987l |
�s�����`�����~�G�ܗւ̊e�����_���� |
�֘A�}�^�F�~�G�ܗ֓��{���_���������A�O���\�`�~�G�ܗ֊e�����_���� |
2018�N |
���t�[ |
| 3987m |
�s�����`�����~�G�p�������s�b�N�̊e�����_���� |
���{�͋�3�A��4�A��3�̍��v10�̃��_���l���B�C�O���ő�11������2010�N�o���N�[�o�[���ȗ���2�� |
2018�N |
���t�[ |
| 3987n |
�\�`�~�G�I�����s�b�N�̊e�����_���l���� |
�֘A�}�^�F�~�G�ܗ֓��{���_���������@�O��o���N�[�o�[�e�����_���� |
2014�N |
�����V�� |
| 3987p |
�o���N�[�o�[�~�G�ܗ֊e�����_���� |
��4���ڂ܂łł̓��_�������͕č����P�ʁB�����_�����ł̓X�C�X���P�ʁB��4��2��15���i���{����16���j�ɓ��{�l���X�s�[�h�X�P�[�g500���[�g���ŋ�_���Ɠ����_���l�� |
2010�N |
�����V�� |
| 3987q |
�o���N�[�o�[�~�G�p�������s�b�N�̊e�����_���l���� |
���{�͋�3���܂ތv11�̃��_�����l���B�O��g���m����9���������B |
2010�N |
������HP |
| 3988 |
�g���m�~�G�ܗ֊e�����_�����i�y�щߋ��ݐϊl�����j |
���݂̓��_�������Ńm���E�F�[�P�ʁB�ߋ��̃��_���l�����́A�h�C�c�A���V�A�A�m���E�F�C���P�ʁ`�R�ʁB���{��13�ʁB |
2006�N |
�����V���A�����V�� |
| 3988k |
�l�Ԃ͂ǂ��܂ő��������̂� |
�������Z�̐��E�L�^���猩��Ə����̑���X�s�[�h�͋����n�⋣�����Ɠ��l����ɒB���Ă��邪�j���̏ꍇ�̓��W�X�e�B�b�N�Ȑ�����Ȃ��㏸ |
2008�N |
Mark Denny�i2008�j |
| 3988m |
�^�����Z�ɂ�����j���̍� |
���{�V�L�^�ł͗��㋣�Z�Ŗ�15���A���j���Z�Ŗ�9���̒j�����B���̑��̋��Z�̉^���\�͂ł͂���ɍ��͊J���A�싅��z�b�P�[�̓���ł�50���ȏ�̍��܂ŁB |
1993�N |
��ؗ��Y�i1996�j |
| 3988p |
����j�q100m�̐��E�L�^�E���{�L�^�̐��� |
���݁A���E�L�^�̓E�T�C���E�{���g��9�b58�i2009�N�j�A���{�L�^�͈ɓ��_�i��10�b00�i1998�N�j |
2009�N |
�����V�� |
| 3988s |
���j�j�q100m���R�`�̐��E�L�^�E���{�L�^�̐��� |
���݂̐��E�L�^�̓u���W���̃Z�[�U���E�V�G���I���46�b91�i2009�N�j�A���{�L�^�͒������I���47�b87�i2018�N2���j |
2018�N |
�E�B�L�y�f�B�A |
| 3989 |
�t�B�M���A�X�P�[�g���{���q�̃I�����s�b�N�ō����т̐��� |
2006�N�g���m�~�G�ܗւōr��Í��I��A���{�l���A�����ĉ��ĈȊO�ŏ��̋����_���l�� |
2006�N |
�����V�� |
| 3989q |
�t�B�M���A�X�P�[�g���{�j�q�̃I�����s�b�N�ō����т̐��� |
2018�N�s�����`�����~�G�ܗւʼnH�������I��A2���A�������_���B�ܗ�2�A�e�͒j�q�t�B�M���A�ł�66�N�Ԃ� |
2018�N |
JOC |
| 3989s |
���{�l�̂悭����X�|�[�c�E�悭����X�|�[�c |
���3�ʂ�g����ƁA�悭����X�|�[�c�E�^���̓E�H�[�L���O�A�S���t�A�t�B�b�g�l�X�A�싅�A�悭����X�|�[�c�͖싅�A�T�b�J�[�A�o���[�{�[�� |
2007�N |
ISSP |
| 3989t |
�X�|�[�c���D�x�̍��۔�r |
�X�|�[�c������̂�����̂��D���ȍ��̓j���[�W�[�����h�A�X�C�X�A�؍��ȂǁA�����肷������D���Ȃ̂̓t�����X�A��p�A�����茩������D���Ȃ͓̂��{�A�t�B���s���A�|�[�����h�A�ǂ���̗]�T���Ȃ��̂����V�A�A�u���K���A |
2007�N |
ISSP |
| 3989u |
�싅�E�T�b�J�[�E�e�j�X�E�S���t���D�x�̍��۔�r |
���D�x�����荑�ɏW�����Ă���싅��S���t�œ��{�̈��D�x�͐��E1�`3�ʁB���E���Ƀt�@���̑����T�b�J�[�ł͏��ʂ͍����Ȃ��B�e�j�X�͂���X�|�[�c�ł͐��E3�ʂ�������X�|�[�c�Ƃ��Ă͈��D�ҏ��Ȃ� |
2007�N |
ISSP |
| 3989z |
�o���[�{�[���E�i���Z�E�o�X�P�b�g�{�[�����D�x�̍��۔�r |
�o���[�{�[����i���Z�͓��{�ň��D�҂������X�|�[�c�����A����ɑ��ăo�X�P�b�g�{�[���͂��Ƃ��Ƃ͓��{�l�ɂȂ��݂��]��Ȃ������X�|�[�c�B�����3���Z�̐l�C�͂Ȃ�ƃt�B���s�������E1�B |
2007�N |
ISSP |
| 3989a |
�����E�S�̂���X�|�[�c�̎�v����r |
���Ă͖싅���l�C�B�p���ƃh�C�c�ł̓T�b�J�[���P�ʁB�t�����X�͂P�ʂ��e�j�X�ŃT�b�J�[�ւ̊S�͈ӊO�ƒႢ�B |
2001�N |
�d�ʑ��� |
| 3989b |
���O�r�[�̋��Z�l���Ɛ��E�����L���O |
���Z�l����ʂQ�ʂ̓C���O�����h�A��A�t���J�A���E�����L���O��ʂQ�ʂ̓j���[�W�[�����h�A�I�[�X�g�����A |
2007�N |
�����V�� |
| 3989c |
���{�l�̍D���ȁu����X�|�[�c�v�����L���O |
�x�X�g�T�́A�v���싅�A���Z�싅�A�t�B�M���A�X�P�[�g�A�}���\���A�w�`�B�Ⴂ�j���̓T�b�J�[�A�����̓t�B�M���A�X�P�[�g�Ȃǐl�C�X�|�[�c�ɂ͐����j���ō��B�D���ȃX�|�[�c�I��͍��ۊ����I��A�����I��B |
2007�N |
�m�g�j�������������� |
| 3989e |
�j�q�}���\���̐��E�L�^�̐��� |
2����3��59�b�̐��E�L�^��@���o�����n�C���E�Q�u���V���V�G�I��i�G�`�I�s�A�j��2���Ԃ��ɂ�20�N������Ƃ̒k |
2008�N |
�����V�� |
| 3989j |
�j�q�}���\���̓��{�L�^�̐��� |
2018�N�̓����}���\���Ő݊y�I���I�肪16�N�Ԃ�ɓ��{�L�^��5�b�X�V����2�ʂ� |
2018�N |
�����V�� |
| 3989k |
���q�}���\���̐��E�L�^�E���{�L�^�̐��� |
���q�}���\���͒j�q�}���\���ƈقȂ��Đ��E�L�^�A���{�L�^��10���N�ȏ�j���Ă��Ȃ��B���q�̏ꍇ�L�^�̌��E�ɓ��B���Ă���Ƃ�����������B |
2018�N |
���C���X�T�C�g |
| 3989f |
���E�̃}���\����� |
�j���[���[�N�V�e�B�A�x�������A�����h���A�V�J�S�̃}���\������3���l�ȏ�̊����Ґ��B���ʃ}���\�����͕č�21�A�C�^���A18�A���{�A�J�i�_13�Ƒ����B |
2008�N |
�����V�� |
| 3989m |
���{�̃}���\����� |
�Q���l���g�b�v3�́A�����}���\���i2���j�A���}���\���i10���A���N11���j�A�m�`�g�`�}���\���i12���j |
2017�N |
�����V�� |
| 3989g |
�告�o�O���o�g�͎m�̐l�� |
�����S���o�g�͎m�����48�l�A����34�l�ƍő��B���͎m���ł̓n���C���S�̕č��A�����ău���W���A�؍��A��p�Ƒ����B |
2009�N |
�����V�� |
| 3989h |
�����̑S���� |
�D��25����ւ鉡�j�������ꏊ���D�����Ă��������m�l�ɑ���\�s���ň��ӈ��� |
2010�N |
�����V�� |
| 3989l |
���Q�̉��j�S���� |
��Q��32�������D����45��Ȃǐ��X�̋L�^���c���Ă����剡�j���Q�����Ɉ��ނ��� |
2021�N |
�����V�� |
| 3989p |
��㉡�j�̏o�g�n |
���j�y�o�l���̍ł������͖̂k�C����8�l�ł���A�X����6�l�A�����S����5�l�A�����ċ{��A���A��t�A�����A�������̊e�s����4�l�������Ă���B���j�Ȃ���16�{���B |
2023�N |
���{���o���� |
| 3990 |
�Ñ�l�̊S�A���E�� |
���t�W�̓o���1�`3�ʂ́A�n�M�A�E���A�}�c�A�����̓u�h�E�A�R���M�A�C�`�W�N�B�L�N�A�T�N���͒����ȍ~�ɉ��ǁA���w�����i�ށB |
�� |
�������� |
| 3990a |
�����o��̋G�ꃉ���L���O |
�x�X�g�T�͉ԁE���A�~�A���J�A��A��B�H�~�ɕЊ��m�ԂƔ�ׂ�ƕ����̋G��͎l�G�ɂ킽�葽�ʁB |
�]�ˎ��� |
���c�^�ꑼ |
| 3991 |
���{�l�̍D���ȉԂ�̃����L���O |
�Ԃ��������g�b�v�B�S�̂Ƃ��ĉԂ�Ƃ������A�������ł�C����������Ă��Ă���X���B |
2007�N |
�m�g�j�������������� |
| 3992 |
�]���u���[�S���E�}�b�J�[���o���v�e���y�[�W�� |
�S20���̂����Œ��́u��Łv�A�����Ɂu�W�F���~�i�[���v�u��n�v������ |
1893�N |
���q�G�� |
| 3993 |
�i�n�ɑ��Y���ҏ����y�[�W�� |
�������Ɂu�ĂԂ��@���v�u��̏�̉_�v�u�̉Ԃ̉��v�u���n���䂭�v�u�����蕨��v |
1984�N |
���|�t�H |
| 3994 |
�~�X�e���[���Е��Ϗd�ʂ̐��� |
���[�v�������ւ̓]���ɂ��A�~�X�e���[�{�̏d�ʉ��X������ |
2000�N |
�x�䌛��Y�i2006�j |
| 3995 |
�Z�N�V�[����������Ƃ���i���۔�r�j |
�A�W�A�́u���v�A�k���́u�܂Ȃ����v�u�ԓx�E�p���v�A�����E�쉢�́u���K�v |
2004�N |
Durex�� |
| 3996 |
����̐��E��M���邩�ǂ����̒n�捷�i���E�Ɠ��{�j |
�����M���Ȃ��l�̓G�W�v�g��0������x�g�i����77.6���܂ŕ��L�����A���{�ł͉����22.3������{���44.8���܂�22.5���|�C���g�̍��Ƒ��ΓI�ɏ����� |
2000�N |
���E���l�ϒ����A�m�g�j�S�������ӎ����� |
| 3997 |
�f��D���̍��� |
�č��l�͐��E�ōł��f��D���B�A�W�A�ł͍��`�A�C���h�ʼnf��D���������B |
1999�N |
���E�̓��v |
| 3998 |
���{�l���D���ȓ��{�̗��j��̎��� |
���a�i���j���g�b�v�ł��邪�O���藦�͑傫���ቺ�B�������u�[���f���]�ˎ��オ2�ʂɏ㏸�B |
2007�N |
�m�g�j�������������� |
| 3998a |
�N��ʂ̔ˍZ�y�ы��Ȗڂ̐ݒu�� |
�]�ˎ���A�ː����v�ƂƂ��ɐݒu���������Ȃ����ˍZ�B�Ȗڂ������̎�w����m�w�ȂǑ��l���B |
1871�N |
�����V�� |
| 3998d |
��㌳���\�i�����\�`���j |
�����\�`���̗�㌳���\���s�҂ɂȂ���č쐬���Ă݂� |
2019�N |
�V�ړ��{�j |
| 3999 |
���N�ʐM�g400���N�L�O�u���N�ʐM�g�Č��s��v�̍s��l���i2007�N�j |
�ő�̓v�T���s��2000�l�K�́B���{�ł́A�Δn�s��400�l���ő�A�n�悲�Ƃł�2���ɂ킽��2��̍s�s��ꂽ�É��s���ő� |
2007�N |
�e���� |
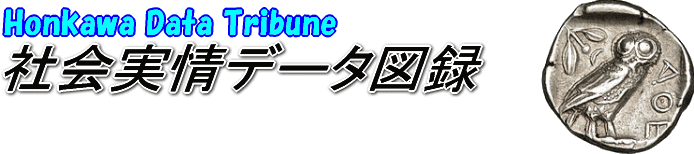
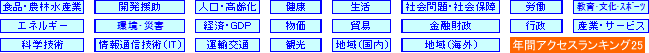

 �@�@���ʔ�
�@�@���ʔ�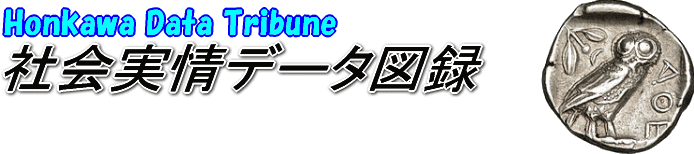
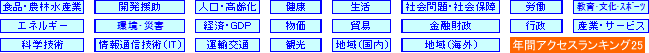

 �@�@���ʔ�
�@�@���ʔ�