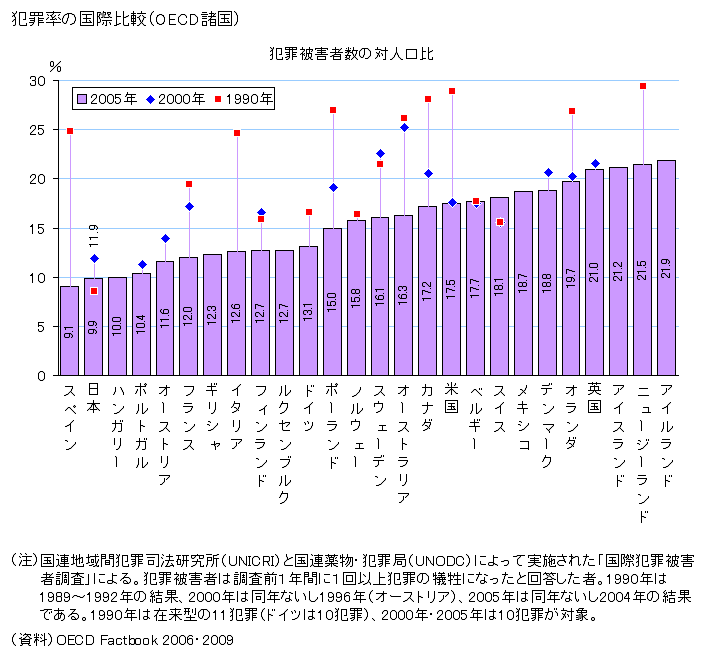
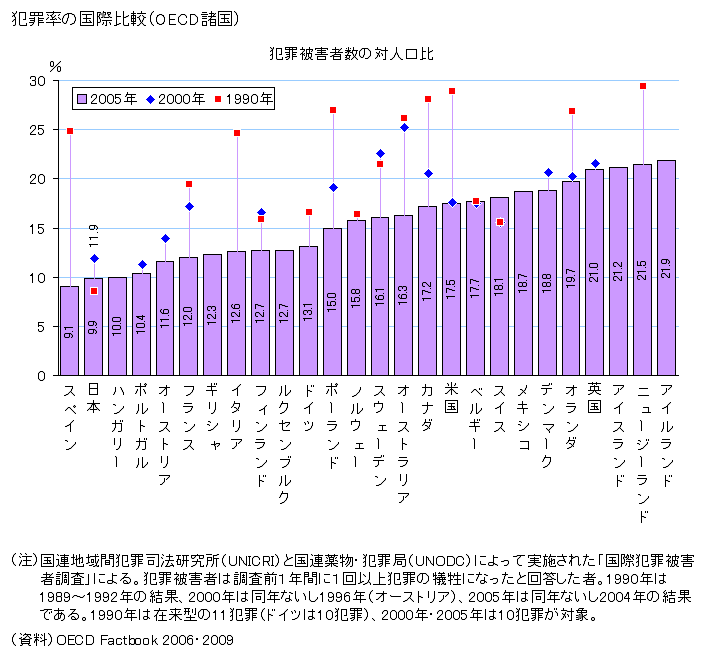
国際犯罪被害者調査は世帯を対象として行われ、世帯員のうち過去1年間に犯罪の犠牲となったかを調べている。ここで被害率の対象となっている犯罪は非在来型の消費者詐欺、汚職を含まない在来型の10犯罪であり、具体的に犯罪名を原語や注釈とともにあげると、自動車泥棒(Theft of cars)、車上荒らし(Theft from or out of cars)、オートバイ泥棒(Motor-cycle theft)、自転車泥棒(Bicycle theft)、侵入窃盗(Burglary with entry、窃盗未遂を含む)、侵入未遂(Attempted burglary)、私物盗難・すり(Theft of personal property and pick-pocketing)、強盗(Robbery)、女性に対する性犯罪(Sexual offences against women、一部犯罪とならない性暴力を含む)、暴行・脅迫(Assaults or threats、性暴力以外の家庭内暴力を含む)である。私物盗難・すり以降は世帯員のうち回答者本人への犯罪についての被害が対象となっている。なお1990年データはこれらに加えて自動車損壊を含む11犯罪が対象となっている。 在来型10犯罪と非在来型2犯罪の各々の犯罪被害者率については、日本とOECD平均について図録2788cに掲げた。 犯罪に関する業務統計とここで使用する調査統計の結果を比較すると、多くが自動車関連の犯罪である点は共通であるが、暴行、特に性的暴行はほとんどの国で業務統計上は報告されることが少ないとのことである(OECD Factbook 2006)。 日本の犯罪率は、2005年に9.9%とスペインを除いて先進国中最低である。1990年の8.5%から2000年の11.9%へと増加したが、その後2005年にかけては再度9.9%へと減少している。図には掲げていないがOECD諸国の平均も2000年から2005年にかけて犯罪率は18.5%から15.5%へと低下している。日本の対OECD比は、同じ時期に0.645から0.639へと低下しており、相対的にも犯罪の少ない国としての地位を高めている。 すなわち、犯罪が増えているという当局やマスコミの発表とは異なり、日本は依然として犯罪の少ない安全な国であり、また安全な国としての地位をさらに高めているのである。 興味深いのは犯罪率の高低と治安への不安の程度は比例しないということである。以下に、同じ調査の中で行われた不安度調査の結果と犯罪率の相関図を掲げた。 これを見ると、日本の犯罪率は最低水準であるが治安への不安(体感治安)は、35%の人が感じており、最も高いレベルにある。それだけ日本人は治安に対して敏感であるということがうかがわれる。日本とは対照的に、犯罪率がトップレベルにあるアイスランドは治安への不安度は最低レベルである。泥棒が多いと自他共に考えているイタリアで実際は泥棒が少ないという点について図録2788gでふれた。格差の実態と格差意識の間にも同様の相関があるという点については図録4677参照。 体感治安と犯罪率との相関については図録2785aにも掲げた。こちらでは途上国まで数に入れると犯罪率が低いほど体感治安も良くなるが、先進国のみだと両者に明確な相関が見られなくなることを示した。 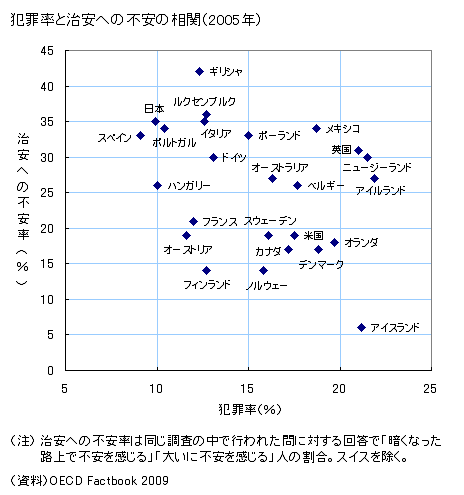 こうした点は、暮らしの質や幸福度を研究してきた者には常識となっているようである。犯罪のリスクがそれらに及ぼす影響について、スティグリッツ委員会報告書(2010年)は、以下のように述べている。
「たとえば犯罪のように、それほど極端(稀?−引用者)ではない要因による危険を感じることにより、きわめて多くの人びとにとって暮らしの質が低下している。それよりもっと多くの人びとが身体に危害を加えられるのではないかという恐怖感を訴えている。 主観的犯罪の恐怖を感じているという人びとの訴えで際立っていることの一つは、恐怖感が実際に犯罪を受けた経験とはあまり関係ないことである。犯罪の恐怖を訴える人びとの多い国々で、犯罪の被害率が高いという事実はない。 その一方で、国内では高齢者と富裕者ほど、若者や貧困者よりも身の危険を感じると訴えているが、実際に犯罪の被害者になる確率は、より低い。 こうした事実は、この問題について公開討論を開始するには、個人の安全度に関する、もっと定期的で信頼できる数値の計測が重要であることを示している。被害者調査は犯罪の頻度と犯罪が引き起こす恐怖感を評価するために必要不可欠である。家庭内暴力や、闘争や戦争に苦しんでいる国々での暴力などによる個人的な身の危険など、他人の脅威を評価するには、他の手法を活用する必要がある。」(ジョセフ・E. スティグリッツ、ジャンポール フィトゥシ、アマティア セン「暮らしの質を測る―経済成長率を超える幸福度指標の提案 警察官密度が高いほど犯罪率が低下する傾向については図録5196参照。 多くのOECD諸国でも犯罪は減少傾向にある(図録9610参照)。犯罪の減少が目立っているのは、米国、カナダ、オランダ、ポーランドである。特に米国は、1990年段階では、世界1の水準であったが(よく言われた「犯罪大国米国」)、2000年と2005年には犯罪率の中位水準にランクされるに至ったため、それだけ余計に、目立っている(図録8808参照)。 米国の犯罪率が低下した後、2005年段階で、犯罪率が高いことで目立っているのは、アイルランド、ニュージーランド、アイスランド、英国といった諸国であり、これらの国は犯罪率が20%を越えている。 同じ調査から途上国の主要都市の犯罪率を図録9370に示した。 なお、一般論として、犯罪発生件数やその増加を取りまとめるのは、犯罪の取締当局(警察)自体であり、犯罪統計の発表の仕方も予算獲得のため犯罪の増加や警察官の不足、国民の安全確保ニーズを強調しがちとなる傾向があると見た方がよかろう。他殺者数が積極的には公表されない点にもこうした傾向がうかがわれる(図録2776参照)。また、部署の成績をあげるための意図的な改ざんも発生しがちである。すなわち、犯罪統計のような、業務上、副産物的に得られる業務統計は、よくよく吟味して使う必要がある。この点については図録作成方針、及び以下のコラムを参照されたい。
調査の対象国は26カ国であり、犯罪率の低い順に、スペイン、日本、ハンガリー、ポルトガル、オーストリア、フランス、ギリシャ、イタリア、フィンランド、ルクセンブルク、ドイツ、ポーランド、ノルウェー、スウェーデン、オーストラリア、カナダ、米国、ベルギー、スイス、メキシコ、デンマーク、オランダ、英国、アイスランド、ニュージーランド、アイルランドである。 (2006年9月23日収録、2009年4月11日更新、2014年8月14日スティグリッツ委員会報告書引用、2014年12月21日コラム追加、2015年8月28・29日各犯罪名改訂、2023年10月4日業務統計のいいかげんさ事例)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||