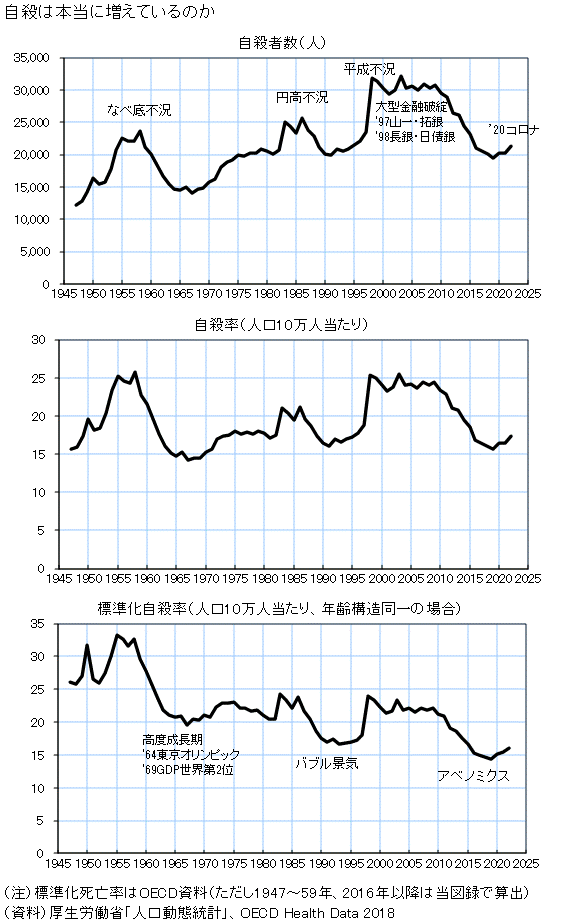
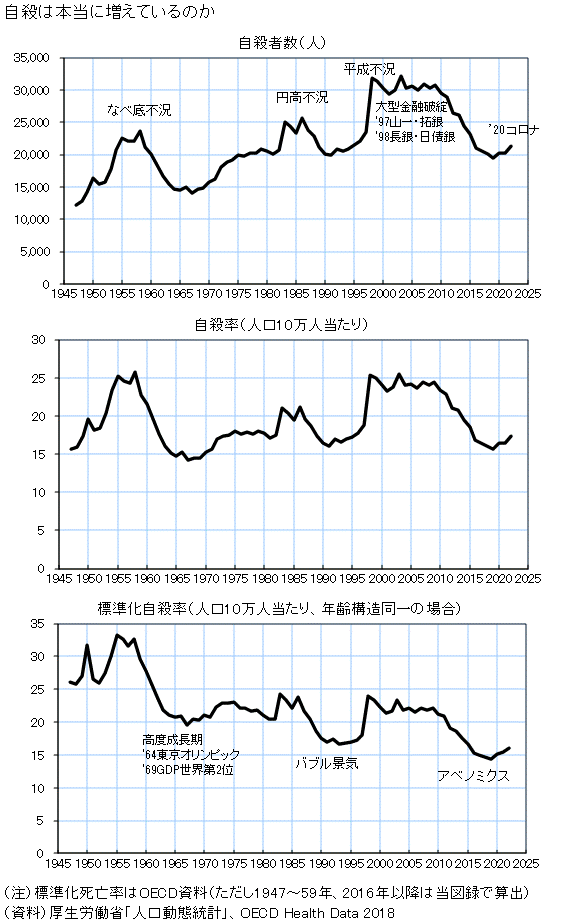
| 丂 | 丂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偼偠傔偵 丂1998擭埲崀2010擭偛傠傑偱帺嶦幰悢偑偐偮偰側偄婯柾偺枅擭3枩恖悈弨偲偄偆堎忢帠懺偑懕偄偰偄偨丅恾榐傪嶌惉偟偨2013擭摉帪偲堎側傝丄僞僀僩儖偼乽帺嶦偼杮摉偵憹偊偰偄偨偺偐乿偵曄偊偨曽偑揔愗偱偁傞偑丄嶌惉摉帪偦偺傑傑偵偟偰偄傞丅偲峫偊偰偄偨傜丄僐儘僫壭偵傛傞帺嶦憹偺忬嫷偲側傝丄嵞搙丄摉弶偺昞戣偑彮偟摉偰偼傑偭偰偒偰偄傞丅 丂帺嶦幰悢偑3枩恖儗儀儖偲憹壛偟偨棟桼偼丄摨帪婜偵怺崗壔偟偨幮夛娐嫬偺曄壔偵媮傔傜傟傞偲偄偆偺偑堦斒偺棟夝偩偭偨丅帺嶦懳嶔傕偙偆偟偨棟夝偐傜摫偐傟偰偄傞応崌偑懡偄丅 丂埲壓偼乽帺嶦3枩恖愗傞丂幮夛慡懱偱庢傝慻傒傪乿偲戣偝傟偨枅擔怴暦偺幮愢乮2013擭1寧27擔乯偱偁傞偑丄偙偆偟偨堦斒揑側棟夝傪偁傜傢偟偰偄傞偲偄偊傛偆丅 乽嶐擭偺帺嶦幰偼2枩7766恖乮寈嶡挕偺懍曬抣乯偱丄15擭傇傝偵3枩恖傪妱偭偨丅3枩恖偲偼枅擔100恖嬤偄恖乆偑偙偺崙偺偳偙偐偱帺嶦偟偰偒偨偲偄偆偙偲偩丅崙傗帺帯懱偺懳嶔偑岠壥傪忋偘偰偄傞偲偄傢傟傞偑丄偦傟偱傕墷暷偺2乣3攞偺悈弨偱偁傞丅帺嶦偺攚宨偵偁傞尨場偵栚傪岦偗丄偝傜偵敳杮揑側夵慞傪恑傔偰偄偐偹偽側傜側偄丅 丂怱偺庛偝傗巰惗娤偺栤戣偺傛偆偵帺嶦傪峫偊丄偁傞偄偼巰偦偺傕偺傪僞僽乕帇偟偰媍榑偡傞偙偲偡傜偨傔傜偆晽挭偑懳嶔偺抶傟傪傕偨傜偟偰偒偨丅柉娫抍懱乽儔僀僼儕儞僋乿乮惔悈峃擵戙昞乯偺挷嵏偵傛傞偲丄帺嶦偺攚宨偵偼幐嬈丄偆偮丄偄偠傔丄壠懓晄榓丄俢倁旐奞丄傾儖僐乕儖埶懚丄夁楯丄夘岇丒堢帣旀傟側偳60埲忋偺梫場偑懚嵼偟丄幚嵺偵帺嶦偵帄偭偨椺偱偼彮側偔偲傕巐偮埲忋偺梫場偑廳側偭偰偄傞偲偄偆丅擭楊傗惈暿傗怑嬈傪栤傢偢丄扤偵偱傕婲偙傝摼傞栤戣側偺偱偁傞丅乿 帺嶦幰悢偺悇堏 丂帺嶦幰悢偺摑寁偵偼丄寈嶡挕偺挷傋偺傎偐偵丄岤惗楯摥徣偺恖岥摦懺摑寁偑偁傞丅恖岥摦懺摑寁偼丄弌惗丄巰朣丄崶堶丄棧崶側偳偺撏弌偵婎偯偒嶌惉偝傟傞摑寁偱偁傞偑丄巰場暿巰朣幰悢偺廤寁偑戝偒側晹暘傪愯傔偰偍傝丄偦偺拞偵巰場偺侾偮偲偟偰帺嶦偑廤寁偝傟偰偄傞偺偱偁傞丅寈嶡挕偺帺嶦摑寁偼1978擭埲崀偟偐摼傜傟側偄偑丄恖岥摦懺摑寁偼柧帯32擭乮1899擭乯埲棃偺挿偄楌巎傪桳偟偰偍傝丄帪宯楍僨乕僞偲偟偰偼傗偼傝偙偪傜傪巊偆曽偑傛偄丅
丂愴屻偺帺嶦幰悢偺悇堏乮俁偮偺悇堏恾偺偆偪偺嵟弶偺恾乯傪尒傞偲丄帺嶦幰悢偑1998擭偵媫憹偟丄偦偺屻偺儗儀儖偼巎忋嵟懡偩偭偨揰丄傑偨晄嫷婜偲暯峴偟偰3搙偵傢偨偭偰帺嶦幰悢偑媫憹偟偨帪婜偑偁偭偨揰偑柧傜偐偱偁傞丅摿偵丄1998擭偵慜擭偐傜偺戝宆嬥梈攋抅偵偲傕側偭偰帺嶦幰偑8愮恖埲忋憹壛偟丄堦婥偵3枩恖戜偲側偭偨帪偺徴寕偵塭嬁偝傟丄宱嵪婋婡偲帺嶦媫憹偼枾愙晄壜暘偲偄偆報徾偑偸偖偄偊側偄傕偺偲側偭偨丅側偍丄寈嶡摑寁偲堎側傝恖岥摦懺摑寁偱偼1998乣2010擭偺偆偪娫寚揑偵4擭師偼帺嶦幰3枩恖枹枮偱偁偭偨偺偱丄3枩恖挻偺挿偄楢懕婰榐偲偼側偭偰偄側偄丅 帺嶦棪偺悇堏 丂愴屻偺挿婜揑側帺嶦幰偺憹壛偵偼丄擔杮恖偺恖岥婯柾帺懱偺憹壛傕婑梌偟偰偄傞偺偱丄偦偺梫場傪庢傝彍偄偨帺嶦棪偺巜昗傪師偵尒偰傒傛偆乮俁偮偺悇堏恾偺偆偪偺恀傫拞偺恾乯丅
丂偑傫巰朣棪側偳懠偺巰場暿巰朣棪偲摨條偵恖岥10枩恖摉偨傝偱寁嶼偝傟傞帺嶦棪傪尒偰傒傞偲丄愴屻偺僺乕僋偼幚偼1958擭偺25.7恖偱偁傝丄嬤擭偺僺乕僋偱偁傞2003擭偺25.5恖傕偙傟傪忋夞偭偰偼偄側偄丅 丂廬偭偰帺嶦棪偐傜敾抐偡傞偲暯惉偺帺嶦儗儀儖偼愴屻嵟懡偲偄偆傛傝丄2夞栚偺愴屻嵟懡儗儀儖偲偡傞偺偑惓偟偄偙偲偵側傞丅 昗弨壔帺嶦棪偺悇堏 丂巰場暿巰朣棪偱偼丄扨弮偵恖岥斾偱寁嶼偡傞慹巰朣棪偺傎偐偵丄昗弨壔巰朣棪乮擭楊挷惍巰朣棪乯偑寁嶼偝傟傞偙偲偑懡偄丅偨偲偊偽丄偑傫巰朣棪偼崅楊幰偺偑傫巰朣棪偑庒擭憌偲斾妑偟偰崅偄偨傔丄崅楊壔偵敽偭偰忋徃偟偰偄傞偑丄擭楊峔惉偑摨堦偩偲偟偰嶼弌偝傟傞昗弨壔巰朣棪偱偼丄抝惈偼1995擭埲崀丄彈惈偼1960擭埲崀丄偑傫巰朣棪偼掅壓偟偰偄傞偺偱偁傞乮恾榐2080乯丅
丂庒擭憌傛傝拞崅擭憌偺曽偑帺嶦棪偑崅偄偙偲偑抦傜傟偰偄傞偺偱乮恾榐2760嶲徠乯丄擭楊峔惉偺曄壔偺塭嬁傪彍偄偨摦偒傪抦傞偨傔偵偼丄摉慠丄昗弨壔帺嶦棪傪嶼弌偡傞昁梫偑偁傞丅 丂昗弨壔巰朣棪偼帪宯楍斾妑偵偍偄偰廳梫偱偁傞偽偐傝偱側偔丄奺崙斾妑偵偍偄偰傕廳梫偱偁傞丅擭楊峔憿偺堎側傞崙傪斾妑偡傞応崌丄偦偺梫場傪庢傝彍偄偰斾妑偟偨曽偑傛偄応崌偑傎偲傫偳偱偁傞偐傜偱偁傞丅偙偺偨傔丄OECD Health Data偱偼擭楊挷惍屻偺昗弨壔帺嶦棪傪奺崙偵偮偄偰1960擭埲崀偺僨乕僞傪宖嵹偟偰偄傞乮昗弨壔偵梡偄傜傟偨恖岥峔惉偼壓昞偺捠傝偱偁傞乯丅
丂恖岥摦懺摑寁偺1960擭傗2015擭偺擭楊暿帺嶦棪傪昞偺擭楊峔惉偱壛廳暯嬒偡傞偲OECD偺抣偲傄偭偨傝堦抳偡傞丅偙偺OECD僨乕僞偲偙傟偵寚偗偰偄傞1959擭埲慜傗嵟嬤擭偺擭師偵偮偄偰寁嶼偟偰曗偭偨昗弨壔帺嶦棪偺帪宯楍僨乕僞傪尒偰傒傛偆乮俁偮偺悇堏恾偺偆偪偺嵟屻偺恾乯丅 丂偡傞偲1950擭戙敿偽偺10枩恖摉偨傝30恖慜屻偺崅偄帺嶦棪悈弨偐傜丄崅搙惉挿婜偵戝偒偔掅壓偟丄偦偺屻丄10枩恖摉偨傝20恖慜屻偺悈弨偱墶攪偄偵揮偠偰丄尰嵼偵帄偭偰偄傞偲偄偆悇堏偺忬嫷偑尒偰庢傟傞丅偮傑傝丄帺嶦偼憹偊偰偄側偐偭偨偺偱偁傞丅 丂捈嬤偵偮偄偰偼丄僶僽儖婜傪壓夞傝丄愴屻嵟掅儗儀儖傪峏怴偟偰偄傞丅偙傟傑偱偵側偔帺嶦偼尭偭偰偄傞傢偗偱偁傞丅壗屘丄偙傫側偵彮側偔側偭偨偺偐傪愢柧偡傞昁梫偑惗偠偰偄傞丅 丂嶲峫偺偨傔丄昗弨壔巰朣棪偺僨乕僞擭師傪偝傜偵愴慜偵偝偐偺傏傜偣丄5擭偍偒乮1947擭偩偗椺奜乯偵嵟嬤傑偱捛偭偨恾傪埲壓偵宖偘偨丅昗弨壔帺嶦棪偱尒傞偲愴慜偺僺乕僋偼廔愴屻偺僺乕僋偲傎傏摨悈弨偲側偭偰偄傞丅愴慜偼崱傎偳崅楊幰偑懡偔側偐偭偨偺偱帺嶦棪偑崅偔側偐偭偨偩偗側偺偱偁傞丅宱嵪敪揥偺偲傕偵帺嶦棪偑崅偔側偭偨偲偄偆尒曽偼廋惓偝傟傞昁梫偑偁傠偆丅宱嵪嬯丄昦嬯偼愴慜偺曽偑戝偒偐偭偨偺偱偁傞偐傜乮恾榐2156乯丅 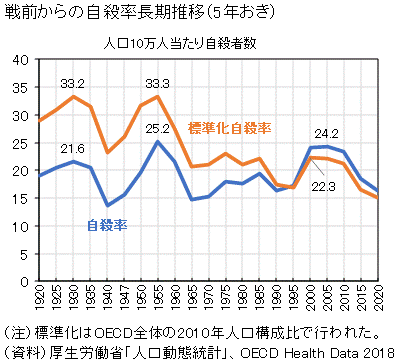 憹壛梫場傾僾儘乕僠偲尭彮梫場傾僾儘乕僠 丂帺嶦幰悢偺悇堏僌儔僼偱偼丄帺嶦偺憹壛梫場偵帺慠偲娭怱偑岦偐偭偨偑丄昗弨壔帺嶦棪偺悇堏僌儔僼偱偼丄傓偟傠丄帺嶦偺尭彮梫場偑壗偩偭偨偐偑廳梫偩偲婥偯偐偝傟傞丅
丂帺嶦僨乕僞偺曄摦偵娭偟偰丄憹壛梫場傾僾儘乕僠偱偼幮夛偺僗僩儗僗偑崅傑傞偲帺嶦偑憹偊傞偲偄偆峫偊曽偵婎偯偄偰悇堏傪夝庍偡傞偺偱偁傞偑丄偦傟偩偗偑惓偟偄傾僾儘乕僠偩偲偼尵偄愗傟側偄丅傓偟傠丄擔杮幮夛偵偍偗傞堦掕偺帺嶦棪悈弨偑幮夛慡懱偺崅梘傗堦懱姶偱掅傑傞帪婜偑偁傞偲偄偆尭彮梫場傾僾儘乕僠偺峫偊曽偱帺嶦偺悇堏傪懆偊傞偙偲傕廳梫側偺偱偁傞丅 丂擔杮偱傕戞俀師悽奅戝愴拞偦偆偱偁偭偨傛偆偵愴憟偺帪婜偵偼偳偺崙偱傕帺嶦棪偑掅壓偡傞孹岦偵偁傞偙偲偑娤嶡偝傟偰偄傞乮忋恾丄媦傃恾榐2774嶲徠乯丅偙傟偵偮偄偰偼偦偺帪婜偵崅傑偭偨乽嫮屌側幮夛揑摑崌乿乮僨儏儖働乕儉乯偺梫場偱愢柧偡傞偺偑堦斒揑偱偁傝丄偙偺応崌偼丄幚偼尭彮梫場傾僾儘乕僠偵棫偭偰偄傞偺偱偁傞丅 丂偙偺傾僾儘乕僠偵棫偰偽丄愴屻擔杮偺帺嶦棪偺悇堏偵偮偄偰傕丄搶嫗僆儕儞僺僢僋乮1964擭乯傗GDP悽奅戞2埵乮1969擭乯偲偄偭偨忬嫷偵戙昞偝傟傞崅搙惉挿婜偺嫽暠丄偦偟偰僶僽儖宨婥乮帒嶻壙奿崅摣偵偲傕側偆崅妟徚旓僽乕儉乯偺嫸憶偑杮棃偺帺嶦棪悈弨偐傜擔杮恖傪巄帪夝曻偟偰偄偨偲懆偊捈偡偙偲偑壜擻側偺偱偁傞丅 丂憹壛梫場傾僾儘乕僠偱偼夝庍偟偑偨偄揰偑尭彮梫場傾僾儘乕僠偱偼棟夝偑梕堈偲側傞丅 丂傑偢丄帺嶦幰悢偺悇堏偺恾偵婰偟偨3偮偺憹壛梫場偺側傋掙晄嫷丄墌崅晄嫷丄偦偟偰暯惉晄嫷偱偁傞偑丄幚偼丄帺嶦偺媫憹偼偦傟偧傟偺晄嫷偺帪婜偲偼昁偢偟傕僞僀儈儞僌偑堦抳偟偰偄側偄丅 丂愴屻娫傕側偄帺嶦偺媫憹乮1955乣58擭乯偼丄惵擭憌偺崅偄帺嶦棪丄暅堳暫偺帺嶦丄抝彈偲傕帺嶦憹偲偄偆摿挜傪傕偭偰偍傝丄愴屻偺壙抣娤揮姺偑庡梫場偲巚傢傟傞丅帪婜揑偵偼側傋掙晄嫷乮1957乣58擭乯埲慜偺恄晲宨婥偺偝側偐丄擔杮恖偑攕愴捈屻偺崿棎婜傪宱偰傆偲変偵曉偭偨帪偐傜偼偠傑偭偰偄偨偲峫偊偞傞傪偊側偄丅 丂傑偨墌崅晄嫷偺嵺傕幚偼媫寖側墌崅傪傕偨傜偟偨1985擭偺僾儔僓崌堄傛傝2擭慜偺1983擭偐傜帺嶦偑媫憹偟偼偠傔偰偄偨偺偱偁傝丄偙偺擭偼媽棃宆幮夛偺恖娫娭學偐傜偺曄梕傪徾挜揑偵帵偡偐偺傛偆偵愴屻偼偠傔偰棧崶偑媫憹偟偨擭偵摉偨偭偰偄傞乮恾榐2780嶲徠乯丅 丂偝傜偵暯惉晄嫷偵偮偄偰偼帺嶦偑媫憹偟偨1998擭埲慜偺90擭戙慜敿偐傜僶僽儖偺曵夡偼偼偠傑偭偰偄偨偺偵僶僽儖偺梋塁偐傜側偐側偐恖乆偼栚妎傔偢丄傑偩傑偩儕僇僶乕偑壜擻側偺偱偼側偄偐偲偄偆娒偄尪憐傪97擭偺戝宆嬥梈攋抅偑偮偄偵懪偪嵱偄偨偺偩偲峫偊傜傟傞丅 丂偙偺傛偆偵帺嶦偺媫憹偼丄媫憹偺梫場傪扵傞傛傝傕帺嶦傪尭彮偝偣偰偄偨梫場偑偄偮傑偱懕偄偨偐偵拝栚偡傞曽偑棟夝偟傗偡偄偺偱偁傞丅 丂僶僽儖宨婥偑擔杮恖偺惛恄偵媦傏偟偰偄偨塭嬁椡偺戝偒偝偵偮偄偰偼丄愴屻偺戝偒側弌棃帠偼壗偐傪暦偄偨堄幆挷嵏寢壥偐傜傕柧傜偐偱偁傞偑乮恾榐2640乯丄帪宯楍僨乕僞偲偟偰傕丄寣埑偲怘墫愛庢検偺悇堏乮恾榐2175丄恾榐2173乯丄偁傞偄偼奜幵斕攧審悢乮恾榐5458乯傪尒傞偲桴偗傞傕偺偑偁傞丅
丂擔杮恖偺暯嬒寣埑偲怘墫愛庢検偼丄寬峃堄幆偺崅傑傝偵偲傕側偄愴屻傎傏堦娧偟偰掅壓丒尭彮孹岦偵偁傞丅偲偙傠偑椺奜揑側帪婜偑偁傞丅僶僽儖宨婥偺帪婜偱偁傞丅僶僽儖宨婥偑偼偠傑偭偨1980擭戙屻敿偐傜怘墫愛庢検偑忋徃偟偼偠傔丄傑偨僶僽儖偑偼偠偗偨偺偪傕偟偽傜偔崅巭傑傝偟丄尦偺孹岦慄偵暅婣偟偨偺偼2000擭戙偵擖偭偰偐傜側偺偱偁傞丅暯嬒寣埑傕偙偆偟偨怘墫愛庢検偺摦偒傪捛偆傛偆偵1990擭戙屻敿偵偼孹岦抣偲斾妑偟偰憡懳揑偵崅偄帪婜偑懕偄偨丅偙傟偑僶僽儖婜偲偦偺捈屻偺惛恄揑崅梘傗嬉戲側怘惗妶傪斀塮偟偰偄偨偙偲偼妋偐偱偁傠偆丅宱嵪偑嬻夞傝偟偼偠傔偰傕傑偩偟偽傜偔偼尪憐偵悓偭偰偄偰丄偮偄偵尩偟偄尰幚偵捈柺偡傞偙偲偵側偭偨偲偄偆偺偑98擭偵偍偗傞枹慮桳偺帺嶦媫憹偺恀憡偩偭偨偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傞丅
丂僶僽儖偺柌傪懪偪嵱偄偨帠審偺傂偲偮偵1997擭偺嶳堦鏆寯偺攋抅丄帺庡攑嬈偑偁偘傜傟傞丅嶳堦鏆寯偼80擭戙屻敿偺僶僽儖婜偵姅庢堷偱婇嬈偵棙夞傝傪曐徹偡傞堘朄側乽偵偓傝乿偱惉愌傪偁偘偰偄偨丅90擭偵姅壙偑媫棊偟偰偐傜乽婇嬈偲偺栺懇傪壥偨偡偨傔丄懝幐傪書偊偨嬥梈彜昳傪堷偒庢偭偨嶳堦偺娷傒懝偼傒傞傒傞朿傜傓丅暿偺夛幮傗儁乕僷乕僇儞僷僯乕偵嬥梈彜昳傪堏偟丄憡応偺夞暅傪懸偮偙偲傕懡偐偭偨丅夛幮娫傪揮乆偲偟丄偳偙偺夛幮偑婲揰偐暘偐傜側偔側傞傎偳暋嶨偵側傞偲乽塅拡梀塲乿偲屇傫偩丅乽亀梀塲亁傪夝徚偡傞偺偼姅壙偺寑揑忋徃偟偐側偄丅嶳堦偼亀恄晽亁傪婜懸偟丄亀旘偽偟亁傪柍尷偵懕偗偨乿乮偙偆攋抅屻偵岞昞偝傟偨幮撪乯挷嵏曬崘彂偼婰偡丅乮棯乯乽旘偽偟乿偲偼丄姅壙偑壓棊偟偰娷傒懝偑弌偨姅傗嵚尃傪帩偮婇嬈偑丄懝幐傪昞柺壔偝偣側偄偨傔偵丄寛嶼婜偺慜丄嶳堦傪拠夘偟偰堦帪揑偵暿偺婇嬈偵堏偡偙偲傪巜偡丅嶳堦偺朄恖塩嬈晹栧偺塀岅偩偭偨乿乮搶嫗怴暦2015擭12寧9擔乯丅 丂懡偐傟彮側偐傟1990擭戙屻敿傑偱丄偙偺傛偆側榗傫偩偐偨偪偱擔杮宱嵪偼僶僽儖曵夡偺偮偗傪愭墑偽偟偵偟丄柌傪偮側偄偱偄偨偺偩偲偄偊傛偆丅 丂枅擔怴暦宱嵪晹婰幰傪1987擭偵傗傔僼儕乕僕儍乕僫儕僗僩偲偟偰妶桇偟偰偄偨浉乮偟傑乯怣旻偼摉帪傪偙偆夞屭偟偰偄傞丅乽僶僽儖曵夡捈屻乮90.擭乯偺擔杮偼丄擔杮偺惢憿嬈偺嫮偝偐傜偡傟偽丄3乣4擭傕偡傟偽僶僽儖曵夡傪忔傝墇偊偰傑偨暅妶偡傞偲怣偠偰偄偨偵堘偄側偄丅偟偐偟丄4擭丄5擭偲夁偓偰傕擔杮偺嵞惗偼偐側傢偢丄90擭戙屻敿偵側偭偰乽偙傟偼偍偐偟偄偧丄戝偒側峔憿揮姺丄楌巎偺曄壔偵墳偠偰丄擔杮傕曄傢傜側偄偲僟儊偵側傞乿偲婥偯偒巒傔傞乿乮乽擔杮恖偺妎屽乗惉弉宱嵪傪挻偊傞乿幚嬈擵擔杮幮丄2014擭乯丅幚嵺丄90擭戙慜敿偵偼丄椻愴峔憿偺曵夡丄ICT妚柦丄儅僱乕宱嵪偺杣嫽丄搶傾僕傾怴嫽崙偺捛偄忋偘丄俤倀偺敪懌偲偄偆悽奅揑側峔憿曄壔偑婲偙偭偰偄偨偺偱偁傞丅 丂1998擭埲崀傕2008擭廐偺儕乕儅儞僔儑僢僋屻偺宨婥掅柪側偳幐嬈偺媫憹傗旕惓婯屬梡偺憹壛傪敽偆宱嵪偺戝偒側曄摦偑惗偠偰偄傞偑帺嶦棪偵偼傎偲傫偳曄壔偑側偄丅偙偆偟偨摦偒偼憹壛梫場傾僾儘乕僠偱偼夝庍偑擄偟偔丄傓偟傠栚棫偭偨尭彮梫場偺曄壔偑側偄偨傔摨堦儗儀儖偑懕偄偰偄傞偲峫偊偨曽偑棟夝偟傗偡偄丅 丂偦偟偰嵟嬤偱偼丄2020擭偺怴宆僐儘僫偺姶愼奼戝偱惗妶僗僩儗僗偑崅傑傝丄堦斒偵偼丄帺嶦憹偑偦偺塭嬁偩偲峫偊傜傟偰偄傞丅偟偐偟丄僐儘僫偑廝偆慜偺2019擭傑偱偺帺嶦悢尭偑傾儀僲儈僋僗偵傛傞塭嬁偩偲峫偊丄僐儘僫偱偦傟偑撢嵙偟偨偨傔帺嶦棪偑尦偺悈弨偵栠偭偨偲偲傜偊偨曽偑揔愗偲傕偄偊傞丅 偝偄偛偵 丂杮峞偲摨庯巪偱帺嶦棪偼崅傑偭偰偄側偄偙偲傪柧傜偐偵偟偨惛恄壢堛偺晊崅扖堦榊乮2011乯乽偆偮昦偺忢幆偼傎傫偲偆偐乿偼偙偆尵偭偰偄傞丅乽尰嵼偺擔杮偺帺嶦幰悢偑3枩恖傪挻偊偰偄傞偙偲偼帠幚偱偁傞丅偟偐偟偦偺愢柧偵偁偨偭偰偼丄壢妛揑偵偐偮椻惷偵峴傢側偄偲偄偗側偄丅擔杮幮夛偑偍偐偟偔側偭偨偺偱丄帺嶦幰偑憹偊偰偄傞偲偄偆埨堈側愢柧偼丄壢妛揑偵偍偐偟偄偟丄帺嶦懳嶔偲偟偰傕娫堘偭偰偄傞丅偦偆偄偭偨愢柧傪恀偵庴偗偰丄悽偺拞傪斶娤偟丄帺嶦傪峫偊傞恖傕偄傞偲偟偨傜丄桳奞偱偡傜偁傞丅乿
丂2010擭戙偺帺嶦棪掅棊偺梫場偲偟偰偼丄憹壛梫場傾僾儘乕僠偵棫偰偽丄幐嬈棪偺掅壓側偳偵傛傞宨婥梫場偺夵慞偑憐掕偝傟丄尭彮梫場傾僾儘乕僠偵棫偰偽丄嘆姅壙偺夞暅傪傕偨傜偟偨傾儀僲儈僋僗偺塭嬁丄嘇強摼偺怢傃擸傒傗幮夛偺掆懾傊偺姷傟丄嘊僗儅儂傗SNS偺屒棫梊杊偺塭嬁丄嘋姱柉偁偘偰偺帺嶦懳嶔偺悇恑岠壥乮2006擭帺嶦懳嶔婎杮朄乯偲偄偭偨梫場偺偄偢傟偐丄偁傞偄偼偦傟傜偺慻傒崌傢偣偑峫偊傜傟傛偆丅 丂尭彮梫場傾僾儘乕僠偲偟偰偼丄傾儀僲儈僋僗偑幮夛慡懱偑嫽暠偟偰偄偨夁嫀2夞偺掅棊婜偲偼彮偟堎側傞忬嫷側偺偱夝庍偼側偐側偐擄偟偄丅
乮2013擭3寧8擔廂榐丄2014擭10寧1擔浉怣旻堷梡捛壛丄暯嬒寣埑傪擭師抣偵曄峏丄2015擭12寧9擔嶳堦鏆寯偺帠椺傪徯夘丄2019擭1寧12擔峏怴丄2寧24擔擭楊挷惍抣嵟嬤擭捛壛丄2023擭9寧29擔峏怴丄僐儘僫壭忬嫷丄10寧1擔愴慜偐傜偺悇堏恾丄2026擭1寧31擔峏怴乯
乵 杮恾榐偲娭楢偡傞僐儞僥儞僣 乶 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||