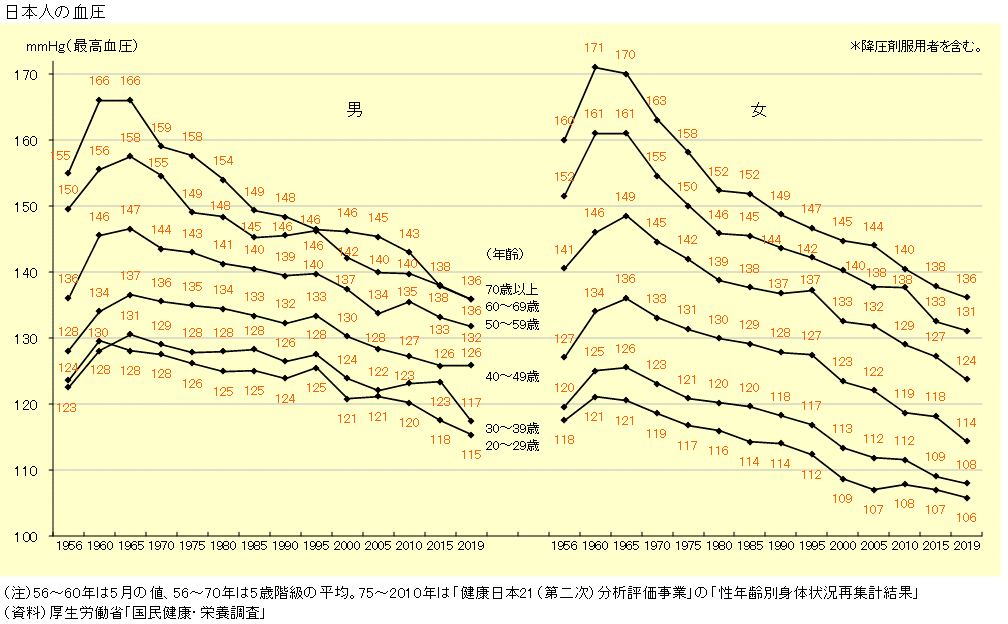
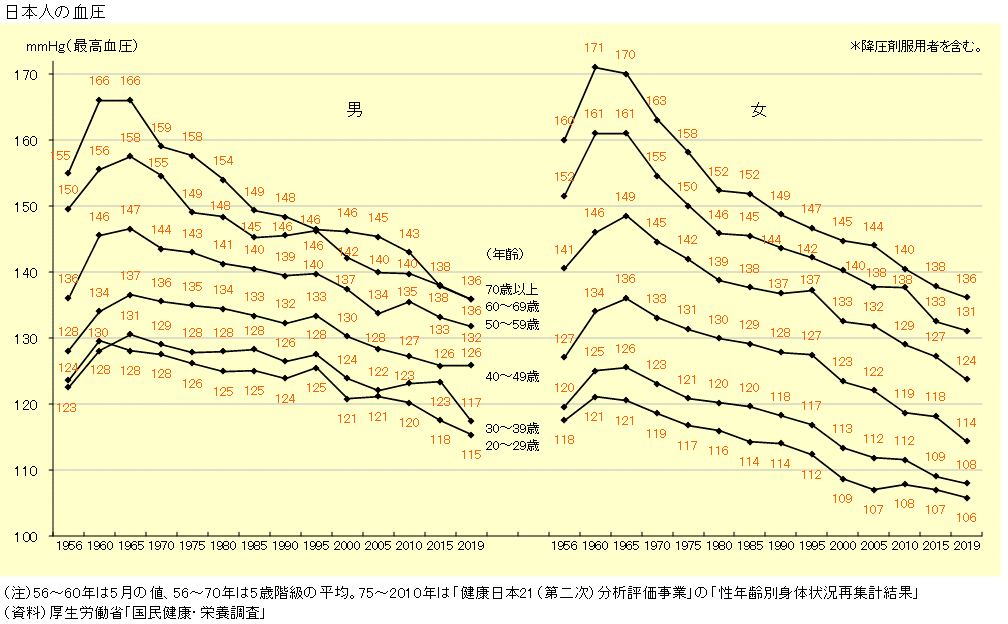
年次に関わりない特徴としては以下の2点が目立っている。
年次推移については以下のような点が目立っている。下に1965年以降の年齢調整平均血圧の推移を掲載したが、これも考慮に入れたコメントである。
かつての高血圧症の設定値は今ほど低くなかった。1960年代後半に日本の医学部で最も広く使われていた『内科診断学』という教科書には、「日本人の年齢別平均血圧」の算出法として、「最高血圧=年齢+90」という算式が載せられていたという(集英社オンライン)。 男より女の血圧低下傾向が著しいことには、男の肥満化傾向、女の痩身化傾向が影響しているであろう(図録2200参照)。 また、平均血圧の傾向的低下には日本人の塩分摂取量の低下が影響していると考えられる(図録2173参照−下に図を再掲)。  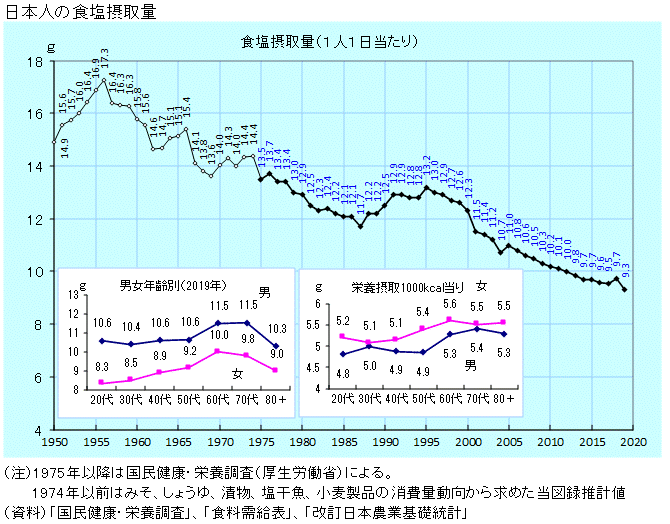 なお、バブル経済の時期をはさんで1980年代後半から1990年代前半にかけて食塩摂取量の一時期な増加が見られ、1990年代後半に長期趨勢値まで低落した。1990年代における上述の日本人の血圧の一時的上昇はこれによるものと考えられる。バブル期のテンションの高さや贅沢志向が食生活にもあらわれ、これが血圧の上昇にも結びついていたのだとしたら、まさしくバブル狂想曲と呼ぶべき時代だったことが裏づけられよう。
同じ血圧のレベルであっても、過去より現在の方が、脳卒中や心臓病になりにくくなっているのだから、これに対応して高血圧症の診断基準も引き上げるべきだといる見解については図録2127コラム「ほんとうに糖尿病や高血圧症は増えているのか」参照。 (2012年6月4日収録、6月5日年齢調整平均血圧を男女計から男女別に変更、7月9日更新、2013年5月27日更新、9月30日鳥居引用追加、2014年6月23日更新、10月1日1977年、81年を75年、80年値に変更、及び年齢調整平均血圧の推移を5年おき値から毎年値に変更、10月10日コメント改訂、2016年6月20日年齢調整毎年血圧1966〜69年、1973年追加、7月2日図録2127コラムへの参照コメント、2017年5月26日更新、7月21日データ改訂、2024年1月12日更新、2025年3月28日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||