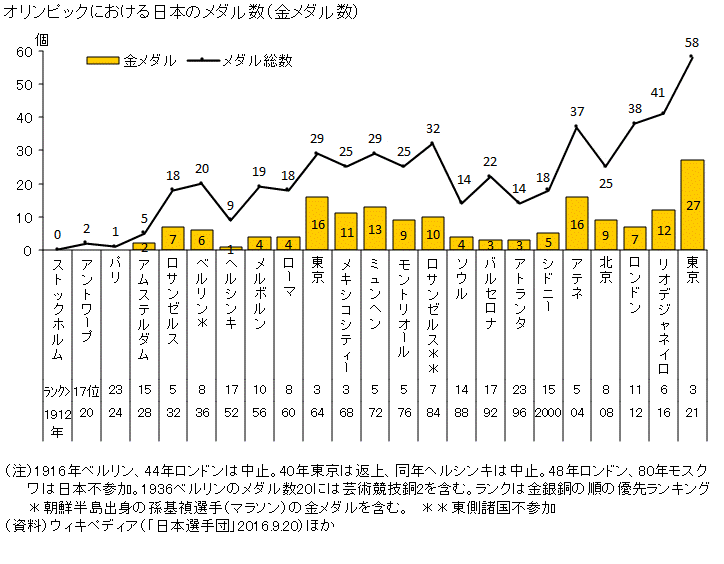
| 計45 | 柔道 | 卓球 | 水泳 | 体操 | 陸上 | レスリング | スケートボート | フェンシング | バドミントン | ゴルフ | セーリング | クライミング | ブレイキン | 近代五種 | 馬術 | |
| 金 | 20 | 3 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 銀 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 銅 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 計58 | 柔道 | 空手 | 卓球 | 水泳 | 競歩 | 体操 | 重量挙げ | バスケ | レスリング | ボクシング | バドミントン | アーチェリー | フェンシング | 自転車 | 野球 | ソフトボール | ゴルフ | クライミング | スケートボード | サーフィン | |
| 金 | 27 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 銀 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 銅 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
(前回東京五輪など過去5回の大会 のコメントは下段で表示選択) パリオリンピックが2024年7月26日(金)〜2024年8月11日(日)の日程で開催されている。通常なら、「世界何カ国・地域の何人のアスリートが集い」とされるはずであるが、ウクライナ戦争、ガザ戦争の影響で確定的な数字をIOCが発表していないので、報道もそうした数字を「約1万1千人以上の選手が集い」などとあいまいに報じているところが複雑な世界情勢を反映していると言えよう。 メダル数は金メダル数20、メダル総数45と、ともに前回東京大会を除く海外大会最多となった。金メダル数20個が日本選手団の目標数だったので目標通りとなった。金メダル数、メダルランキングともに世界第3位とランキング上は前回東京大会に並ぶ過去最高タイだった。予想以上の健闘と言えよう。 国の強化策も功を奏したと言えよう。「国は世界選手権などの実績を基に「重点支援競技」を選んで予算を手厚く配分しており、パリは柔道、体操、フェンシング、ブレイキン、レスリングの五つを最高ランクに指定。「選択と集中」の戦略は成果を上げた」(東京新聞2024.8.13)。 (メダル獲得の経過) 日本勢初メダルについては、柔道の女子48キロ級決勝で初出場の角田夏実選手が今年の世界女王バーサンフー・バブードルジ(モンゴル)を破り、日本勢の夏季五輪通算500個目のメダルを、今大会1号となる金メダルで飾った。女子48キロ級の金メダル獲得は2004年アテネ大会の谷亮子(旧姓・田村)以来(スポーチ報知)。 3日目の7月28日には柔道2、スケートボード、フェンシング、29日にも体操、スケートボード、30日にも柔道と日本の金メダルラッシュが続いたため、日本時間の7月31日朝の段階では金メダル7個と中国、オーストラリアの6個を上回る単独首位、メダルランキングでも中国上回る単独首位となって、3日目から5日目まで3日間は世界1のメダル国となっていた(図録3983rパリ五輪各国メダル獲得数参照)。 6日目にはさらに体操個人総合で金メダルを獲得し、金メダル数8となった(メダルランキング3位)。10日目にはフェンシングで金メダルを獲得し、金メダル数9となった(メダルランキング7位)。11日目には体操で金メダルを獲得し、金メダル数10となった(メダルランキング7位)。12日目にはレスリングで金メダルを獲得し、金メダル数11となった(メダルランキング7位)。13日目には前日に続きレスリングで金メダルを獲得し、金メダル数12となった(メダルランキング7位)。14日目には3日連続レスリングで金メダルを獲得し、金メダル数13となった(メダルランキング7位)。 15日目にはレスリングで2個、ブレイキンで1個、計金メダル3個を獲得し、金メダル数16となった(メダルランキング4位へ浮上)。16日目には陸上女子やり投げ、レスリングで金メダル計2個獲得し、金メダル数18となった(メダルランキング4位)。最終日17日目にはレスリングで金メダル2個獲得し、金メダル数は20個と日本選手団の目標数に達した。メダルランキングも3位と前回東京大会に並んだ。 2008年北京五輪からレスリング女子が採用されてから、“新お家芸”としてメダルを量産してきた日本。だが、過去5大会で最重量級は金メダルがなかった。最終日17日目に女子フリースタイル76キロ級決勝が行われ、鏡優翔選手が米国のブレーズ選手を破り、金メダルを獲得。最重量級で日本女子初の快挙となった。これまでは最重量級での日本勢の最高位は2004年アテネ、08年北京の浜口京子の銅メダルだった。 北口榛花選手が獲得した陸上女子やり投げの金メダルについては、オリンピックで日本選手が陸上の投てき種目で金メダルを獲得したのは、2004年のアテネ五輪で室伏広治(現スポーツ庁長官)が男子ハンマー投げを制した1度だけ。陸上女子の金メダルもマラソンで優勝した2000年シドニー五輪の高橋尚子、04年アテネ五輪の野口みずきに続く3人目となった。 11日目8月5日、72年ミュンヘン大会以来52年ぶりの金メダルを目指したバレーボール男子日本代表はイタリアにフルセットの末、2−3で敗れ、2大会連続の準々決勝敗退に終わった。この結果、サッカー、ホッケー、水球、バレー、バスケ、7人制ラグビー、ハンドボールと団体球技の7競技は全滅となった。サッカー、バレーボール、バスケットボールとメダルを期待されていたのだが。 (注目競技) 日本勢の好成績が期待される競技は以下の通り。 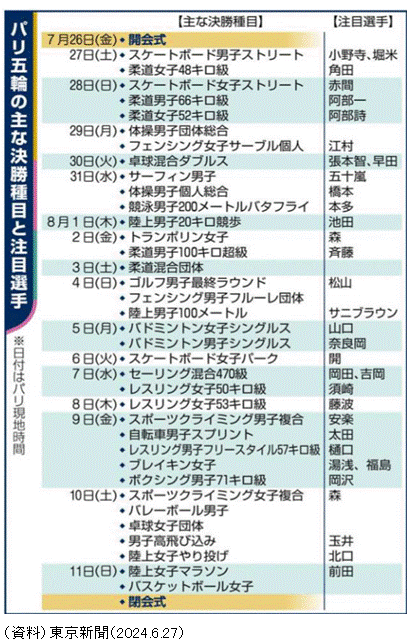 (メダル数目標) 日本選手団はパリ五輪の目標を金メダル20個に定めた。今回、海外開催では最も多い31競技に出場が予定されており、これまでで海外開催では最多の2004年アテネ五輪の16個を4個上回る目標としたのである。前回東京五輪27個の勢いを生かせるかが問われる(東京新聞2024.7.6)。 (メダル数予想) スポーツデータの分析や提供を行う専門会社、グレースノート(本社・米国)は6月26日、パリ五輪のメダル予測を発表し、日本は金メダル12個とした。(下図参照)。 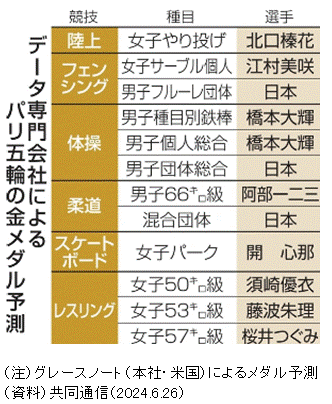 THE DIGEST編集部によると(2024.7.16)、イタリアのスポーツメディア『OA Sport』は、各国のメダル獲得予想を公開した。ベスト10の予想は以下のとおり。日本の金メダル20個は期せずして日本選手団の目標と同じである。 1位 米国/金51、銀33、銅42、計126 2位 中国/金37、銀30、銅21、計88 3位 フランス/金28、銀24、銅13、計65 4位 日本/金20、銀18、銅14、計52 5位 オーストラリア/金13、銀16、銅22、計51 6位 オランダ/金13、銀10、銅12、計35 7位 英国/金12、銀24、銅24、計60 8位 イタリア/金12、銀18、銅14、計44 9位 ドイツ/金10、銀11、銅14、計35 10位 韓国/金8、銀8、銅7、計23 上記グレースノート(本社・米国)の開幕時の予想では、今大会の日本選手団のメダル数は、金13個、銀13個、銅21個の計47個とされた(各国のメダル獲得予想は以下の通り)(nippon.com、2024.07.27)。 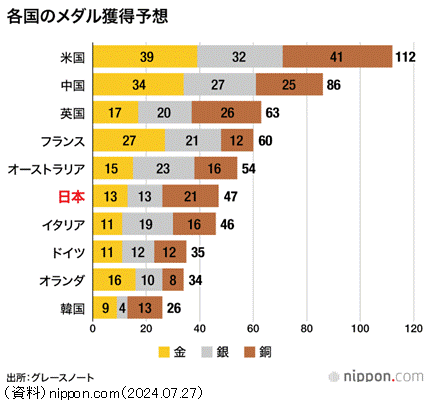 2.メダル数のこれまでの推移
金メダル数は2021東京大会が27個で1964東京大会、2004アテネ大会の16個を上回る過去最多だった。2024パリ大会では目標の20個を達成した。前回大会には及ばなかったが、それを除くと過去最多となった。 メダル総数では2024パリ大会は45個と2021東京大会の58個には及ばなかったものの2004アテネ大会の37個と上回り海外大会過去最多となった。 メダルランキングでは2024パリ大会は世界第3位であり、1964東京大会、1968メキシコシティー大会、2021東京大会と同順だった。1〜2位は前回大会と同様米国、中国であり、1964年と1968年は米国、ソビエト連邦だったのと比べると時代の変遷を感じさせる。また、1964年、1968年、2021年、2024年の1位米国と3位日本の金メダル数は、それぞれ、36:16、45:11、39:27、40:20となっており、金メダル数が国力の反映だとすると米国の4分の1から半分とかなり米国との差が縮まったことになる。 日本のメダル数は徐々に増加している傾向が見て取れるが、オリンピックの競技数がだんだんと増え、メダル数が増えている要因で増えている側面もある。そこで下図では世界全体のメダル数に占める日本のメダル数の割合の推移を掲げた。 これを見ると、メダル数割合では、1964東京大会の金メダル数、メダル総数が、それぞれ、9.8%、5.8%とともに過去最高だったことが分かる。金メダル数、メダル総数が海外大会最多だった2024パリ大会でもメダル数割合は、それぞれ、6.1%、4.3%と前回東京大会だけでなく、1968メキシコシティー大会、1972ミュンヘン大会を下回っており、海外大会最高とは言えない。 メダル数割合の推移の特徴としては、一度、1964東京大会前後まで上り詰めた増加傾向が、その後、落ち込んでいき、20世紀末のバルセロナ大会、アトランタ大会を底に、再度、上昇傾向をたどっていると言えよう。ただし、今後、高度成長期の勢いの中で頂点を迎えた1964東京大会を越えるのは難しそうである。 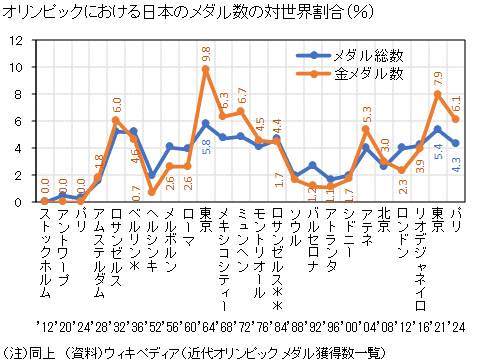 3.金メダル(種目別)と金銀銅メダル(主要競技別)
4.柔道と全体のメダル数
日本のメダル獲得総数に大きく寄与している柔道男子・女子のメダル数の推移を以下に掲げた。 1992年バルセロナ・オリンピック以後、アテネまでは、金メダル数では柔道における獲得数がいずれの大会でも5割以上となっていたが、北京では44%と5割を下回り、ロンドンではついに金メダル1個で14%となった。リオデジャネイロでは、25%まで回復したがかつてほどの比率ではない。リオデジャネイロでは、金メダル数は多くないが、総数では男子では全階級でメダルを獲得し男女計とともに過去最多のメダル数となった。ただし総メダル数でも全体の3割は越えていない。 リオデジャネイロ大会で柔道のメダル総数は過去最多となった。これには、他の競技と同様、施設、人材面の強化対策が功を奏しているとされる。「ロンドン五輪で史上初めて金メダルゼロに終わった柔道男子を全階級メダルで復活させた井上康生監督は現役引退後の09年1月から2年間、JOCの制度を利用し、英国へコーチ留学。身につけた科学的知見を生かし、国際化する柔道の潮流も踏まえて改革した」(毎日新聞2016.8.22)。 さらに東京大会では総数では過去最多タイ、金メダル数では最多の9個となった。 しかし、パリ大会ではそれぞれ8個、3個とそれほどは振るわず、レスリングンのメダル獲得の方が目立っていた。そのため日本の総数に対する比率は最低レベルとなった。、
5.金メダル推移(男女別獲得数)
以下に金メダル数の推移を男女別に掲げた。 シドニーまでの金メダル数は男子が女子を上回っていたが、アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロ、東京と2021東京までの5大会では、女子が男子を上回っていた(女子選手比率推移については図録2710も参照)。 2024パリ大会では再度男子が女子を上回った。女子金メダリスト8人のうち7人が五輪初出場。レスリングの4人をはじめとする新世代が大舞台でのびのびと実力を発揮し、日本の力を示した。 2021東京大会では、メダル数の女性優位は米国の方が顕著である。女子のメダル総数は過去最高の66個と男子の41個よりも多く、3大会連続で女子が男子を上回っている(毎日新聞2021.8.8)。 参加選手女性比率が50%を越える場合があるのは女子チーム競技の参加が大きい。ロンドン・オリンピックの女性選手比率は53.2%であるが、日本選手団の選手293人のうち、女性のみの競技である水泳のシンクロ9人、体操の新体操6人、及び女子チームのみの参加のバレー12人、ホッケー16人、計43人の女子選手の参加が影響している(毎日新聞2012.7.25)。これは日本だけの傾向ではなかった。ロンドンにおける「メダル数上位の米国、中国、ロシアはいずれも参加選手数、獲得メダル数とも女子が男子を上回った。」(毎日新聞2012.8.13夕) 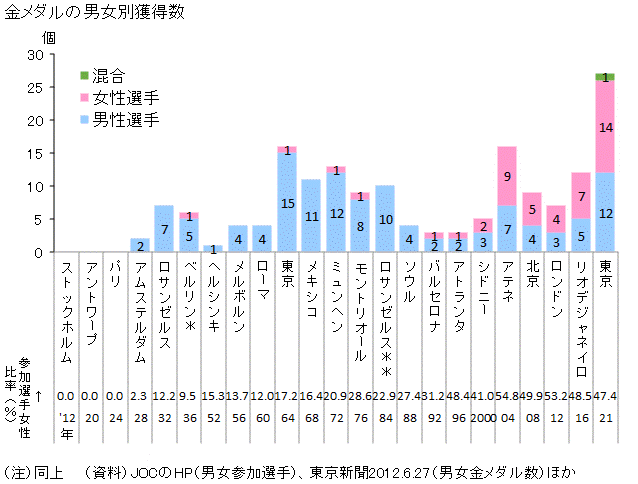 【過去の記事】2021年東京〜2004年アテネ 2021年 東京オリンピック(各国メダル数は図録3983t)
1年延期となった東京オリンピックが2021年7月23日〜8月8日の日程で開催された。 7月30日の柔道女子78kg超級とフェンシング男子エペ団体の金メダル獲得で、金メダル数合計17個と1964年東京、2004年アテネの16個を上回る過去最多に達した。 8月5日の競歩男子20kmで銀と銅のダブルメダルの獲得で前回リオ大会の41枚を上回る過去最多のメダル合計43枚に達した。 最終的には、金メダル27個、総メダル数58個と過去最多となった。金メダルはJOCの目標30個には及ばなかったが、グレースノートの予想26個は上回った。 メダル数が過去最多となった背景としては、日本と比べると欧米のコロナ禍の方が深刻だったことや強化体制や事前準備などで地元有利な面があったためである(こうした点は図録3983tも参照)。 新競技や新種目で活躍が目立った。スケートボードでは、ストリート男子の堀米選手ら3個の金を獲得。日本発祥の空手は男子形で喜友名諒、野球・ソフトボールも期待通りにそれぞれ金メダルを手にした。卓球の混合ダブルスでは、水谷隼、伊藤美誠組が世界王者の中国ペアを破って頂点に立った。 競技種目によってメダル数の成績で明暗が分かれている。これにはやはりコロナ禍の影響が考えられる(以下、東京新聞2021年8月11日、12日「延期五輪の足跡」中・下による)。 柔道とレスリングは、対人格闘技という性格から練習で感染する可能性が高いとされ、思うように強化を進められなかったが、ふたを開けてみれば、柔道は金9個、レスリングも金5個と期待以上の好成績だった。ともに直前まで味の素ナショナルトレーニングセンターで調整を続けられたのが幸いした。 逆に、バドミントンは金メダル確実と期待が高かったのに終わって見れれば混合ダブルスの銅メダル1個にとどまった。コロナ禍で国際大会での実戦不足が影響しているとみられる。 マラソンも国内を拠点とする中村、服部両選手はそれぞれ62位、73位と振るわなかったが、延期により代表決定から2年もの間、重圧を背負い続けたことに加えて、これまで大会前に実施してきた米国での高地合宿ができなかったのも要因のひとつである。一方、米国を拠点とする大迫選手はケニア合宿で十分に練習を積んだ効果や海外では周辺の期待の声などのプレッシャーも小さかったことが幸いして6位入賞を果たせた。 コロナによる一年延期が世代交代を進めることができて比較的好成績だったのが体操競技である。メダルには届かなかったがバレーボール男子にも同様なことがいえる。 逆に、競泳陣は世代交代が一年延期で遅れた。個人種目で決勝に進んだ6人のうち男子200メートルバタフライ銀メダルの本多灯選手を除けば、全員20代中盤から30代。個人メドレー2冠の大橋選手も25歳とベテランの域にある。 なお、東京大会のメダル記録のひとつとして47都道府県すべてに金メダリストが誕生した点が挙げられる。ボクシング女子フェザー級で鳥取県出身の入江選手、空手男子形の喜友名選手と野球の平良選手が沖縄県出身者として初の頂点にたったからである(東京新聞2021.8.14)。 (メダル数予想) 米データ会社グレースノートの東京五輪の各国・地域のメダル獲得数予想によれば、日本は金26、銀20、銅14の計60個である。金メダル数は過去最多となるものの、日本オリンピック委員会(JOC)が目標に掲げた30個には届かないとしている。金最多は米国の40個としているが、新型コロナウイルスの影響を受けた東京五輪について「通常よりも予測のできない大会になる」と指摘しているという(時事2021.7.20)。 他方、“コロナ下の五輪”で開催国の利が増しているとして、スポニチ紙のメダル予想では、金メダルは32個、メダル総数は86個と金メダル数は過去最多の64年東京、04年アテネの16個の2倍となるとしている(スポニチ2021.7.21)。 a.東京オリンピック(コロナ前の段階) (メダル数予想) 今後、内外で数多くメダル予想が発表されるであろうが、1月の段階での東京新聞の予想は金24、銀28、銅30、計82というものである。金メダルは1964年の東京五輪、2004年のアテネ五輪を上回ると見通されている(下表参照)。
(メダル数目標) JOCは東京五輪の金メダル数の目標を過去最多の16個を大きく上回る30個に設定した。JOCの山下泰裕強化本部長(当時)によれば、「一部でその数字に驚かれたようだが、各競技団体が分析した上で出してきた数字」という(東京新聞2018.7.25)。 金メダル目標30個について聞かれた山下泰裕JOC会長は直近の世界選手権で獲得したメダル数は若干足りないが(下表参照)、銀、銅をうまくやっていけば達成できる。(中略)そのためには地の利を生かすことが重要になる」と答え、食事、調整における地元大会の優位性と日本国民の応援を挙げた(東京新聞2020.1.5)。
2016年 リオデジャネイロ・オリンピック(各国メダル数は図録3983v)
リオデジャネイロ大会の金メダル数は12個と世界順位は前回の10位から6位へと躍進、過去の大会の金メダル数と比較すると04年のアテネを除くと76年のモントリオール大会以降最多となった。公式メダルランキング(金銀銅順の優先ランキング)でも北京8位、ロンドン11位から6位に回復。また、金銀銅のメダル総数では41個と過去最多となった。 こうした成果については、やはり、オリンピックへ向けたこれまでの長年の強化策が功を奏したという見方が主である。 「出発点は1996年アトランタ五輪の惨敗にある。本格的強化が始まった64年東京五輪以降で最少タイのメダル総数14個(金3、銀6、銅5)だった。92年バルセロナ五輪で、プロ選手の出場が全面解禁され、競技水準が劇的に上がった。危機感を覚えたJOCは01年、国際競技力向上戦略「ゴールドプラン」を作成し、ジュニア選手の育成や、指導者の養成に着手して、国にも支援を働きかけた」(毎日新聞2016.8.22)。 「日本は2000年以降、選手を医・科学の側面からサポートする国立スポーツ科学センターや、各種トレーニング施設と宿泊所が完備されたナショナルトレーニングセンター(いずれも東京都北区)を設置した。競技団体は強化合宿を定期的に実施できるようになり、練習場所の確保などに四苦八苦することがなくなった。08年にはメダル獲得の可能性が高い競技を重点的に支援する制度も立ち上がり、用具・用品やトレーニング機器の開発、映像による分析などが選手らと一体となって行えるようになった。また、前回のロンドン五輪から選手村の近くに「マルチサポートハウス」を設置し、施設内のジムやプール、体育館を選手が自由に利用できるようにしている。これらの選手支援は米国などが以前から取り入れていたが、日本もようやく追い付き、実をつけてきた」(東京新聞2016.8.22社説)。 国は次の東京オリンピックでは世界3位(金メダル数20〜33個)を目標にしている。このため橋本聖子・日本選手団長は総括記者会見の中で強化予算の拡充を求めた。 2016年リオデジャネイロ大会の女子レスリングは金メダル4個という快挙となった。「ピリオドごとに得点をリセットできたロンドン五輪に比べ、攻め続けないといけない現在のルールはスタミナのある日本選手に有利な印象」(東京新聞2016年8月19日「小原日登美の目」)。これが結果として証明されたようだ。 2016年リオデジャネイロ大会の女子レスリング58キロ級金メダルを獲得した伊調馨選手は女子個人種目で全競技を通じてオリンピック史上初の4連覇を達成した。オリンピックでの個人種目4連覇は以下の4選手に続いて5人目となる。
2012年 ロンドン・オリンピック(各国メダル数は図録3983z)
世界にならってオリンピックに対し国家支援が強化されるようになっている。スポーツ基本法(2011年制定)ではスポーツを国家戦略として推進することとされ、2012年春策定のスポーツ基本計画(文科省)では日本の五輪での金メダル順位の目標が「夏は5位以内、冬は10位以内」と設定された。オリンピックの強化策としてはJOC経由で各競技団体に配分される強化費に加えて2008年度から文科省のマルチサポート事業という国の直接支援が実施され、5年目の2012年度にはメダルが有望なターゲット競技に重点配分されるマルチサポート事業の予算(27.46億円)がJOC補助(25.88億円)をはじめて上回った(毎日新聞2012.7.22)。 JOCはロンドンで政府の目標を達成するためには金メダル15〜18個が必要と考えている。そしてJOCの皮算用では、柔道6〜7、レスリング4前後、体操2〜3、競泳2、ハンマー投げ1、サッカー女子1で達成可能とみていた(同上)。ちなみに日本の金メダル順位は前回北京では8位、前々回アテネでは5位であった。 結果は、金メダルは7つにとどまった。日本選手団のメダル目標は上記のとおり金メダル5位以内であったが実際の順位は10位であり、目標達成はかなわなかった。これは旧ソ連各国など外国勢が力を伸ばしてきた結果、柔道の金メダルが女子1個に止まったことが大きく影響している(上段参照)。 しかし、メダル総数は過去最多の38個となった。これは実施競技の半数の13競技でメダルを獲得したからである。練習環境の充実も背景の1つであった。「今回は味の素ナショナルトレーニングセンター(NTC)、文部科学省のマルチサポート事業が本格的に稼働した五輪だった。NTCの効果が表れたのが、フェンシング、アーチェリー、バドミントン、ボクシング、卓球、レスリングなど。これまでは練習拠点に苦慮していたが、NTCの整備により年間で活用することができるようになった。」(毎日新聞2012.8.14) 今後、選手へのさらなる支援が必要という考え方もある。日本選手団の「橋本聖子副団長は「(外国に比べ)日本のスポーツに掛ける予算はまだまだ少ない。(スポーツ予算に対する)メダル獲得率は世界一に匹敵するのでは」とたたえた。また、躍進の一因として橋本副団長はマルチサポートハウスを挙げ、「(現地入り後は)激しいトレーニングが既に終わっているので、コンディショニングが一番大事。ご飯などの日本食や炭酸泉が良い効果を上げた」と分析した。」(毎日新聞2012.8.13) 2008年 北京オリンピック(各国メダル数は図録3984)
オリンピック北京大会における金メダル数は9個、メダル総数25個となった。金メダル、メダル総数ともに前回を大きく下回る結果となった。もっとも一回前の2000年シドニーと比較すると金メダル数、メダル総数とも北京の方が上回っている。 北京の日本選手団はよくやった方だという評価が一般的である。「アテネ以降の世界選手権の実績を加味すれば、ほぼ実力通りだ。」(毎日新聞2008.8.25)という訳である。メダル数の減少を福田日本選手団長はこう説明しているという。「日本の実力はアテネの時点と変わらないが、世界の競技レベルが上がった。」(同上)この「実力」自体が世界と比較すると問題である点は、図録3984の人口比を考慮した評価を参照。 北京オリンピックでの特徴は、アテネで活躍した選手がそのまま力を維持したことである。競泳男子平泳ぎで連続2冠を達成した北島康介選手をはじめ金メダルのうち7個が連覇だった。 なお、北京オリンピックのメダル数が関心を集めている中、「「金」10個なら株高?−五輪効果に市場も期待」という新聞記事で、ロサンゼルス五輪(1984年)以降の6大会の開催期間中の日経平均株価を調べると金メダル10個のロスで3.5%高、16個のアテネで1.4%高、一方、5個以下の4大会でいずれも下落だった点から、株式市場からも「頑張れニッポン!」コールが高まってきたと報じられた(東京新聞2008.8.15)。 2004年 アテネ・オリンピック(各国メダル数は図録3985)
オリンピック・アテネ大会における金メダル数は16個と過去8大会を上回り、過去最高の東京大会と同じであった。メダル総数は、過去最高のロサンゼルス大会を上回り、過去最多の37個であった。 どうしてアテネ・オリンピックでメダルが増えたかについては、政府の支援策強化、若者のマインド変化、女性力の向上、訓練方法の改善、個人種目選手の海外高地特訓、ドーピング検査強化の影響などがあげられていた。 (2004年8月22日収録、2008年8月16日メダル数ジンクス記事追加、8月17日柔道メダル数の表追加、8月25日更新、8月26日種目集計、コメント追加、2012年6月27日男女別金メダルのグラフ追加、7月23日ロンドン・オリンピックの項作成、7月25日女性選手比率コメント追加等、7/31・8/2・8/6・8/10・8/12・8/13更新、2012年8月14日コメント追加、2016年8月13日柔道結果、8月17日更新、8月18日・19日・20日・22日・23日更新、9月20日図にランキング推移追加、2018年7月29日金銀銅メダル(主要競技別)の表、2020年1月5日2019年世界選手権メダル数、1月24日メダル数予想、2021年7月24日直近のメダル予想、7月25日2021東京五輪の日本メダル数表、8月8日最終結果、8月14日コメント拡充、2024年6月26日以降更新、7月6日メダル目標、7月16日各国メダル獲得数予想、7月27日開幕、7月31日長期推移の項目と対世界割合推移図を追加、8月10日グレースノート開幕時メダル予想、8月15日柔道メダル更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||