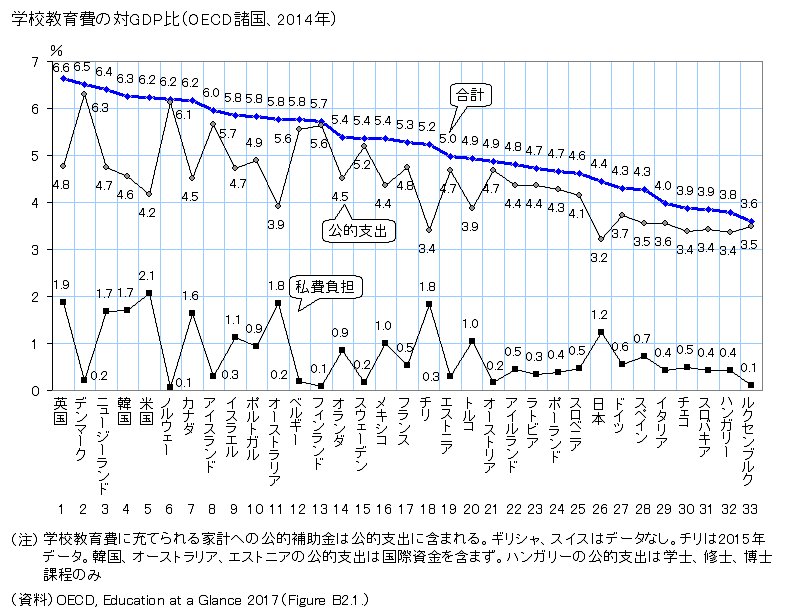
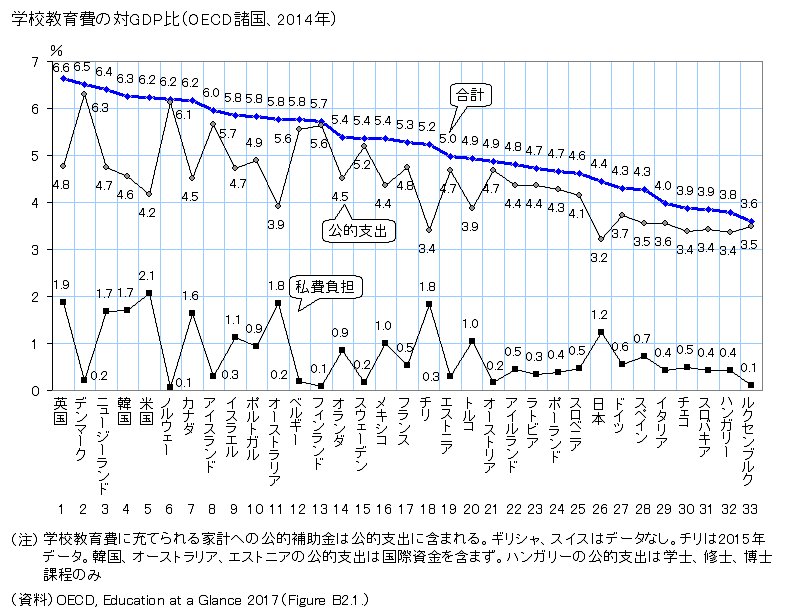
対象国は、ギリシャ、スイスを除くOECD33カ国であり、具体的には、合計の値の高い順に、英国、デンマーク、ニュージーランド、韓国、米国、ノルウェー、カナダ、アイスランド、イスラエル、ポルトガル、オーストラリア、ベルギー、フィンランド、オランダ、スウェーデン、メキシコ、フランス、チリ、エストニア、トルコ、オーストリア、アイルランド、ラトビア、ポーランド、スロベニア、日本、ドイツ、スペイン、イタリア、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ルクセンブルクである。 私費負担が高いのは米国の2.1%に次いで英国の1.9%、オーストラリア、チリの1.8%である。韓国は1.7%とこれらに次いでいるが、韓国の場合、学校教育費の他に、塾や家庭教師の私的負担もこれに加えて大きいといわれる。 英国、韓国、米国と並んで、ニュージーランドやカナダといった英語圏諸国、デンマーク、ノルウェー、アイスランドといった北欧諸国の学校教育費比率が高くなっている。英語圏諸国は私費負担が多く、北欧諸国の場合は公的負担がほとんどである。 日本はOECD諸国の中で第26位と学校教育費の対GDP比の水準は低い。ただし、私的負担の比率は対GDP比で1.2%となっており、低くはない。逆に公的負担の比率は3.2%と低く、OECD諸国の中で最下位となっている。最近では格差社会論などとの関連で、教育費の社会保障的な側面、すなわち貧乏人でも良い学校へ行けるという機会の平等が日本では失われてしまっている証左として、こうした学校教育費の公的負担割合の小ささがあげられることが多い(広井良典「持続可能な福祉社会―「もうひとつの日本」の構想」ちくま新書、2006年、p.25、橘木俊詔「格差社会―何が問題なのか」岩波新書、2006年、p.180)。 なお、教育は、こうした社会保障的な側面というより、従来からは、社会あるいは個人の投資としての側面が重視されてきたが、教育費の高さが、各国の教育に対する熱心さ(重視度)、あるいは教育投資の程度をあらわしているといえるとしても、教育投資の効率が分からないので、実質的な教育投資の程度を必ずしも反映しているとは限らない。 社会保障費は高齢化比率と比例しており、ただでさえ社会保障費が少ない日本は高齢化比率を考えに入れると一層社会保障費の少なさが目立っている(図録2798)。それでは、学校教育費は年少人口比率と比例しているはずであり、その点を考慮すると日本の教育費は多いのか、少ないのか。これを見るため、下に、年少人口比率との相関図を描いた。OECD諸国の中でもメキシコやトルコといった低所得国、あるいは高所得国の中でも特段の出生促進政策をとっているイスラエル(図録1025)を除いた。 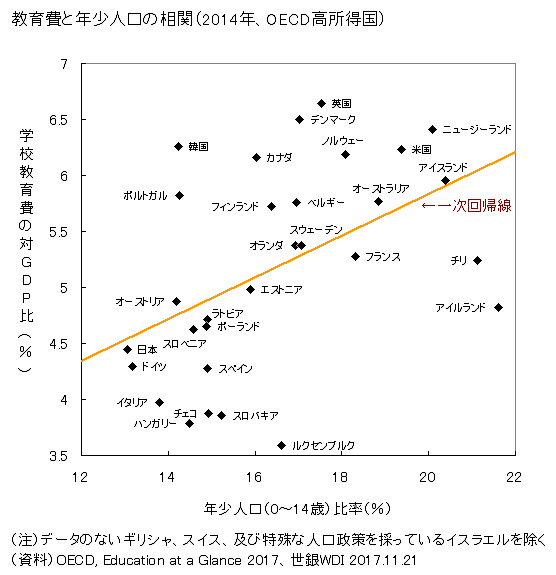 これを見ると、学校教育費の主な対象となる年少人口(0〜14歳人口)の比率との相関では、日本はほぼ一次回帰線上にあり、日本の学校教育費はそれほど少ないとはいえない。ドイツ、イタリア、スペインといった国の方が年少人口との相関では教育費支出が少ないといえよう。
逆に韓国はただでさえ多くを教育費に支出しているが、年少人口比率との相関では世界の中でも最も熱心に教育費にお金を注ぎ込んでいるということがわかる。年少人口比率の割に教育費が多い点からは、ポルトガル、カナダ、デンマーク、英国なども韓国と似た教育熱心な国であろう。 米国やニュージーランドの教育費比率が案外高いのは年少人口比率が比較的高いからだということもわかる。 文部科学省は学校教育費が冒頭の図のように先進国の中でかなり低い水準である点をあげて、教育費予算の増額を要求しているが、財務省から、学齢人口1人当たりではそれほど低いわけではないという資料を突きつけられて、なかなか先進国並みの少人数学級を実現するのに十分な予算獲得に至らない状況にある。日本のような「小さな政府」で(図録5194)、高齢化が進んで社会保障費が増大し、それでも社会保障費は高齢化比率との見合いでは先進国並みには確保できていない現状(図録2798)を理解した上で、ここで掲げた散布図を見ると財務省の言い分にも一理があるといえよう。 もともと儒教的な志向のあるマスコミは文部科学省の後押しをする傾向がある。例えば、OECDからの2015年版の教育費比較のデータ公表を受けて東京新聞は2015年11月25日に「教育公費、日本また最下位」という見出しで次のように報じている。「日本の国公立小の一学級当たり児童数は27人(OECD平均21人)で加盟国中3番目に多く、国公立中の一学級当たり生徒数は32人(同24人)で二番目に多かった。また、物価の上昇率を勘案した国公立小中学校の勤続15年の教員給与は、OECD平均が増加傾向なのに、日本は05年から13年の間に6%減ったと指摘した。アンドレイアス・シュライヒャーOECD教育・スキル局長は「給与、勤務条件を見ると、日本の場合は悪化しており、問題があるように思われる。優秀な人材を教職に引き付けることが重要だ」と述べた」。 ところが、OECDが世界的に公表したこのデータに関するコメントは以下のようなものだった(OECD東京センター訳、2015年11月24日づけニュース)。 「「図表でみる教育2015年版」では、政府が抱える教育資金の問題も明らかにしています。2010年から2012年にかけて、ほとんどの国でGDPが上向きに転じ始めましたが、OECD加盟国の三分の一以上の国々で、初等教育から高等教育までの教育機関に対する公財政支出が減少しました(オーストラリア、カナダ、エストニア、フランス、ハンガリー、イタリア、ポルトガル、スロベニア、スペイン、米国)。初等、中等教育への予算が削減される中、ほとんどの国々が学級規模を大きくすることではなく教員の給与を削減することを選びました。しかし、OECDのPISA調査からは、フィンランド、日本、韓国といった成績の高い国々がインフラや学級規模よりも授業と教員を優先していることが明らかになっています」。日本の教員給与は悪化したとはいえ、他の職業と比べなお有利という前提でコメントしているのである。PISA調査では日本の教員は仕事への不満は非常に大きいが、職業選択について後悔している者は少ないのである(図録3879、またエストレーラ誌2016年1月号参照)。 その後、データ的には似た状況が続いているが、2017年10月の解散・総選挙で安倍首相が消費税引き上げの増収分をこれまで予定していた財政赤字の削減ではなく幼児教育の無償化など教育費に充てると公約したため、与党圧勝を受け、教育費の公的支出の増加が予想される事態となっている。 (関連図録) 教育費の私的負担の比率は家計消費支出の中の教育費負担の状況に影響している(図表2270参照)。 また、韓国の私的教育費負担の高さは、韓国の非常に低い合計特殊出生率の1要因であるといわれる(図録1550参照)。 さらに、少子化対策と合わせて教育費の公的負担が、年金、福祉など高齢者対策に比して高い国ほど出生率が高く、逆に高齢者対策のみが大きくなると子育てを逃れる者(フリーライダー)が増えて出生率が低くなるという点(日本が典型)は図録1587参照。 (2004年8月18日収録、2005年7月20日更新、2006年10月13日更新、2007年9月20日更新、2009年5月8日更新、2011年10月10日更新、2012年1月3日更新、2013年7月27日更新、2014年8月23日年少人口比率との相関図追加、2015年8月9日更新、11月25日更新、2017年11月21日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||