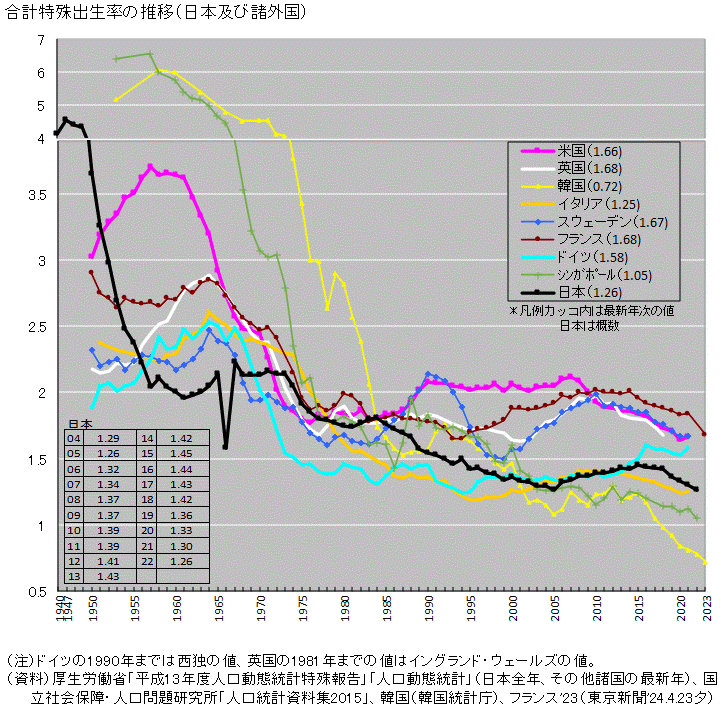
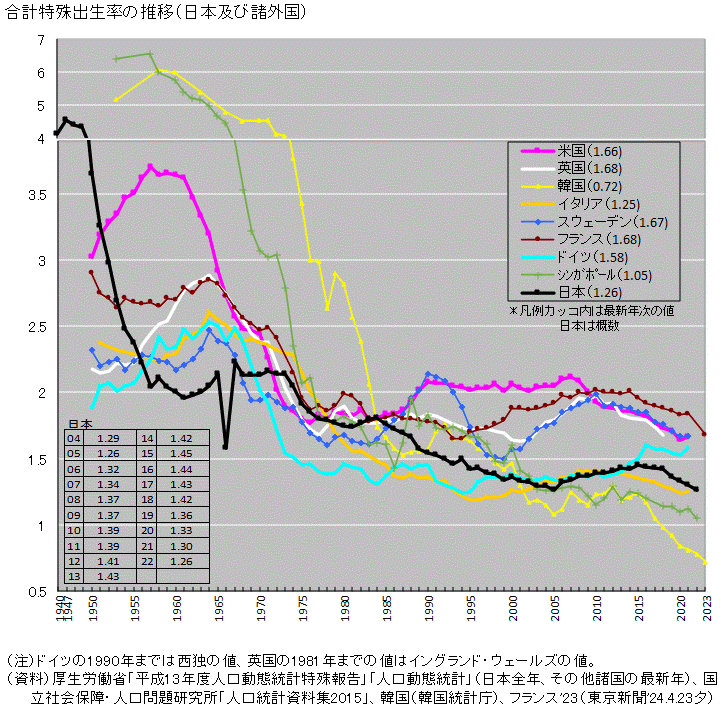
世界各国の直近の合計特殊出生率の分布マップは図録1449d参照。 日本の最新2024年の値は1.15と昨年の1.20からさらに低下し、過去最低となった。 出生率は、2前後の水準の4カ国(米英仏ス)と1.5以下の5カ国(日韓伊独シ)と両極に分かれているのが目立っていたが、最近は、前者も2以下に低落した。またシンガポールは韓国に続いて1を切った。 なお、参考として、これと重なる諸国で実施された「少子化に関する国際意識調査」の結果を図録1544から以下に再掲した。当然ではあるが、合計特殊出生率の高低と「子供をもっと増やしたいかどうか」とはほぼ平行した結果となっている。もっともフランスは「増やしたくない」がやや多い割りに出生率は高い。 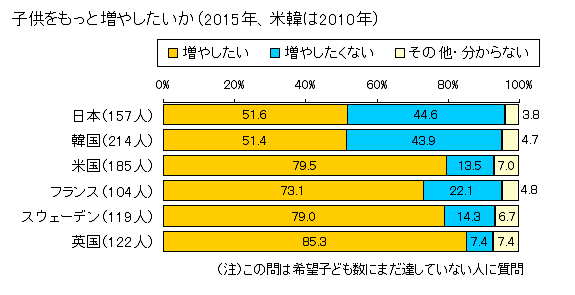 また、同調査による「理想の子ども数の国際比較」(図録1550a)を見ると理想の子ども数には各国そう違いはなく、理想と現実のギャップが大きい日韓と小さい欧米の対比が理解される。 下図のように日本の合計特殊出生率の予測と実績は1990年代まで食い違いが大きく、予想以上に落ち込んだことが分かる(クリックで原資料へ)。現在はほぼ2002年〜12年推計はむしろ予想より高く推移することもあったが、2017年推計は再度実際が大きく下回った。2023年推計も24年から回復することになっているがあやしそうである。 ▼最近の動向 (日本、東アジア)
日本では1989年に合計特殊出生率が急落し、過去最低だったひのえうまに当る1966年の1.58を下回ったことから起こった「1.57ショック」をきっかけに政府は少子化対策に取り組んできた。 近年の動向は、2005年の1.26を底に上昇傾向をたどり、2015年には1.44まで上昇したが、その後、低下傾向に転じ、2019年には1.36と対前年でマイナス0.06と大きく低下、2020年、2021年もそれぞれ1.33、1.30とさらに低下した。最近2年の低下にはコロナの影響もある。 他方、出生数や粗出生率の動きは一貫して低下傾向が続いている(図録1553)。 2015年の出生率上昇について、厚労省は、平成「25、26年ごろに経済状況や雇用情勢が好転し、子供を産もうと思った人が増えたことが考えられる」としている(産経新聞2016.5.23) 2014年の出生率低下については、これまで出生率を上昇させていた第2次ベビーブームの団塊ジュニア(1971〜74年生まれ)の30歳代になってからの「駆け込み出産」の効果がこの世代が40歳代となって尽きたからとされる(毎日新聞2015.6.6)。 2010年の上昇について、厚労省は「晩婚化が進んだ30代後半の団塊ジュニアを中心に出生数が増加したことや、第2子以上の出産が増えたためと分析している。」(産経新聞2011.6.1) 2008年までの「合計特殊出生率の上昇について厚労省は、長期低落傾向にあった20代の数値が下げ止まったことを要因ととらえ、理由の一つに昨年秋までの景気回復を挙げる。同省は「(昨年秋以降の)景気悪化の影響は注意深く見守りたい」としている。」(毎日新聞2009.6.3) 2007年の合計特殊出生率は1.34と2年連続の上昇となった。上昇の理由として厚生労働省は「団塊ジュニア世代を中心とした30代後半の”駆け込み出産”が要因のひとつと見ている。」(東京新聞2008.6.5) 2006年の合計特殊出生率は1.32と05年の1.26からかなり回復した。政府の見方であるが、「厚労省は、同出生率の上昇要因として、(1)第3子以降の出生率が12年ぶりに増えるなど、第2、3子以降の増(2)71〜74年生まれの団塊ジュニア世代女性の出生率増(3)結婚数(73万973件)の5年ぶり増による第1子増――を挙げる。(1)〜(3)はいずれも景気の回復が一因と厚労省はみている。」(毎日新聞2007.6.7) 2005年の合計特殊出生率は1.25と例年になく大幅な低下であり、発表時が政府の少子化対策の発表直前ということっもあって、こんな対策で大丈夫かという懸念がもたれている。(その後、国勢調査人口確報値にもとづく確報値が発表され、1.26に訂正) 2004年の合計特殊出生率は1.29とかろうじて前年度と同じであった。長らく日本を下回っていたイタリアの同年値は1.33とついに日本と逆転するに至っている。 2003年の合計特殊出生率1.29は前年の1.32からかなり低下した値であった。この数字と同じ値の概数値が発表されたのは、国民的な関心が集まった年金法案が国会で可決された直後であり、年金収支の将来展望のベースとなった合計特殊出生率の将来想定値以下となったため年金収支の将来フレームの信頼性を揺るがすものとして注目された。 その際、出生率回復のための年金制度の工夫として、フランスとスウェーデンの例があげられた。毎日新聞(04年6月11日)によれば、「フランスでは3人の子どもを9年間養育した男女に年金額を10%加算するなどし、出生率を94年の1.65から02年に1.88に回復させた。スウェーデンは、子どもが4歳になる間に所得が減っても、年金計算は(1)子どもが生まれる前年の所得(2)年金加入期間の平均所得の75%(3)現行所得に基礎額(約50万円)を上乗せした金額−の3通りから最も有利なものを充てるなどの対策で、01年に1.57だった出生率は02年に1.65に伸びた。」 なお、韓国では、2000年から05年にかけて、合計特殊出生率が1.47、1.30、1.17、1.19、1.16、1.08と急激に低下し、日本やイタリアを下回るに至っている点が韓国国内でも関心事となっった。韓国における出生率の低下は日本より急激であり、日本においては祖父母と子の世代の子育てに関する意識ギャップと同様なものが韓国では親と子の世代に生じていると想像される。その後、06年からは回復に転じ2010年には1.22となっている。しかし、その後、さらに出生率が低下し始め、2017年には1.05、そして18年にはついに1を下回り、0.98にまで達した。このため、5年ごとの将来人口推計を急遽早めて推計しなおし、それによると場合によっては来年から人口減少、さらに将来は日本を上回る高齢化率に達するとの見通しである(東京新聞2019.6.3夕)。 韓国は日本と同様の傾向を辿っているが、ともかく動きが急であり、毎年の動きが激しい点が日本と異なる。国連推計2019年改訂で高齢化率の将来予測が2050年以降日本を上回るに至った点については図録1157参照。 韓国の出生率の低さについては、教育費、特に塾代を含めた家計負担の大きさをあげられる場合が多い。確かに、学校教育費の私的負担では韓国は世界1の高さとなっている(図録3950参照)。さらに、ソウルへの一極集中の影響が指摘される。「韓国はソウルを中心として、急速に経済発展を遂げてきた。その結果、多くの若者がソウルにある大学、企業を目指すようになり、現在は人口の約半分がソウルの首都圏に集中。不動産価格や教育費の高騰などを招き、結婚や出産がしにくい社会環境が生まれた。未婚女性の48%が「子どもがいなくてもいい」と感じているとの統計もある」(東京新聞同前)。 エマニュエル・トッドは韓国の出生率の低さをドイツや日本と同じように直系家族(0003)ならではの教育重視、特に「産んだ子どもをグローバル競争に参加できるレベルにまで教育すること」を目指すからとしているが、それにしてもその極端な低さは、社会学者であるチャン・キョンスプが提示した「圧縮された近代」、すなわち「北ヨーロッパの生活様式と消費水準に追いつこうとする強力な努力」「子供の数が少なければ少ないほど、高い消費水準と外見的にモダンな生活水準により早く到達でき」るという誘引に求めている(「我々はどこから来て、今どこにいるのか? 下」、文藝春秋、p.165)。 シンガポールも、出生率の大きな低下が少し先行しているものの、韓国とよく似た長期推移をたどっており、日本を含めて、経済発展をとげた儒教国としての共通傾向をあらわしているのではないかと思わせる。 時系列データが得られなかったので図には取り上げていないが、WHOによれば、中国の合計特殊出生率は、1992年に2.0、2002年に1.8とされており(Core Health Indicators)、それほど高くない。これが一人っ子政策の効果によるものか、一部で言われているように、政策を実施しなくとも中国でも教育費などが高くなり、余り多くの子供はそもそももてないという要因の効果なのかは分からない。 図録1560では、日本、中国、韓国を含めたアジア諸国の合計特殊出生率を比較しているので参照のこと。また、都道府県ごとの合計特殊出生率と教育費の高さとの相関を図録1570に示したので参照されたい。日本の粗出生率(人口千人当たりの出生数)の推移は図録1553参照。理想の子ども数との対比は図録1551参照。 (欧米)
米国の出生率が少し前まで高水準で推移していた理由としては、(ア)TFRが3.00と高いヒスパニック系人口の増加、(イ)高い若年出生率、(ウ)出生力の高い宗教人口の存在、が挙げられていた。もっとも最近はサブプライムローンやリーマンショックの影響による不況で2007年をピークに移民女性を中心に出生率が大きく低下している(図録8650参照)。 出生率が比較的高く、水準が上昇傾向にあったグループである米国、英国、フランス、スウェーデンにおいて、金融危機以降、出生率が低下している点が注目されている。図には掲げていないが同等の水準にあるノルウェーやオーストラリアでも最近出生率が低下し続けている。当初は、世界金融危機、欧州債務危機の短期的影響で出産年齢の女性が出産を遅らせているだけだと考えられていたが、6〜7年経っても反転の気配がなく、むしろ、構造的な変化が起こっているのではないかという考えが台頭している(The Economist April 30th 2016, "The strange case of the missing baby"による。以下同様)。 こうした低下傾向の要因としては、ひとつには、出生率水準の上昇に寄与していた移民人口の出生率水準が近年顕著に低下している点があがられる。この点については、図録9020のコラムを参照されたい。 この他、英国での住宅難が要因としてあがられる。英国では、民間賃貸住宅で暮らす25〜34歳の10年前は24%だったのが2014〜5年には46%へと上昇している。賃貸でも子どもは生めるはずであるが、自分が育った環境と違う環境での出産にはブレーキがかかるというイースタリン説が当てはまるのではないかと考えられている。 さらに、子育てできないというより、かつてより家庭生活が困難になったという漠然とした心理的要因が効いているのではとも考えられている。英国エコノミスト誌は豊かな国11カ国では64%が子どもたちの世代が親の世代より暮らしが悪くなると考えている点を指摘している(図録4532でもふれているのと同じピューリサーチセンターのデータ)。そしてこれは米国大統領選でのトランプの躍進、フランスの国民戦線の脅威、英国でのEU嫌いやスコットランドの分離運動といった最近の政治意識とも共通の根をもつものとされている。 一方、欧州全体の低下傾向とは対照的にもともと水準の低かったドイツではむしろ上昇に転じている点が目立っている。やはり経済情勢の好転が影響しているのであろうか。 (スウェーデン) スウェーデンでは、1980年代前半までは、女性の労働市場参加率の大きな拡大(図録1505で詳述)に対応して出生率は低下傾向をたどったが、その後は雇用情勢の好転が出生率増、悪化が出生率減にむすびつくかたちに変化した(失業率の動きについては図録3080参照)。
「1983年までは女性の労働力参加が出生率の低下を引き起こしてきた(あるいは少子化が女性の労働力参加を可能にしてきた)。しかし1984年以降は出生率は景気に左右されるようになる。すなわち、景気がよくなると女性の雇用が増え、かつ出生率も急上昇する(1980年代の後半)。景気が悪くなると女性の雇用が減り、かつ出生率も低下する(1990年代)。後者の背景には、税収の悪化のため、公的に雇用される女性が減ったことと、高い失業率のために若者が就業延長や復学して結婚を先延ばしにしたことがあると思われる。(中略)他方で2000年以降の出生率の上昇は、失業率だけでは整合的に説明できない。2002年から2005年までは失業率は増加し、女性労働力参加率が横ばいであったが、その間出生率は増加している。これは、長く続いた1990年代の不況のもとで産み控えをしていた人々が子どもをつくりはじめた、という事情もありそうだが、このデータから原因を読み取ることはできない」(筒井淳也「仕事と家族」中公新書、2015年、p.64〜65)。 ▼合計特殊出生率レベルの3グループ 毎日新聞「核心」コラム(2012年3月26日)に国立社会保障・人口問題研究所人口構造研究部長、鈴木透氏が合計特殊出生率レベルの3グループについて整理しているのでこれを引用する。
「近年の各国の出生率を比較すると、三つのグループに分けられる。 第1は合計出生率が1.5を超える北西欧(ドイツ語圏を除く)と英語圏先進国。第2は1.3〜1.5の間に入るドイツ語圏・南欧・東欧諸国で、日本もこのグループに属す。第3は1.3を下回っている韓国・台湾である。 韓国は2005年に1.08、台湾に至っては10年に0.895という驚くべき低出生率を記録した。 出生率が高い農村部を含む人口数千万の国や地域で1.0を下回る合計出生率が記録されたのは、台湾が初めてだ。 経済成長率の鈍化、若者の失業や就業の不安定化、教育費など子育て費用の高騰、働く女性が増え、賃金やキャリアなどのマイナス面を考えると出産しにくい、といった低出生率をもたらす要因は3グループに共通している。 こうした変化が出生率を引き下げる度合いは、文化圏によって異なる。結果から事後解釈するなら、北西欧および英語圏の家族パターンはそうした変化に耐性が高いとみられる。 だが、北西欧型と異なる家族パターンを持つ国がそうした変化に直面すると、社会経済システムと家族システム間の不整合が大きく、出生率がより低い水準まで低下するのだろう。 日本の家族パターンがドイツ語圏・南欧・東欧に近く、北西欧型からやや距離があるのに対し、韓国・台湾の儒教的家族パターンは北西欧型からさらに遠いと思われる。 中国の統計はいまひとつ信用できないが、少なくとも沿海部では韓国・台湾並みの低出生率が現れている兆しがある。 韓国・台湾とも問題の深刻さを認識し、出生促進策に踏み切った。韓国は06年以降、「低出産・高齢社会基本計画」を策定。養育のための休暇制度の改善や活性化のほか、結婚・出産・育児に対する現金・現物給付などを実施している。 台湾は08年に人口政策白書を発表。保育サービスの質的向上と多様化、住宅ローン補助のような現金給付、勤務形態の柔軟化や企業による保育支援、休暇制度の充実などを少子化対策として打ち出した。 韓国・台湾とも、大きな財源を要する政策はハードルが高く、政府支出は日本と比べても微々たる水準である。 一方で、両者は外国人労働者の導入を既に始めており、産業研修生制度以外にはごく限られた受け入れ制度しかない日本に比べると先を行っている。 滞在期間を限定するなど条件付きではあるが、韓国は04年から、外国人雇用許可制度を実施している。台湾は1990年以降、外国人労働者の雇用を認め、製造業、家事使用人、介護士などで東南アジアの外国人労働者が増えているとされる。 こうなると近い将来、日本と韓国、台湾の間で優秀な移民の獲得競争が行われる可能性もある。日本は少子化・高齢者対策だけでなく移民政策を含む人口政策全般について、より詳細な比較研究と対策が必要だろう。」 ▼長期動向 (人口転換) 工業化と近代化に伴って人口転換が起こるとされる。すなわち保健医療の発達と子ども数の減少のタイムラグから多くの国は、多産多死→多産少死→少産少死の過程をたどる。多産少死の過程で人口爆発現象が生ずる。 日本の場合、戦前から多産から少産の動きははじまっていたが、戦後のベビーブームの終息という状況も加わって、1950年代に合計特殊出生率は大きく低下した。この出生率低下は、当初は人工妊娠中絶によるところが大きかったが、急速に避妊(受胎調節)の普及によって取った代わられていった(末尾の【コラム】参照)。 米国でもベビーブームが起こったが日本より少し遅れた。韓国では、多産から少産へのシフトは1960年代〜70年代に起こった。ヨーロッパでは人口転換は戦前に終了していた。 いわゆる少子化の問題は、こうした人口転換にともなう多産から少産へのシフトが終わってからの更なる子供数の減少を指す。 (少子化の動向) 1960年代以降の合計特殊出生率(TFR、生涯で女性が何人子供を産むか)の変化を見ると、日本より水準の高かった欧米は、日本のなだらかな低下とは対照的な急激な低下を経験し、1980年代前半には欧米、日本ともほぼ同じ少子化水準に達した。(第1期) それ以降1980年代〜90年代前半も欧米と対照的である。すなわち、米国、スウェーデン、デンマークなど欧米では反転して高くなった国も多いのに対し、日本はなお低下を続けている。(第2期) しかし、1990年代前半以降は、一定水準まで高まってから安定する国もあれば、再度の出生率の低下と回復を繰り返す国もある。(第3期) (想定される理由) 第1期の違いは、欧米における女性の労働力率の急上昇から生じていると考えられる。 第2期の違いは、福祉国家的な託児所の整備、企業の支援制度や男女の育児分担、子育て世代への財政的支援・税制優遇によるものと考えられる。また、プロテスタント系の国における婚姻と出産との分離(婚外子)の社会認知も影響していると思われる。 第3期の欧米の再低下・回復は財政的な制約を背景とした福祉国家的政策の見直しやそのまた再見直しによるものと考えられる。 なお、以上のような少子化の相対比較の要因分析は仮説的な性格の強いものであり今後研究を深める必要がある。 (展望) 欧米では少子化をくい止めるために長い間かけていろいろ工夫してきたがなお財政上の制約もある。日本の場合、第2期と第3期の欧米の課題に同時に取り組んでいく必要が生じている。今後女性の労働力率の上昇を期待するならなおさらである。
(2004年6月11日データ更新、6月12日・8月7日・8月18日コメント改訂、9月9日日本確報値、2005年5月18日・6月1日・9月14日更新、2006年4月17日更新、4月28日参考図追加、6月2日・12月1日更新、2007年5月28日更新、2008年5月22日・6月4日更新、2009年3/9・6/3更新、2010年6月2日更新、11月10日米国コメント追加、2011年5月31日参考図更新、6月1日更新、2012年3月26日「▼合計特殊出生率レベルの3グループ」追加、6月6日更新、2013年3月29日コラム追加、6月5日更新、2014年6月4日更新、12月13日米国コメント改訂、2015年6月2日日本以外1995年以降値を人口統計資料集2015で更新、グラフ改善、6月5〜6日更新、2016年5月23日更新、6月12日欧米の最近の出生率低下傾向について、「少子化に関する国際意識調査」更新、12月5日国調確報により1.46から1.45に修正、2017年2月23日スウェーデンの記述追加、6月3日更新、6月7日シンガポール追加、2018年6月1日更新、2019年6月8日更新、6月26日韓国コメント補訂、8月28日韓国値更新、2020年6月10日更新、9月2日韓国値更新、2021年6月4日更新、9月25日予測と実績の食い違い、2022年2月25日日本最終確定値、6月3日更新、12月11日エマニュエル・トッド引用、2023年2月22日韓国最低値更新、6月2日更新、2024年2月29日韓国最低値更新、6月5日更新、6月12日予測と実際のギャップ図更新、7月13日日本以外ソースを国連人口推計に変更し更新、2025年2月27日韓国最新、6月4日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||