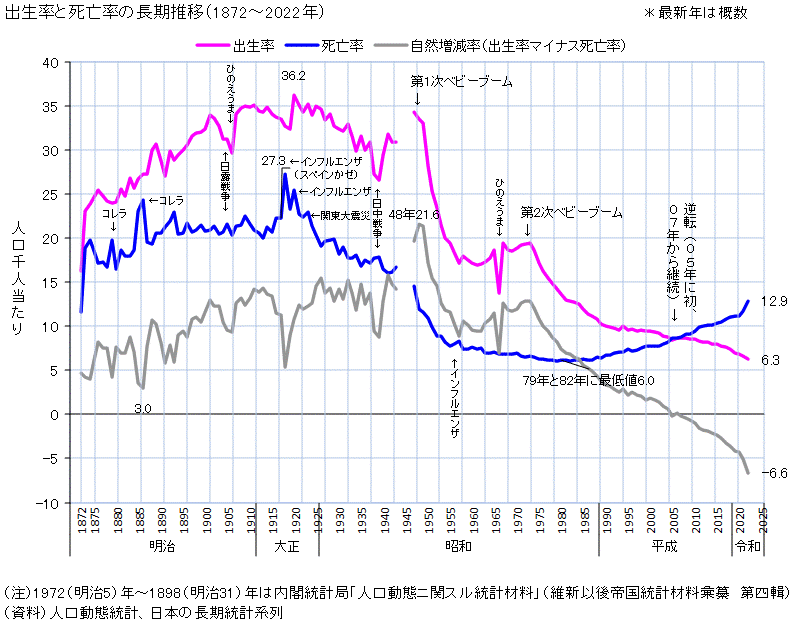
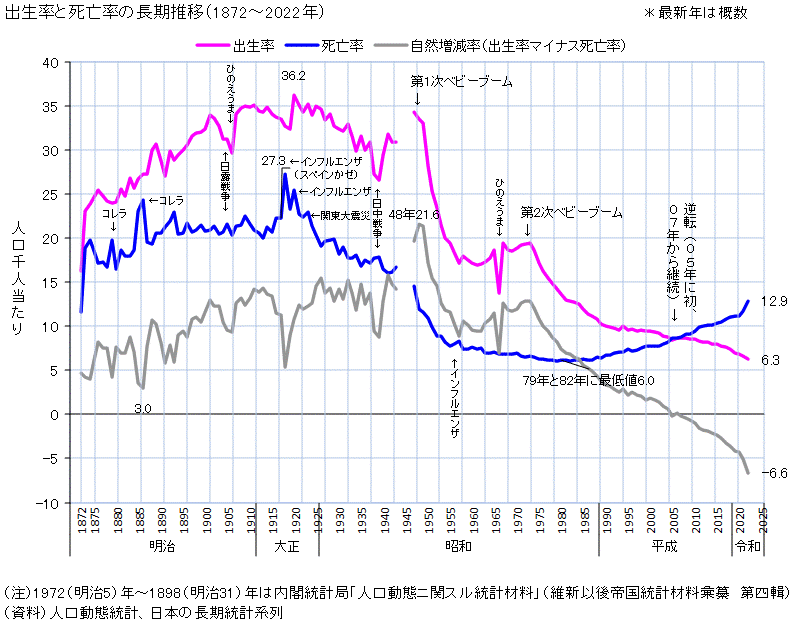
| �@ | �@ | ||||||||||||||||||
�@�o�����͖��N�̕ϓ����������������ڂł͖����ȍ~�A�吳����܂ŏ㏸���i�s�[�N1920�i�吳9�j�N�j�A����ȍ~�A�傫���ቺ���Ă����B �@�吳����ɂ�����o�����̑������猸���ւ̓]���̌_�@�ƂȂ����̂́A�Y�������ւ̓������ʉƒ�ւ̓d���̕��y�̉e���ƍl�����Ă���B �@�j���[���[�N��1916�N�ɎY�������N���j�b�N���J�݂������ƂŗL���ȃT���K�[�v�l��1922�N�ɗ������A�u�w�l���E�v��u��w�̗F�v�Ȃǂ̎G�����v�l�̎咣�⍑���̔��Θ_�ɂ��ďЉ��ȂǎY�������ւ̋C�^�����܂����B���ʂ̊����g��Ȃ������Ŋm���ȕ��@�Ƃ��āu���쎮��D�@�v���J�����ꂽ�̂����̍��ł���i�����Z�E��������q�u�吳�f���O���t�B ���j�l���w�ł݂����Ԃ̎����v���t�V���A2004�N�Ap.223�`224�j�B �@�u����43�N��194.9�����ɉ߂��Ȃ��������{�S���̓d����t�����́A�吳14�N�ɂ�2732.1�����Ɩ�14�{�ɑ����Ă���B���̂Ȃ��ɂ́A�ƒ�p�ȊO�̂��̂��܂܂�Ă���ɂ��Ă��A15�N�Ԃɂ��ꂾ���̑������݂����̂́A���̎��������ł���B�d���͏����́u��̐����v��ς����A�Ƃ����Ă������낤�B�d���̂��ƂŁA�l�X�͎G���⏑�Ђ�ǂނ��Ƃ��ł������A��Ȃd�����e�ՂɂȂ����B�吳���Ɏn�܂�s�s�̏o�����̒ቺ�́A�d���̕��y�Ə��Ȃ��Ƃ������I�ɂ͈�v���Ă���B�s�s�ł͖�̌�y�������A�_���ɔ�ׂĂ��������Ⴉ�����o�����́A����ɒႭ�Ȃ����v�i���㏑p.74�`76����̈��p�҂ɂ���\��j�B �@1906�i����39�j�N�A1966�i���a41�j�N�̏o�����̈ꎞ�I�ቺ�͕��߁i�Ђ̂����܁j�̔N�ɓ�����A���̔N���܂�̏����͋C�����������A�v��K�ɕ~���A�v�̖����k�߂�Ƃ������M�ɉe������ďo���������Ȃ��������߂ł����i���j�B �i���j�Ђ̂����܁i���߁j�̖��M���Љ���ɂȂ����̂͑吳����炵���B��Ƃ̐�[�N���́u���߂̖��]�A���v�i1925�N�A�S�W��26��p.79�`81�j�Ƃ����G�b�Z�C�ł��������Ă���B�u�����������߂̖��������ʊ��Ȃ�Ŏ��E�����߂��̂́A���ꂪ�V���̋L���Ƃ��ďo���߂��̂́A�吳�\�N�̂��Ƃł���v�B�����āA�u���߂̖��ɂ͏����C�ŁA�����ŁA�q���ȏ����s�v�c�ɑ����v���R�Ƃ��āA�ُ�ȂقǍ����̊Ԃň����S�����g�������I�푈���ɐ��܂ꂽ�Ƃ����v����Ǝ����Ƃ��Čf���Ă���B�u�����O�\��N�ɐ��ꂽ���̑唼�͎O�\���N�����N�ɂ����ĕ�̑ٓ��ɂ����B�����Ŕޏ��͂ǂ�ȑً��������B���܂ł��킢�Ə����Ƃ̐F�ɐ��܂����A���ƓI�����ł���B�e��̐l�ł�����ƒ낾���̊����z�����Ă��Y���̓����͖��炩�ł���v�B�܂��A�u�M�����m�Ɣނ��{���ɑҘ̂т����Ƃ̊����Ɗ���Ƃ̌����ɂ���ďh�����̂��A���߂̖��ł��邱�Ƃ��v���A��퐦�S�̋C�ɑł��������B���������͂ɂ͍��ƓI����ƍ����Ƃ�����B�����̂��Ƃ͓ǎ҂�낵����z�������v�B �@1939�N�̗������݂͓����푈�̓����ɂ����̂ł���B �@�I��O��̏o�����ቺ�ߍ��킹��悤��1947�`49�N�ɂ͑�1���x�r�[�u�[����������A����ɂ��̎q�ǂ��̐��オ���܂�鎞���ɑ�2���x�r�[�u�[�����N�������B �@���������o�����̒Z�������͊e�Εʂ̐l���s���~�b�h�ɂ����Ղ��c���Ă���i�}�^1164�Q�Ɓj�B �@���S���͒Z���I�ȑ����������Č���ƁA�����ȍ~�A������x���������������Ă������A���a�ɓ����Ēቺ�X�������ǂ�A���̍��x�������܂ő傫�Ȓቺ�X�����������B����ȍ~�͉����X���ƂȂ������A����20�N�͍���̉e���Ŏ��S�����X���I�ɏ㏸���Ă��Ă���B �@�吳�������玀�S�����ቺ�X����H�邱�ƂɂȂ����̂́A�@���O�q�����Ðݔ��̏[���ɂ��s�s���̎��S���̒ቺ�i�s�s�a�n���������Ă͂܂�_�������s�s���̕����Ⴉ�������S�����吳���ɋt�]�j�A�A�a�@�o�Y�̑����A���~���N������ɂ��M��̗e�Չ��Ȃǂɂ��������S���̒ቺ�i��O���{�͍H�ƍ��̒��ł��ł������������S���̍��������j�ɂ����̂Ƃ����i�����Z�E��������q�u�吳�f���O���t�B ���j�l���w�ł݂����Ԃ̎����v���t�V���A2004�N�Ap.220�`221�j�B �@�ߔN�̏o�����̒ቺ�Ǝ��S���̏㏸�̌��ʁA�����ȍ~�͂��߂Ď��R��������2005�N�Ƀ}�C�i�X�ɓ]���A�܂�2007�N����͖��N�}�C�i�X�������Ă���B���v����o������2005�N���ɂ��₩�ȏ㏸�ɓ]���Ă��邪�i�}�^1550�j�A�o������o�����͒ቺ�X���𑱂��Ă���B �@��������吳�ɂ����āA�ȉ��̂悤�ɗ��s�a�A�u�a�ɂ��A�傫�����S�����㏸����N���J��Ԃ��ꂽ���A���ɓ���ƁA�q�����̉��P��u�a��̐i���ɂ�薈�N�̎��S���̕ϓ��͑傫�������Ă����B
�@���{�ɋߑ�I�ȏ㐅�����������ꂽ�̂́A19���I�ɂ�����R�����̗��s�����������ł���B�i��ו��̕��e�i��v��Y�͓����Ȃ̉q���Ǐ��L���Ƃ��ĕp�����Ă����R�����̑嗬�s�Ɋ�@�����o���A1885�N�Ƀ��[���b�p�����̉q����Ԃ����@���u�㐅���ǁv�̏d�v�����w�E�B�p������E�B���A���E�o���g���Ƃ������Ƃ������A�����̐������y�ɐs�͂����Ƃ����B�ו��u�n���Y杁v�ł���̉Ƃɏオ������l���ɁA���͐����łȂ���˂̐��Ȃ璃�����܂Ȃ��B�u�킽�����͉Ԗ��a�����ނ���`�u�X�̂悤�ȓ`���a������Ă��邩��v�ƌ��킵�߂Ă���̂́A���������o�܂�m���Ă��邩�炾�Ƃ����i��{�O�Y�u�ו��̏��a�E�O���v�V���I���j�B �@1886�N�A���Ȃ킿�u����19�N�̉Ă͂Ђǂ������A���V���Â��A�R���������s���i�����s�������ł�����10���l�Ƃ����j�A���̏�A�ǂ�ȍ������炩�u�K�X���ܗL���Ă��������p����ƁA�R�����ۂɔƂ���Ȃ��v�Ƃ����L�����o�����V�����������̂Ń����l����Ԃ悤�ɔ��ꂽ�Ƃ����v�i��ˎ��u���������v�i�c����u�H�����v�����V���Ap.65�`66�j�B �@2022�N�ɂ͎������p���Ă����u���p�U�̂̂ǂ������船�v�̔���ꂪ�����������B����͗��p�U�₱�̈����R���i�\�h�Ɍ��ʂ�����Ƃ��邤�킳�������ōL�܂�A�����q��������߂�����ƌ�����B��������������ǂ̗��s�ɂ͕s���S���ɂ��ƂÂ��ė\�z�O�̏W�c�s�����Ђ�����������̂炵���B �@���̑��A��O�ɂ́A�푈���k�Ђɂ��e�����傫�������B �@�ߑ�̐l���]�����_�ł́A���Y�������瑽�Y�������o�āA���Y�����Ɏ���ߒ��ŁA���Y�����̎����ɐl�����������s�[�N�ƂȂ�Ƃ����i�}�^1561�j�B �@�f����ꂽ�o�����Ǝ��S���̐��ڂł́A�ߑ�̐l���������͂��܂�Ƃ���閾�����ɂ́A���S�����ቺ�Ƃ������A�o�������㏸���钆�Ől�����������������Ă���A�K�������A���̐l���]�����_�̌ÓT�I�}���ʂ�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B �i2013�N4��30�����^�A6��6���X�V�A2014�N6��4���X�V�A2015�N4��14��2013�N�m��l�A6��5���X�V�A2016�N5��23���X�V�A7��27���吳�f���O���t�B���p�A2017�N6��9���X�V�A2018�N6��2���X�V�A2019�N6��26���X�V�A2020�N6��10���X�V�A2021�N6��4���X�V�A11��20�����ߖ��M���I�푈�N�����A2023�N6��2���X�V�A�R�����ƃ����l�A2024�N6��7���X�V�A2025�N7��21���X�V�A�R�����Ɠ����̐����j�@
�m �{�}�^�Ɗ֘A����R���e���c �n |
|
||||||||||||||||||