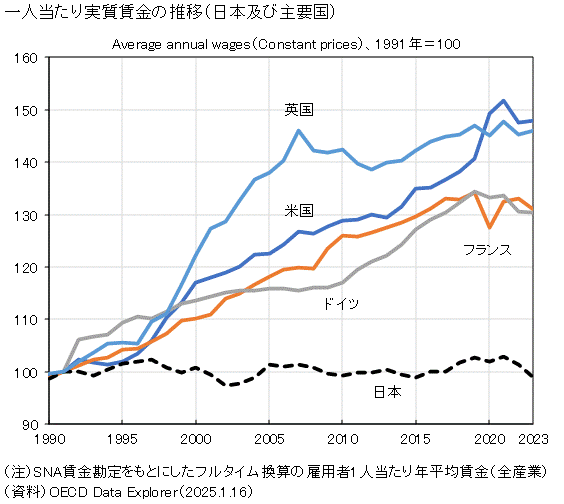
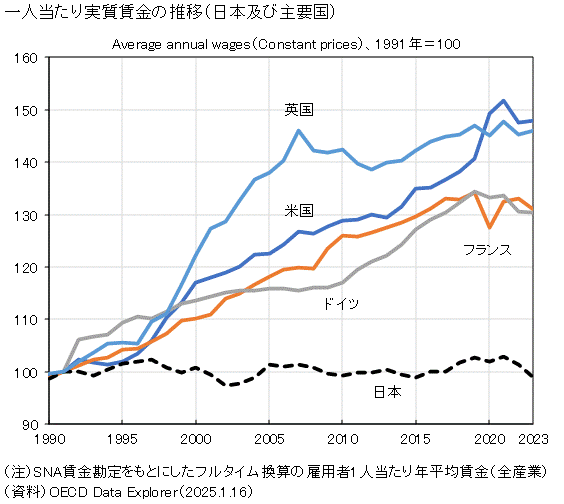
ドイツの1990年データがないので、1991年を100とする指数で実質賃金の推移を追っているが、1991年対比で、ドイツ、フランスはほぼ3割増し、米国と英国は5割増しに近い伸びを示しているの対し、日本はほぼ100と横ばいである。 なお、2020年には米国を除いて各国で実質賃金が一時期落ち込んでいる。特にフランスや英国の落ち込みが著しかった。これが新型コロナの影響であることは言うまでもなかろう。 米国だけは2020年はむしろ実質賃金が上昇し、2022年になって落ち込んでいる。 各国で2022年には回復しつつあった実質賃金が再度落ち込んでいるが、おそらくコロナ回復による消費に生産が追いつかないことで生じた世界的インフレの影響であろう。 下には、OECDデータの起点である1990年をさかのぼる長期的な実質賃金の推移を示した(ただし2011年まで)。ただし、これは過去の米国労働省の生産性・人件費の国際比較報告書による1950〜2011年の推移であり、製造業のみの実質賃金推移である。指数の基準年は元の2002年から日本のオイルショック時である1973年に計算し直してある。 日本の実質賃金は、オイルショックの1973年をターニングポイントとして、高度成長期に欧米諸国と比較しても高かった伸びのテンポが落ち、それでもその後欧米並みに伸びていたのが、さらにバブル崩壊後、特に2000年以降、実質賃金が停滞局面に入ったことが分かる。 OECDデータの推移を比較すると製造業と全産業の違いがあらわれているが、日本の動きはほぼパラレルのようである。 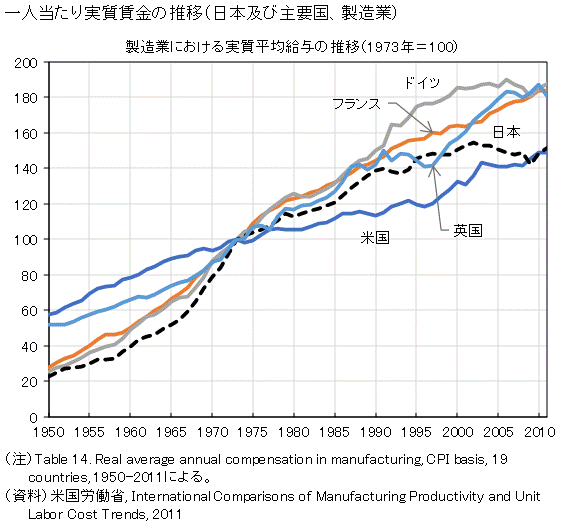 (2025年1月24日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||