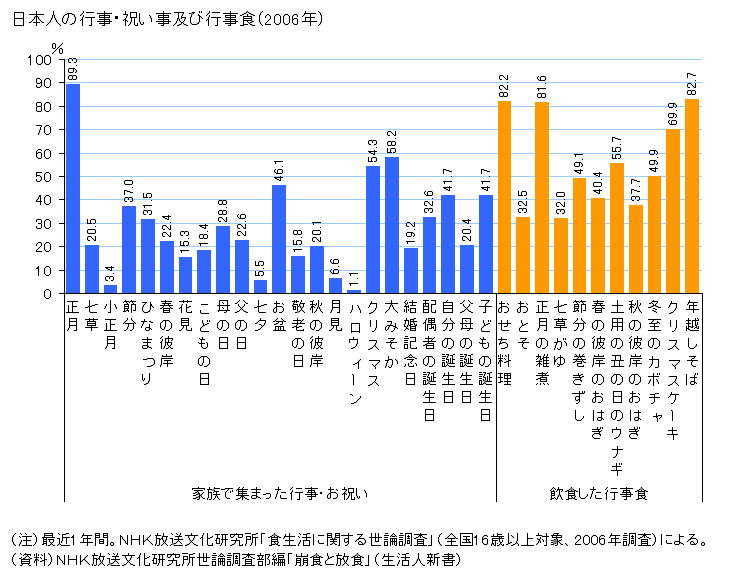
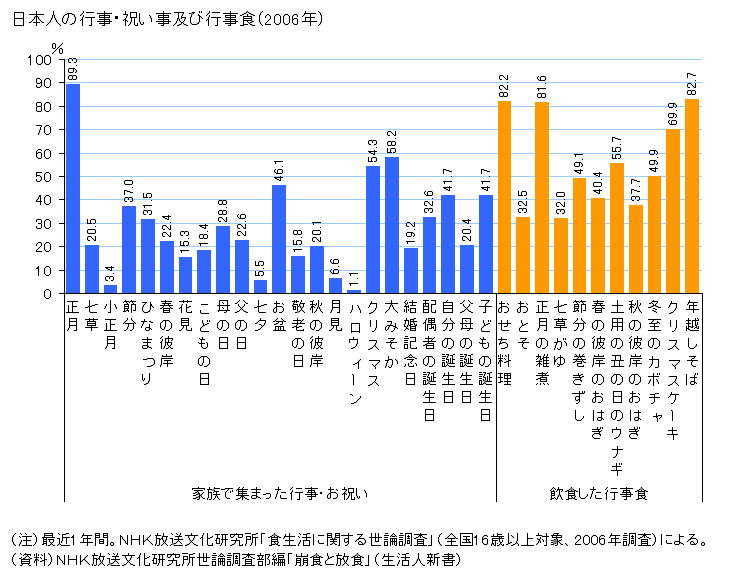
家族で集まった行事・お祝いとしては、正月が約9割で最も高く、大みそか、クリスマスが5割台で続いている。日本人にとって正月は特別の行事となっていることが分かる(注)。大みそかがやや正月より少ないのは、正月に間に合わなかったり、友人・恋人と過ごす場合もあるからであろう。クリスマスがお盆より多くなっている点に、海外文化の定着をうかがうことができる。 (注)かつて正月行事は特別の呪術的な意義があった。取越正月 (とりこししょうがつ)という慣習があった。これは暦日上の正月を待たずに年の途中に儀礼的に正月を迎え、旧年から脱しようとすることである。天候不順で秋の実りが危ぶまれたり、悪疫が流行したり、天変地異が続くと、ときならずだれが始めるともなく餅を搗き、門松を立て、しめ縄を引き、服装を改めて正月礼に歩くことが起こり、次々に近隣に流行することがあった。これはその年の忌まわしさから脱し新たな嘉年を期待して行われるもので、仮作正月(かさくしようがつ)とも流行正月(はやりしようがつ)ともいわれる。近代以前にしばしば行われたことで、時期的には6月前後が多かったという(世界大百科事典)。 小正月、七夕、月見などの伝統行事は1割以下とかなり衰えている。海外からのハロウィーンも100人に1人と馴染みは薄いことが分かる。 誕生日では自分と子どもが4割台と多く、いない場合もある配偶者や父母は2〜3割とやや少ない。配偶者との関係では結婚記念日より相手の誕生日の方が1.5倍実施率が高い。 行事食としては、おせち料理、正月の雑煮、年越しそばが8割以上で多く、クリスマスケーキの7割が続いている。土用の丑の日のウナギも55.7%とこれらに次いで高い。 よく食べる行事食の世代差については図録0327m参照。 大みそかやクリスマスの参加率より、年越しそばやクリスマスケーキの飲食率の方が高いのは、仕事仲間、友人や恋人など家族以外と食する場合もあるからだと思われる。 なお、報告書では行事食の地域性や由来にも言及されている。「「節分の巻きずし」は、近畿地方では81%の人が食べたと答えているのに対して、関東・甲信越では35%にとどまっています。「節分の巻きずし」は恵方巻きとも呼ばれ、もともと関西の一部地域で行われていて、一時すたれたものの、海苔の消費拡大のイベントとして復活したとされています。そして、コンビニが全国のチェーン店で販売をはじめたのをきっかけに、ここ数年で全国に広がりました。...土用の丑の日にウナギを食べるというのも、江戸時代にウナギの消費拡大の宣伝戦略として広がったとされています。」(NHK放送文化研究所世論調査部編「崩食と放食」) 最後に検索を考え、取り上げた行事等の名称をすべて掲げておく。正月、七草、小正月、節分、ひなまつり、春の彼岸、花見、こどもの日、母の日、父の日、七夕、お盆、敬老の日、秋の彼岸、月見、ハロウィーン、クリスマス、大みそか、結婚記念日、配偶者の誕生日、自分の誕生日、父母の誕生日、子どもの誕生日、おせち料理、おとそ、正月の雑煮、七草がゆ、節分の巻きずし、春の彼岸のおはぎ、土用の丑の日のウナギ、秋の彼岸のおはぎ、冬至のカボチャ、クリスマスケーキ、年越しそば。 (2009年6月10日収録、2025年4月14日取越正月の(注))
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||