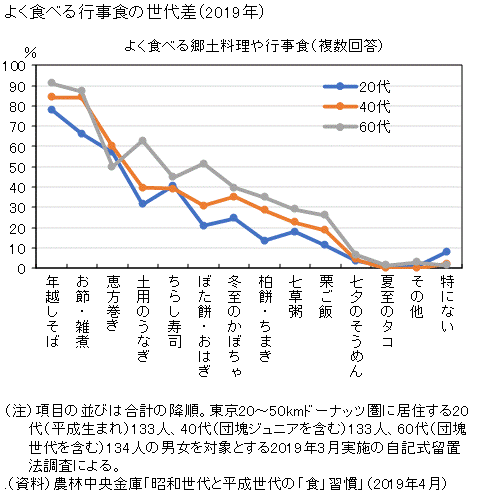
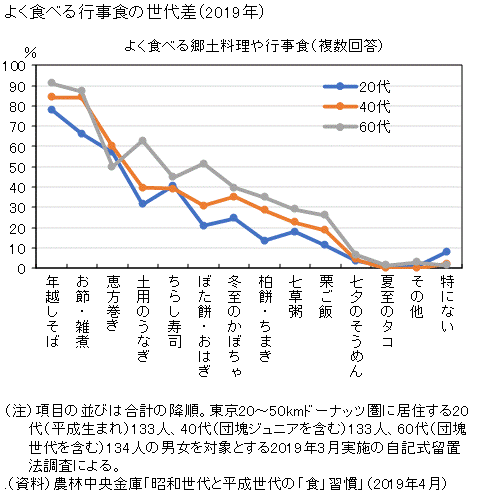
同調査の「食習慣の世代差」各図録 ・好きな家庭食(0327j) ・子どもの頃のごちそう(0327k) ・好きな給食メニュー(0327g) ・よく食べる行事食(0327m) 調査対象となった世代は、当時の20代、40代、60代であり、それぞれ、平成生まれ、団塊ジュニア、団塊の世代に当たっている(ただし60代は団塊の世代の後期層)。 もっともよく食べられているのは、「年越しそば」であり、「お節・雑煮」がこれに次いでいる。大晦日と正月の行事食がもっとも馴染み深いものとなっている。もっとも正月7日に無病息災を願って食べる「七草粥」は2〜3割とぐっと低くなる。 余り食べられていない行事食として、「七夕のそうめん」や「夏至のタコ」は各世代1割以下の回答率であり、習慣が衰えた、あるいは地方限定的な行事食だとえいえよう。 食習慣の世代差に関する他の項目と比較して、行事食については、世代による異なる特徴は余りない。 むしろ、目立っているのは、60代より40代、40代より20代とだんだんとそれぞれの行事食を挙げる比率が全体として低下傾向になっている点である。季節の移り変わりに沿った昔ながらの習慣が衰えていく時代の変化を感じざるを得ない。 もっとも回答が多い「年越しそば」は10%ポイント程度の低下であるが、「土用のうなぎ」や「ぼた餅・おはぎ」は30%ポイント以上の低下となっている。 世代ごとの低下傾向の例外として目立っているのは、「恵方巻き」と「ちらし寿司」である。 「恵方巻き」は郷土食から新しく全国に普及した行事食であり(注)、60代の方が20代・40代より食べる比率がむしろ低くなっている。「ちらし寿司」で世代差が小さいのは、それが郷土食・行事食(ひな祭りや七夕)というより、通常の家庭食として定着した料理になっているからであろう。 (注)「恵方巻き」は大阪・船場で商売繁盛、無病息災、家内円満を願ったのが始まりとされるが、全国に広まったきっかけは、1989年に広島県のあるコンビニで節分に「恵方巻き」という名の巻き寿司が売り出されたことがきっかけと言われている。1998年にはセブン・イレブンが「恵方巻」と名付けて全国展開し、2000年代に入ると全国の各コンビニエンスストアを中心に販売促進キャンペーンが行われた。節分では今や豆まきよりも恵方巻が主流になってきていると言われる。 取り上げられている郷土料理・行事食を挙げておくと、よく食べられている順に、年越しそば、お節・雑煮、恵方巻き、土用のうなぎ、ちらし寿司、ぼた餅・おはぎ、冬至のかぼちゃ、柏餅・ちまき、七草粥、栗ご飯、七夕のそうめん、夏至のタコである。 (2025年4月9日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||