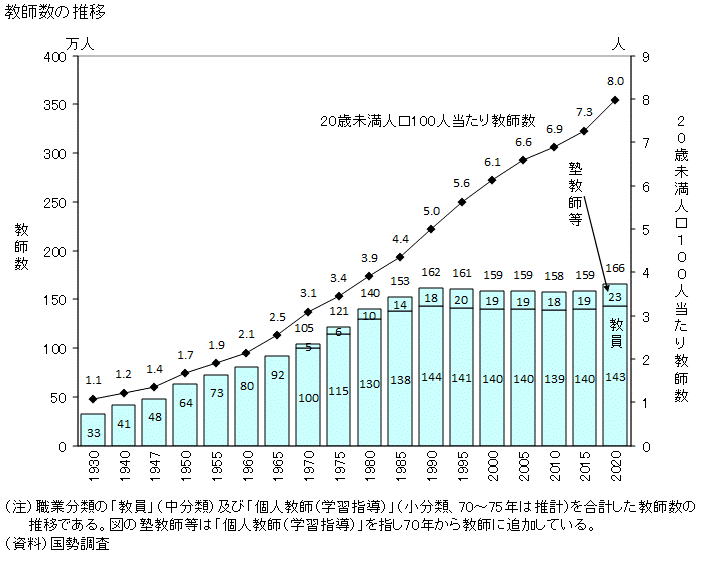
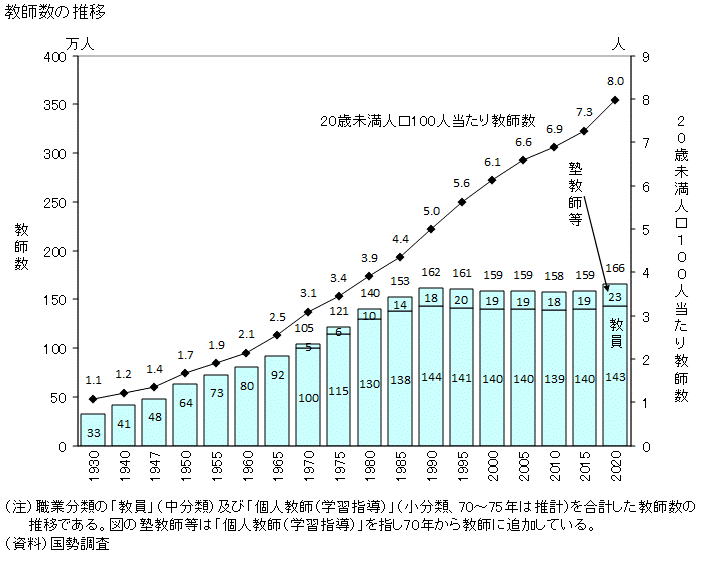
さらに、教育の密度の濃さの程度、及び教育費コスト負担の拡大の程度を測る観点から、子ども1人当たりの教師数の指標もグラフに加えた。具体的には、ここでは、20歳未満の未成年人口100人当たりの教師数という指標として算出している。教師には、大学教師など20歳以上を対象とする者も含まれ、未成年人口には就学前の子供も含まれ、成年人口にも教育対象者がいるなど、教育の範囲を教師、対象者の両面から厳密に特定できない面があるが、おおまかな状況を把握することをここでは目的としている。 教師数は、1990年以降、減少に転じているが、未成年人口はそれ以上に減少しているので、未成年人口100人当たりの教師数は増勢を維持している。 それにしても未成年人口100人当たりの教師数の長期的な増加には目を見張るものがある。1930年には1.1人であったのが、高度成長期末期の1970年には3.1人と3倍となり、それ以降、2010年の6.9人へと更に倍増した。これでもまだ国際的には日本の学級規模は大きい(図録3870)。 2020年には、教員数も増えているが、塾教師等がそれ以上に増え、教師数は159万人から166万人へと大きく増加し、1980年以降横ばいだった推移から増勢に転じた点が目立っている。その結果、未成年人口100人当たりの教師数も7.3人から8.0人へと約1割増と急上昇した。 こうした教師数の増加には、教育密度の上昇(教育機会の普及、教育内容の質的上昇)というプラス面と過剰教育(無駄な教育費の支出−学校と塾の重複など)というマイナス面の両面があると考えられる。時代とともに前者のプラス面から後者のマイナス面が目立つようになっている。教育の投資面での効率低下、あるいは過剰教育が大きな教育費負担を通じて少子化につながっている面を否定できない以上、教育改革の重要性は極めて大きいといえよう。 (公立小中学校の学級基準の推移) こうした教師数増加の背景には公立小中学校の学級基準が見直されてきた経緯が存する。公立小中学校の学級基準は1958年の義務標準法の制定時は「50人」だったが、64〜68年度の5年間で「45人」、80〜91年度の12年間で「40人」に引き下げられた。しかし、その後は少人数化の議論が停滞し、2011年度に小1の35人学級が実現しただけにとどまっていた。しかし、2020年に入ってコロナ対策のソーシャル・ディスタンスの風潮もあり、次年度予算編成にあたり、政府は小学校に限り、全学年を来年度から5年かけて段階的に35人まで引き下げる方針を固めた(毎日新聞2020.12.16)。
(2004年7月7日収録、2013年2月4日更新、2014年11月4日2010年国調確報、2020年12月17日更新、公立小中学校の学級基準、2021年7月17日年表、2023年4月15日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||