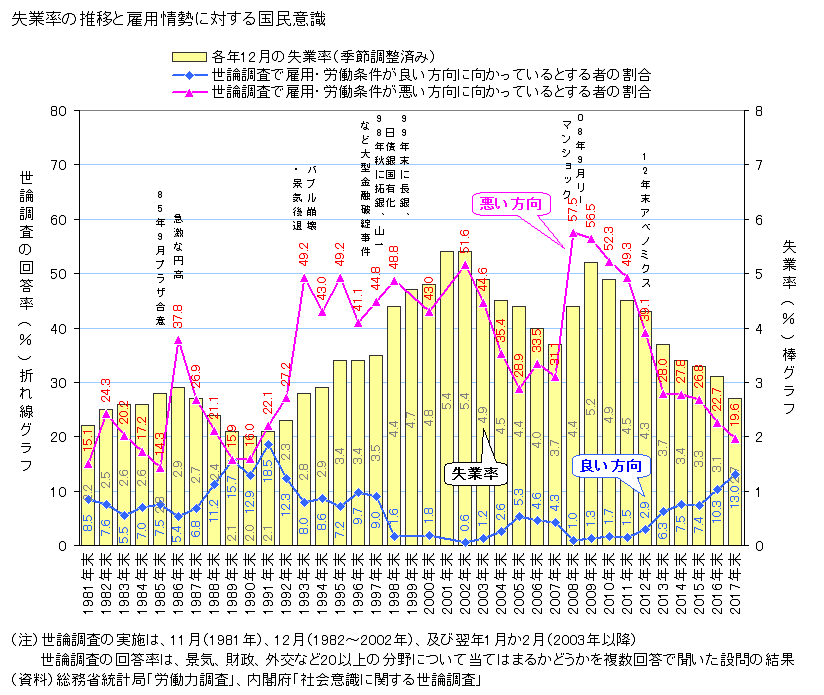
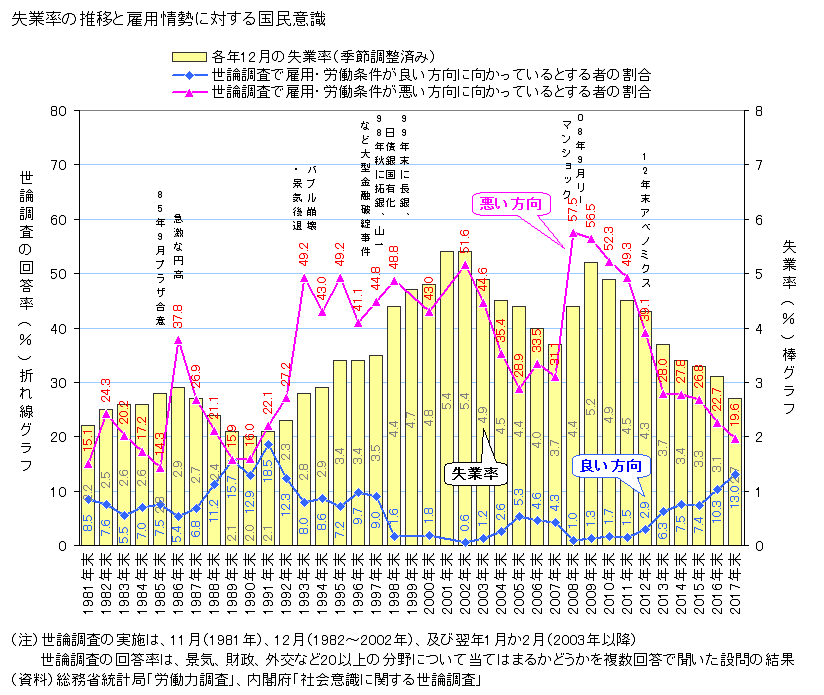
まず、失業率が改善し、雇用・労働条件が良い方向に向かっている時にも、国民の意識はそう認識することは少ないことを確認しよう。 ここで国民意識の毎年の変化は内閣府世論調査によっている(雇用・労働条件以外の分野でどう推移しているかは図録3070参照)。国際的に、経済が好調かの判断と失業率がどう相関しているかについては、図録4513参照。 上の図では、全期間を通じて「良い方向」意識が「悪い方向」意識を上回ったことはなく、すべてでどちらかといえば悪い方向と国民は考えていた。失業率は全体的には上昇傾向にあったが、低下して時期もあったにも関わらずである。マスコミが失業率の悪化などは報道しても、改善はほとんど報道しないことも影響していよう。 唯一、今では信じがたいことであるが、バブルの全盛期、1989年には「悪い方向」が15.9%と「良い方向」の15.7%と拮抗していた。それだけ当時、プラス志向に気分が染まっていたことが裏づけられる。今とは正反対なのが印象的である。 バブルが崩壊した1991〜93年の時期を過ぎても、なお、「良い方向」とする者が8〜9%と一定程度存在していたのであるが、1998年の拓銀・山一の破綻をきっかけにほとんどいなくなり、ついに国民はバブルの夢から決定的に目覚めたといえよう。 2002年から2007年にかけて失業率はかなり改善の方向にあったが、雇用・労働条件が良い方向に向かっていると考えていた人はせいぜい5%ほどに過ぎず、3〜4割は悪い方向に向かっていると考えていた。 この時期は「改革なくして成長なし」の掛け声とともに小泉政権(2001年4月〜2006年9月)の構造改革政策が進められていた時期であり、労働の分野でも後に問題となる派遣労働の規制緩和などが進められていた。失業率であらわされる雇用情勢は良くても、当時さかんだったリストラや成果主義導入、あるいは雇用面の規制緩和によって、雇用・労働条件が「悪い方向」と理解される場合も多く、「良い方向」が余り増えなかったのだとも考えられる。 なお、雇用・労働条件の「悪い方向」は、一般的、世界的な景気情勢によって大きく揺れることもこの図から理解できる。「悪い方向」の比率が急増した1986年、1993年、2008年は、それぞれ、プラザ合意後の激しい円高、バブル景気崩壊、リーマンショックの時期に当たっており、当時の雇用情勢の悪化の見通しによる不安から意識の大きな変化が生じたことがうかがわれる。 2012年末には総選挙によって民主党政権から自民党安倍政権へ政権交代が起こり、同時に、安倍内閣の経済政策アベノミクスを通じて雇用情勢は改善の方向に向かったため、目立った賃金上昇が見られないためもあって「悪い方向」が「良い方向」をなお上回っているものの、両者の割合は、バブル以降、もっとも、前者が低く、後者が高い状況となっている。 全体的に、まとめると、実際の雇用情勢より雇用・労働条件に対する国民意識は悲観的。これは、悪いニュースばかり伝える報道姿勢や悪化に敏感な人間の習性が影響していると考えられる。さらに雇用制度の柔軟化が非正規労働の増加などを通じ国民不安を伴っている側面も無視できないだろう。 似たような状況は米国でも見られるようだ。 下には、経済情勢、雇用情勢のかなりの変動があるにもかかわらず、米国民の意識としては、経済ニュースに関して、いつも「良いニュースもあれば悪いニュースもある」が6割台と余り変化がない点、および、「ほとんどが良いニュース」と回答する者は1割以下と少なく、「ほとんどが悪いニュース」と回答する者が20〜40%と常に上回っている点が示されている。 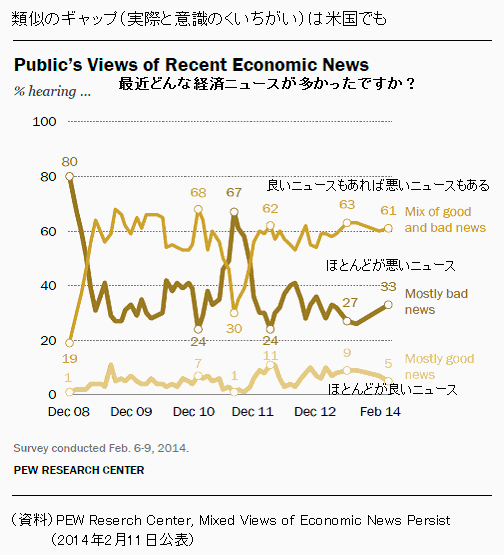 (2017年6月8日収録、2018年4月6日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||