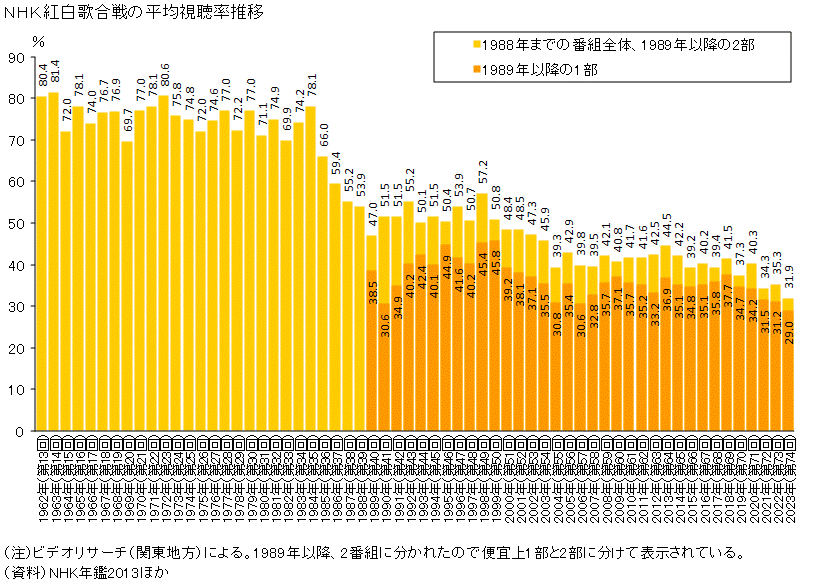
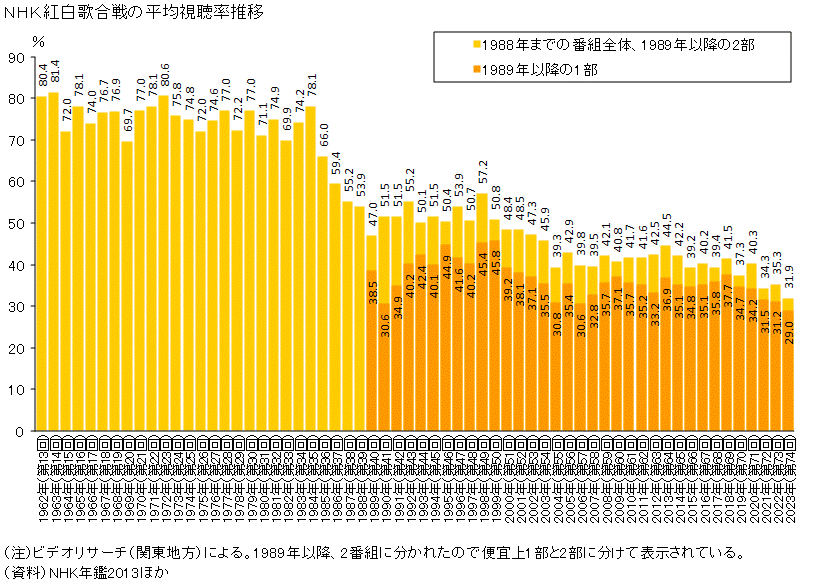
(2025年) スポニチによると、大みそかに東京・渋谷のNHKホールから生放送された「第76回NHK紅白歌合戦」(後7・20〜11・45)第2部(後9・00〜11・45)の平均世帯視聴率は35.2%だった。25年は24年から第1部で1.8ポイント、第2部で2.5ポイント上昇。第2部の大台の40%には届かなかったが、3年ぶりに35%突破した。テレビ離れが進み、視聴率が右肩下がりとなる中で、放送100年の節目に存在感を大きく示す結果となった。テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務めた。 (2024年) 盛り上がりを見せる第2部の“合格点”は40%とされているが、昨年のワースト記録は上回ったが、32.7%という結果で4年連続で40%には届かなかった。 2024年は、ME:I、Number_i、こっちのけんと、Creepy Nutsら10組が初出場を決めた一方、41年ぶり2回目の出場となったTHE ALFEEをはじめ、GLAY、イルカ、特別企画での出場となった氷川きよしなど復活組が多数出演した。 さらに、特別企画で連続テレビ小説「おむすび」の主題歌を担当しているB’zが初出場。当初は事前収録や別会場からの出演とみられていたが、NHKホールにサプライズ登場した。「おむすび」主題歌「イルミネーション」のほかに、代表曲「LOVE PHANTOM」、「ultra soul」を披露して盛り上げた。 テーマは「あなたへの歌」。パリ五輪・パラリンピックに歓喜し、高揚した一方で、相次ぐ自然災害や終わらぬ紛争…多くの悲しみもあった2024年の大みそかに「ひとりひとりに最高の歌を」と思いを込めた(スポニチ)。 (2023年) 海外メディアの報道で明るみとなった創始者による性加害問題により旧ジャニーズ事務所勢の出場がなかったことで視聴率が注目されていた2023年大みそかの「第74回NHK紅白歌合戦」は、第2部(午後9時)の平均世帯視聴率が、関東地区で31.9%(関西地区32.5%)と、過去最低だった21年の34.3%から2.4ポイント下げ、過去ワーストを更新した。 今回のテーマは「ボーダレス」。総合司会はタレントの有吉弘行と女優の橋本環奈、浜辺美波、同局の高瀬耕造アナウンサーが務めた。音楽ユニット「YOASOBI」が昨年最大のヒット曲「アイドル」を国内の音楽番組で初歌唱。また、素顔を見せないパフォーマンスが話題の「歌い手」Adoは、京都・東本願寺の能舞台からサプライズ中継を行った。 特別企画では、内村光良、千秋、ウド鈴木によるユニット「ポケットビスケッツ」と、ビビアン・スー、南原清隆、天野ひろゆきによる「ブラックビスケッツ」が25年ぶりに出場して番組を盛り上げた。デビュー50周年の3人組アイドル「キャンディーズ」のメンバーで女優の伊藤蘭は、46年ぶりの出場となった。 またジャニー喜多川氏(2019年死去)による性加害問題に揺れる旧ジャニーズ事務所(現スマイルアップ)からは、前年の6組から1979年以来44年ぶりの出場者ゼロ。JO1やBE:FIRSTの人気男性グループに加えて、Stray KidsやSEVENTEENの韓国グループの出場も目立った(スポーツ報知)。 視聴率がここまで低下したのに、これまでのようなかたちで紅白歌合戦を続けること自体に疑問を呈する声が出始めたのも2023年の特徴だったと言えよう。ネット記事にはこうある。 「コロナの行動制限が解除された久しぶりの年末でした。例年3〜5億円という制作費をかけてまで、紅白を存続させる意義が見出せませんが、今回特に解せなかったのが、放送中にアナウンサーに『受信料で支えて頂き有難うございます』と、何度も“受信料”を連呼させたことです」(スポーツ紙記者) SNSでは、能登半島地震や羽田でのJAL機と海保機の衝突事故など、自然災害や事件、事故の報道に受信料が使われることに納得の声が多い一方で、年々視聴者が少なくなった歌番組に多額の制作費を投入することに疑問の声は少なくない(日刊ゲンダイDigital、2024.1.5)。 (2022年) NHKホールで3年ぶりの有観客となった2022年の「第73回NHK紅白歌合戦」は第2部(午後9時)の平均世帯視聴率が、関東地区で35.3%(関西地区36.7%)だった。過去最低だった前年の34.3%から1ポイント上げたがワースト2。出場歌手は、韓国の人気グループなど若者層を意識した初出場組を大量に投入。その一方で、中高年層を意識した松任谷由実(68)、加山雄三(85)、安全地帯、桑田佳祐(66)率いる“同級生バンド”らも特別枠で投入。歌手活動休止前ラストの氷川きよし(45)も話題になった。しかし、大幅な視聴率アップでの“大台”となる40%超えどころか微増にとどまった。 テレビ番組に詳しいコラムニストの桧山珠美さんは「特別企画は八つにもなったうえ、その出演者の方が(若者狙いの正規の出場歌手より)格上に見え、付録の豪華さで購入させる雑誌のような印象だ。特別企画やゲストのトークが増えた結果、最も重要なはずの歌を聴く時間が削られている」と指摘する(読売オンライン、2023.1.5)。 現行の視聴率測定方法では、録画やスマホなどの配信視聴がカウントできておらず「音楽のCD売り上げ枚数を比べるようなもので、過去との比較にさほど意味はない」(民放関係者)との声もある。 (2021年) 2021年大みそかの紅白歌合戦第2部の平均世帯視聴率は過去最低の34.3%となった。別調査によるとテレビを見ている人たちの中では、「紅白」視聴の占有率が格段に高まっていたという。つまり、大晦日の夜テレビをつけず、ネット動画視聴など他のことをする人が増えたために視聴率が下がってしまったというのが真実のようだ。 (2020年) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため史上初の無観客開催になった2020年大みそかの紅白歌合戦第2部の平均世帯視聴率は昨年より3.0%ポイント増の40・3%だった。視聴率が下がらなかったのは、無観客に対応した演出の工夫のほか、コロナ対策で居宅者が多かったことが影響していると考えられる。 「コロナ禍でステイホームが呼び掛けられた。公共交通機関の終夜運転もなく、初詣に出掛ける人も少なかったことから、総世帯視聴率(HUT)がアップしたとみられる。実際に、裏番組も日テレが1・6ポイント、テレ朝1・7ポイント、フジテレビ2・1ポイント、テレビ東京0・1ポイントそれぞれアップするなど、各局とも前年を上回っている。テレビを付けていた世帯の全体的な増加が、紅白の数字も押し上げたといえそうだ」(日刊スポーツ2021.1.3)。 (2019年) 令和初なる2019年の紅白の2部(後半)は37.3%と過去最低となった。 (2018年) 平成最後となる2018年の紅白の2部(後半)は41.5%と2年ぶりに40%台を回復した。これは、シンガー・ソングライター、米津玄師(27)のテレビで初めての歌唱、北島三郎(82)の5年ぶり復帰に加え、フィナーレにおけるサザンオールスターズの桑田佳祐(62)と松任谷由実(64)との印象深い共演が反響を呼んだため。 (2017年) 2017年の2部(後半)は39.4%と2015年の39.2%、2004年の39.3%に次ぐ歴代ワースト3位となった。18年9月に引退する安室奈美恵(40)のラスト紅白など話題は多かったが、40%の大台に届かなかった。 (これまで) 過去を振り返ると、1963年には81.4%とピークの値をしるしたが、その後も、1984年までは80%前後の高い値を維持していた。国民の多くが年越しとともにこの番組を見ていたといえる。紅白歌合戦の視聴率は他の高視聴率番組と比較しても図抜けた高さをもっていた(図録3964a)。 1970年代には紅白と並ぶ大みそかの国民的番組となったレコード大賞に出演した歌手が番組終了後に大急ぎで紅白の会場へ向かう様は年末の風物詩となった。 こうした状況が変化したのは1985〜1990年の時期であった。平均視聴率のレベルは70〜80%の水準から50%前後の水準へと急落したのである。 バブルへと向かう1980年代には、テレビは一家に一台というより一人に一台でも驚かれない時代となり、娯楽の好みも大みそかの過ごし方も“個人化”が進んだ。大みそかに家族みんながテレビを前に勢揃いして料理をつつきながら一年の思いを語らい同じ番組を観る、という「絵」はまさに絵に描いた餅になっていった。豊かさを手にした日本人にとって賞レースものの代表である日本レコード大賞への関心は低下、歩調を合わせるように紅白も次第に迷走を始める。 この時期は、また、いわゆるバブル経済が頂点に達しようとしていた時期である(図録5075「株価」、図録2173「塩分摂取量」、図録2670「ディスコなどバブルの象徴」)。日本人は浮かれてしまっていて年末に家族そろって紅白歌合戦という雰囲気とは疎遠になったのであろう。 それでは、バブル崩壊で、再度、紅白がよく見られるようになったかというとそういう訳ではない。1990年代はほぼ50%前後の水準で推移、2000年代に入ると40%前後へと低下するなど長期的に視聴率は低迷した。 2010年代に入るとやや回復傾向が認められ、2013年には44.5%と45%水準にまで戻している感じである。2011年の東日本大震災が家族の絆を再確認する効果をもたらした影響かもしれない。しかしこれも一時的現象だったようであり、14年から低下傾向となり15年には39.2%と過去最低となっている。 下に歴代司会者を掲げた。NHK番組出演者を中心に当時の人気アナウンサーや人気歌手・俳優等が名を連ねている。紅組の司会者は2010年の松下奈緒から2020年の二階堂ふみまですべて「連続テレビ小説」や「大河ドラマ」の出演者である点が目立っている。 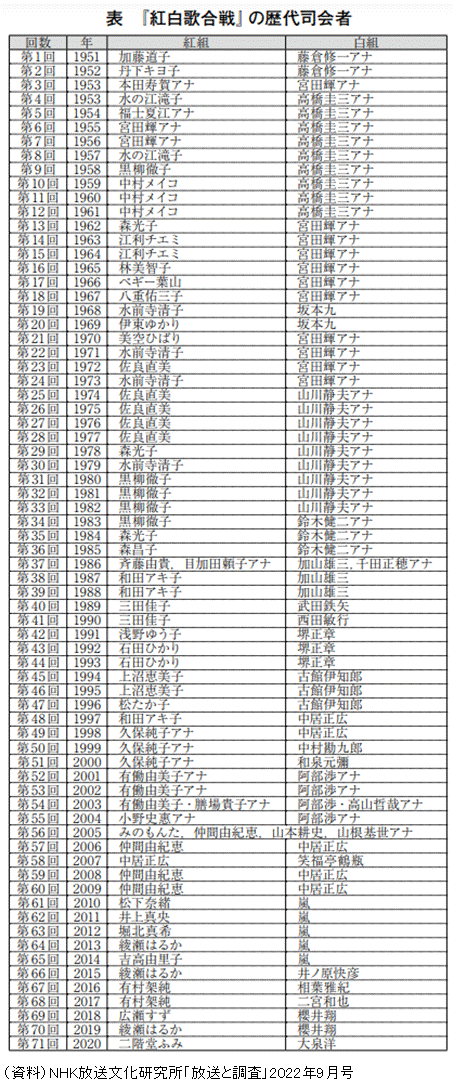 参考までに以下にNHK紅白歌合戦の歩みを年表風にまとめた。
(2014年8月8・9日収録、12月22日年表追加、2015年1月2日更新、2016年1月2日更新、2017年1月2日更新、2018年1月2日更新、2019年1月2日更新、1月23日歩み表更新、2020年1月2日更新、2021年1月2・3日更新、2022年1月2日更新、1月4日コメント・歩み表補訂、2023年1月2日更新、1月3日・1月5日コメント補訂、7月5日歴代司会者表、2024年1月2日更新、1月5日コメント補訂、2025年1月2日更新、2026年1月2日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||