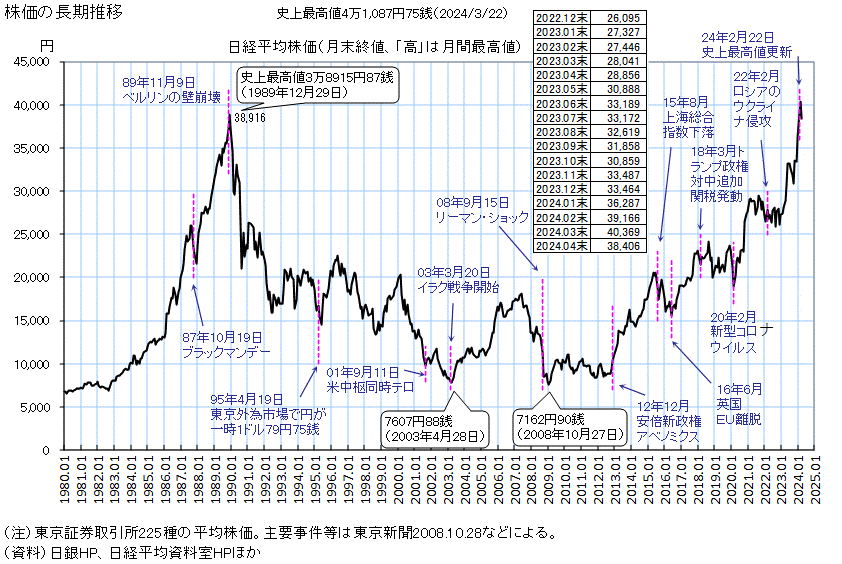
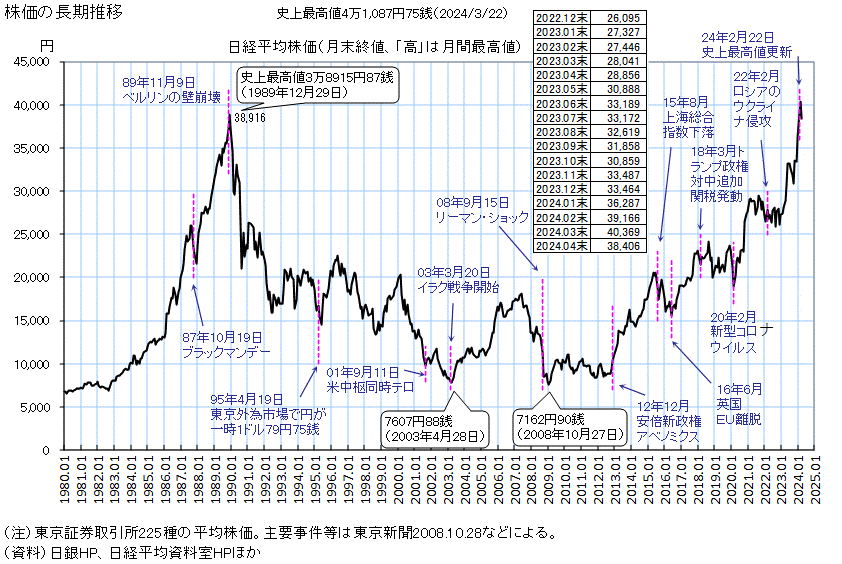
(直近) 9月12日には、8月18日、13日、19日、9月9日以降連日のように史上最高値を更新し、16日にはついに4万5千円を上回り、さらに18日、19日、10月6日にも史上最高値を更新。10月6日には4万8千円を上回った。その後も7日、9日、20日、21日にはさらに史上最高値更新。27日にはついに5万円台を越える。その後も29日、30日、31日、11月4日、26年1月14日に史上最高値更新。 2025年8月12日、日経平均株価は、およそ1年1か月ぶりに史上最高値を更新した(4万2,999円71銭。更新前は2024/7/11の4万2,426円77銭)。 株価が上昇したのは、米国の関税措置をめぐり先の日米合意の内容が反映されるという見方が広がって先行きの不透明感が薄らいだことに加え、米国が中国の輸入品に対する追加関税の一部の停止期限を延長すると発表したことで、米中の貿易摩擦への懸念が和らいだことなどが要因とされる。 (推移) 2024年8月5日の東京証券取引所・日経平均株価は取引開始直後からほぼ全面安の展開となり、終値は先週末の終値に比べ4451円28銭安い3万1458円42銭と、これまでに最も大きかった終値ベースの下落幅である、世界的に株価が大暴落したいわゆる「ブラックマンデー」の翌日に当たる1987年10月20日に記録した3836円48銭安を上回り、過去最大の下落となった。市場関係者からは、「売りが売りを呼んでる。市場は極寒だ」といった困惑の声や、「アメリカの景気先行き不安からのハイテク株下げと円高進行のトリプルパンチ。それに加えて午後に一段と円高が進行し、これが4つ目の要因でパニック的な売りだ」などといった指摘が相次いだ(FNNプライムオンライン)。 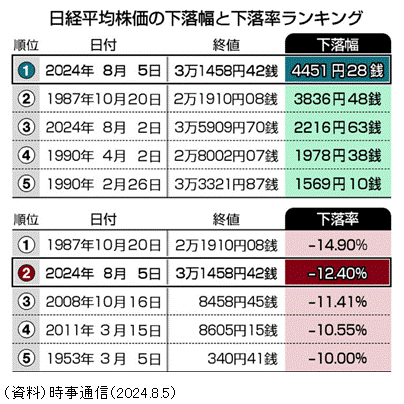 2024年1月から2月にかけ、企業の業績拡大への期待感、能登半島地震を受けた日銀の利上げ遠のき、円安継続→外国投資家の投資継続、米国株高などを背景に幅広い業種で買いが入り、何回もバブル後最高値を更新していたが、2月22日にはついにバブル期の最高値を上回り、約34年ぶりに史上最高値を記録した(終値ベースと取引時間中のいずれも最高値を更新。終値は3万9098円68銭。取引時間中の最高値は3万9156円97銭)。 そして次の営業日2月26日以降も史上最高値を更新している。そして3月4日にはついに終値を含め4万円の大台に乗せた。 こうした株価上昇が異常なのかを判断する材料として下図に日米欧の株価推移を比較した。欧米では、特に米国ではとっくに過去の最高値を大きく上回っている。 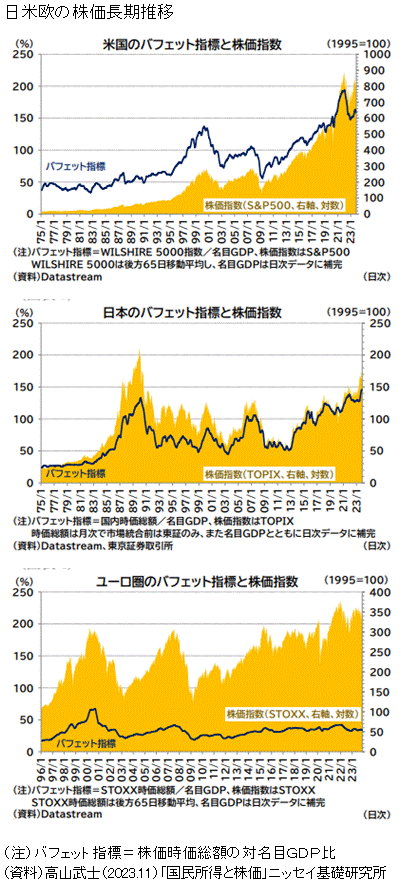 さらに米国の著名投資家のウォーレン・バフェットが参考にしているとされる株価の割高感を示すバフェット指標(株価時価総額のGDP比)は日米ともに150〜200であり日本だけが異常に高いわけではない。バフェット指標の最近の日米の上昇は株主に帰属するキャッシュフローや企業利益の増加にそったものであり、また日米では企業が生産して得られた所得の消費者への分配経路として配当の割合が高まっているので、言わば当然の動きという見方もある(図の原資料)。 2023年11月末には33,487円と月末値としてバブル以降最高値を更新した。そして、「2023年の大納会を迎えた12月29日の東京株式市場で、日経平均株価の終値は3万3464円17銭となった。新型コロナウイルスの「5類」移行を受けた経済の正常化や円安に伴うグローバル企業の業績改善を背景に、年末としては史上最高値となったバブル経済最盛期の1989年(3万8915円87銭)以来、34年ぶりの高値を付けた」(時事通信2023.12.29)。 東京株式市場は2022年12月30日、年内最後の取引となる「大納会」を迎え、日経平均株価は1年前から9.4%安の2万6094円50銭で取引を終えた。前年末を下回るのは2018年以来4年ぶり。今年は米国の急激な利上げもあって歴史的な円安に見舞われ、対ドル円相場の年間の変動幅は38円超と36年ぶりの大きさになり、株価も円相場や米国の利上げに大きく左右された(朝日新聞2022.12.31)。 2021年の大納会を迎えた30日の東京株式市場で、日経平均株価の終値は2万8791円71銭となった。「今年は新型コロナウイルスワクチン普及や米国の大型経済対策への期待を背景に、2月に3万円の大台を回復。その後、コロナ変異株への懸念などから一進一退が続いたが、年末としてはバブル経済最盛期の1989年(3万8915円87銭)以来32年ぶりの高値を付けた。 今年の日経平均は、2月から夏にかけて下落基調。変異株「デルタ株」拡大に伴う度重なる緊急事態宣言の発令や半導体不足の影響拡大、菅義偉内閣の支持率低下などにより、8月には取引時間中に2万7000円を割り込む場面もあった。 その後、菅氏の自民党総裁選への不出馬表明で政治をめぐる不透明感が払拭(ふっしょく)され、9月半ばに今年の高値3万0670円まで急伸。しかし、総裁選で岸田文雄氏が勝利すると海外投資家の売りに押され、再び2万7000円台に下落するなど不安定な相場が続いた」(時事通信2021.12.30)。 2008年9月の米リーマン・ブラザーズの破綻以降の世界的な金融不安の中で同年10月下旬には、日本の株価はバブル後最安値を更新した。
2012年に入って3月末には1万円を超えたのち欧州債務危機、円高などの影響で8000円台で低迷していたが、野田首相の解散宣言以降回復傾向となり、安倍次期首相のインフレターゲットを踏まえた大胆な金融緩和発言で円安化とともに株価もさらに上昇、年末にはこの年最高額を更新し、2013年に入っても引き続き上昇、年末には1万6千円を超えた(いわゆるアベノミクス)。上昇は12月末の16,291円まで進んだが、2014年に入ると米国金利の上昇予想などの下で一時停滞傾向となった。しかし年の後半からは上昇基調となった。 2015年末の値は年末の終値としては2012年から4年連続の上昇となり、また1996年以来19年ぶりの高水準となった(毎日新聞2015年12月31日)。しかし、その後の2016年に入ってからの展開は海外の動きとも連動して急落の傾向を辿った。 2015年5月末の値は、2万円を越え、月末値としては1997年6月(20,605円)以来の高値となった。その後、7月末にはさらに高値を更新したが、8月に中国株式市場の上海総合指数などが下落し(下図参照)、中国経済の低迷懸念から、これが世界各国の株価の下落にむすびついた。日本でも8月末には1万8,900円を割り込んでいる。中国経済の低迷懸念については、生産年齢人口の増減率推移・将来推計を示した図録1158参照。 その後、6月の英国のEU離脱でもう一段の下落が生じたが、年の後半からは上昇基調となり、トランプ候補が米国大統領選で当選したことも追い風となり12月末には1万9千円を超え,、翌2017年6月末には2万円を越えるまでに回復した。 2017年の10月の衆議院解散総選挙の結果安倍政権の存続が決まったので株価が上昇し、同年10月末に22,012円と1996年以来、21年ぶり、また、11月末には22,725年と1991年以来、26年ぶりの高値をつけている。 2017年末の値は年末の終値としては1991年末以来26年ぶりの高値水準となった。前年末の終値を約2割も上回り、年間ベースではバブル経済が崩壊して以降では最長となる6年連続の上昇となった。 2018年末の値は対前年末マイナスとなり、2012年末の第2次安倍政権誕生以降、毎年、対前年末プラスという継続的な上昇傾向に7年ぶりに終止符が打たれた。トランプ政権が進める日中貿易戦争の下で生じた米国の株価下落の波及とはいえ、株高を推進力としてきた安倍政権の「アベノミクス」にとっても逆風が吹き始めた感が否みえない。 中国上海株式市場の上海総合指数の動き(下図)を見ると2018年1月までは中国経済の堅調振りを反映して上昇傾向にあった株価が一転下落傾向に転じ、トランプ政権が対中貿易制裁を打ち出した3月以降、株価下落が加速していることが分かる。米中経済の行方とEU離脱にゆれる欧州経済の動向によって今後も日本の株価は影響されると予想されている。 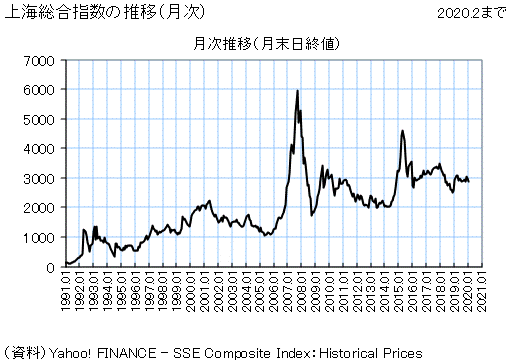 2019年の大納会を迎えた12月30日の東京株式市場で、日経平均株価の終値は2万3656円62銭だった。年末としてはバブル期の1990年以来29年ぶりの高値だった。 2018年3月のトランプ政権による対中追加関税発動以来、2019年を通じ、中国の報復関税や米国の制裁関税の引き上げの応酬で株式市場は翻弄され続けている。欧米中央銀行の金融緩和で株価の底割れは回避されているが、米中対立の火種は残っており、2019年末は収束へ向けた部分合意に達したのでやや持ち直しているものの、2020年も波乱含みである(毎日新聞2019.12.31)。 2020年後半、11月に入って株価は29年ぶりの高値を更新している。理由として、新型コロナウイルスのワクチン開発が進み、経済活動再開が期待されていること、また、トランプ米大統領がバイデン前副大統領への政権移行業務を認めたと報道されたことも好感された点が指摘される。 しかし、製造業が比較的好調なのも要因の1つとして挙げられている。背景としては、旅行、外食、エンターテインメントといった対面型サービス消費の代替需要がある。「世界的に国境をまたぐ移動に制限がかかる下で交通費が減少。人が密集するイベントは激減し、外食も制限がかかっている。人々は本来そうした“コト”に使うはずだったお金をIT製品(スマホ、PC、タブレット)、自動車、家電に振り分けていると思われる」(東洋経済オンライン、2020.11.27)。 2020年最後の取引となる大納会を迎えた12月30日の東京株式市場は、日経平均株価の終値が前日比123円98銭安の2万7444円17銭となり、大納会としては1989年以来、31年ぶりの高値を付けた。2020年の株価は「2万3000円台でスタートしたが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて3月に1万6000円台まで急落。しかし各国の大規模な金融緩和や財政出動が相場を押し上げた。その後は米バイデン次期大統領の政策や、開発中のコロナワクチンの有効性への期待から、年末にかけて株高が加速した」(毎日新聞2020.12.31、下図参照)。 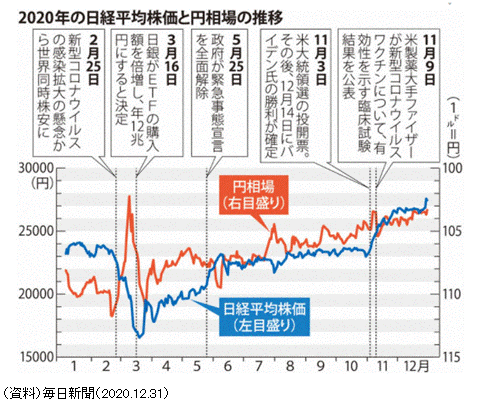 (2008年10月28日収録、以後、最近年以外単なる更新は省略、2015年9月6日上海総合指数のグラフ追加、2019年12/31図・コメント補訂、2020年12/312020年推移図、2023年6/6以降最高値も、2024年1/10・1/11・1/12・1/15・1/17・1/22・1/23最高値、1/31更新、2/9・2/13最高値、2/22史上最高値、2/23バフェット指標、2/26・2/27・3/1・3/4・3/7・3/21・3/22史上最高値更新、4/1・4/30・6/26・7/1・8/1更新、7/5・7/9・7/10・7/11史上最高値更新、8/5大幅下落、8/30・9/30・11/2・12/2・12/30更新、2025年2/1・3/22・3/31・4/30・6/30・8/12・8/19・8/20・9/10・9/12・9/16・10/3・10/6・10/7・10/9・10/20・10/21・10/27・10/30・11/21・12/4・12/30更新、2026年1/14・2/9更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||