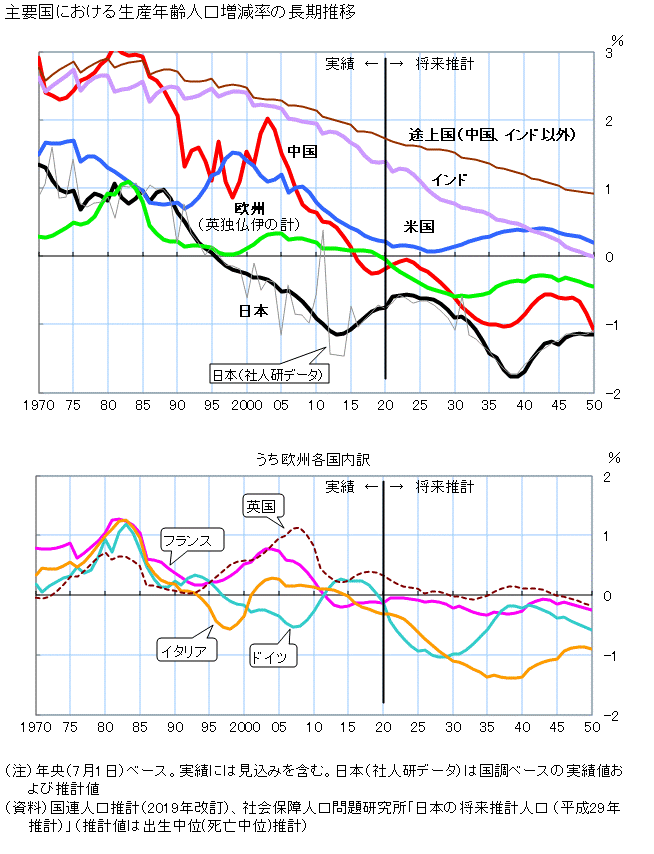
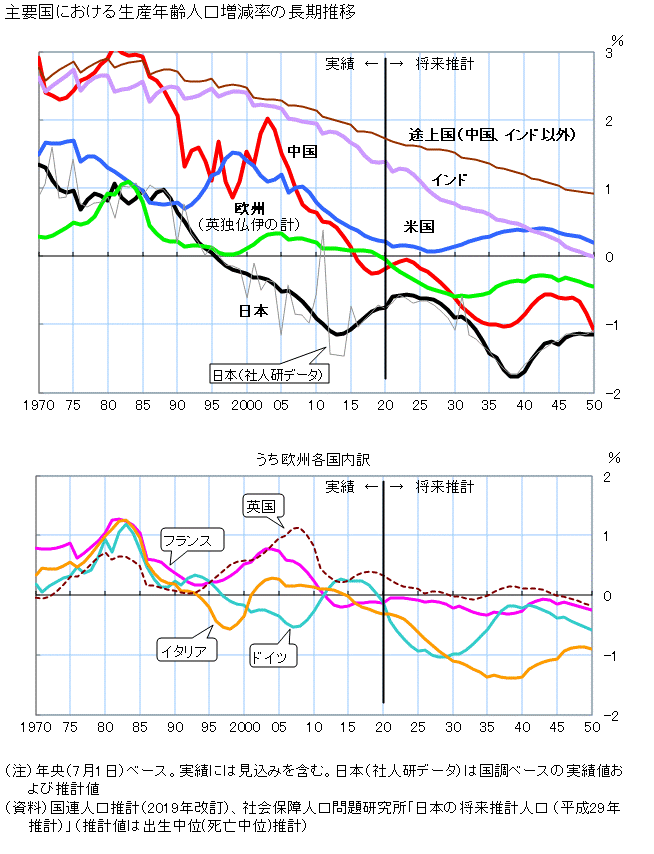
各国の経済動向を判断するのに生産年齢人口の動きに着目する見方がエコノミストの間で有力である。生産面、供給面から就業者数の動向が経済情勢を大きく左右する。 生産年齢人口が大きく減れば、(多少女性の社会進出で労働力率が上昇しても)就業者数も減るという単純な経済効果だけでなく、先進国では経済情勢の悪化は早期退職を促すが、生産年齢人口が減少するということは退職者の母数が増えているということなので、それだけ経済不況を根深いものにするといった側面も無視できない。 また、需要面でもこの年代の人口動向が大きく経済にインパクトを与えるとされる。生産年齢人口向けの消費財の需要だけでなく、それを当て込んだ投資財への需要も大きく左右される。 さらに、生産年齢人口の動向は、高齢化と裏表の関係で結びついており、貯蓄率への影響を通して利子率にも影響があるだろう。社会保障の給付を支える年齢層の人口動向は社会保障の収支構造を変化させ、政府の財政支出や債券発行の制約条件にも影響を与える。 あれやこれやで、結局、生産年齢人口の動きで経済情勢が決まる側面が大きいという訳である(The Economist November 22nd 2014の"Free exchange"記事参照)。 主要国の生産年齢人口の増減率の実績と将来推計をグラフにした。 日本については実績値は国勢調査にもとづく毎年の推計人口、将来値は日本の公式推計である社会保障人口問題研究所(社人研)の将来推計値の増減率も参考として掲げておいたが国連の実績・将来推計値はほぼこれをスムージング化したかたちとなっている(出生率の設定がきいてくる頃の将来値は2017年改訂までは設定がより高い国連のほうが減少率がやや小さくなっていた−図録1151コラム参照−。ところが、2019年改訂以降では社人研の推計にほぼ沿う形となった)。 日本の動きを見れば、生産年齢人口の増減率が経済情勢を大きく左右したことが分かる。 1980年代の後半はバブル経済期としてわが国の年代記に刻まれているが、この時期、日本の生産年齢人口は、なお、ほぼ1%増のレベルを維持し、米国や欧州の水準を上回っていた。戦後のベビーブーム世代(1947〜49年生まれ)の子どもの世代である第2次ベビーブーム世代(1971〜74年生まれ)が15歳以上となったためであるが、こうした人口動向を背景に、ちょうど生産年齢人口の増加率が低下していた米国や欧州とは対照的に経済がヒートアップし、この点が世界的にも目立っていたのだととらえられる。 その後の経済の長期低迷はデフレ経済期として記憶されているところであるが、生産年齢人口が増加から減少に転じ、減少率もどんどん上昇していった時期にちょうど当る。これだけの人口のメガトレンドを背景にして経済が好転させるのはいかにも難しかったととらえられる。 2010年代に入ると、第1次ベビーブーム世代が65歳以上となり、減少率が2013年に-1.4%のボトムとなった。その後は、減少率は縮小傾向となった。アベノミクスによる経済好転は政策の影響と見えるのは見せ掛けであり、こうした人口動向の転換点に当ったからととらえることも不可能ではない。 今後について生産年齢人口の増減率でうらなうと、2020年代までは比較的経済は好調であろうが、その後は再度落ち込んでいくであろう。 なお、更新前の国連2019年改訂による長期推移図はここ。更新前と比べると中国の長期低迷が目立つようになっている。特に2045年以降は日本は回復するに対して、中国は人口的には一層低迷する。2045年以降は米国がインドを上回るようになるのも印象的である。20年ちょっと経った2045年以降は世界の様相が変わる可能性がある。 日本においては特に地方における生産年齢人口の減少が目立つようになろう。下図は、日本の市区町村の生産年齢人口減少率の区分別数と都道府県別の半減割合である。半減割合地域図では、東京圏から福岡にかけてのいわゆる太平洋ベルト地帯で割合が低く、それから離れた地域で半減割合が大きい点が目立っている。 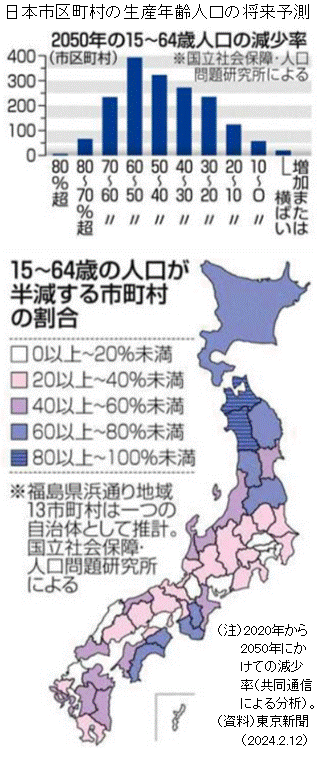 他国についても、例えば、非常に高かった中国経済の成長率が最近低下してきているのも、生産年齢人口の増加率がマイナスに突入したためと見れば納得できる。中国は2020年代後半にはやや持ち直すが、その後、成長率はさらに低下すると予想される。 中国は一人っ子政策を長い間続けていた点で途上国としては特殊である。インドの出生率は中国より高かったので、なお、生産年齢人口の高い増加率を継続しており、今後、2050年にやっとゼロに近づくと予測されている。インド経済の躍進はしばらく続きそうである。中国とインド以外の途上国は推移パターンはインドと同じであるが、インドよりさらに一貫して増加率が高い。中国、インドからそれ以外の途上国(例えばアフリカ)に世界経済の牽引者がシフトしていくこともありえよう。 米国はリーマンショックの影響が長引き、2009〜11年に失業率が10%近くとなるなど経済が低迷していたが(主要国の失業率動向については図録3080参照、以下同じ)、これも、生産年齢人口がこの間急速に増加率を低下させたためと見れないことはない。これからは、マイナスに落ち込んだままとなる欧州や中国、日本と比べて、プラスの増加率を維持するので経済の見通しは明るいともいえる。そして、何んと、2040年以降はインドの増加率を上回ってしまうと予測されている。 欧州に関しては、2005年前後にドイツの失業率が10%以上と英仏伊と比べて高くなったのも生産年齢人口のマイナスが欧州で唯一継続していたからだととらえられる。こうした危機に対応して、労働市場に関するハルツ改革という痛みを伴う対応を行った影響もさることながら、2010年代には生産年齢人口が再度増勢に転じたため、最近のドイツの失業率は英仏伊と比べて低くなっているといえよう。フランス、イタリアが最近失業率の上昇が目立っているのは、実は、生産年齢人口の増加率が急速にゼロに近づいているためかもしれない。 これからの欧州については、英国とフランスはほぼゼロ水準前後で推移するのに対して、ドイツとイタリアはマイナスがかなり大きくなるので、長期的には両者は対照的な経済動向となろう。 関連して、主要国の高齢化率のこれまでと将来推計は図録1157参照。 (2015年1月21日収録、8月20日国連人口推計2015年改訂による更新、2017年6月23日2017年改訂による更新、6月26日日本の公式推計値を併載、6月29日インド、中印以外途上国追加、2019年6月28日2019年改訂による更新、2024年2月12日日本市区町村将来予測、7月14日国連2024年改訂による更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||