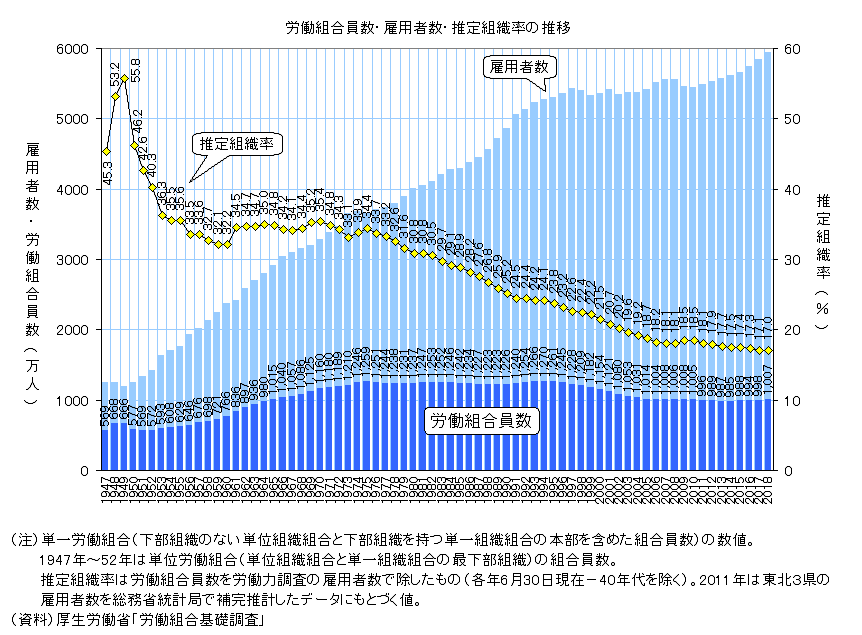
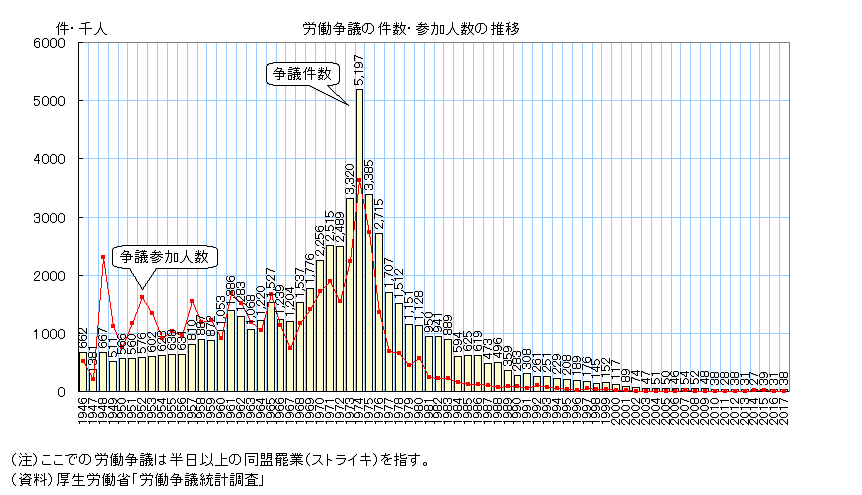
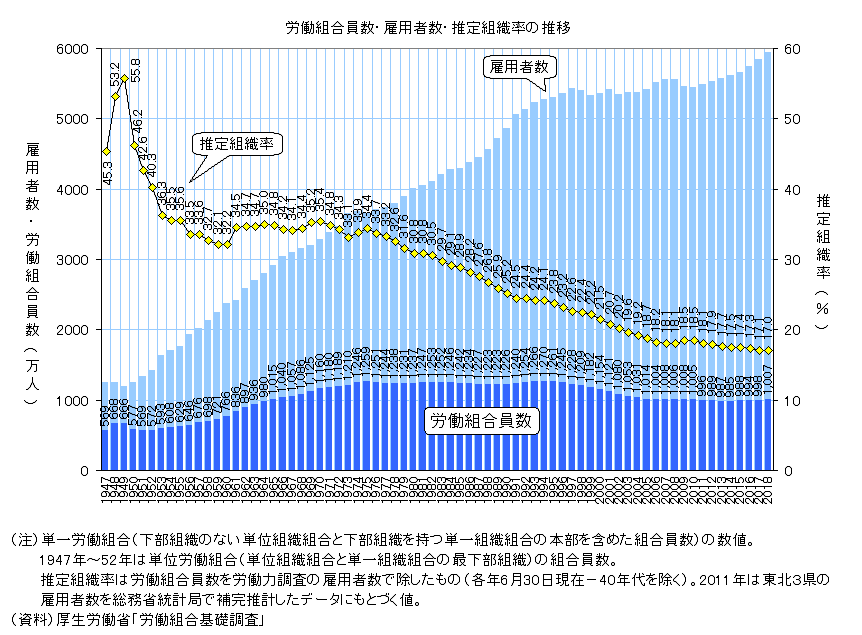
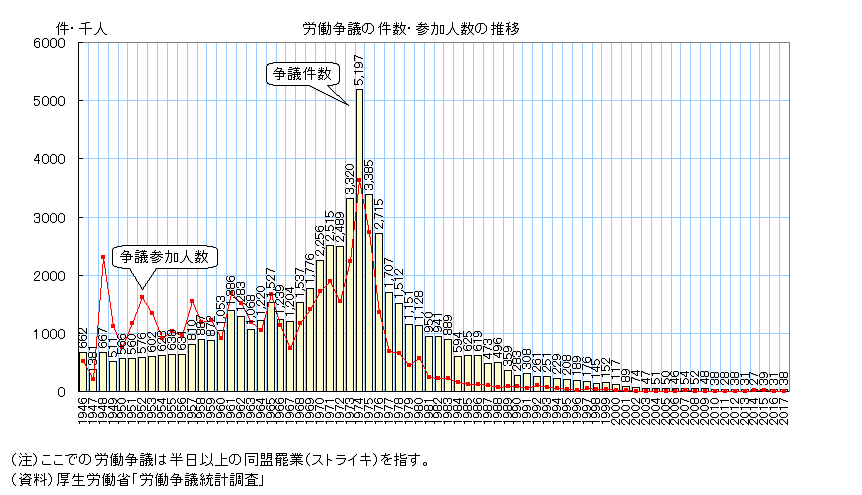
第2次世界大戦直後、なお、農民が半数を占めていた日本では、雇用者は1千数百万人とそれほどは多くなかった。しかし、占領下における労働運動の高まりを反映して、47〜48年当時、労働組合員数は660万人と雇用者の5割以上を占めていた(ピーク48年55.8%)。同時期進められた農地改革が実現せず、農民運動が下火にならなければ、労農提携によって日本に革命状況が生じていたかもしれない。 1955年の春闘の開始は、それまでの政治主義的な労働運動(政治的活動によって労働者の利益がもたらされると言う考え)から経済主義的な労働運動(賃上げなど経済的利益の追求が政治的な効果にもつながると言う考え)への転換を象徴する出来事であった。この転換がうまく行ったためもあって、その後の高度成長期には、急増する雇用者数に合わせて労働組合員数も大きく増加し、組織率はほぼ3分の1で堅調に推移した。 こうした高度成長期の労働運動からの転換点となったのは、労働運動の高まりを受けて行われた1975年の国労・動労など公労協のスト権ストの敗北である。この年以降、組織率は低下を続け、2003年から2割を割り込み、2012年には18.1%にまで低下した。1980年代中頃までは、組織率は下がっても雇用者数が増加していたので、労働組合員数の絶対数は維持されていたが、1994年の1,270万人をピークに組合員数自体が減少に転じている。2011年には996万人とついに1,000万人を下回った(その後、2018年に再度1,000万人台に)。 2009年には組織率が18.5%へと1975年以降はじめて上昇した。組合員数がやや増加しているせいもあるが、むしろ雇用者数が景気低迷でかなり減少し、母数が減った影響が大きい。このため景気がやや回復した2012年以降には組織率が再度継続して低下し18年には17.0%と過去最低を更新している。 半日以上のストライキを伴う労働争議の件数は、戦後、増え続け、高度成長期が終わった1974年に5,200件のピークに達した後、急激に減少し、2017年には38件と極端に少なくなっている。戦後高度成長期までは争議が大規模だったので、参加人数は、一貫して多かった。高度成長期の後半から争議は小規模化し、件数に比して、参加人数は少なくなった。 (2005年9月25日収録、12月14日更新、2006年1月23日更新、2009年12月11日更新、2011年12月23日更新、2013年2月11日更新、12月19日更新、2015年12月26日更新、2018年12月19日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||