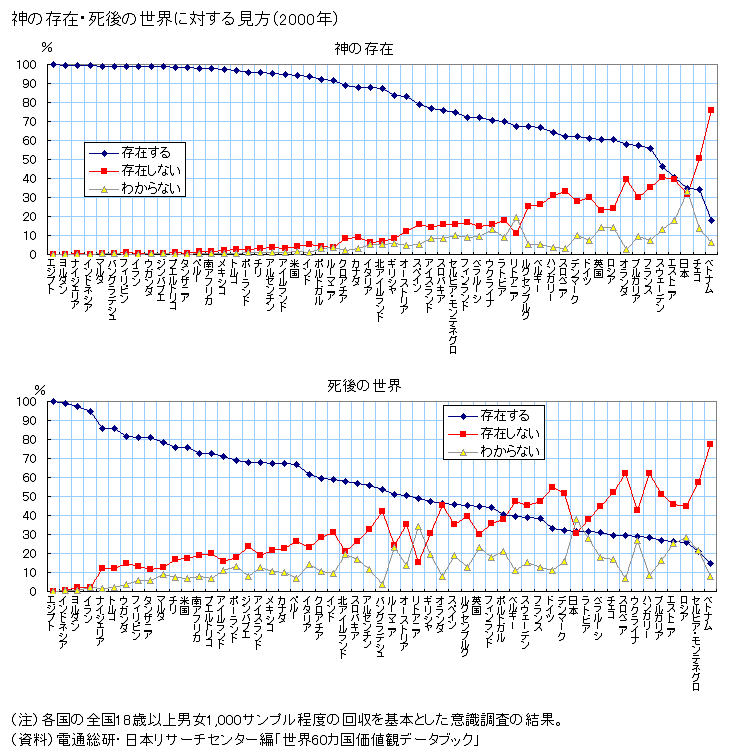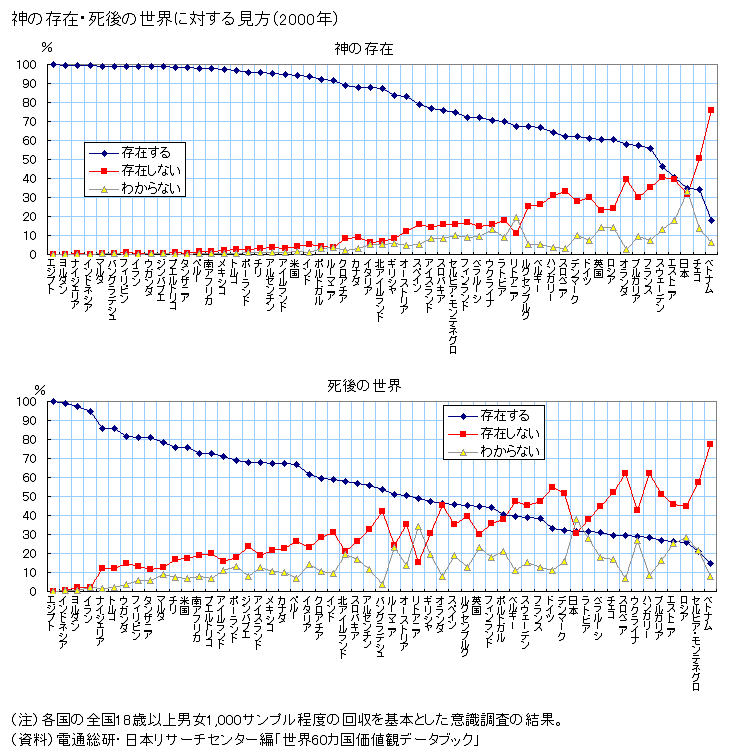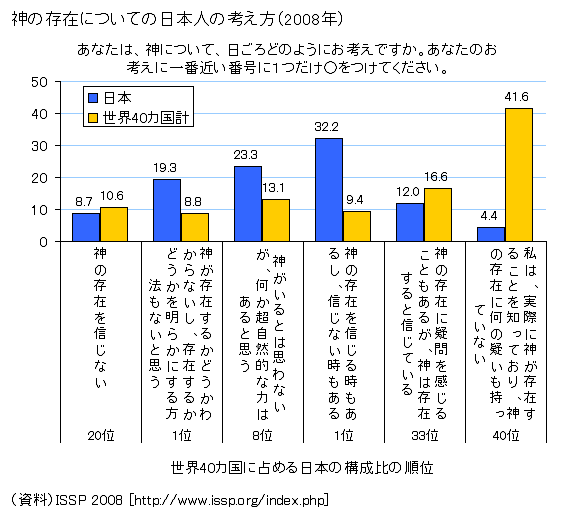�@�ђm�ȕv�i1996�j�u
���{�炵���̍\���\������ƕ������͂���
�v�i���m�o�ϐV��Ёj�́A�C�O��r���܂߂������������̒����~�ς���A���{�l�炵��������킷�u�i�|�ԓx�v�̓����Ƃ��āA�ȉ��̂R�_�������Ă���B
�@�l�ԊW�d��
�A���ԓI�̑�������
�B�@����M���Ȃ����@���I�ȐS���ɂ���
�@�����ŁA���ԓI�Ƃ́A�u���ɂ悢�v�Ɓu�܂��悢�v�Ȃ�A�u�܂��悢�v�̕��̉A�܂��u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�A�u������Ȃ��v�Ƃ��������w���B
�@�����āA1953�`88�N�̌p�������ɂ����āA�V�����N���̕����u�i�|�ԓx�v�I�ł���A�܂������_�ł͎Ⴂ����̕����u�i�|�ԓx�v�I���ƕ��͂��Ă���B�܂��A���ԓI�ɂ��ẮA�ȉ��̂悤�ȃv���X�̕]����^���Ă���B
�u���͂��̒��ԓI�����锭�z���̂��̂́i�����j�{���钷�̂����u���S�i���炲����j�v�Ȃ��f���Ȍ������ł��A�s�m��̉��ł��܂��Ώ����邱�Ƃ������Ȃ��ł��钷���ł���Ǝv����B�v�u���ԓI�D�݂͍��ۉ�����ɓK�p���Ȃ�����u�͂�������̂������v�Ƃ����l�����邪�A����͓��{�l�����{�l�łȂ��Ȃ邱�Ƃ��Ӗ�����B�v
�@���̗��e�͋ߑ�I�Ȗ��邢�Ƒ������낤�Ɠw�͂��A�m�荇���̃C���e����t�ɂ������ꂽ��A�����V���Ȃ��w�ǂ����肵�Ă������A���F�A���o�͎m�̑��q�Ɩk�O�D��̑����ł���̂ŁA����^�̃��_���E�{�[�C�ɂ͈�đ��Ȃ��Ă����B
�@���́A�c�����A����l������}���i�̂�����j�̕�e�̗F�l���K��A���y���ɂȂ������̂��Ƃ��v���o���B��̗F�l�ł���ߑ�I�Ȋ����̕v�l�́A�`�Ƃa�Ƃǂ��炪�H�ׂ����Ǝ��ɐq�˂��̂ŁA���̋^����Ȃ��A�u�ǂ���ł������ł��v�Ɠ������B����������A�u�ǂ���ł������ł��v�ł͂Ȃ��āu�`�������v���邢�́u�a�������v�Ƃ������Ⴂ�Ƃ����Ȃ߂�ꂽ�B���͎�̓I�Ȕ�������������������h�����ƂɂȂ�Ƃ����v�l�̍l�����ɓ��ӂ���ƂƂ��ɁA����܂ŋ^����Ȃ��g���Ă�������I�Ȕ����ɔ��邱�Ƃ����o������ꂽ���Ƃɏ����������B��ōl���āA�u�ǂ���ł������ł��v�Ƃ́A�����A�`���a���ǂ݂̂��債�����ƂȂ��H�����Ƃ����܈ӂ͂����Ă͂��炸�A�P�Ɂu���Ȃǂ͂����f��������Ȃ����Ō��\�ł��v�Ƃ����ւ肭����i�����j�̕\�������邱�Ƃő������ʂɒu�������Ƃ������Ƃ������̂ɂȂ��A�Ǝ���̌y�����S���Ԃ߂��̂������B
�@�s�m��ł��A�͂�����`���a����\�����Ȃ��ƁA���ɐi�߂Ȃ��Ƃ���l�����ƁA�m�肵�Ă��Ă��A�`���a�����͂����肳���Ȃ������A���̒����܂������Ƃ����l�����́A���ꂼ��ɂ���Ȃ�̗L����������̂ł��낤�B
�@���ԓI�̋�̗�́A���̐}�^�̂ق��A�}�^
8062�i�A�W�A�I���l�ς̊e����r�i���{�E�؍��E��p�E�����j�j�A�}�^
8598�i�č��𐢊E�͂ǂ����Ă��邩�j�ɂ�������B�����ł́A���Ă����łȂ������A�؍��ȂǂƔ�r���Ă����ԓI�������Ƃ������{�̓����͖��m�ł���B
�@�����������{�l�̓����́A�����̃V���̂ł������ɂ��e����^���Ă���悤���B�č����T���[���X�ݏZ�̏����̎蔪�_���q�́A�L�������C���E�P�l�f�B������g�̃V�����b��ɂȂ��Ă��邱�ƂƊ֘A���āA���������Ă���B�u���N�̃A�����J��炵�łł����V���́A���{�ʼn߂����Ă�����ł����ł��낤�V���Ƃ͈Ⴄ�Ǝv���Ă���B���Đl�͕\��L���ɘb���̂ŁA�p��̏�B�ƂƂ��Ɏ�������ȕ\�������悤�ɂȂ�V�����������B���ɂ��ł��Ƃ܂Ԃ��B���������Ȃǔ��т��������艺�����肵�Ă���ƃV���ɂȂ����B���Ƃ������Ɏ�ĂȂ��ō����ɏ��̂ŁA�j�̕ӂ�ɂ������o���B
�v�i�����V���u�����������k�|�V������v2014.1.24�j
�@�ْ��u���v�f�[�^����� ���{�l�̑傫�Ȍ���v�ł����y�������A�u�����������{�l�̂����܂����́A�l�ԊW�d���̂Ȃ��Ő��������̂��Ɛ���ł���B���m�ȕ������ő��l�������Ȃ��z�����S�̓����Ƃ��ďK�������Ă���Ƃ�������̂ł���B���ꂪ���{�Љ�̉߂����₷����ł��邱�Ƃ��m���ł��낤�B�v�ip.232�j
�@���{�Љ�͉��ď����Ɣ�r���Ē�X�g���X�Љ�ł���_��}�^
3274�łӂꂽ���A���������ŕ�炵�Ă������߂ɂ́A���邢�́A�ߐ��ȍ~�́h�ނ�h�Љ�̌��������ێ����邽�߂ɂ́A���{�l�����݂ɂȂ�ׂ��p�˂������Ȃ��������̍H�v�����Ă����w�͂̌��ʂƂ����悤�B���A�W�A�̎������̒��ő����ƈقȂ���{�̓����Ƃ��āA�e���q�ɋ����������_�I�ԓx�Ƃ��ē��{�l���������u�v�����v���1�ɂ����Ă���_�ɂ����������_�����m�ł���i�}�^
8068�Q�Ɓj�B������v�����̂́A��������̂��߂����ł͂Ȃ��ƍl������B��c�ő���̌��m�Ɏw�E����̂ł͂Ȃ��A���܂킵�ɕ����点��H�v���Â炷�̂́A�ʂ̋@��ɁA�����̌�肪�[�I�Ɏw�E����ď����̂���������ɑ���Ȃ��B��������Ȃ��H�v���X�g���X�̒ጸ�ɂȂ���̂ł���B
�@�}�^
3274�ł����p�������A�C�O�Ƃ���r���Ȃ��獑���������ɒ����g������ђm�ȕv�͂��������Ă���B
�u���{�l�́u���{�Љ�͐l�ԊW���ώG�ō��X�g���X�Љ�v�ȂǂƂ����A�}�X���f�B�A�̖������ȕ�M������ł��邪�A����͂܂������̌��ł���B�ނ���A���{�l�̈ꌩ�ώG�Ɍ�����l�ԊW�̂�������A�l�Ԃ̂��U���������炰�A�l�ԓ��m�̒��ړI�ȏՓ˂���������邱�Ƃɖ𗧂��Ă���ƍl����ׂ��ł���B�v�i�ђm�ȕv�E�N��땶�i2002�j�u
���������������{�l�̐��ݗ́|50�N�Ԃ̍����������f�[�^���ؖ������^��
�v�u�k�Ёj
�@�^�U�E����̔��f������ȂƂ��ɂ́u�ܒ��̖@�v�ɏ]���A�o���ɂݑ��̔����ɂ���Ƃ����̂����{�̒����̖@���O�ł���A����ɂ��ƂÂ��u���ܗ����s�v�����K�����A�ߐ��ɓ����Ă��A���R�̕��������@�Ƃ��ꂽ�B�u���Ƃ���ƁA�ܒ��͂��͂�A�����I�Ƃ��������{�I�ƌĂԂׂ��v�l�K���ł���B���{�l�͗���̌���������̂������̂��B���̏K���ɂ͂ЂƂɂ́A�W�c���̘a���݂������̂����₪������ЂƂ̏K���̂����炵�ނ�Ƃ��납������Ȃ����A��荪��I�ɂ́A���m�ȗ���̑��݂ɂ��Ẳ��^�I�Ȏv�l�Ȃ̂����Ȃ̂ł���B�ނ�͐��܂�Ȃ���̑��Ύ�`�҂ł����āA�����ЂƂ̐^���Ƃ����̂͋��S�n����邢�̂��v�i�n�Ӌ���u
���{�ߐ��̋N���v�m��АV��y�Ap.156�j�B
�@���{�l�̓����̗R���ɂ����āA�����A�W�c�̘a�̂��߂̎�i�Ƃ������ʂ����邱�ƂȂ���A�ނ���A�����ł��邱�Ƃ��琢�E�̑�v�z�̉e�����]��[���Ȃ��A���̌��ʁA��v�z���ˈȑO�̑��Â̐��_����ێ��������Ă���Ɨ�������̂��ǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���n�߂Ă���i�}�^
3971d�A�}�^
9528�Q�Ɓj�B
�@�ӎ������ɑ��ē��{�l���u�킩��Ȃ��v�Ɖ���䗦�������_�Ɋւ��āA�C��w�҂̗�؏G�v�́A����́A���m�́u�����̎v�l�v�ɑ��ē��m�́u�X�т̎v�l�v�ɓ��{�l�����ɐe����ł��邽�߂ƌ��Ȃ��Ă���B
�@��؏G�v�́A�h�C�c�l���A�킩��Ȃ��Ƃ������ς���āA�����̗�����莩���̈ӌ����͂����莝�Ƃ������Ƃ�D�悷��ԓx���Ƃ�A�Ⴆ�A�悭�m��Ȃ��ɂ��ւ�炸�u�˂�ꂽ���������ς肵���ԓx�ŋ������肷�邱�Ƃ��h�C�c�ł̐����Ō��������ċ������Ƃ����o���������A����ɑ��āA���{�l�́A�l�Ԃ̔��f�������̂Ƃ݂Ȃ������̎v�z�ɉe������A�������Ă��邱�Ƃł������̗����͕s�\���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ɗ����A�ނ���u�킩��Ȃ��v�Ɖ�������������肷��C����������̂��Ƃ��Ă���i�u
�X�т̎v�l�E�����̎v�l
�v�m�g�j�u�b�N�X�Ap.14�`18�j�B�����āA�������������̍l�����̈Ⴂ���C�y�ɉe������Đ��܂ꂽ���̂Ƃ��Ă���B
�u���̂悤�ȓ�����̘_���̕����ꓹ�́A�ǂ����Ă����������B�����ɁA�����ƐX�т���������Ă���Ǝ��͍l����B�����ł́A�����̓�������Ɏ��铹�ł��邩�ۂ��ǂ��炩�Ɍ��f�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̓������ւ̓��ł���Ɣ��f���邱�Ƃ́A���̓��͖łւ̓��ł���Ɣ��f���邱�Ƃł���B����ɑ��āA�X�тɂ́A�����[�������Ă���B���ւ̓����łւ̓����v���킸�炤�K�v���Ȃ��B���Ɩł���ʂ���K�v���Ȃ��B�l�Ԃ��A���ꂾ�Ǝv����������������Ƃɂ���āA�������ē�����������B�v�ip.83�j
�@�����ŁA�C������ׂ��́A������؍��͂ނ���u�����̎v�l�v�̉e���������Ƃ����_�ł���B�����v�z�ɂ�����_��́u�V�v�́u�X�т̕����̔@�����́A�����̃L���X�g���̐_�ɋ߂��v�ip.104�j�B�؍��ɂ��Ă͂������B�u�����C�̋������ł��鑾���m�̕����ɂ͓��{�������̂悤�ɘA�Ȃ��Ă��āA�J�͂����ő啔�����Ƃ���Ă��܂��Ă���B���{�̎����Ɗ؍��̊����͗����̊W�ɂ���킯�ł���B�T�n������A�A���r�A�A�^�N���}�J���A�S�r���ւĒ����k���ɂ�����劣���n�т́A������̉����̕����Ƃ��Ċ؍��̗���𗝉����邱�Ƃ��ł���B���̌��Ƃ����̂悢�؍��ł́A���{�ɂ͂Ȃ��A�ō��_�̐��q���`���Ƃ��Ă������v�ip.112�j�B������A�L���X�g�����Ȃ��Ȃ����y���Ȃ��������{�ƑΏƓI�ɁA�؍��ł̓L���X�g�����ϋɓI�Ɏ�e���ꂽ�Ƃ�����ł���B
�@���̂悤�ɍl����Ə�ŏЉ���悤�Ȉӎ������ɂ����āA�؍��l���u�킩��Ȃ��v�Ɖ��銄�������{�l�Ƃ͑ΏƓI�ɏ��Ȃ��̂����_�������B