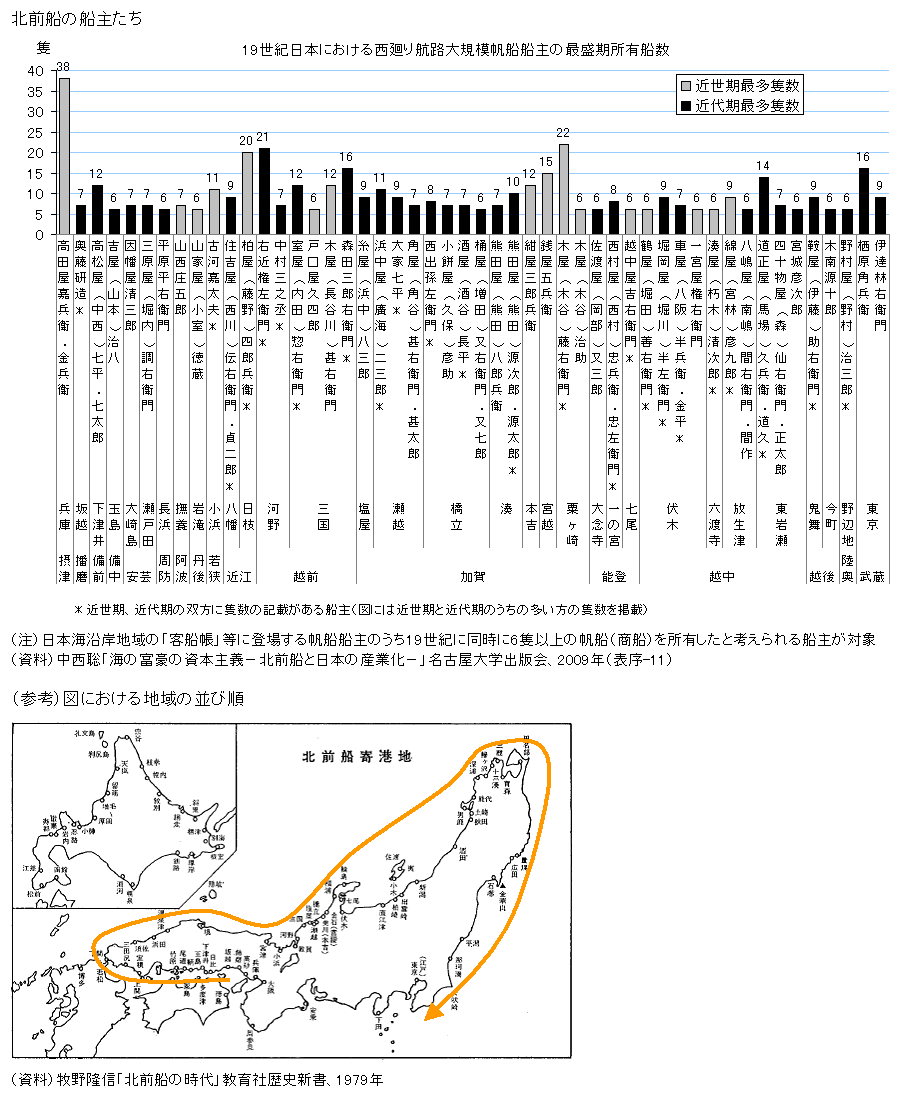
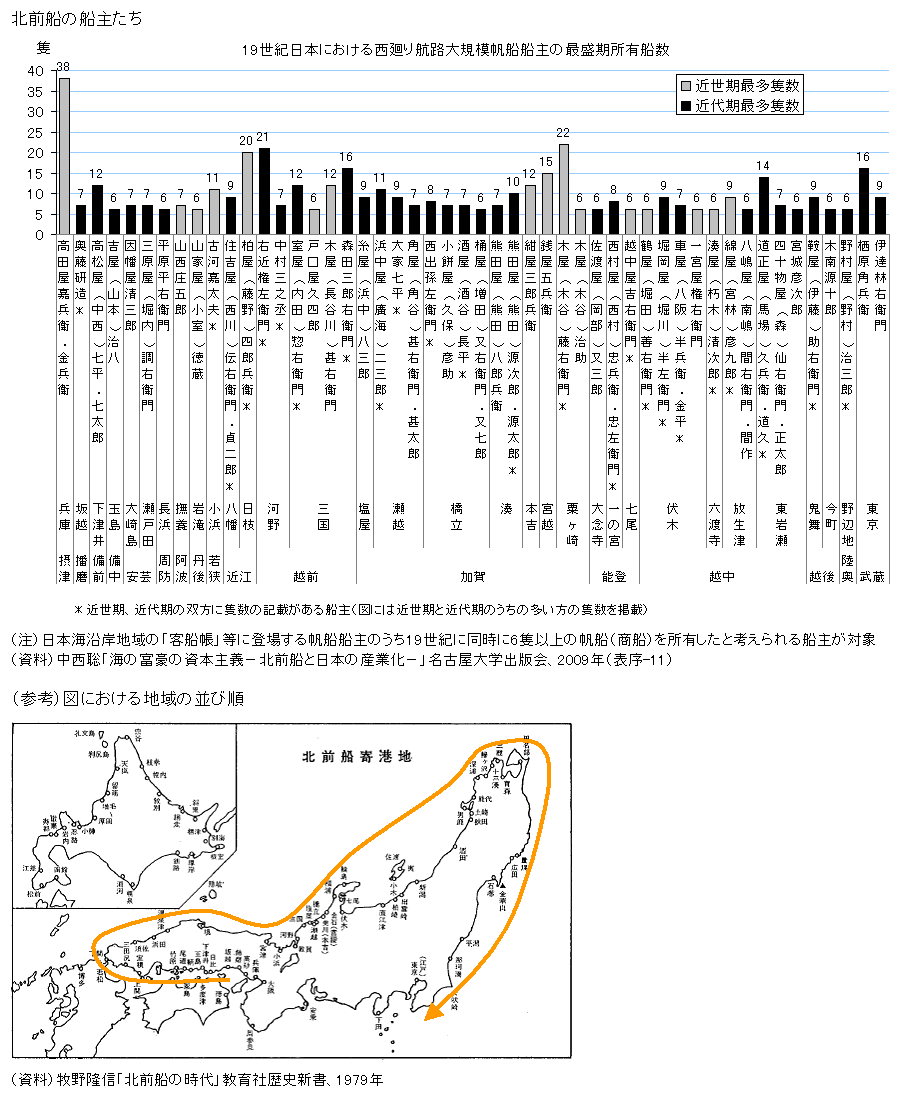
| ○北前船とその影響 秀吉の全国統一により年貢米などの流通が列島横断的となり、朝鮮出兵に伴う諸大名による兵員・物資の肥前名護屋回漕で本州日本海沿岸から北九州へ向かう航路が開かれた。近世に入り17世紀から以下のようなかたちで国内海運が発達した。 ①近江商人が送った荷所船 蝦夷地交易のための松前藩による場所請負制に近江商人が進出、関西への輸送船(荷所船)往来開始(北陸の船乗りを使用、敦賀-琵琶湖-大津経由) ②東廻り航路・西廻り航路(下図参照) 河村瑞賢による幕府天領米の江戸回漕のための東廻り航路、西廻り航路の整備 ③菱垣廻船・樽廻船(下図参照) 大消費地江戸へ物資(下りもの)を定期的に運ぶ菱垣廻船、樽廻船がはじまり大阪・江戸航路が発達(運賃積み船) ④琵琶湖ルートが西廻りルートに代替 延喜式以来の敦賀-琵琶湖-大津経由の「短距離水陸積み替えルート」に対し、西廻りの下関-瀬戸内海-京阪神「遠距離海運ルート」の経済性が凌駕 ⑤北海道漁業と西日本農業の連携 西日本の米や綿・藍・菜種などの商品作物の生産拡大にともなうニシン魚肥の需要増に対応して18世紀にかけて北海道との交易が拡大 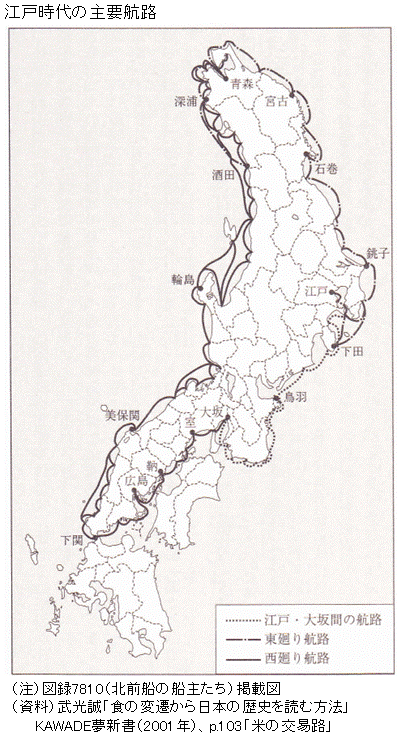 こうして、東廻り航路・西廻り航路、および大阪・江戸航路という全国沿岸海運ネットワークが形成された。近世に入ってからもしばらく江戸は生産地というより消費地としての性格が強かったため、東回り航路や大阪・江戸航路は帰り荷の少ない物流ルートだった。これに対して、西廻り航路は、距離は長いが、西日本の各地や北海道・東北・北陸を相互にむすぶ帰り荷の多い物流ルートであり、航路・港湾・船舶の発達によりますます日本経済の大動脈となっていった。 北海道の場所請負制の下、荷所荷を内地に送っていた近江商人は敦賀や小浜の港を利用し、北陸の船乗りを船頭や水主として用いていたが、北陸の元船乗りが、1750~60年代(宝暦・明和期)には、近江商人から資金提供を受けて船を造り、近江商人に船を貸したり、自ら荷を買い付けて買積船として活動するようになった(牧野隆信1989)。北陸を中心とした船主らは、近江商人の「持ち下り商法」(天秤棒でかついで隣国にものを売り、その代金で仕入れた産品をまた別の国に売る)に学んで、運賃・用船料収入(荷所荷輸送、米の回送など)から売買収入に重点を移しながら独自の沿岸海運経営を発達させたいった。これが北前船であり、その活躍は、明治期にまで及んだ。牧野隆信(1979)は北前船の定義を「北国の船で、蝦夷地と大阪を結んだ不定期廻船で、買い積みを主体とし、その船型は北国船・ハガセ船・ベンザイ船から西洋型帆船におよぶものである」としている。 ベンザイ(弁財)船までは1年1航海であり、西洋型でも数航海にすぎぬが、汽船は週1回も運航する。ただし、汽船の経営形式は運賃稼ぎが主となるので、純然たる北前船と言い難くなる。1年1航海時代の加賀の北前船の航海は次のようなサイクルである。春祭りが終わると、旅支度をととのえた船乗り(水主)は船主邸にあいさつに行く。真宗のご本山にお参りしながら、海路、陸路をたどって敦賀・湖西経由で大阪に4~5日かけて移動。大阪で、昨年暮れから預けてあった船の準備(修繕と積み荷の買い付け)を1カ月はかけて行う。彼岸前後に出帆。瀬戸内各地に寄港し、品物を買い集める。下関をまわる時、これからの波風の激しい日本海での航海安全を祈って裸で「角(つの)島まいり」行事を行う。故郷に立ち寄り、船主にあいさつ、家族に大阪土産を渡す。能登半島をまわって2週間をかけて函館・小樽へ向かう。積荷を北海道の問屋経由で売り捌くとともに、海産物を仕入れる。鰊は5~6月に漁獲される。乾燥、油絞り等の加工を手伝ったりして、荷物を積み込み、8月中に帰路につく。下関まで一気に登り(明治以前は中間も立ち寄り)、瀬戸内で取引をしながら各港を回り、終点大阪に晩秋か初冬、時に年末に到着する。「木津川口などの淡水に船をつないで船食虫を防ぎ、あるいは船底を薫蒸して番人をおいて、前のように歩いて郷里に帰るのは大晦日に近かった。」氏神さまへのお礼参り、船主宅の雑用・掃除・餅つき、山中温泉への湯治などを経て正月を迎える。 大阪から北海道へ向かう「下り荷」としては、大阪で仕入れる酒、飲食料、衣料、たばこ、また、瀬戸内で仕入れる塩、砂糖、蝋、東北で仕入れる米などがあった。特に、北海道の漁獲物処理に必要な塩は重要だった。北海道から大阪へ向かう「登り荷」は、種類は少なく、魚肥の丸干鰊、胴鰊、〆粕、白子、食用の身欠鰊、数の子、昆布などである。上で、西廻り航路は帰り荷の利益があったといったが、それでも、「下り荷」からの利益より、「登り荷」からの利益の方が大きかった。「登りの利益はよほど悪いときでも下りの利益の2~3倍、よいときには10倍以上に及ぶのが常であった。一般には下りの荷物は空荷にならぬ程度に考え、登りでうんと利益をあげる計算だった。」 幕末・明治初期の北海道産水産物の本州への移出状況については図録7812参照。ここには北陸の北前船が大きな役割を果たしていたことが示されている。 北前船の影響で日本海側や関西では昆布やニシン(鯡)などの北海道の食材が食生活の不可欠の一部となったが、太平洋側や江戸ではそうした要素が希薄のままとなった。肥料になる内臓を取り除いた身欠きニシンを使った昆布巻きやにしんそばが京都の名物産品となっているのもそうした事情による。  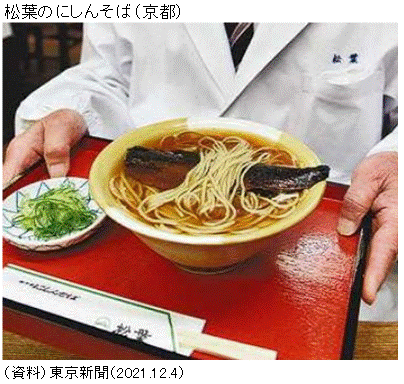 「にしんそばが生まれたのは140年ほど前。1861(文久元)年創業の老舗そば店「松葉」の二代目、松野与三吉が発案した。四方を山に囲まれ、タンパク源をニシンやタラといった干魚類に頼っていた京都。そばとニシンの組み合わせは次第に人気となった」(東京新聞2021.12.4)。 大阪生まれで30歳で江戸に移った喜田川守貞が著した幕末の風俗誌である「守貞謾稿」は京阪と江戸との対比がちりばめられているのが特徴だが、「鯡昆布巻売り」の項でこう印象深く記している。「鯡、江戸これを食す者稀なり。専ら猫の食とするのみ。京都にては、自家にこれを煮る。あるひは昆布巻にす」(「近世風俗志―守貞謾稿 (1) 」 岩波文庫、p.287)。 会津には郷土料理としてニシンの山椒漬けが伝来している。これは各家庭で毎年山椒が芽吹く春から夏にかけて貴重なたんぱく源の身欠にしんと山椒の葉を重ね合わせ、しょうゆと酢、好みで隠し味に酒と砂糖を入れ、2~3週間漬けてつくる保存食品であり、にしんを漬けるための会津本郷焼の「にしん鉢」は古くは会津の嫁入り道具の一つとされていた。これは会津が阿賀野川(福島県内阿賀川)を通じて北前船文化圏に属していた証拠であるといえよう(流域図は図録9416参照)。  東北の郷土食の中には、上方料理のアイデアが北前船で伝わって生まれた例もある。京都の「いもぼう」は、海老芋とよばれる大きな海老の形をしたお芋と、宮中への献上品にもなっていた北海道産の棒鱈(干しダラ)を炊き合わせた名品料理である。山形名物にいも煮、あるいは芋煮会があるが、その発祥は地元食材の里芋を使った「いもぼう」だったという。  山形市の隣町である中山町は「芋煮会発祥の地」と称している(ここ)。最上川舟運がより上流の荒砥まで通じる1694年までは現在の中山町長崎付近が最上川舟運の終点であり、ここが米沢方面へ船荷の積み換えが行われた要地となっていた。内陸からは米、紅花などを運び、一方、京都からの帰り荷には衣料、蚊帳、ひな人形など上方文化を積み帰ってきていた。船着き場付近には「鍋掛松」という老松があって、そこが船頭たちの休み場だった。酒田から船で運ばれてきた塩や干魚などの資材はここで降ろされ、人足たちに背負われて狐越街道を越え、遠く西置賜地方へと運ばれた。船頭たちは船に寝泊まりしながら何日も何日も船が着くのを待つことが多かった。そんな時に、京都から運ばれた棒鱈と地元の里芋を材料に河岸の松の枝に鍋を掛けて煮、飲み食いしながら待ち時間を過ごした。やがてこの松が「鍋掛松」と呼ばれるようになったという。そんな退屈しのぎの料理として発生したのが芋煮会のはじまりだと言われているのである。 この他、山形市には上方から北前船を通じて伝わり、現在、無くならないよう再興へ向けての取り組みがなされている郷土料理「すっぽこ」などもある。 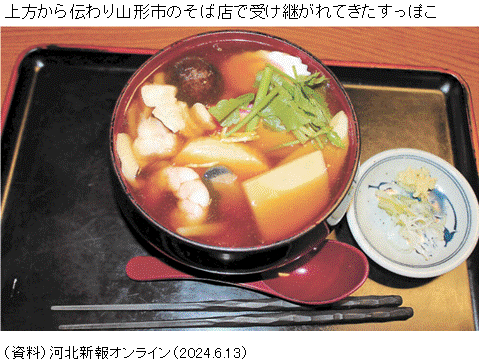 「すっぽこ」は、江戸時代の近江との交易がルーツと伝わる冬限定のあんかけうどんであり、片栗粉で強めにとろみをつけたつゆにゆでうどんを入れ、干しシイタケの煮付けやエビ、かまぼこ、だし巻き卵などを載せる。滋賀県長浜の「のっぺいうどん」が、すっぽこによく似たあんかけうどんだということから、上方で親しまれたあんかけが近江商人を通じて根付いたと考えられる。かつては、具が豪華で値段も高かったので裕福な旦那衆が出前で頼んでいたメニューだったという。 北前船の影響が東西の食文化の違いの大きな要因となっている点については、図録0668(昆布消費の地域パターン)、図録7805(金沢の人がとくに好んでいる食べもの)、図録7806(富山の人がとくに好んでいる食べもの)も参照。 発酵文化の日本海側優位が北前船によってもたらされたという説がある。全国を渡り歩いて、日本人の生活を分析した民俗学者の宮本常一が気がついた日本海側と太平洋側との違いの観察が興味深い。彼は、昭和21年に、東北地方を、福島~宮城~岩手~下北半島~弘前~秋田~山形~米沢~東京と民家に泊めて貰いながら巡回した。そこで気がついたのは、太平洋側では濁酒も漬物もふるまわれなかったのに、津軽以降の日本海側では、毎回、それらが出てくるという経験をしたという。このことから彼はかつては舟で運ぶしかなかった樽や壺といった重たい容器の普及の差が酒や発酵食品の普及の差を生んだと分析している(宮本常一・潮田鉄雄(1981)「食生活の構造」柴田書店、p.37~38)(注)。 (注)壺の入手容易さから発酵食品の産地が生まれた事例としては、福山(鹿児島県霧島市)の黒酢がある。福山は薩摩藩の時代に商業港として栄えており、そのため原料である米と発酵に欠かせない壺を入手しやすかったことが黒酢の産地となった経緯だという(尾形希莉子・長谷川 直子「地理女子が教える ご当地グルメの地理学」ベレ出版、2018年)。 遊里文化にも北前船文化圏の影響が大きかった。「新潟での「かねつけ」(芸娼妓の水揚げを既婚者の鉄漿つけになぞらえる風習-引用者)は京都と同じように寛政期にはすでにはじまっていた。(中略)遊里が上方系か江戸系かで、水揚げをするかしないかの境界線も引かれるのではないだろうか。舟運の関係で新潟も京都文化圏に含まれていた。京風文化は日本海に沿って津軽から北海道の松前にまで及んでいた。(中略)西国では上方遊里のしきたりがいっそう濃厚に伝播していたはずである。港町の娼妓のほとんどは芸娼妓兼業だった」(宮島新一「芸者と遊郭」青史出版、2019年、p.120)。 北前船は、江戸後期・明治前半期に最盛を迎えたが、その後、蒸気船との競合、電信による遠隔地間価格差の縮小、鉄道輸送の発達、北海道ニシン漁の縮小、西日本の綿作・藍作などの衰退(輸入品に代替)で西廻り航路の衰退がはじまり、北前船船主は、北海道商業への特化、遠洋漁業、地主経営、銀行業、産業資本家への転出などへと経営を転換していった。 ○北前船の船主たち 図に掲げた北前船の船主たちについては、以下のようにコメントできる。 (高田屋嘉兵衛・銭屋五兵衛) 幕府や藩とのつながりが深く、近世には大きく経営を拡大し、歴史上も著名となった船主としては、やはり、「高田屋嘉兵衛」と「銭屋五兵衛」をあげるべきであろう。
淡路島生まれの高田屋嘉兵衛は、兵庫を根拠に日本海・松前方面との廻船業を始め、幕府の北方政策に密着して1800年には択捉島に至る航路や同島の漁場を開発し1801年には幕府から蝦夷地定雇船頭を命じられた。1812年、ゴローニン逮捕の報復として国後島付近の海上でロシア船に捕らえられたが、その後ゴローニンの釈放に尽力し釈放された経緯は、高田屋嘉兵衛を主人公にした司馬遼太郎の「菜の花の沖」で世に知られる所となった。 「高田屋は19世紀初頭に大坂と江戸に支店を開設し、幕府蝦夷地直轄でいったん廃止された場所請負が再開されると、1810年から択捉場所・幌泉場所を、15年から根室場所を請け負うことになった。択捉場所では鮭・鱒が主要漁獲物で、幌泉場所(現えりも町)では昆布が主要産物であったが、いずれも太平洋沿岸のなかでは産物の豊富な場所であり、太平洋岸を請け負った場所請負人のなかでは高田屋が最大の運上金を納めた。(中略)1824年には本店を箱館に移転し、兵庫店を支店としたが、この頃が高田屋の全盛期であったと考えられる。その前年の1823年に幕府の蝦夷地直轄が終了し、松前藩に蝦夷島が復領されたが、北海道での有力な後ろ盾を失った高田屋は、結果的に密貿易の疑いをかけられて松前藩によってとり潰された。没収された高田屋の資産として38隻の船があり、そのうち12隻が公売された。このとき3隻を前述の(当図録では近江の箇所に後述の)柏屋(藤野家)が取得し、また柏屋は高田屋処分後に根室場所を請け負い、以後柏屋が太平洋岸を請け負った場所請負人のなかで最大の運上金を納めた」(中西2013)。 加賀藩北部の金沢藩領域では、木屋藤右衛門や銭屋五兵衛が「北海道への進出よりも藩米輸送に力を入れ、藩権力との距離が近かった点で、大聖寺藩領域(塩屋、瀬越、橋立)の船主と異なり、藩の政争に巻き込まれて、木屋も一時的に断絶の危機を迎え、銭屋は結果的に取り潰された。そうした御用を重視した経営展開は、近代初頭の廃藩置県により、事業機会を失うこととなり、近代以降に木屋などは、海運経営を発展させ得なかった」(中西聡2009、カッコ内は引用者)。 銭屋の場合、弘前藩・盛岡藩域での材木取引・藩貸付、金沢藩直営海運請負に続いて、藩にとっての税収増、自分にとっての地主経営のため着手した大規模な河北潟埋立新開で生活権を奪われる漁民の反対を受け、魚を食べて中毒死する者も出たため流毒の疑いがかけられ、この疑獄事件で牢死した(息子は磔刑)。銭屋五兵衛は、高田屋嘉兵衛とは異なり船頭をしたこともなく、藩財政と関係を深めながら躍進した豪商が北前船船主にも乗り出したという側面が強かった。反銭屋の激しい世論に対して、藩当局との癒着を疑われる事態に発展するのを恐れ、事実が究明されないままに厳しい処断で一件落着が図られた。当初は、大儲けしていた銭屋に反感をもった一般庶民も厳しい処分の反動でむしろ同情を寄せたり、もっと大きな密貿易事件などを想定して納得しようと考えたようだ。この結果、世上に朝鮮人参や対ロシアの密貿易や南部・津軽材木買占め容疑説も流布し、この結果、明治以来、「海の百万石」などと称され、ノンフィクションや時代小説の格好の題材となった(木越隆三2001)。 農産物からの年貢収取を主たる財源とした近世支配体制の中で、富豪の生まれる余地は、幕府直轄の貿易や鉱山経営、あるいは大名との間の中抜きとなる地主経営にはなく、もっぱら遠隔地間取引からの商業収入にあったため、海運技術に立脚した船主が豪商となる可能性は大きかったが、支配権力との結びつきが強すぎると、御用金の負担も大きく、また政敵らの動きで取りつぶされるリスクも高かったことが理解できる(図録7809コラム参照。 (瀬戸内海地域) 西廻り航路は、瀬戸内海海運と日本海海運に大きく分けられるが、瀬戸内海海運の船主にはもともとは特産物輸送の廻船に依拠していた場合が多い。例えば、播磨の坂越の「奥藤研造」は赤穂の塩を専門的に扱う塩廻船、阿波の撫養の「山西庄五郎」は藍業・塩業・藍作肥料魚肥の廻船問屋であり、かつ船主でもあった。山西家は海運経営のほか、土地取得を進め、また酒造・醤油醸造など経営多角化を図り、明治時代には徳島県での上位の資産家になったと推定される(中西2013)。因島の西に位置する瀬戸田には、塩田を開発し、その塩を北前船で北海道に運んで繁栄した豪商「三原屋堀内調右衛門」がいた。現在、この家の土蔵が瀬戸田町歴史民俗資料館として公開されている。
備前・備中の海岸部の開拓で綿、菜種、い草などの栽培が広がり、現在瀬戸大橋のたもと近くに位置する下津井(倉敷市)や高梁川河口の玉島(同市)は蝦夷地のニシン肥料を運ぶ北前船でにぎわった。下津井には岡山城下をしのぐ豪華さをほこった遊女屋が港を囲むように広がっていたといわれ、祇園神社には北陸の商人、船頭に交じって寄付をした遊女の名前が玉垣に刻まれている。同神社には塩屋(加賀市)の北前船主新後長四郎が祇園ばやしに導かれて嵐を逃れたことから寄進したといわれる石灯籠も残る(加藤2002)。「高松屋」の母家やニシン蔵は「むかし下津井回船問屋」として当時に近いかたちで復元されている。玉島では1670年に築かれた潮止め堤防が、沖投錨、伝馬船運輸が通常だった江戸時代にはめずらしく北前船が直接接岸する岸壁として利用されていた(加藤2002)。 (近江) ①に掲げた通り、北陸地方の北前船のおこりは近江商人が共同で雇った荷所船の船乗りだった。表の船主には、近江商人が2人掲げられている。「西川伝右衛門」は、建部七郎右衛門、田附新助、岡田弥三右衛門とともに16世紀末には蝦夷地にまで商圏を拡大した。また加賀市橋立には、「藤野四郎兵衛」を御本家と呼ぶ家が多かったという。
近江八幡の代表的商人だった「住吉屋西川家」は、越後への荒物行商から17世紀には北海道へ進出し、北海道で請け負った場所で漁業を行い、その漁獲物を手船(自己所有船)で本州に輸送し販売した。小樽に隣接した忍路や高島が主たる請負場所だった。住吉屋西川家の船舶輸送は、運賃積でも北前船に典型的な買積船でもなく、自家用輸送船だったが、遠隔地間の価格差で高利益を得ている点からは北前船と呼ぶことができる。北海道へ進出した近江商人たちは当初両浜組という仲間組織をつくり、松前藩の御用金負担と引き替えに免税特権を得、共同で荷所船を雇って漁獲物を運ばせていた。ところが田沼時代の幕府による北海道開発計画を契機に江戸系商人が北海道に進出し、特権を失った両浜組商人の多くが北海道から撤退したことで荷所船の船主は買積船経営へと転換し、典型的な北前船主となっていった。これに対し、住吉屋は自身で船を所有し、北海道の請負場所(忍路・高島)、松前、下関、大阪、敦賀、江戸をつなぐ自家輸送を行うことで江戸系商人に対抗していったのである(時代により経路は変化)。明治維新後の場所請負制の廃止、また北海道への日本郵船(三菱)や三井物産の進出に対しては、新規漁場の開拓による漁獲量の拡大や近江農民の肥料購買組合設立促進などの販売網再編で対抗した。1890年代には海運業からは撤退し、経営の主力を北海道に移し、忍路、高島に加えて北見にも新漁場を開き、巨大漁業家として展開し、1920年代までは有力資産家の地位を維持した。北海道での西川家の新事業として缶詰事業があり、1888年からタラバ蟹の缶詰を製造し、高品質で賞も得たが贅沢品のため販路は広がらなかったという(中西2009、2013)。 近江の日枝出身の「柏屋藤野家」も西川家とほぼ同様の経緯を辿った。初代藤野喜兵衛が松前にわたったのは12歳。1800年20歳で独立し柏屋を興し、有力場所請負商人となり、北海道各地の漁場開拓に成功。商標は「又十」。藤野家の手船「長者丸」が松前藩主が津軽海峡を渡る時の御座船となり、また藩の御用達になって藩権力との結合を次第に強めた。2代、3代四郎兵衛と傑出した経営者が続き藤野家は富豪に成長した。膨大な物資輸送に北陸の船も雇い、この中から後に独立する人々が輩出。加賀の橋立では「又十」を終生本家とした家がいくつもある(加藤2002)。江戸時代の柏屋は、宗谷、利尻、枝幸、斜里など日本海・オホーツク海沿岸の請負場所との運航は松前(福山)を拠点とし、また根室、国後など太平洋岸の請負場所(上記の通り根室は取り潰しにあった高田屋からの受け継ぎ)との運航は箱館を拠点とし、大阪での問屋経営と組み合わせた蝦夷地奥地の巨大請負兼手船経営として活躍するとともに、上記住吉屋手船とともに江戸との間の手船輸送にも進出、北海道産物の太平洋航路による輸送にも道を開いた。近代以降の遠隔地間価格差の縮小に対しては、西川家のように海運業から撤退せずに、汽船経営への転換を図り、また漁場開拓とともに缶詰工業や農牧業へと経営の多角化を進めた(中西2009、2013)。 図に見るとおり、北前船の船主は、若狭・越前(福井)から越後(新潟)までの北陸地方に多かった。 (若狭・越前) 古くから敦賀、ついで小浜、三国などが開け、港町としての繁栄は越中・越前より早かった。敦賀では、戦国時代末期から江戸時代当初に道川(どのかわ)や高島屋などの豪商が大名の廻米を担って大きな力をもっていたが、江戸中期以降には、こうした古い海商に代わって図に掲げたような北前船が繁栄した。
若狭・越前地域の有力北前船主は3つのタイプに別れる(幕末期に廻船経営から撤退した河野の「戸口屋」「木屋」を除く)(中西2009)。
五代目嘉太夫が文化12(1815)年に小浜藩主を迎えるため造成した「護松園」が小浜市北塩屋に残っており、北前船の昔日の勢威を今に伝えている。七代目嘉太夫は、維新の際、会津討伐を命じられた藩のため持ち船全部を大阪で売却し、軍用金として献上し廃業した。明治に入って再度船を購入して廻船業を再開し、八代目が交易を盛大にしたが、病弱の身と北前船の将来を予見し明治12年には再び廃業を決定した。 三国の「森田家」は御用金負担が少なかった分幕末期に資産蓄積が可能となり、1875年頃には16隻の和船を有するに至った。松方デフレの打撃により1883年には海運経営から撤退した。その後、兼営していた醤油醸造のかたわら、蓄積資産を銀行設立に投入(94年森田銀行)、折から敦賀より福井、小松へと鉄道が延伸整備されたのを受けて、さらに鉄道貨物を扱う倉庫運送業に進出し成功した。三国の他の北前船主が家産を減らす中で、森田家のみがこうした転身により三国地域最大の資産家となった(中西2009)。 河野の「右近家」・「中村家」は天明・寛政の頃から弁財船をつくって海上に活躍した。右近家は早く芦屋に移ったが中村家は長く河野村に邸宅を構え、明治40年代には北洋漁業に進出した。 越前河野の「右近家」は、他の多くの北前船主と同様に近江商人両浜組が雇う荷所船主としての活動からはじまり、両浜組と荷所船主との関係が不安定となると、買積船主に転換し、船数を増やしていった。下関を廻って畿内まで毎回運ぶのではなく、敦賀で折り返して年に複数回北海道と本州を往復することで年間利益額を増やす工夫をしたのが右近家廻船の特徴であった。近代に入っても所有船数を増やし、大家七平家や広海二三郎家などと同じように、西洋型帆船による買積経営と大型汽船による運賃積経営を併存させながら、北海道での漁業経営、小樽での倉庫業を行った。資産家として大阪の銀行・保険業の発展に貢献し、右近家当主は、大阪商業銀行の頭取、日本火災保険会社(北前船主が中心となって設立)の社長を務めた(中西2009)。 *北陸五大船主・・・広海二三郎(瀬越)、大家七平(瀬越)、浜中八三郎(塩屋)、右近権左衛門(越前河野)、馬場道久(富山岩瀬)。彼らが中心となって、明治20年、「北陸親議会」が結成された。これは、三菱系・三井系船社が合併して日本郵船が発足、日本海側へ進出してきたのに対抗するためといわれる(加藤2002)。彼らの船は、2大大手資本の日本郵船、大阪商船両社の「社船」に対して「社外船」と呼ばれた。 (加賀) 福井県との県境の海岸部に位置する塩屋、瀬越、橋立は、加賀藩の支藩大聖寺藩の領域にあり、現在は、旧江沼郡の町村が合併して出来た加賀市の一部になっている。
大聖寺川の河口に位置する塩屋は、大聖寺川を利用する水運と連結する便があり、藩政時代には大阪廻米もここから送られた。塩屋の北前船主としては西野小左衛門・小右衛門、「浜中八三郎」、能登屋吉与門、新後長四郎などが知られている。 明治22年の石川県所得税納税者名簿には、以下のように、浜中姓の者が塩屋村に5人出てくる(松村敏氏の情報提供による)。
私事にわたるが、私の母方の曾祖父は、ここに登場する石川県塩屋村(現加賀市)の北前船の船商「浜中又吉」である。 又吉(写真)は1899年には帆船3隻を所有し、1910年代に北海道古宇郡・宗谷郡に漁場をもっており、1925年時点の資産額は40万円だった(中西聡(2009)の「表補Ⅰ-1北陸親議会加盟有力船主の経営動向」による)。北海道に移り、岩内(岩内倉庫合資)と稚内、および大阪に店をもって北海道との物流・商取引で財をなした又吉は、のちに金沢に市中の川から取水した大きな池をもつ豪華な居宅を構え、美術・骨董商も出入りしていたという。明治維新の際、江戸から陸路で北海道まで退き五稜郭に立てこもった幕臣の娘勝を北海道でめとり、店の経営に携わらせたと聞いている。  岩内出身の画家木田金次郎とつながりがあった関係で母は木田の静物画を所有していた(苹果の図、昭和13年、木田金次郎作)。三男であった私の祖父貞雄は早稲田大学を卒業し、親から資金を与えられて商社を東京で起こし、のち軍需工場を設立、ビニール製靴底製造へ出資するなどの活動を行った。母は娘の頃、大きな庭があり、飼っていた三頭のシェパードを住み込みの書生が世話するような裕福な家庭で育った。 塩屋村だけの事例ではあるが、図に示されているような大きな船主の他に、中小の北前船船主が多くいたことがうかがわれる。 河口の塩屋から少し遡った所の瀬越は「港のない船主の村」であるが、「広海二三郎家」、「大家七平家」の両家が名高い。 広海家には、早くに神戸市に移ったが、文禄二(1593)年江沼郡を領した溝口秀勝によって、敦賀までの貢米を託され、代わりに諸役を免除するとのお墨付きをもらったという家伝がある。安政元年生まれの五世二三郎は社外船(日本郵船、大阪商船の2大海運会社の船舶を社船と言うのに対し、それ以外の船主の船をこう呼ぶ)には珍しく、洋帆船に加えて、蒸気船を購入し、硫黄(豊後、薩摩)、石炭(筑前)の鉱山経営にも手を広げるなど積極多角経営を行った。 四世大家七平は大阪に本店を有し、広海家同様汽船を所有、明治29(1896)年には逓信省の命を受けシベリア諸港との定期航路を開き(当初、函館・小樽・コルサコフ間と新潟・函館・ウラジオストック間、後に、函館・小樽・コロサコフ・ウラジオストク・韓国の元山、釜山・日本海沿岸諸港を航行する日本海線航路へと拡大)、日露戦争の際には御用船として汽船3隻を供出するなど国策に協力した。この他、硫黄採掘(福島県)、金銀銅山(栃木県)の経営、地主経営(近在及び兵庫県)など手広く事業を展開した。 大聖寺藩の港として元禄初頭に船番所が設置された橋立では、久保一族の総本家である久保(小餅屋)彦兵衛やその分家「久保彦助」、「西出孫左衛門」が有力船主だった。久保家、西出家は献金等を通じた大聖寺藩政への協力でも知られる。十一代西出孫左衛門は、北前船が衰える明治末期以降、函館を拠点とした北洋漁業に転身し、北海道経済界の重鎮として活躍した。函館山は、明治中頃までは西出孫左衛門が所有していたため、「西出山」と呼ばれていた。 橋立の酒谷家19世紀中葉には箱館の問屋から魚肥を買い入れて大坂・兵庫の湊に運んで販売した。近代期の酒谷一族は、本家の長平家と分家の長一郎家が北前船を継続、雇船頭の小三郎を店主として1890年に函館に支店(酒谷商店)を開設し、この支店からの荷物を畿内・瀬戸内に販売した。汽船網・電信網の発達により、地域間価格差が縮小したので、日露戦後に南樺太が日本領になると、樺太漁業に進出し、自らの漁獲物を廻船で輸送したが、コストとの割には利益が上がらず、1918年に酒谷長一郎家は海運業から撤退した(中西2013)。 加賀国湊の「熊田屋源次郎・源太郎家」は、近世期の瀬戸内海産の塩や越後産米の買積経営から、近代に入って、和船を西洋型帆船に転換して海運をさらに発展させるとともに、土地を取得し石川県域の最大級地主となり、鉱山経営にも進出した。二代源太郎は多角化を進め、北海道での漁業経営・農場経営、地元での銀行、鉄道、倉庫などの経営に関与した。結果的に地元の企業勃興に最も貢献したのは、銭屋のような旧金沢藩域の大規模御用北前船主でも、広海家、大家七平家のような旧大聖寺藩域の大規模北前船主でもなく、熊田家のような旧金沢藩域の中規模北前船主だった(中西2009)。 本吉(美川)は、手取川対岸の今湊とともに廻船業の繁昌したところであり、船主としては、幕末の長者番付で東大関「宮腰銭五」に対し西大関「本吉紺三」といわれた「紺屋三郎兵衛」が有名である。明治5(1872)年石川県庁が美川に開設されたため、三郎兵衛は町の要職につかされ、海との関係を絶ったという。美川港自体の海運も鉄道の開通とともにさびれた。 金沢の外港として栄えた宮腰(宮越)は、明治の鉄道開通までは海上運送の中心地だった。上でふれた銭屋五兵衛が「海の百万石」として天下に知られた豪商だったが、もともとは、質流れの三人乗り古船で米の廻送に従事した小北前船主から身を起こしたという。 金沢の外港粟ヶ崎では、西国武士出身の「木屋家」が、図の北前船主たちの中では、高田屋嘉兵衛に次ぐ最盛期22隻の大船主だった。取扱品に材木や薪が多かったので「木屋」と称した。加賀藩、富山藩、大聖寺藩への資金提供を繰り返し、大聖寺藩では木屋の山中温泉入湯に見舞いの使者まで出すほどだった。同家は銭五ほどの風雲児ではなく、数代にわたり家産を蓄えた。 木材は建設・造船用材、エネルギー源として現代の鉄・セメント・石油といった資材を合わせた重要性を持っていた。城下が繰り返し大火にあい、橋が春先融雪時の増水で毎年のように流される度に木材の需要が発生した。加賀藩では用材を越中や能登の他、隣接する飛騨からも庄川・神通川下りで入手していたが、飛騨が元禄5(1692)年に天領となってからは、河口の伏木・東岩瀬に集められた飛騨材は江戸・大坂方面に海上輸送されるようになった(運んだのは大阪・瀬戸内の船)。このため加賀藩は東北・蝦夷方面から用材を求めざると得なくなった。こうした背景の中、特に、宝暦9(1759)年の金沢大火の復興需要を受け、「木屋藤右衛門家」は北方に買い付けし海上で運ぶ材木商として肥大化していったのである。18世紀後半の加賀藩の重商主義的産業政策の中で藩との関係が密接となり、持ち船規模も天明6(1786)年に29隻と巨大化した一方で、藩の財政改革の中で利を貪ったとして隠居5代目、及び6代目が逮捕入獄、5代目は天明7(1787)牢死という目にもあった(6代目は1791年出牢、財産返却)。その後、持ち船は寛政12(1800)年22隻ののち、天保8~10(1837~39)年6隻、安政年間8隻と減らしたが、これは「危険な船商売から土地集積にあたったから」だといわれる(高瀬1997)。 北前船は船主が直接売買取引する「買積み」運送に特徴があるが、材木海運の場合は原木伐採の請負人への前貸し契約で買い付ける材木問屋が海運業者に運送を依頼する運賃稼ぎの「賃積み」運送も多かった。この場合、海難時に「船主運賃損、荷主荷損」となり、荷主の負担が大きいので、「敷金積み」という海運も行われた。これは、船主が荷物代の半分程度を敷金として荷主に預託し、海難時には運賃のほかに敷金も船主の負担となる方式であり、荷主の負担が緩和されるので、藩の蔵運送でも採用されたという(木越2001、p.48~55)。 「木屋木谷家」は17世紀に材木問屋を開業、19世紀前半は北海道産物を扱ったが、19世紀中葉以降は、登り荷として越後・庄内地域の産米を専ら扱い、それらを瀬戸内で販売し、下り荷として塩・蝋などを新潟や津軽鰺ヶ沢で販売した。こうした関係により蔵米の販売や財政資金融通で弘前藩との結びつき強めた。弘前藩の他、地元富山・金沢藩や東北・日本海沿岸諸藩との深い関係の中で船主経営を行った。維新後は諸藩の保護もなくなり、海運業から銀行業へ転換、1881年には最後の船を手放した。その後、銀行業や鉱山経営などは傾き、醤油醸造業で家を継続させた(若狭・越前の①タイプと同じ)(中西2009)。 (能登) 能登の一の宮は、神社の鳥居も海に近く、古くから船乗りが海上に活躍した。一の宮出身で大阪で躍進したのが「西村屋忠兵衛」であり、その後、二代、三代と続き、明治20年頃には北海産物取り扱いトップとなり、「銀行の鴻池、鉱業の古河、海運の西村」が「浪華財界の三羽烏」とうたわれた。しかし、息子の放蕩、大阪と国元の二人妻からおこる一族の抗争、汽船沈没、拡大した事業の不振などで、三代目で大阪本店を閉鎖、故郷に帰り、七尾を中心に汽船会社を経営したが、昔日の繁栄は期すべくもなかったという(西村1964参照)
(越中) 金沢藩領であった越中西部の高岡は、大阪に次ぐ生産量を誇っていた新川木綿(にいかわもめん)の産地(越中東部新川地方)への流通中継地として藩が綿場を設定した。このため、畿内から綿を運び入れる伏木湊や放生津湊の北前船主や廻船問屋、そして高岡綿場商人が綿流通で利益を分け合っていた。また高岡の後背地には砺波平野が広がっており、米生産が盛んだった。このため、伏木湊や放生津湊の北前船は、綿と米の取り扱いが多かったが、近代に入り、綿織物や綿糸の輸入が増加したのを受けて、綿・米から北海道産物取引に本格的に転換した(以下越中に関しては中西2009、高瀬1997による)。
伏木の「鶴屋(堀田)善右衛門家」の養嗣子となった堀田勝文は伏木町長、県会議長をつとめたが、その息子が作家の堀田善衛である。 伏木湊に隣接した放生津の「綿屋宮林家」は、能登国守護畠山氏に仕えた武士だった先祖が砺波郡に移り、漁具・網を作る藁工品を放生津の漁民に供給していたが、後に放生津に転居して、漁業経営に乗り出したという伝承がある。18世紀には網元として大規模に鰤漁や魚肥となる鰯漁を行うようになった。その後19世紀前半に和船を所有し、畿内で買い付けた綿を伏木に運び(屋号の由来)、また北海道交易も行う買積経営に乗り出すとともに、金沢藩・富山藩の領主米輸送に携わり、1840年代以降に村役人を務め、幕末期から近代に入っても土地取得を進めた。宮林家は、藁工品資本が漁業資本、海商資本、地主資本におきかわっていったとされる。宮林彦九郎家は明治10年代に「草高二千石、網高二千石、合わせて四千石」と俗称された。海運経営からは1880年代前半の松方デフレ期以降に撤退した。「綿屋宮林家」は、北前船主を先祖に持つ藤井能三とともに、三菱汽船の伏木寄港を誘致し、次にはその横暴に対抗して北陸通船社を創立し、三菱に対抗する勢力を結成した。明治20(1987)年以降船の経営をやめたが、高岡米会所、銀行などの役員活動を通じ地元財界のリーダー的な存在であった。 神通川河口の港町東岩瀬(金沢藩領)の「道正屋馬場家」は、近世期から、富山藩の御用をつとめ、遠隔地間の海運経営を行う大規模北前船主だった。後背地の新川地方が近世期には著名な木綿産地だったので高岡で繰綿を仕入れて新川の綿屋に販売する綿商人も兼ねていた。近代に入って、米・塩・綿・砂糖から天保以来の北海道と瀬戸内・畿内を結ぶ北海道交易に比重を移すとともに、汽船経営への転換を進め、県下の多様な会社の経営に携わり、また土地を大規模に所有して富山県最大の資産家となった。馬場家は藤井らと協力し、つねに政府と結ぶ中央の三菱汽船らに対抗し、日本海運業同盟会でも中心的存在だったという。 東岩瀬の「宮城彦次郎家」は、馬場家廻船の雇船頭を努め、近代に入って独立した家である。明治以降地租金納化により米作地帯の富山では米穀・肥料商が輩出、宮城家はこれら米穀商の頂点の1つで、富山県内のみならず能登・越後にまで買い付けの手を広げた。明治10年代の早い頃は北海道に米を運んでも損となったが、北海道移民・出稼ぎ増により米穀市場が成長、一方で、越中米の大阪での評価下落(藩による厳密品質管理がなくなったため)もあり、北陸から北海道へ米が運ばれるようになった。明治20年代の宮城家の活動は、富山県の米を北海道に運び、北海道の鰊肥など海産物を富山県及び近県・瀬戸内・大阪へ運び、瀬戸内との競争で縮小した能登塩に代わる瀬戸内の塩、および瀬戸内の麦・豆を富山県及び日本海側に運ぶという形となっていた。 宮城家や「森家」(邸宅が明治前期の町屋遺構として価値が高いため富山市指定文化財)など北海道産魚肥を多く扱うようになっていた東岩瀬の北前船主の多くが、20世紀に入って近畿との物流が鉄道に転換し(大阪からの北陸線が1897年に富山まで開通)、北海道産魚肥の物流が鉄道と汽船を介して行われるようになると黒龍江、樺太・沿海州、カムチャッカなど、北洋漁業への転身を図った(道正屋馬場家は除く)。 (越後) 越後鬼舞(現糸魚川市)の「鞍屋伊藤家」は江戸期から北前船を営むとともに幕末から土地集積を進め、近代期には西頸城郡最大の地主となり、手作農場も有した。伊藤家の廻船経営は、越後米の取り扱いに力点がおかれ、飯米需要の拡大に応じ、江戸後期には畿内諸港へ、北海道開拓が進んだ明治に入ると北海道諸港へ販売した。地元移入品としては北海道の昆布、瀬戸内・畿内の塩・砂糖・蝋・綿があった。北陸北前船に典型的な西廻り航路を1年1往復するする船のほか越後と北海道を複数回往復する船を多く有していた。綿作地帯と異なって地元米作地帯の魚肥需要が大きくなかったこともあって北海道産魚肥取引への参入は1880年代以降と一般の北前船に遅れ、本格参入後も経営にしめるシェアはそれほど大きくなかった(中西2009)。
(陸奥-青森県) 東北地方で買積船の経営を行い富を蓄積した船主も航路・輸送形態としては北前船主と見なすことができる。下北半島の付け根に位置する野辺地の「野村屋治三郎家」は18世紀末から問屋業のかたわら和船を所有しはじめ、19世紀中から末まで大規模な買積経営を行った。北陸の船主と異なり、登り荷(地元産大豆・魚肥)もさることながら、下り荷として、畿内で仕入れた木綿類の地元での販売に力点があった。幕末開港後、輸入綿糸・綿製品が拡大する中で、廻船業は1893年、問屋業は1890年代に撤退した。その後は、従来からの酒造業とともに、商業的蓄積を土地取得に向けて地主経営、牧場経営を大規模に行い(サラブレッド育成、1901年時点の所有馬104頭)、また銀行と電力会社に積極的に投資した(中西2009)。
(武蔵) 江戸系商人として東京にカウントされている「栖原角兵衛」は初代(17世紀)が紀州栖原地方湯浅出身で房総の天羽郡萩生に移住し漁場を開き、後代は江戸で材木問屋を営み、その関係で下北半島大畑を経て、1785年に松前城下に材木問屋と海産物問屋を兼ね出店。松前藩御用金引き受けとともに北海道場所請負に進出、手船を所有して北海道産物を運び、江戸や大阪の自店を通じて販売した。1799~1822年に幕府が蝦夷地を直轄した時期には幕府の「箱館産物会所」用達に任命され、1810年には樺太漁場を伊達林右衛門と共同で開き、1841年から択捉場所も両家で共同請負するに至り、明治維新後の場所請負制廃止まで続く。1875年の樺太・千島交換条約で樺太漁場を失い、1882年にかけて西洋型帆船6隻を購入し近代化を図ったが、85年経営危機に陥り、融資を受けていた三井物産会社と北海道海産物の委託販売契約を結んだ。1895年には北海道における漁業の多くを三井物産会社に移譲(HP検索情報、中西聡2013)。
奥州伊達郡(福島県)出身の「伊達林右衛門」は1788年に蝦夷地に渡り、場所請負人となり、漁業とともに手船数隻を所有し、江戸との間を行商した。代々、栖原家とともに北海道開発に当たったが、維新後、家運衰退に直面した5代は漁場を栖原家に譲渡し撤退した(HP検索情報)。 (近世から近代にかけての全体傾向) 北陸の船主の中には、近世より近代に拡大した船主と近世期に活躍し、近代期に入って撤退する船主とがいた。「越前国では河野浦の右近・中村家が20世紀まで海運経営を継続し、近世後期よりも近代期に経営規模が拡大したが、三国湊の有力北前船船主はいずれも幕末か1880年代までに海運業から撤退しており、右近・中村家とは正反対の経営展開を遂げた。加賀国でも瀬越・橋立など南部の北前船主は20世紀初頭まで帆船経営を行い、汽船経営へ進出するものも多かったが、本吉・粟ヶ崎など北部の北前船主は1880(明治13)年前後までには海運業から撤退した。越中国でも同様に、近代期に海運業を拡大させた東岩瀬の有力北前船主と1880年代から海運業から撤退した伏木の有力北前船主では正反対の経営展開を遂げた。」(中西2009)
近代以降土地取得を進めて地主経営に展開した船主も多い中で、近代に入っても海運や海運関連業を展開していった事例は、「福井県河野、石川県瀬越・橋立の有力北前船主や石川県一の宮の西村家で、これらの家は北海道産物の買積経営という近世来の本業に関連する部門として北海道漁業・日本海海運での活動を重視し、汽船経営や北洋漁業に進出した。それ以外の地域の有力北前船主でも、北海道漁業を近代期の経営の中心においた滋賀県八幡・日枝の西川家・藤野家や東京の栖原家もこのタイプに含められる。」(中西2009) 中西聡(2009)は、従来、国家資本の役割が強調され過ぎていた日本の資本主義の発達において、民間資本の雄たる北前船主たちの富の蓄積の意義を明らかにしようとしている。中西氏の研究の結論をいきなりではあるが紹介すると、「北陸地域の場合、農家自身の兼業志向に加え、北前船船主の兼業志向が、第一次産業・第二次産業・第三次産業のバランスの取れた経済成長を支え、その結果として多様な雇用機会が確保され、それらの所得を加味することで、1920年前後までは大都市との生活水準の格差拡大は押し止められたと思われる。(中略)第二次世界大戦前には、過疎・過密を社会問題化させるほどの一般民衆の生活水準の地域間格差は、まだ生じていなかったと思われる。その点に、工業生産の拡大のみを追い求めるのではなく、北前船主の家業維持と複合経営の志向性に支えられ、米・海産物そして織物などの生産とその流通・売買という第一次・第二次・第三次産業間のバランスの取れた産業構成で生活の豊かさを目指す道の可能性を北陸地方にみてとれる。また、北前船主家の出身であった堀田善衛が述べたように、北陸地域の近代期の文化水準が、必ずしも東京・大阪より劣ったわけでなく、生活の豊かさは、個々の家計収支バランスに加え、文化の問題をも含めて検討する必要がある。」 この点に関しては、明治維新の頃には、北陸が、南関東と肩を並べ、畿内を上回る人口規模だったことも忘れるべきではなかろう(図録7240、図録7242参照)。また、北前船の寄港地に今でも老舗企業が相対的に多いという点も興味深い(図録7465参照)。 ○あとがき 当図録は、「金沢の人がとくに好んでいる食べもの」(図録7805)との関連(何故、金沢では、生鮮魚介類や寿司外食への消費金額が全国トップなのか)、内航海運史への関心、及び私の先祖探索・ルーツ探しを兼ねて作成されたものである。
【参考文献】 1.牧野隆信(1979)「北前船の時代―近世以後の日本海海運史 」教育社歴史新書 2.牧野隆信(1989)「北前船の研究 」法政大学出版局 3.中西聡(2009)「海の富豪の資本主義 -北前船と日本の産業化- 」名古屋大学出版会 4.中西聡(2013)「北前船の近代史―海の豪商たちが遺したもの 」成山堂書店 5.高瀬保(1997)「加賀藩の海運史 」成山堂書店 6.加藤貞仁(2002)「北前船 寄港地と交易の物語 」無明舎出版 7.木越隆三(2001)「銭屋五兵衛と北前船の時代」北國新聞社 8.西村通男 (1964)「海商三代―北前船主西村屋の人びと 」中公新書 *石川県がつくっているHP「北前船」があり、日本各地の北前船とそのゆかりの地を紹介している。 図の北前船の船主家を順にあげると以下である。高田屋嘉兵衛・金兵衛、奥藤研造、高松屋(中西)七平・七太郎、吉屋(山本)治八、因幡屋清三郎、三原屋(堀内)調右衛門、平原平右衛門、山西庄五郎、山家屋(小室)徳蔵、古河嘉太夫、住吉屋(西川)伝右衛門・貞二郎、柏屋(藤野)四郎兵衛、右近権左衛門、中村三之丞、室屋(内田)惣右衛門、戸口屋久四郎、木屋(長谷川)甚右衛門、森田三郎右衛門、糸屋(浜中)八三郎、浜中屋(廣海)二三郎、大家七平、角屋(角谷)甚右衛門・甚太郎、西出孫左衛門、小餅屋(久保)彦助、酒屋(酒谷)長平、桶屋(増田)又右衛門・又七郎、熊田屋(熊田)八郎兵衛、熊田屋(熊田)源次郎・源太郎、紺屋三郎兵衛、銭屋五兵衛、木屋(木谷)藤右衛門、木屋(木谷)治助、佐渡屋(岡部)又三郎、西村屋(西村)忠兵衛・忠左衛門、越中屋吉右衛門、鶴屋(堀田)善右衛門、堀岡屋(堀川)半左衛門、車屋(八阪)半兵衛・金平、一宮屋権右衛門、湊屋(朽木)清次郎、綿屋(宮林)彦九郎、八嶋屋(南嶋)間右衛門・間作、道正屋(馬場)久兵衛・道久、四十物屋(森)仙右衛門・正太郎、宮城彦次郎、鞍屋(伊藤)助右衛門、木南源十郎、野村屋(野村)治三郎、栖原角兵衛、伊達林右衛門。 (2011年11月25・26日収録、12月12・13・15日追補、2013年3月28日高瀬資料により追補、4月12日越中部分高瀬資料により追補、5月1日加藤2002により追補、2015年9月2日、2016年5月18日中西2013、木越隆三2001による加筆、2021年5月1日発酵文化・遊里文化への影響、10月14日山形名物芋煮会の発祥、2022年8月2日にしんの山椒漬け・いもぼう画像、9月4日ニシンの昆布巻き記事、2023年4月1日福山の黒酢事例、9月5日江戸時代の航路図、2024年6月14日すっぽこ)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||