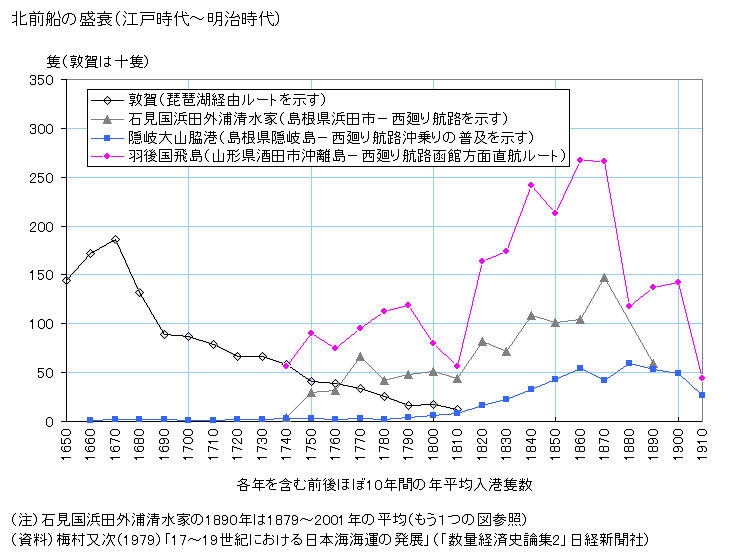
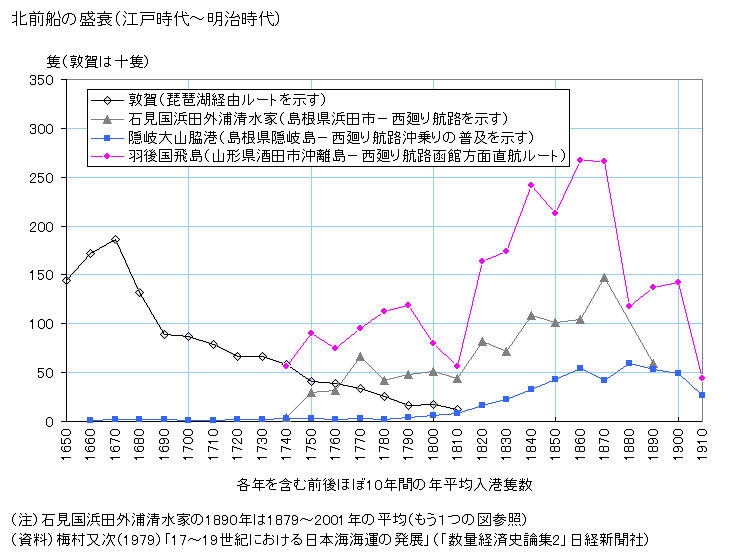
こうした動向を示すのが、船員たちの世話をしたり荷物の取引をしたりする船宿の「御客船帳」記録である。図には、日本海に面した4港、すなわち西の浜田、隠岐、東の飛島(酒田市)、そして中間に位置する敦賀の年平均入港隻数の推移を示している。 一般に、寛文期(1661年〜1672年)以降の西廻り海運の発達により、東北・北陸諸藩の敦賀・琵琶湖経由の藩米回送が相対的に減少していったといわれており、図において1680年前後からの敦賀の入港隻数の減少はこれをあらわしているといえよう。しかし、寛文期には鰊、長崎俵物などの「松前物の入津は逆に増加するという現象を示し、松前物を廻送する松前交易は、一部西廻り航路を利用してはいるが、大部はまだ敦賀経由のコースに依存していた。それというのも、近江商人がこのルートの流通独占を握っていたからであり、その意味では、荷所船というのは、敦賀を経由して上方市場と直結していた商品流通段階での日本海海運のあり方を如実に示しているといえよう。」(柚木学1986) 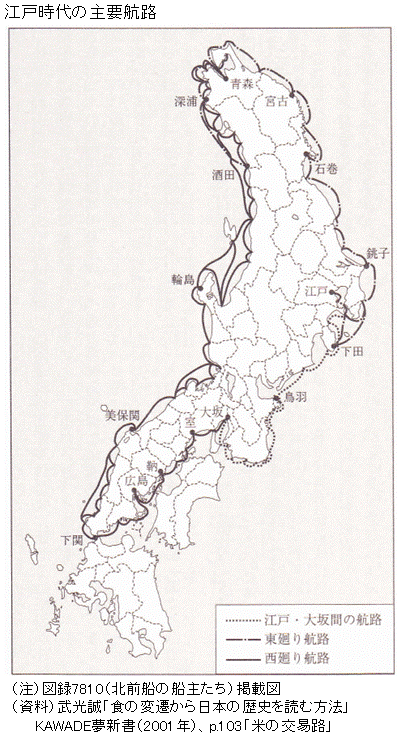 ここで荷所船(にどこぶね)とは北海道の場所請負を行う近江商人団が共同で雇った加賀の橋立、越前河野、敦賀などの運賃積み廻船を指す(手船という自社船で運んでいたのはごく一部の有力近江商人のみ)。荷所とは敦賀の荷物扱所のことであり、敦賀の問屋が近江商人(荷主)と荷所船船主との間に立って廻船の仕立てや積荷の売買を司った。 敦賀着の運賃積みの荷所船に代わって西廻り航路の買積みの北前船の時代に何時入ったかのメルクマールについては、北海道の松前藩の代々の藩主の墓所の石廟が越前(福井)産の「笏谷石(しゃくだにいし)」から瀬戸内産の「花崗岩(御影石)」に代わった明和から安永にかけて(1772年が区切り年)とする見方がある。北海道への下り航路では運航を安定させる重しとして石材を積んだが西廻り航路が主流となって石材が福井産から瀬戸内産に変更されたので墓所の石材の産地も変化したと考えるわけである(加藤貞仁2003が紹介した牧野「北前船の研究」の説)。確かにこの時期に図においても敦賀経由からそれ以外に転換が起こっているようである。 北前船の時代の開始を告げるメルクマールについては、もう少し大きな地域経済構造の変化に求めることもできる。 稼ぎの大きな北前船を表現するのに「一航海千両」といわれるが、利益の多くは松前からの上り荷によるものだった。中でもドル箱商品は鰊肥料であった。北前船は種々様々な交易品を北海道と大阪の間、また西廻り航路沿岸地域相互に輸送したが、利益の大きい輸送があったから、その他の輸送もペイしたという側面が大きい。例えば、上記のように北前船は石材を下り荷として運んだが、これは下り航路では荷物が少なく、石材を船を安定させるバラストとして積み込んだためである。当時、魚肥は農産物の収穫を倍増させる効果を持つ商品であり、日本全国の農業生産力を維持するのに不可欠の存在だった。そのため、これを運ぶ北前船にも大きな利益を安定的にもたらすことができたのである。 西日本からはじまって東日本まで魚肥などを使った多肥農業の形成が進む中で、関東産干鰯(ほしか)の近畿向け出荷が関東・東海農村の需要増との競合で1724年、34年、43年にそれぞれ130万俵、50万俵、12万俵と激減したのを受け、これに代わるものとして、低価格の北海道の鰊肥料が近畿向け出荷の中心にのし上がっていったが(荒居1988、図録7812参照)、この点に北前船の時代の幕開けを求めることが可能である。18世紀末に北海道に広く広がった漁場から松前、江差、函館という出荷拠点まで鰊を運ぶのに大船が許可され鰊肥料の大量生産・大量輸送のシステムが完成した(加藤2003)。この時点をもって北前船の時代への本格移行と位置づけることができよう。 反対に、北前船の凋落も上り荷の鰊肥料が儲からなくなったことから生じたと考えられる。日本の肥料使用は、明治の初年までは魚肥中心であったが、中期以後はダイズかすが登場してきて魚肥とともに肥料の中心となり、末期からはさらに化学肥料が用いられるようになってきて、魚肥は中心ではなくなった(大豆粕・化学肥料は輸入で急増)。また、同時に、瀬戸内地方の綿・藍作は、輸入品との競争で衰えていったため、一大供給先が失われた。商品作物の中心は綿から輸出向けの養蚕にシフトし、肥料需要も西日本から東日本へ重点が移ったのである。海運から鉄道輸送への転換とともに、こうした肥料需給構造の変化がドル箱商品を失わせ、これが北前船の終焉をつげたといえる。 北前船は、鰊肥料とともに起こり、鰊肥料とともに衰えたともいえる。ニシンの漁獲量は低下傾向にあったが、むしろ、他の肥料や他の輸送手段との競合もあり、魚肥が利益の中心とはならなくなったものと考えられる。
【参考文献】 ・柚木学(1986)「近世日本海海運の発達と北前船」(柚木学編「日本海水上交通史」) ・牧野隆信(1989)「北前船の研究 」 ・加藤貞仁(2003)「海の総合商社 北前船」 ・荒居英次(1988)「近世の物資流通と海産物」(「近世海産物経済史の研究 」) ・高瀬保(1997)「加賀藩の海運史 」 (2013年4月10日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||