





さらに、1970年代にまでさかのぼると北陸・近畿が最も多いが、次に多い地域は日本海側全域にわたっており、関東、四国など太平洋側は少なかったことが分かる。かつて「東京では昆布は売れない」が定説だった点については、樋口直哉「“消えゆく業界”から海外シェフ注目の食材へ 日本の食文化を守る「幻の昆布問屋」」(ダイヤモンド・オンライン連載第16回) つまり、昆布は、もともとは北陸・近畿に消費の中心があったのであるが、納豆などと同様に(納豆の場合は東から西へであるが)食の全国平準化が進んで関東でもよく消費されるようになったのである。昆布消費の県庁所在市上位5位に対する下位5位の消費額平均の倍率は1973~80年平均では2.8倍であるのに対して2010~15年平均では2.2倍に低下しており、平準化が進んでいることが分かる。 また、3つ目の図には「こんぶ」と「こんぶつくだ煮」の消費額を散布図であらわしたが、おおむね両者は比例しているなかで、富山は「こんぶ」消費が特段多く、那覇は「こんぶつくだ煮」消費が特段少ない点が目立っている。実は、昆布をだしに使うかやだしに使った後、つくだ煮にするかなど消費法にも地域性がある。 昆布は北海道に特有の産物なのに産地では消費が多くなく、むしろ、北海道から離れた北陸・関西圏に消費の中心があり、日本海側のほうが太平洋側より消費が多かったのは何故であろうか。また、昆布の利用方法に地域性があるのは何故だろうか。これらの点を理解するには、昆布が食材として全国に普及していく長い歴史を振り返ってみる必要がある。 1970年代の家計調査による昆布消費と昆布の産地や輸送の発達史を関係づけてトータルな構図を明らかにした研究が北海道大学の昆布博士と呼ぶべき大石圭一によって行われた。これを要約すると、北陸・近畿で最も消費量が多く、次にそれ以外の日本海沿岸一帯が続き、関東など太平洋岸は概して消費量が少ないという昆布消費の分布が見られるが、これは、4段階に分かれ生産量が10倍づつスケールアップしていった北海道における昆布産地の拡大と本土への供給エリアの拡大に対応している(大石圭一(1987)「昆布の道 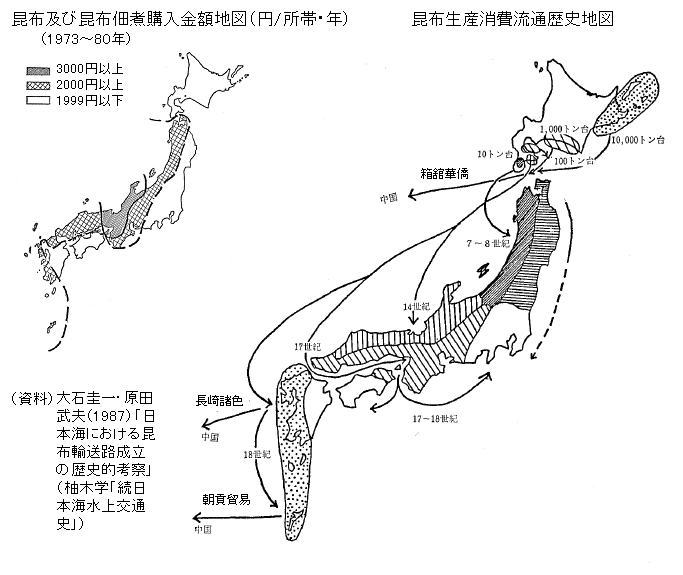
昆布の生産・消費拡大の四段階は次の通りである。
第一段階は、奈良・平安の時代、第二段階は鎌倉・室町時代である。供給エリアが大阪まで広がった第三段階は、1639年の加賀藩による藩米の西廻り廻漕からである。北前船で大量の昆布が集まった「京・大阪を中心に、室町時代末から江戸時代の高級料理にコンブだしが使用されるようになり、上方料理のコンブだし、江戸料理のカツオだしといわれた」(石毛直道「日本の食文化史」岩波書店、2015年、p.254)。中国まで輸出できるようになった第四段階は1799年の高田屋嘉兵衛によるエトロフ航路開拓からである。そして、生産量は各段階ごとに、それぞれ、10トン台、100トン台、1000トン台、10000トン台と拡大していった。 国内は第三~第四段階で大体普及し、食文化的にも、ダシ、とろろ昆布、昆布佃煮と成熟し現代のかたちになった。北陸は、北海道から昆布を運ぶ北前船の根拠地であり、昆布の使い方をいろいろ開発した中心地となった関西食文化の影響も受け、かつ関西より安く昆布を得られたことから消費が最大となったと見られる。 「クーブイリチー」など沖縄料理はだし利用というより直接の大量の昆布食が特徴である。「肉食が禁じられなかったので、だしは豚肉や鰹節でひき、コンブを利用するのは、一般的ではなかった」(石毛、前掲書、p.255)。かつては沖縄女性の黒髪が美しいのはヨード分の多い昆布をよく食べるからだと言われていた(週刊朝日百科「世界の食べもの」no.97-郷土の料理⑰沖縄、1982年10月、p.10-185)。これは、江戸時代に道東昆布が中国にまでに輸出(密輸出)される第四段階に沖縄が中国輸出の中継基地となっていたからなのである(江戸期の昆布輸出については図録0669参照)。現在の家計調査で沖縄の昆布消費はそれほど目立たないが、こんぶのつくだ煮の消費が少ない点には、第三段階ではなく、第四段階の昆布消費の特徴があらわれている。 富山の昆布消費が特段に多いのが越中人の昆布漁進出によるものだという点については図録7806参照。 江戸時代には、現代ににまで引き継がれている昆布を使った定番おかずが登場していた点については図録0260のコラム参照。 最後に、参考までに、こんぶ、煮干、かつお節のうちどの出汁の消費量が多いかを新旧にわたって分析した図録7238jから消費額から見た好きな出汁の分布図を再掲した。 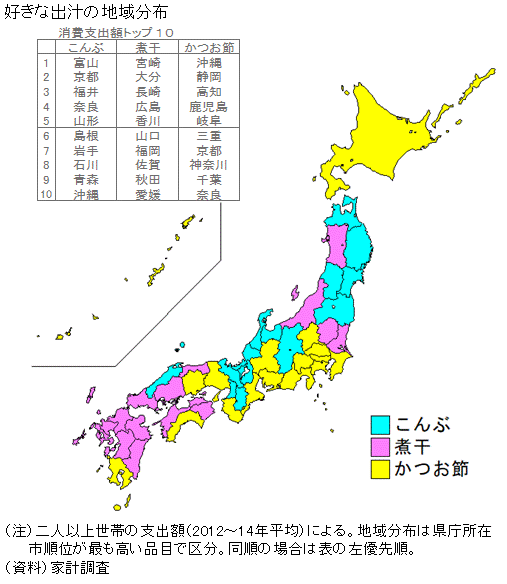 (2016年5月2日収録、2023年5月22日好きな出汁の分布図再掲)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||