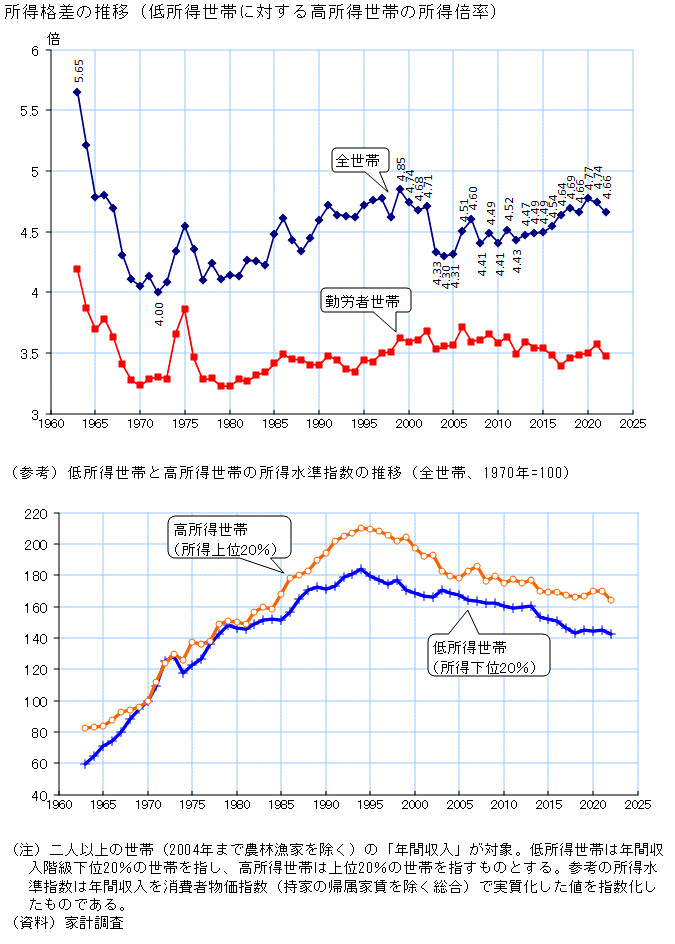
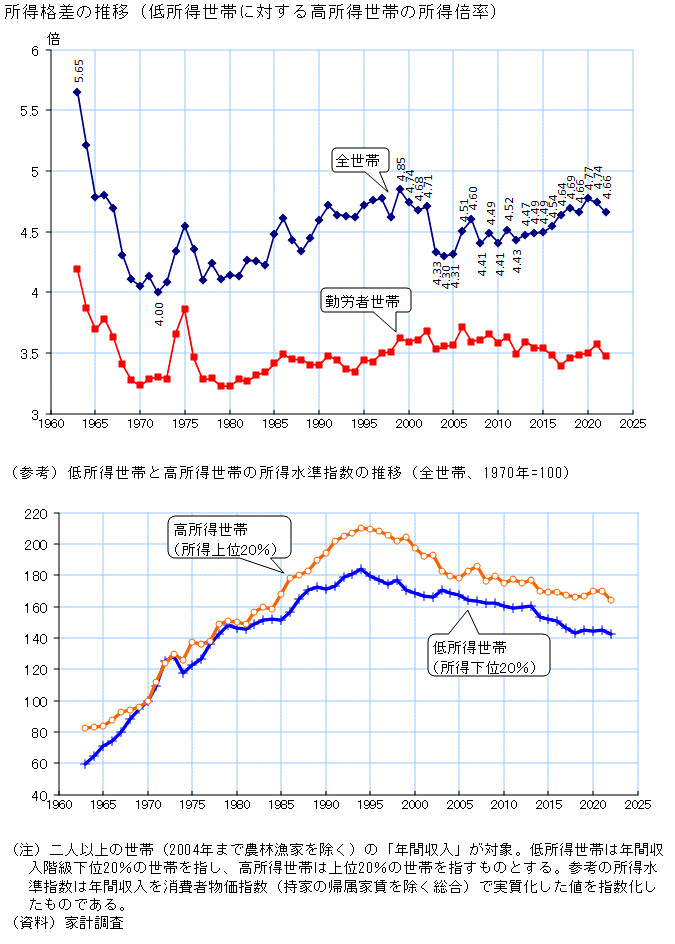
| �@ | �@ | ||||||||||||||||||
|
�@2006�N�̒ʏ퍑��ł́A���C�u�h�A�̖x�]�M���В��i�z���G�����j�̑ߕ߂Ȃǂ����������ɂ��āA�����i2001�N4���`2006�N9���j�̍\�����v����ɂ���āA�Љ�i�����L������邱�Ƃ��A����_��̂P�̃e�[�}�ɂȂ�A���{�����̒ʏ퍑��ł��i�����͑傫�ȃe�[�}�ƂȂ����B�����A��}�̔ᔻ�ɑ��āA����́A�q�σf�[�^�ł́A�����ɂȂ��ē��Ɋi���g��͐i�s���Ă��Ȃ��Ƃ��Ă������A���̌�A���₩�Ȋi���g��͈ȑO����i�݂��邱�Ƃ�F�߁A2��2���ɂ́A�u�i�����o�邱�Ƃ������Ƃ͎v��Ȃ��v�u�����g�A�����g�Ƃ������A�����g�ɍĒ��킷��`�����X������Љ������v�̐i�ޓ��v�Ƃ����_�@�ɓ]�����B �@���ꂩ��10�N�A2015�N�̒ʏ퍑��ł́A�i����_�����u21���I�̎��{�v���{��Ŋ��s�ɔ����t�����X�̃s�P�e�B���������������̂��āA����}�̉��c�V��\��2��16���̑�\����̖`���Łu���i�߂�o�ϐ���u�A�x�m�~�N�X�v�Ɋւ��u�����̉ʎ��������ɕ��z���邩�Ƃ����ϓ_�������Ă���v�Ɗi�������̏d�v����i�����B�́u�i�������e�ł��Ȃ��قNJg�債�Ă���Ƃ����ӎ��ω��͊m�F����Ă��Ȃ��v�Ɣ��_�����v�i�����V��2015.2.17�j�B �@�Љ����f�[�^�}�^�̐��i��A�i���ɂ��Ă̖��N�̋q�σf�[�^���f���Ă����Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��B �Q�D�g�p�f�[�^
�@����܂Ő}�^4650�Łu���E�e���̕n�x�̊i���v�A�}�^4660�Łu�䂪���̏����i���̒������ڂƐ�i���Ԃ̐��ڔ�r�v���������B�O�҂͕x�T�w20���ƕn���w20���̏����Ȃ�������̊i���������A��҂ł́A�i�����Ȋw�I�ɐ��m�Ɏ�����W�j�W����p���Đ�O����̊i���̐��ڂ������Ă���B �@����_��ł��W�j�W�����p����ꂽ���A���m���������邽�߂ɕ�����₷���������Ă���A�i���̎��Ԃɂ��Ă��������ăC���[�W�̔����_����������ʂƂȂ��Ă���B�����ł́A������₷���O�҂̕����A���Ȃ킿�Ꮚ���w20���ƍ������w20���̏����i���̖��N�̃f�[�^���������Ƃɂ���B�Ȃ��y�[�W�����ɏ����i�����ڂɂ����鏊���{���ƃW�j�W���Ƃ̑Δ���f���Ă����B �@���グ�����v�����͉ƌv�����ł���B�ƌv�����͐�O�̎Љ���I�ȓs�s�J���҂̐��v����̌n���ɘA�Ȃ钲���ł���A�ΘJ�Ґ��шȊO�̎��c���т̎����敪�����͍s���Ă��炸�A�܂��_�ы��Ƃ�P�g�҂��܂ނ悤�ɂȂ����͍̂ŋ߂ł���B�������A�N�Ԏ����i�ߋ���N�Ԃ̌��������j�ɂ��Ă͎����K���敪�̏W�v�̂��ߑS���тɕ����Ă���A�������n��f�[�^�������A�܂��l�X���e����ł�����\�����������Ȃ̂ŁA������g�p������̂Ƃ���B �@�P�g���т��܂�ł��Ȃ��f�[�^�Ȃ̂ŁA�P�g�̃j�[�g�E�t���[�^�[�̏�P�g����Ґ��т̏́A���f����Ȃ��_�ɗ��ӂ��Ă����K�v������B �R�D�\�z�O�̏����i������
�@���x�������ɑ傫���k�����������i���́A���̌�A1972�N�̂S�{����1999�N�̂T�{�߂��ւƏ��X�Ɋg�債�Ă������B���c�Ǝ҂�����A��A�Ǝ҂��܂ޑS���т���łȂ��A�ΘJ�Ґ��тɂ��Ă����l�̓����ł���B �@1980�N��㔼�̃o�u���o�ς̎����́A���ɁA�i�����g�債�������ł������B�����Ƃ��A���̎����͋ΘJ�Ґ��т݂̂��݂�Ɗi���͊g�債�Ă��Ȃ��_�ɂ͗��ӂ��K�v�ł���B �@�������������I�Ȋi���g��X���ɔ����āA�J�Ԃ̌����⍑���̊i���ӎ��i�}�^4670�j�Ƃ͗����ɁA����Ȃ��\�����v�A�K���ɘa�̐��i���f����2001�N4���ȍ~�̏������ł́A�ނ���A�����i���͏k���ɓ]���Ă���B����͂ǂ��������Ƃł��낤���B �@�ȏ�A�y�тS�D�ȉ��ł́A�i�����k������2003�N�`05�N�̏�O��ɃR�����g�����Ă���B�Ȃ��A�������̏����i���k���ɂ��Ă͐}�^4667���Q�Ƃ̂��ƁB �i���̌�̐��ځj �@2006�`15�N�ɂ��ẮA�i���͍ēx�g�債���̂��A08�N�`10�N�ɂ͍Ēቺ���A���̌㉡���Ő��ڂ��Ă���B�Ꮚ�����т̏�����������钆�A���������т̏��������A08�N�ɐ��E���Z��@�ōēx�ቺ��������ł���B2013�N�̓A�x�m�~�N�X���ʁi�����㏸�ɂ�鍂�����҂̏����㏸�j�Ŋi�����傫���L���������Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��B2014�N�͏���ő��łɂ�蕨�����㏸�������A�����͂���قǑ����Ȃ��������߁A���������͍������҂��Ꮚ���҂����l�Ɍ��������B2015�N���������҂��Ꮚ���҂����������̓����ł���B �@2016�`18�N�͒Ꮚ���҂̏������ł��Ȃ�i�����g�債���B �@�R���i�N�ƂȂ���2020�N�ł͍������҂̏������Ŋi�����g�債���B �S�D�Ꮚ���w�ƍ������w�̏��������̐���
�@�����i�����g�傷��̂́A�Ꮚ���w�̏����������������āA�������w�̏��������������̏ꍇ������A�Ꮚ���w�̏��������������ō������w�̏������㏸����ꍇ������B�܂��Ꮚ���w�̏���������������A�������w�̏����������オ�������ʂł���ꍇ������B�i�����k������̂́A�����Ƌt�̏��X�̃P�[�X�����肤��B���Ԃ͂ǂ��������̂��낤���B��������邽�߁A�Ꮚ�����тƍ��������т̏��������w�����r�����Q�l�}���쐬�����B �@���x�������̋}���Ȋi���k���́A�������w�̏����㏸���Ꮚ���w�̏����㏸�����}���������߂ł���B���̎����̍H�Ƃ̔��B�ɂ��A�Ꮚ���w���A����I�Ȋ�ƌٗp�ɋz������Ă��������ʂł���ƍl������B���̎�����L�����Ă���l�́A���̎����A�X����n�����l�������Ă��������Ƃ��v���o���ł��낤�B �@1973�N�̃I�C���V���b�N�ȍ~�̎����́A�������w�̏����̐L�т��Ꮚ���w�̏����̐L�т�����A�i�����g�債�Ă������B �@�����āA�o�u��������1990�N�㔼����̒����o�ϒ���̎����ɂ́A�Ꮚ���w�A�������w�Ƃ��ɏ����������ቺ�ɓ]�����B�S���тł͊i���͉����A�ΘJ�Ґ��тł́A���i���g��̏ƂȂ����B �@2000�N��ɓ���ƁA�������w�̏����ቺ�͑��������A�Ꮚ���w�͒ቺ�Ɏ��~�߂�������A��q�̒ʂ�A�i���͂ނ���k�����Ă���B�܂��A�������w�̏����̕ϓ������̎��X�̌o�Ϗ�̉e���������Ă��Ȃ�傫���̂ɑ��ĒᏊ���w�̏����̕ϓ��͂قƂ�ǂȂ��_���ŋߖڗ��悤�ɂȂ��Ă���B����ɂ͒����◿���������u����Ă��Ă��f�t���Ŏ����͏㏸����Ƃ������J�j�Y���̉e�����������ƍl������B2014�N�ɂ͕����������~�܂����̂Ő����u���̏ꍇ�͎����͉�������Ƃ������ԂƂȂ������Ƃ�����B�����㏸�̏ꍇ�A�Ꮚ���҂̏����ቺ�̎��~�߂͂Ȃ��B �T�D�Ꮚ���w�ƍ������w�̎���
�@�����ŁA�Ꮚ���w�ƍ������w�̎��Ԃ��������Ă����Ȃ��ƁA�i���̗����͐[�܂�Ȃ��B���}�ɁA���ю�̔N��ʂ̏����K�w���z���f�����B �@20�Α�ȉ��ł́A�N�Ԏ����K���T�i�����ł͒Ꮚ���w�ƌĂ�ł���j��U�������B30�Α�ł͇V���ł������B40�Α�ł́A�W�������A50�Α�ł͇X�i�������w�Ƃ����ł͌Ă�ł���j�������B�N�������҂��������߂�60�Έȏ�ł́A�ēx�A�T�A�U�A���ɇT���ł������Ȃ�B �@�Ꮚ�����сA���������тƂ����Ă��A���́A�N����d�˂閈�ɏ����������Ȃ郉�C�t�T�C�N���f�������ʂ��傫���̂ł���B2000�N����2015�N�ɂ����Ă̕ω�������ƁA�X�ōł�����50�Α�̊�������܂��Ă���i2000�`04�N�ɍ��������тŊ������ቺ�j�B�N������^�̏������z�̑��ʂ��������Ȃ��Ă��Ă���B�܂��T�ɂ�����70�Έȏ�̊��������ɑ����Ȃ��Ă��Ă���B����͍���ɔ����ω��ł���B �@�Â��́A���V�A�ɂ�����_���w�����Ɋւ��郌�[�j�������ƃ`�����m�t�����̑Η��Ƃ��Ď�����Ă��������ł���B���[�j���́A�_���w�̗�בw�Ƒ�K�͑w�̊i�������{��`�̔��B�ɂ����̂Ƃ��āA�Љ��`�v���_�ɂȂ����B�`�����m�t�́A���̊i���͔_�Ƃ̐���ω��ɂ��Ⴂ�f���Ă�����̂ɉ߂��Ȃ��Ƒ������B���Ƃ�Ƒ���������Ɣ_�n�������邪�A�����ł�����x�_�n���ו������Ƃ����T�C�N�������肵���̂ł���B 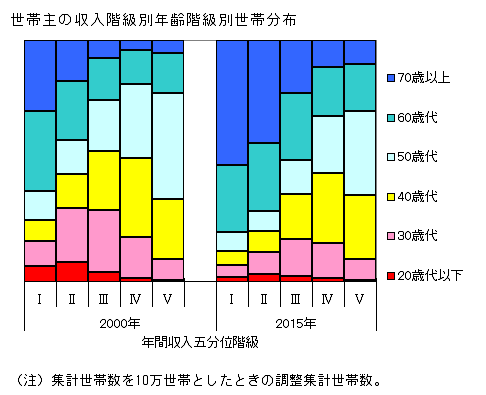 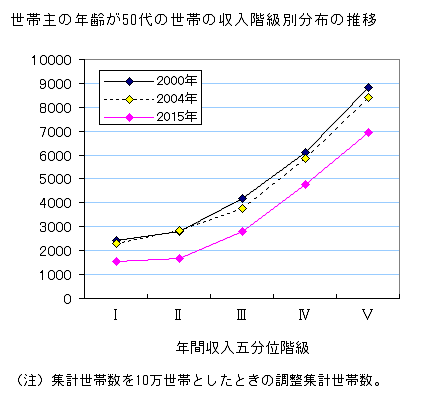 �U�D�i���g�傩��i���k���ւ̓]���̐^��
�@�`�����m�t�I�ȃ��C�t�T�C�N�������ɂ��A�I�C���V���b�N��̒����I�Ȋi���g��́A�Ⴂ����ƒ����N����̏����i���̊g��A���Ȃ킿���{�I�o�c�̔N���������x�̊m���ɂƂ��Ȃ����̂ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���i�}�^3330�Q�Ɓj�B �@�Ƃ��낪�A�o�u�������A���������N���������x�͊�Ǝ��v�̒���̒��Ō�������A�����J�[�u�̃t���b�g�����i�s���Ă���i�}�^3340�j�B1990�N��ɂ͑S�̂Ƃ��ăt���b�g�����i�s�������A2000�N��ɂ͂���Ɠ��ɒ����N40�Α�㔼����50�Α�̃t���b�g�����i�s�����B�ސE�������ɑ呲�z���C�g�J���[�ő傫���팸���ꂽ�i�}�^3328�j�B���X�g���̓����⑁���ސE���x�Ȃǂ����G�ɂ������������𑣐i���Ă���ƍl������B�����N�̎��E���������̂����������Љ�̍\�����v�̒ɂ݂f���Ă�����̂ƌ��Ȃ�����i�}�^2760�Q�Ɓj�B�����N�̑��ΓI�Ȓ��������̈��������́A���R�A�N��\�����������錩������́A�i���̏k���Ɍ��т��B �@�`���̎Q�l�}�ɂ�����Ꮚ�����тƍ��������т̏��������w���̐��ڂ�����ƁA�������ł́A�Ꮚ���w�̏����ቺ�Ɏ��~�߂��������Ă���̂ɁA�������w�̏����ቺ�͂Ȃ������Ă���B�c��̐��オ���X�g���Ώ۔N��ƂȂ������Ƃ��傫���̂ł͂Ȃ����낤���B���X�g���ΏۂɂȂ����҂Ƃ����łȂ��҂Ƃ̏����i���͍L�����Ă��邾�낤���A�����N�ƎႢ����Ƃ̏����i���͂ނ���k�����Ă���A���ꂪ�S�̂̏����i���k���ɂȂ����Ă���ƍl������B �@���ہA���}�ɖ`���̊i�����ڐ}�̑S���т̓����ƍ���������b�����ɂ�鐢�ю�̔N��K���ʏ����i���i�����ł�30�Α㐢�ю��50�Α㐢�ю�̐��я����̊i�������グ�Ă���j�̐��ڂ��r�������A���҂́A���x�������͕ʂɂ��āA����ȍ~�A�傫���́A�p�������ȓ����������Ă���A����2001�N�ȍ~50�Α�̑��Ώ����̒ቺ���ƌv�����ɂ�����2003�N����̏����i���̏k���Ɍ��т��Ă�̂ł͂Ȃ����ƂƂ�铮�������ĂƂ��i�ƌv�����̏����͊e���̉ߋ���N�Ԃ̏����̕��ςȂ̂Ŏ��ۂ͕\���N��蔼�N�ߋ��ɂ���Ă���_�ɂ����Ӂj�B 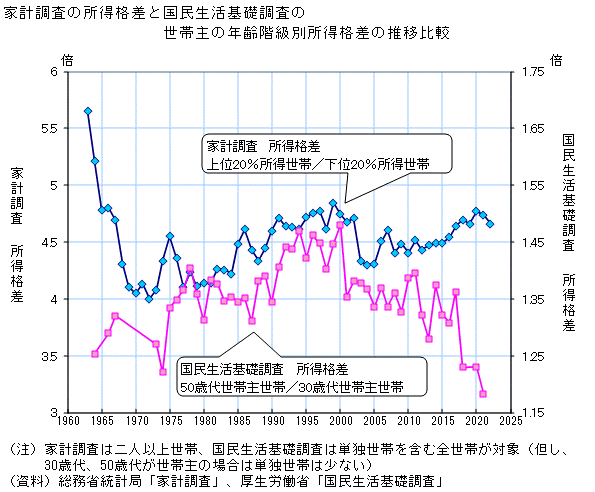 �@����ɁA�Љ�ۏႪ�m�����Ă��钆�ł̍���҂̑������傫�Ȋi���k���̗v���ł���B�ŋ߂̒Ꮚ���w�̏����ቺ�̎��~�߂ɂ́A�Ꮚ���w�̑������߂鍂��N�����т̏����́A�Œ���̈��ȉ��ɂ͉�����Ȃ����i�̂��̂ł���_���傫����^���Ă���ƍl������B�f�t������ɂ͐��x���肪�Ȃ��Ǝ����z���㏸�A�����ی쐢�т̑Ώ۔͈͂��g�傷��X�����������̂ł���i�����ی쐢�тɊւ��Ă͐}�^2950�Q�Ɓj�B�Љ�ۏႪ�Ꮚ�����т̏����ቺ�Ƀ��b�N�������Ă���Ƃ�������B
�@�����Ƃ�2005�N�ȍ~�͏����̔N��i���͏k���X���ł���ɂ�������炸�A�����i���S�̂͏㏸���Ă���A�{���̈Ӗ��ł̎Љ�i�����L�����Ă���\��������B �@�N��\���ɂ�鏊���i���ւ̉e������菜���ď����i���̏����邽�߂ɂ́A�N��w���̏����i���ׂ̏�悢�B�}�^4665�ɁA�ƌv�����̊g��łł���S��������Ԓ����ɂ��N��ʂ̏����i���̐��ڂ��W�j�W�����g���Đ}�������B���_���猾���ƁA�N��w���Ƃ̊i���́A���Ƃ��Ƃ͊i���������������Ⴂ�w�ł́A�g�債�A�i�����傫����������ґw�ł́A�ނ���k�����Ă���B����҂̊i���k���́A�N�����x�̊m�����v�����Ă���Ƃ�����B�Ⴂ�w�ɂ�����i���g��́A�\�͎�`�I�Ȓ������x�A���邢�̓j�[�g�A�t���[�^�[�̊g��Ȃǂ��e�����Ă���ƍl������B�ƌv�����ƈقȂ菊���i���͋ߔN�ł��g�債�Ă���B����́A��Ƃ��āA����͊i���̑傫�ȍ���ґw�̃E�G�C�g���傫���Ȃ��Ă��邩�炾�Ƃ���邱�Ƃ��������N�Ԏ����̎����̍��ł���\��������B �V�D�܂Ƃ�
�@���̂悤�ɋߔN�̏����i���́A�ƌv�����ɂ��A�����ӎ��Ƃ͋t�ɁA�����J�[�u�̃t���b�g����Љ�ۏ�ɂ��Ꮚ���w�̏����ቺ�}���@�\�ɂ���āA�k�����Ă���B�`���Ɉ��p�����悤�ɏ����̐��i���g���ڎw���Ă���Ƃ�����A����͎��s�ɏI����Ă���A���邢�͂��ꂩ����ʂ��������ނ̂��̂ł���ƌ��_�ł��悤�B �@���v�f�[�^�͑�ʊώ@�ɓ���������B�����ӎ��́A�����I�Ȏ�����o�������Ƃ炦�ē����B�����g�╉���g�A�j�[�g�E�t���[�^�[�̑����A��ׂ�����Z�{�q���Y�̓�����ƁA�����ی쐢�т̑����Ȃǂ́A�i���g��Ɍ��т��Љ�ۂł���B�����������ۂɂ���Ċi���g�傪���i����Ă���ʂ����R���肦��B�������A��ʊώ@�̌��ʂ́A�ނ���A�N��ʒ����J�[�u��Љ�ۏ�̏[���Ƃ����������Ƒ傫�ȕω��f���Ă���̂��ƍl�����悤�B�����łӂꂽ�f�[�^�����ł������_�Â���̂́A���v�����m�ꂸ�A���ؓI�Ȍ����Ȃ��K�v�ł��邪�A�������������ł��������ł��Ȃ��f�[�^����X�͎�ɂ��Ă���B �@�������̊i���g��_�̕��r�ɂ��ẮA�������G�R�m�~�X�g�̏������v�吳��w�������A�u�����̌o���v�Ƃ����ǔ��E�g��쑢�܂���܂��A2019�N�̓��{�o�ϐV���u�G�R�m�~�X�g���I�Ԍo�ϐ}���x�X�g10�v��1�ʂƂȂ����o�Ϗ��̒��ŁA���̂悤�ɑ������Ă���i���{�o�ϐV���o�ŎЁA2019�N�Ap.172�`174�j�B �u�i���̊g��́A���v�f�[�^����͊m�F�ł��Ȃ��v�Ƃ����u�o�ϓI�Ȋi���̌���ɂ��Ă̏����Ă������ɂ�������炸�A�����Ƃ��Ă̊i���ӎ����܂łɂ͎��炸�A�u���{�́v�i���Љ�ɂȂ��Ă��܂����v�u���̌����́A�������s�ꌴ���I�ȉ��v��i�߂�����ł���v�Ƃ����c�_�����{�S�̂��悤�ɂȂ����B �@���̊i���Љ�_�Ǝs�ꌴ���ᔻ�́A�����}�ɕs���ɍ�p���A���̌�̖���}�ɂ��I����̏����Ɛ������ɂȂ����Ă����v�B �@�����āA�u����ɂ������̂́v�A���̑I����ɂ����ẮA����}�̐����Ƃ����łȂ������}�̐����Ƃ܂Łu��}���̎s�ꌴ���ᔻ�A�i���ᔻ���ނ������A��}�̎咣�ɕ��݊�낤�Ƃ��Ă����悤�Ɍ�����v�ip.175�j���Ƃ��ƌ����Ă���B �@�����O�f���́A�i���g�傪�������ƍl����ꂽ���R�Ƃ��Ď��̂悤�ȓ_���w�E���Ă���B�����A�����̒����͑S�̂Ƃ��Ēቺ�X�������ǂ��Ă������A�u�����̌����ɒ��ʂ�����ʍ����́A���ꂪ�A�u�S�ʓI�ȏ����̌����v���u���ΓI�Ȋi���̊g��ɂ����̂��v��ł��邾�낤���B�_���\�i�i���g��͌���̐��̎������疾�炩���Ƃ��������̌����}��\�|���p�ҁj�̌����u�����v�ɂ́A���������u�S�ʓI�ȏ��������v���u�i���̊g��ɂ�鎩�����������̏��������v�ƌ�F�����\��������B �@�Ȃ��A���������S�̂Ƃ��Ă̊i���͊g�債�Ă��Ȃ��̂�����A���R�̂��ƂȂ���A�s�ꌴ���I�ȏ�����v�̐i�W�ɂ���Ċi���Љ�ɂȂ����Ƃ����c�_���ے肳���͂��ł���v�ip.173�`174�j�B �@���v�I�Ȏ������d�鏬�͊i���g��̈�ʕ����m�ɔے肵�Ė�ł��邪�A���ł��A�������ɖ{�}�^�̂悤�ɁA�i���͏������ɂނ���k�����Ă���A���̗��R��Nj�����Ƃ����Ƃ���܂ŁA����ɁA�_��i�߂�܂łɂ͎����Ă��Ȃ��̂��c�O���B �@�Ȃ��A�ƌv�����̂悤�ɓ�l�ȏ㐢�тł͂Ȃ��A�P�Ɛ��т��܂ޑS���т��Ώۂł��鍑��������b�����ɂ�鏊���i���̐��ڂ�}�^4664�Ɏ������̂ŎQ�Ƃ̂��ƁB�܂�OECD�ɂ�鑊�ΓI�n�����̐��ڂ�2000�N������2000�N���ɂ����Ēቺ���Ă��蓯���X���𗠂Â��Ă���i�}�^4654�j�B 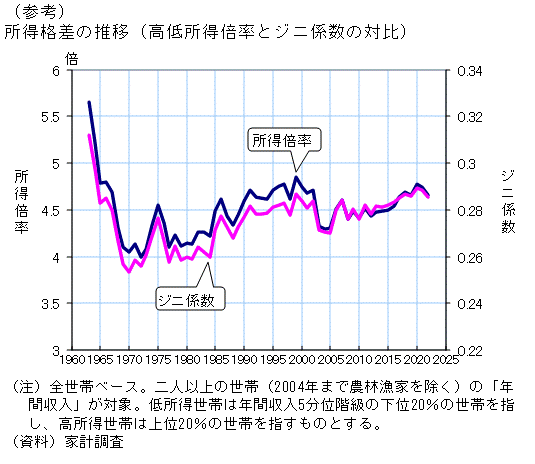 �i2006�N2��2�����^�A2��10��2005�N�f�[�^�lj��A2��22������������b�����f�[�^�A��r�R�����g�lj��A2007�N2��14���E2008�N2��15���X�V�A10��9���ސE���R�����g�lj��A2009�N2��14���X�V�A2010�N2��16���X�V�A2011�N2��15���X�V�A2012�N2��23���X�V�A2013�N2��20���X�V�A2014�N2��18���X�V�A2015�N2��17���X�V�A2016�N2��16���X�V�A5��30�����ѕ��z�}2015�N�lj��A9��27���u�T�D�Ꮚ���w�ƍ������w�̎��ԁv�̐}�����ǁA10��13�������{���ƃW�j�W���̑Δ�}�A2017�N2��20���X�V�A2018�N2��17���X�V�A2019�N2��15���X�V�A2020�N2��7���X�V�A10��17���������v���p�A2021�N10��28���X�V�A2022�N9��30���X�V�A2023�N7��24���X�V�A2025�N4��7���X�V�j
�m �{�}�^�Ɗ֘A����R���e���c �n |
|
||||||||||||||||||