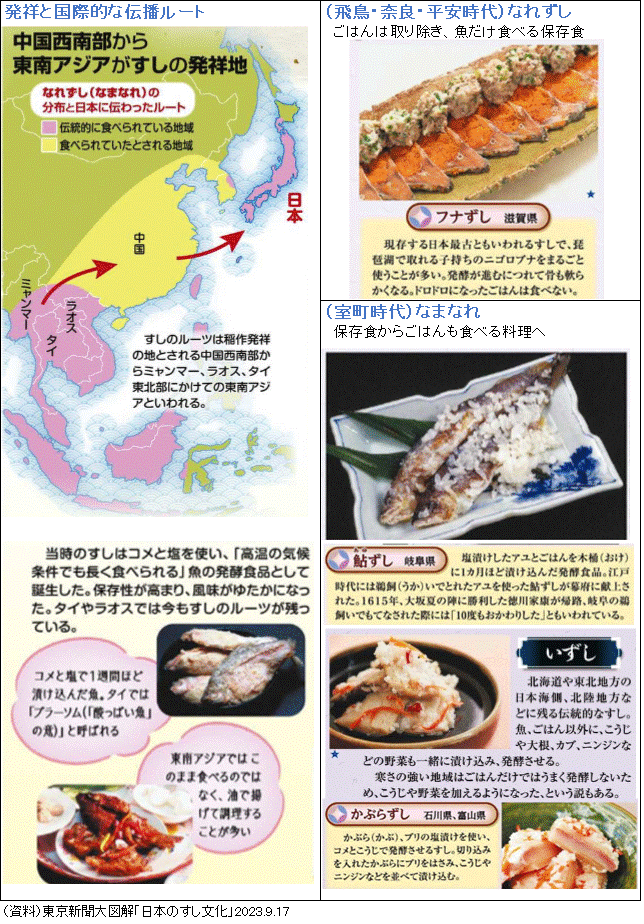
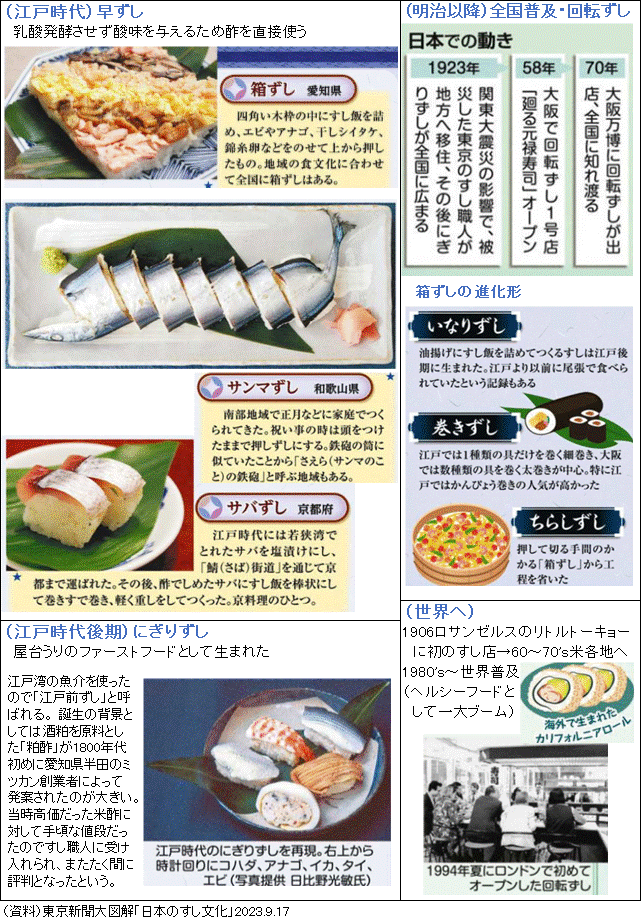
�y�N���b�N�Ő}�\�I���z
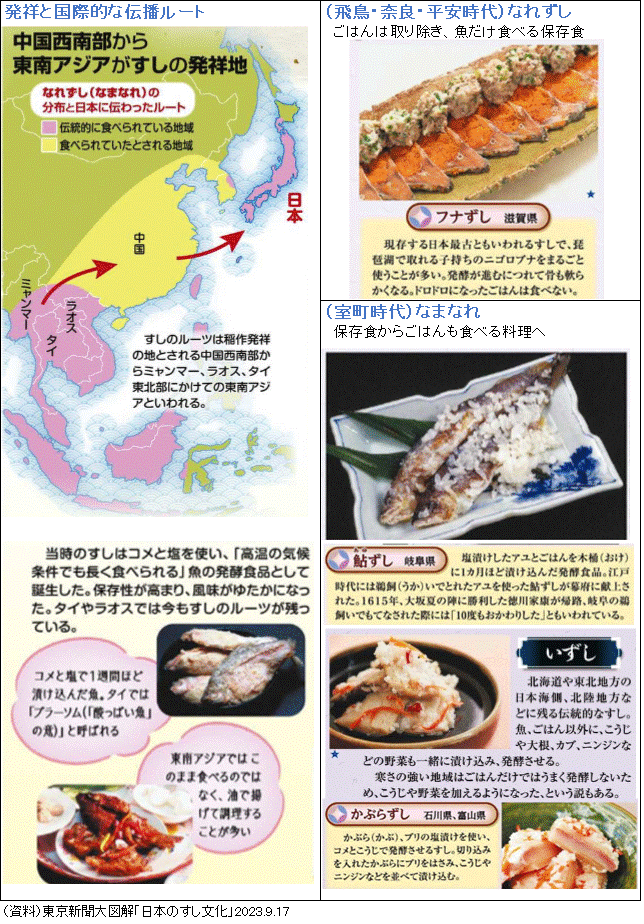 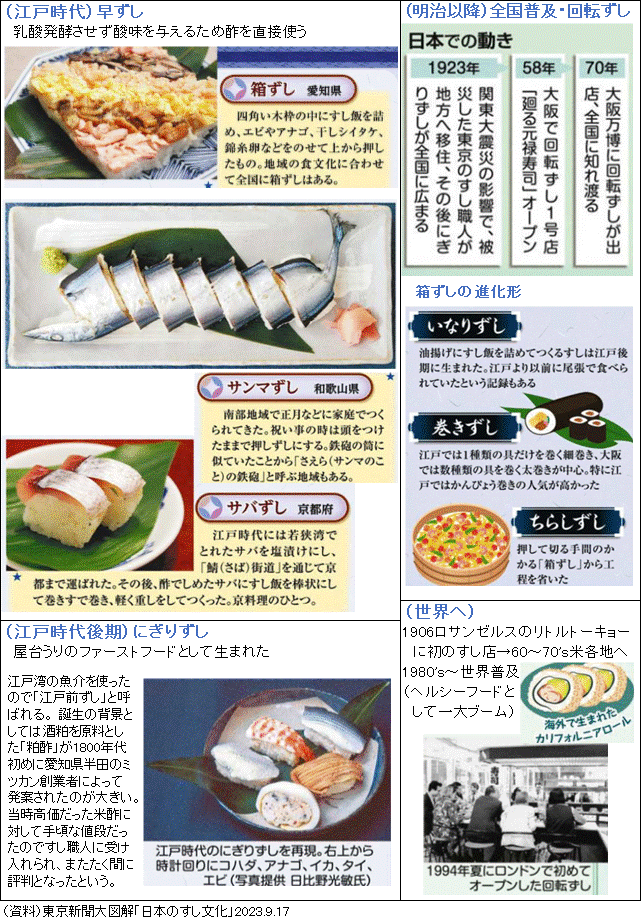 |
| �@ | �@ | |||||||||||||||||||
�@���{�l�̍D���ȗ����̑�1�ʂ͂����i���i�A齁j�ł���i�}�^0332�j�B�܂��ߔN�ł́A���N�u���̂Ђ낪��ɂ���]���i���ӂ��ߐ��E���ɂ����u�[�����L�������i�؍��͐}�^0331�A�A�W�A�͐}�^8035�j�B �@�����ŁA���������̗��j����̓����V����}������̔������p���Q�l�ɊȒP�ɐU��Ԃ��Č��悤�B �@���{�̂����̌��`�́A�W�����Ȃǂ��������ĂƂƂ��ɒ����ԉ��ŒЂ�����œ��_���y�������ۑ��H�i�A�i���Y�V�ł���A����A�W�A�⒆������`���A���{�Ɍ×���葶�݂��Ă���B����Ɏc���Ă���i���Y�V�Ƃ��Ă͔��i�ΌΔȂ́u�ߍ]�̃t�i�����v���L���ł���B���̏ꍇ�A���y���r�`���r�`���ɂȂ����Ĕѕ����͎̂Ăċ������������H�ׂ�B �@�����̋N���͕ۑ��p�̉������ɂ�������A�W�A�̓������ŋG�ߓI�ɉ�������싛���R���̂ł�Ղ�̓��_���y�𗘗p���ĕۑ��������Ƃɂ��ƍl������i�c��1975�Ap.185�`186�j�B �@�^�C�ł́A2011�N�A7������㗬�ō~�葱������J�ɂ��^���ɂ��A��s���Ƃ�܂��L���͈͂Ŋ������A10���ɓ����āA�����ԁE�d�@���[�J�[�ȂǓ��n��Ƃ��������ő��ƒ�~�ɒǂ����܂ꂽ�B����A�W�A�ł́A��N�A�J�����犣���ւ̕ς��ځi�^�C�ł�10���j�͉J�����̉J�ɂ��^���̃V�[�Y���ł���A����̔�Ђ͍^���̒��x���傫�������ɉ߂��Ȃ��B�^�C�ɂ́u�����Ђ��A��������H�ׁA�^���̎��͋����A����H�ׂ�v�Ƃ������Ƃ킴�������i���j�B���E�̒��œ���A�W�A�ʼnJ�����犣���ɂ����đ�ʂɕߊl�����W�����̕ۑ����@�Ƃ��ċ��݂ƂƂ��Ƀi���Y�V�����������ƍl������B �i���j���̂��Ƃ킴���{���ɐl�����Y�t���Ă��邩�����^�C�ݏZ�̏��Ѓ}���������F�l�ɗ���Œm�荇���̃^�C�l�ɐq�˂Ă�������Ƃ���m���Ă���l������Βm��Ȃ��l������Ƃ����������B�^�C�ł��R���i�̉e�����[�������A�ό��s�U�Ŏ��Ƃ������Ă���`�F���}�C�ݏZ�̓��{�l�o�Ƒm�ɂ��A�^�C�l�̊Ԃł͌o�ς������ƗD�悳���悤�Ƃ������͂����ꂸ�A�ނ���u�c�ɂɋA��J�I�j���I�ƃi���v���[���炢�͂��邩��v�ƌ����Č��N��D�悳�������������l�����𑗂��Ă���Ƃ����B�����̒��ł����݁i�i���v���[�j�ɐe����ł��邱�Ƃ�������B�Ȃ��J�I�j���I�͌��n�̂����Ă̂��Ɓi���t�[�j���[�X2021.2.22�j�B �u���݂̌����͒W���ɐ������鏬���ł��邱�Ƃ������B���̂��鏬�������̂܂ܗ����ŐH�ׂ邱�Ƃ͏��Ȃ��B���̋������Q����鎞���ɏW�����ċ����s����B��ʂɕ߂ꂽ������ۑ����A�N�Ԃ�ʂ��ĐH�ׂ邽�߂ɉ��H�������̂����h�⋛�݂Ȃ̂ł���B���̋��l�̎����̓A�W�A�̋C�ی��ۂł��郂���X�[���̉e�����Ă����B�����X�[���Ɩ��ڂɊW����_�ƌ`�ԂƂ����ΐ��c���ł���B����A�W�A�̑嗤���ł͉J���ɑ��������͐삩�琅�����ӂ�Đ��c�ɗ��ꍞ�݁A�����ŋ������B����B����u���c���Ɓv�Ƃł������ׂ����ƌ`�Ԃ��������Ă���̂ł���B�ĔтƋ��Ɖ��ō����i���Y�V�����݂��A���c���Ƃ̂Ȃ��Ŕ��W���Ă������ƍl������B���{�̌Ñ�ł��i���Y�V�ɂ͒W�������p�����Ă����B����ƁA���Ȃ��Ƃ��i���Y�V�͐��c���ɔ����ē`�d�����\��������v�i�Ζђ���2017�j�B �@��������ɂ́A�i���Y�V�ł͐H�ׂȂ������т�H�ׂ���̂ɂ����i�}�i���i�����j�Ƃ����������������ꂽ�B�A���A�E�i�M�A�R�C�Ȃǂ̋���^�P�m�R�Ȃǂ̖��тƉ������g���Z���Ԃ̔��y�Ŏ_����тт������H�i�ł���B�u�͂��߂͕����������������́A�싛�̐����Ő��L�݂��悷���邽�߂��A�I�����S�ɂ����v�i�c1970a�j�B�ዷ�Ƌ��s�����ԎI�X���A�F���ƓޗǓ암�����ԓ��F��X����ʂ��ĉ��I���^��A���I�̗��p�@�̂ЂƂƂ��Ă̐����������o�āA���s�̎I�����A�ޗǂ̂��Ζ_���i�A�`�̗t���i�Ƃ����������������̒a���ɂȂ������B �@����ɉ��Ђ���������A���邢�͎��������邱�Ƃɂ���āA���y�𑁂߂����nj^�̃i���Y�V�����܂ꂽ�B�k�C������k�����{�C���ɂ����ẴC�Y�V�i�H�c�̃n�^�n�^�����A�k���̃J�u�������j�����̂P�ł���B �@�����āA�]�ˎ���ɂ͂���ƁA�|��тɂ��Ă鑦�ȃY�V���J������A�����͎ד��Ƃ���Ă������A18���I�ȍ~�A�]�˂��痬�s���A���Y�V�̎嗬�ƂȂ�B�|�тɋl�߁A���̏�ɂ�����̋��L���̂��A�����Ԃ������ďォ�炨�����������Đ����ԉ����Ƃ����������i���������j���l�Ă���A��������ƂȂ����B�܂��A�]�˒����ɂ͍]�ˑO�̋������d����A19���I�͂��߂ɂ́A�i���Y�V�A�����������t�@�[�X�g�t�[�h�������H�i�Ƃ��āA�|�тɎh�g���̂������肸�����o�ꂵ���B����ł��A�ŏ��͋���ނ͂����Ɉ����Ȃ�̂ŁA�ݖ��Ђ��̂����˂����g���Ă����Ƃ�����B �@�]�ˎ���̈��肸���́A���������������ƘH��̉���X�̗����ŏ����Ă����B����ł́A���炩���߂����������ĕ��ׂĂ����q�͂�������I��ōD���Ȃ�����H�ׂ��炵���B�����ė����^�������͉���u�[����������X���ɉ���X�y�[�X������A����̃J�E���^�[�����̂������ւƔ��W�����Ƃ����B��]���i�́A���肸�����ˎ��̉�������̌���I�Č����Ƃ�����i�����1999�j�B �@�����̕������ł���u���攍e�v�i1853�i�Éi6�j�N�A1867�i�c��3�j�N�܂ł̒NjL����j�ɂ��A�]�˂œo�ꂵ�����肸���͍]�˂ł͋��㕗�̔��̉����������쒀���A�]�˂̈��肸���A����̔������Ƃ����p�^�[�������������B���Â��������Ŏ��̂悤�ɈقȂ��Ă����Ƃ����B�u�����齐|����������ǂƂ��B�ߔN�A�]�˂̐��|���͂Ȃ͂��W���B齂̖{�ӂ������B�v�i��c����1853�Ap.295�j�Ȃ��A�����̋���ƍ]�˂�齂̑Δ�ɂ��Ắy�R�����z�Q�ƁB �@�]�ˎ���ȍ~�A�S���e�n�ŁA�i�}�i���̊e����nj^�ɉ����A���������i�֓��̃m�������A���̑������j�A�_�����i���s�̃T�o�����j�A���炵�����A���Ȃ���i�i���É��N�����ʐ��j�ȂǑ��푽�l�Ȏ��i���V���ɊJ������钆�A��{�I�ɂ́A��������吳�ɂ����āu�֓��̈��肸���A���̔������v�Ƃ����������Ă����Ƃ�����B �@�����Ƃ����A�����̂悳�����̂��̈��肸���A���邢�͈��肸���𒆐S�Ƃ���]�ˑO���i�Ƃ����l�������H�ɂ��邳�������l�Ȃǂ̔����������ĕ��y���Ă������B�H�ʕ����l�̑�\�i�ł���D�R�l�i1952�`53�j�͂��������Ă���B�u�]�ˑO���i�̏�����i�ƈقȂ�Ƃ���́A�ޗ��A��������ыZ�@�̑���ɂ���B����͂����܂ł��Ȃ����A�܂����͐��C�̂���Ȃ��ł���B�]�ˑO���i�͊ȒP�ŁA���������Ȓ����@��p���A���q�̖ڂ̑O�Ő����̂����Ƃ�����݂��A���S�����Ȃ���H�ׂ�Ƃ���ɓ��F������B����ɁA�܂���̎��b�������Ԃ�Z���ł���Ȃ���A����������Ɏc��ʂƂ��������������āA�܂��ɓ��������Ƃ��ċя�Ԃ�Y���Ă���B���̂��닞�㗬�����i�́A����̉����̒n���ɂ��͂���Ă��邪�A�Ȃ���i����Ƃ��钲���ɈӋC�̂Ȃ������������A�����ɐ�����]�˃b�q�ɂ́A�Ƃ�ƌ}������l�q���Ȃ��B�킽�����͓��R�̂��ƂƁA�������b�����v��Ȃ��B�i�����j�Ȃɂ͂Ƃ�����A���̔����i������Ɉ��|���ꂽ�̂́A���i�H���̏����ŁA���i���̕����ł���B�v �@�����͂��Ƃ��Ƃ͕ۑ��H�i�������̂ŁA�������i���肸���̊O�H�X�j�ł����Ă��A���������ٓ��̐��_�������p���ł����B�����]�ˋ��u�g��齁v��l�g���f�Y�i�܂����j�ɂ��A�u�����́A���Ƃ����肸���ł��A���鎞�Ԃ��K�v���B���邻����H�ׂĂ����͉̂���X�̂��ƂŁA�ꌬ�̓X�����ȏ�A�o�O�Ŕz�B���čs�����A���傤�ǂ��̂Ƃ��ɂ��܂��Ȃ�������Ȃ��B���̂���̂悤�ɁA�����ƈꌬ�̓X�����܂��Ă��Ȃ���A���邻����H�ׂ�i���ĕ��́A�吳�\��N�̓�����k�ЈȌ�̘b���B����ʼn���X���Ȃ��Ȃ��āA�ꌬ�̓X�����܂����̂͂悢���A����X�̕��܂œX�ɂ�����������̂��B�i�����j�v�ۓc�����Y�������̐ԊL���̂ǂɂ߂Ď��R�B�̂͂���ȔS����͕̂K���|�i�������������j�ŃT�b�Ɛ�������̂����A�߂���͐V�N�����ɂ������āA���̎葱�������Ȃ�����A����Ȕߌ���������B�v�i�c1970�j �@���̃R�[���h�`�F�[���̔��B�ɂ�萶�C���V�܂ł������i�l�^�ƂȂ��ł���A�ۑ��H�i�ł���Ȃ���ۑ��H�i��E�����H�������߂�̂����{�ɂ����邷���̖{���ł���Ƃ���Ύ��X�Ȃ܂łɋ��ɂ̎p��Nj����Ă���Ƃ�����B �@�����i1999�j�́A�������������̗��j�����A�т�H�ׂ�i�}�i�����u�����̑��v���v�A�|�̎g�p�ɂ�鑁�Y�V���u�����̑��v���v�A�����āA�e�n�ɍ��Â����X�V�����ɑ��鈬�肸���̑S���W�J���u�����̑�O�v���v�ƌĂ�ł���B���肸���̑S���W�J�́A�@�������{�ɂ�铌�������̐����A�A�֓���k�Ђ��Ђɂ�邷���E�l�̒n�����o�A�B���肸���݂̂����O�Ƃ������H�Ɖc�Ƌ֎~�i1947�N���H�c�Ƌً}�[�u�߁j��ʂ��Đi��ł������Ƃ����B �@�����̔��˒n�ł��铌��A�W�A�ł͂����̌Ì`�����낤���ĕۂ���Ă��邪�A�`�d�̌o�R�n�ł��钆���ł͂����͖ł�ł��܂����B����ł́A���́A�Ō�ɍs�����������{�����ŁA�������������̂悤�ɑ��ʂȔ��W�𐋂����̂ł��낤���B �@�ЂƂ̗v���́A���{�́A�����ł��邱�Ƃ���傫���ϑJ���Ƃ���嗤�����������I�Ɏ����K�v���Ȃ��A���̂��߁A�Ñ�̏K���╶�������ɓ`���Ă���H�L�ȍ�������ł���i�}�^0214�́i�U�j�Q�Ɓj�B �@�����P�̗v���́A���H��������������������ł���B�u�@����̗��R�v������H������Ă������{�l�́A���̌��ʂ̐H�����̖��C�Ȃ������Ƃ��������邽�߁A���ܖ��������炷�悤�ȐH�ނ̍H�v�┭�y�̊��p�ɂ���Ęa�H�ƌĂ��Ɠ��̗����̌n�����Ԃ������ĂȂ�Ƃ��J�������B�����͂��̑�\��Ƃ������ׂ��H�i�Ȃ̂ł���B �@�a�H�̊�b�ƂȂ��Ă��邾���i�o�`�j���́A�������R�Ŕ��B�������̂ł��邪�A�������������p�����J���[��[�����������ȍ~�̊O���H�i�ɂ�������炸�A�V�������{�H�Ƃ��Ĕ��B���A���E����]�������悤�ɂȂ����̂��A�]�ˎ���܂łɔ|��������H�����̒~�ς������Ă��邩�炾�ƍl������i�}�^0332�A�}�^0208�Q�Ɓj�B �@���{�l�͒������Ԃ������������������g�݂̌��ʂƂ��āA���܂��܁A���N�⓮������A�����Ċ��ɗǂ��H�����������ł����킯�ł��邪�A���ꂪ�����ɂȂ��ē��H�Ȃ��邱�ƂƂȂ������Ă𒆐S�ɁA���E���œ��{�H�u�[�����N���Ă��闝�R�ƂȂ��Ă���Ƃ����悤�i���Ɠ��H�̊W�ɂ��Ă͐}�^4183�Q�Ɓj�B���C�⋛������g���₩��҂傤�ő�ւ��悤�Ƃ������j�i�}�^7714�A�}�^7839�j���炤��������悤�ɁA���{�l�́A�����������̂��H�ׂ��Ȃ������̂ł��������ɕq���ɂȂ��������ł���A���Ƃ��Ɛオ�삦�Ă����킯�ł͂Ȃ��B
�i2023�N9��20�����^�A�}�^7762����L�q��Ɨ����A�s�ȑO�̗����F2015�N9��3���R�����R�lj��A2018�N6��3���Ζш��p�A2021�N2��22���`�F���}�C�ł����݂��e���܂�Ă���G�s�\�[�h�A2023�N5��8���c���i1975�j�u�嗤�̂����v�A2025�N2��4���c���i1970a�j�I�̐����j
�m �{�}�^�Ɗ֘A����R���e���c �n |
|
|||||||||||||||||||
�@