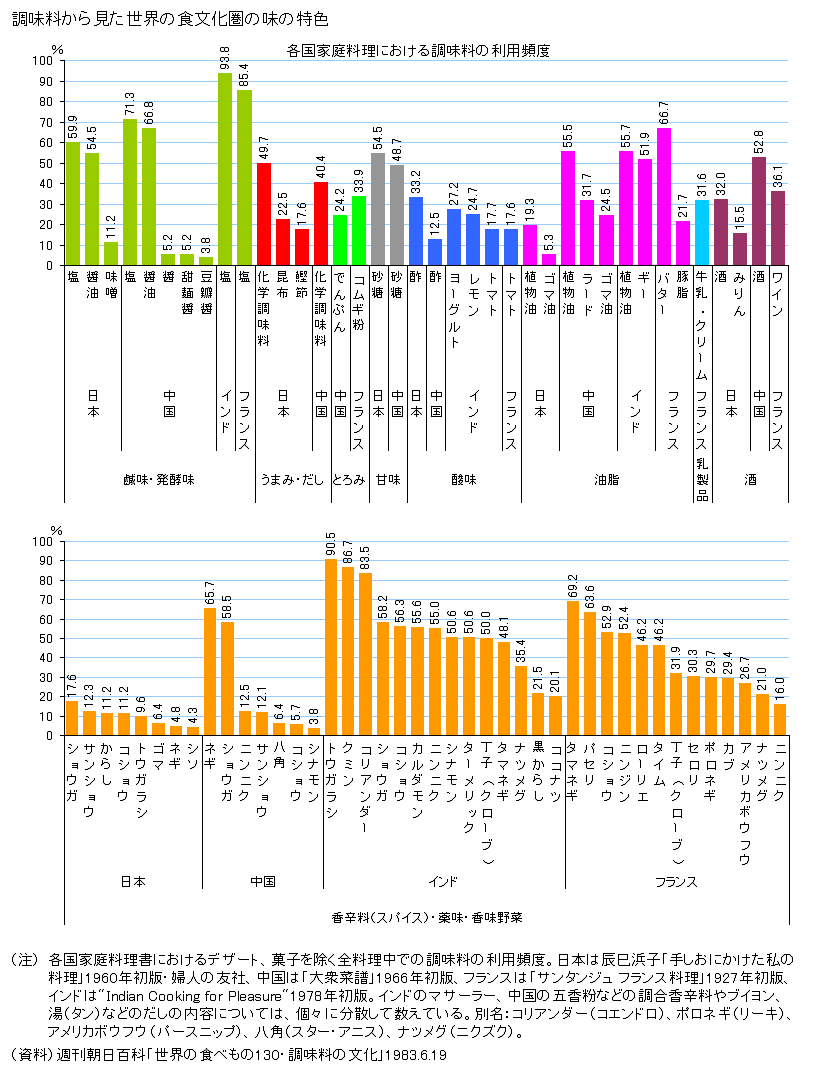
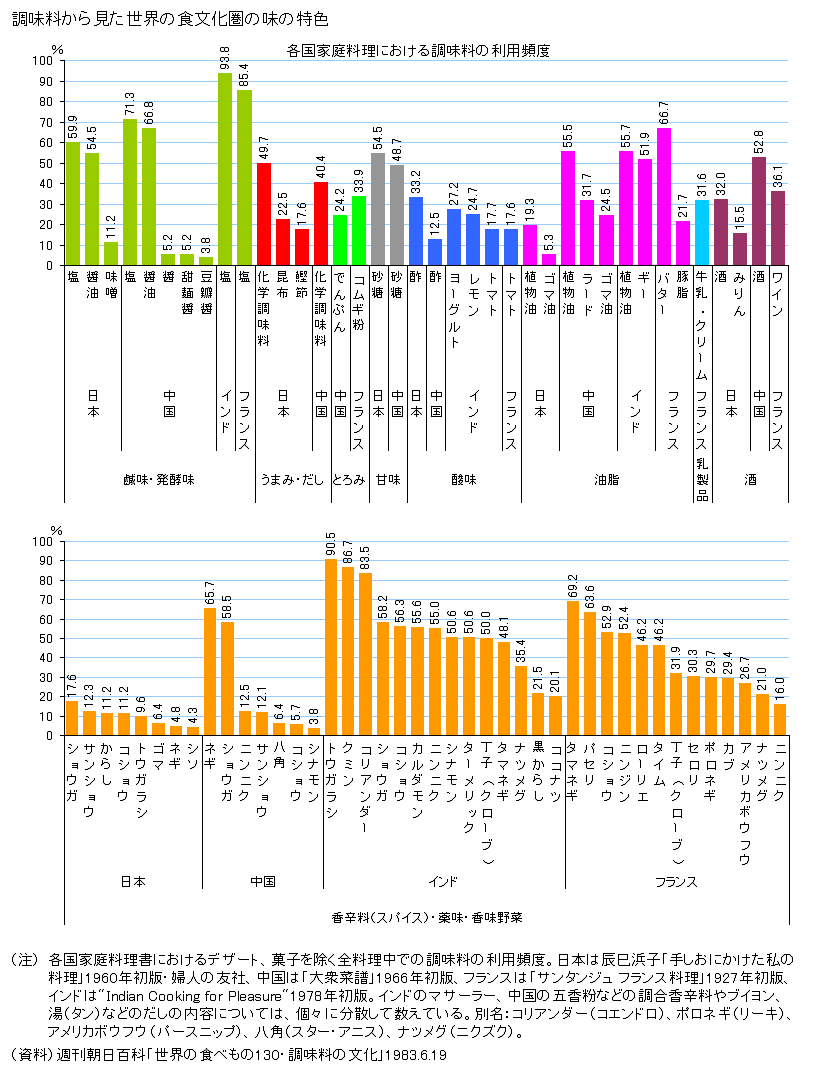
| 調味料から見た食文化圏の味の特色 図を見ると以下のような特徴がうかがえる。
日本の食文化の特徴と歴史的位置づけ (1)油脂の調味料としての性格
油のもつ「うま味」の根拠については謎とされる。「油自体も、昔から洋の東西を問わず、料理の大切な調味料の一つであるわけだが、それが何か舌に対する油の物理的性質に基づく作用であるか、それとも油自体の「うま味」によるものであるか不明である。油は数多くの脂肪酸のグリセリドの混合物であるから、そのうちの特定の脂肪酸のみが、特別にこのような「うま味」を感じさせる作用をもつものであるかどうかについては、以前から筆者が問題にしているのだが、誰か一々のグリセリドを分離して味わってもらいたいものと思っている。」(坂口謹一郎「「かつおぶし」の味」1964年(坂口謹一郎酒学集成 (5) 一説によれば、油脂には塩味をマイルドにするという「疑似うま味」作用があるとされる。「日本では、かつては油の少ない素材が多く、しかも油をあまり使わないことに料理法の特徴がありました。そのために種々の調味料のストレートな味に「こく」を与えるために「だし」が不可欠のものとなり、うま味に対して、敏感になったという説もあります(中尾佐助)。」(大塚滋「うま味の利用と歴史」(山口静子監修「うま味の文化・UMAMIの科学 (2)世界史における油脂の食文化の展開
中尾佐助「油脂の起源と普及」(週刊朝日百科「世界の食べもの」131[1983.6.26])によれば、油脂の食文化の展開は地域別に以下のようなものであった。 ヨーロッパは古来、豚脂など動物脂肪を中心とした地域であり、やがて乳脂肪の生産・保存技術の発達でバターが中心となった。植物油はサラダオイルの用途に限られて利用されている。 インドでは、ヴェーダ時代から、脂身を利用した動物油脂は使わず、むしろ、バターを精製して作るギーを使ったフライ料理が登場している。その後、カラシナとアブラナ類を中心とした植物油も利用されるようになり、フライ料理などは高価なギーを使うことはまれになった(現代では植物性のギーが市販されている)。 中国の油脂の歴史は豚脂からはじまり、のちにゴマ油やダイズ油が開発され、日本にも伝来したが、油脂の使用量が多いという特徴を持つ中国料理は、元代のモンゴル人の影響下に起こったとされる。 いずれにせよ、油脂の食文化は、古い起源をもつが、一般に普及したのは砂糖と同じここ200年くらいのことである。 (3)油脂の食文化が普及しなかった日本料理
「大体、植物油というものはどういうものかといったら、...脂肪、つまり動物の脂の代用品として食生活に入ってきたものなんです。したがって、動物の脂身を使う習慣のところはずうっと植物油が早く入ってくるわけなんです。日本なんかは家畜を飼ってその肉を食うということがなかったから、動物の脂を食べるということを日本の食文化は知らなかった」(中尾佐助「植物油の文明史」(1982年)中尾佐助著作集〈第2巻〉料理の起源と食文化 明治以前「日本では料理に使う油の量は少なく、日本料理ではどんな立派な御馳走でも殆ど油をつかうことなく、つくられてきた。,,,中国料理に油が大量に常用化したのは元代からと考えられる。支配者のモンゴル族はバターを好み、従って油料理が多かった。(中略)モンゴル人の支配は当時の東亜の文明国の食生活にかなり大きな影響を与えたようで、その前の宋では魚のなれ鮓が最盛期だったが、モンゴル人は魚に興味が無いこともあって、中国料理の中から鮓が消失し、以後復活していない。一方料理に油脂を常用する風習が強く定着し、次の明代に更に進展したと考えられる。朝鮮では一度廃絶した牛肉などの肉食が、モンゴル人の影響で復活して、現在に及んでいる。だから日本に神風が吹かず、蒙古軍がもし日本を占領していたら、日本はその時から肉食国に変わっただろうと言われている」(中尾佐助「油脂の歴史と文化」(1985年)著作集〈第2巻〉料理の起源と食文化)。 「私は日本人のこの異常なまでの油脂拒否は、その底に「米食」があるのではないかと考えている。一般に小麦やその他の雑穀類は蛋白質の含量は高い(20%以上)が、その蛋白質はアミノ酸組成が悪く、それだけ食べていては特殊のアミノ酸(たとえばリジン)の不足をきたす。したがって、かならず優秀な蛋白質の副食物(鳥獣魚肉等)をとってその不足を補わなければならない。故に、雑穀にたよっている民族では太古からかならず肉食が発達している(さもなくば栄養失調で死に絶えたはず)し、派生的に油脂に親しんできた。なかには油脂を主要カロリー源とさえしている。 米の場合これに対し、蛋白質は非常に優秀で、肉類のそれに近いから、その蛋白質だけで十分生理的需要を満たしうる。ただ、残念ながら、その含有量が雑穀類に比べて少ない(15〜6%)。それゆえ、米だけ食べても生きていけるが、そのかわりいちじるしく余分のデンプンを摂取することになる。高価な鳥獣魚肉が要らないから経済的ではあるが、胃の負担はぐんと重くなる。もちろん、油脂類を受けつける余裕もないし、第一、その必要もない。過剰のデンプンでカロリーは十分足りているのだから」(篠田統「舌ざわり後あじ」、石毛・大塚。篠田『食物誌』中公新書、1975年、p.200〜2001)。 最後の篠田統説を裏づけるアミノ酸組成等のデータは図録0218参照。 (4)東洋に特有の味噌醤油、魚醤系のうま味
東洋人の味覚としては、ひとつは古代から調(みつぎもの)として使われていた煎汁(いろり)またはカツオの煮汁を煮詰めた堅魚煎汁(かつののいろり)といった海産物を利用した調味料、もうひとつは大豆を使った発酵食品としての醤油・味噌があり、日本への伝来ルートとしては、前者は海を伝っての南からの伝来、後者は中国・朝鮮を経ての伝来と見られる(坂口謹一郎「醤油のルーツを探る」1979年(坂口謹一郎酒学集成 (5)))。「煎汁系の調味料の味は、茸の味を含めて醤や醤油味噌と同系列に属する「うま味」で、東洋人には何千年来親しみのある味だが、油と塩と乳と肉汁で育ってきた西洋人の味覚には全く新奇な異質なものであった。」(同上)モンゴルの家畜文化にも影響されなかった日本では、「だし」の料理文化が生まれ、この「だし」の化学的分析から世界に先駆けてうま味成分が日本で発見されることとなった(図録0216参照)。 魚醤系うま味の起源についてタイ・ビルマ系ではなくそれ以前に東南アジアの支配的民族であったオーストロアジア系によるものという説については、図録8130参照。 「だし」はもともとは肉食が制限されていた中で開発されたものであるが、肉食とも相性が悪いわけではなく、沖縄料理では和風だしの豚肉煮込み料理や小麦粉麺(沖縄そば)があった(図録7734参照)ほか、現代では、もとをただせばインド・中国伝来のカレーやラーメンなどが日本料理に特有のうま味、ダシを活用しながら進化をとげ、日本人の好きな料理として躍進している(図録0332参照)。 (5)和食の味わいを決める「だし」、発酵食品
「和食 日本人の伝統的な食文化」が2013年年12月にユネスコの無形文化遺産に登録された。和食文化を保護継承しようとする有識者の会議の主要メンバーである伏木亨(京都大大学院教授)は、和食の味わいを決める「だし」、発酵食品などについて次のように語っている(毎日新聞2015年3月29日の記事を要約)。 「だしは世界中にある。欧米や中国のだしは、いろいろな食材から長時間で煮出して、ゼラチン質も脂も、洗いざらい引っ張り出すのが主流だが、カツオ節、昆布、イリコだしが中心の日本のだしは、できるだけ雑味を出さないよう、うまみ成分だけを出すことに徹底しており、結果として、日本の「一番だし」はうまみに特化・純化している。日本のだしが純粋だというのは、素材の味を大事にする。素材の味を鈍くさせない。素材らしさを出す、ということである。これに対して、欧州のだしは、自分が作っただしのスープのうまさで全ての物を征服しようと思っている。欧州の人たちの自然と人間の関係の違いから来ている。彼らは、自然は征服すべきものであり、日本は、自然を敬って一緒に生きていきたいと思っている。 栄養素の最も主要なものはたんぱく質、でんぷん、脂肪である。三つとも味は無く、消化酵素も出ない。たんぱく質を分解するとアミノ酸、でんぷんを分解すると糖、油脂を分解すると脂肪酸がそれぞれ出てくる。この三つが味わいを作っている。発酵・熟成は、元々味がしない、味が薄いものを微生物の力で分解して、人間が感じやすい味を作っているのだと考えると、とても面白い。味がしないたんぱく質、でんぷん、油脂に、調味料を添加することですごくおいしくなるのが、発酵食品の極めて重要な点である。発酵は、おいしさだけを出す微生物の作用を引き出す高度な技術である。たんぱく質の分解によるうまみは、うまみを重視する日本人の好みに大きく寄与しているのは間違いない。その理由の一つは、日本ではかつて、油脂や砂糖が十分でなかったことだ。カロリーや油脂の摂取が少ないという、外国人が注目している日本人の健康面は、これは偶然であろうが、油脂と砂糖が十分でなかったからだ。それが注目され、強みになっているのが面白いところだ。油脂は手に入らず、砂糖は高価だったし、結局は、うまみと塩しかなかったのである。そうしたなかで、すごくおいしいものを作ってきて、高いレベルに達したのである」。 のちに伏木亨は「だしの神秘」(朝日新書、2017年)の中でこうした点を著作として明らかにしている。そこでは、油脂と砂糖とだしという3つが「やみつき」になることを動物実験でどう証明したかという点にふれたあと、「マウスの神経を遮断する薬品を使って行動に関わる神経系を健闘したところ、これらの執着は耽溺性の薬物に対する執着とメカニズムが同じなのです。もちろん薬物に比べると極めて弱いもので、溺れることはありません。むしろ、価値のある食べ物を取ったときのご褒美の快感といえるものです」(p.104)とし、直接言及していないものの、薬物中毒の進化上の由来が食物摂取上のメカニズムにあるのではないかということを示唆している。 さらに同じやみつきでも3つの食品には違いもあることが指摘される。「やみつき行動を起こすことが実験で確かめられている食品成分は、油脂と砂糖とだしです。マウスが油脂にやみつきになるには匂いも味も不必要でした。砂糖では甘味が必要でした。だしには、うま味と匂いとエネルギーが必要でした。やみつきの成立条件は複雑なようで、うま味単独ではマウスはやみつきになりませんが、うま味と匂いとエネルギーの3者がそろうと報酬系を刺激する効果があるようです。やみつきにあるようなだしの美味しさには、鰹と昆布のうま味に加えて、鰹節を中心とした香りや、同時に食べるご飯などのエネルギーの共存が必要であることが示唆されたのです」(p.106)。 そして、上の発言と同じように、こうも言っている。日本では、「なぜ、だしをこれほど重視する料理の文化ができあがったのか。それは、日本にはだしのほかに美味しいものがなかった、と言わざるを得ない歴史があるからです」(p。122)。 日本の歴史の中で油脂と砂糖が十分でなかったのは偶然であろうか。上述のように、世界の中でもめずらしく肉食の忌避が継続したので、肉や骨を使ったスープ・ストックというかたちのだしを活用できなかったためではなかろうか(下記参照)。その結果、意図したわけではないが、和食ならではの素材重視の味つけを極めることになったのだと考えられる。 (6)人類史上の「古代」を現代、そして未来へ引き継ぐ日本("Ancient to the Future")
欧州、インド、中国など古くから家畜文化が発達した地域では、油脂の食文化が制覇していったため、一時期古代ローマで魚醤が普及したのに衰えたことからもうかがえる通り、うま味の文化は背景に追いやられることとなった。中国・東アジア、東南アジアを含むアジア一帯では、もともとは魚醤や穀醤、大豆発酵製品などが生まれ、また仏教文化の普及により肉食が制限されていたため、食文化の発展の中でうま味にスポットライトが当たる条件が成熟していった。しかし、中国北方民族の家畜文化が再度アジアに普及したため、日本においてのみうま味文化が純粋に発達していくこととなった。(日本においてお膳における箸の置き方が横なのは、中国古代と同じだという点など図録3854参照) 現代では過食が肥満、糖尿病、高血圧などにむすびつき、健康が害する事態に陥りがちである。味の満足感は科学的には脂肪、砂糖、ダシにより、同じメカニズムで得られるという。「多くの国では満足感を得るために、油脂を大量に摂取する。デザートには砂糖などもよく使う。いずれもやみつきになる食品である。一方、日本型のやみつき感はダシの香りとうま味で達成できる。うま味の主成分はアミノ酸であり、デンプン程度のカロリーに過ぎない。塩分も必要だが、それも生理的な範囲と言えよう。無理して減塩するよりもダシのおいしさと塩加減を極めて欲しい。油脂と砂糖が乏しかった。そのおかげでダシの文化が花開いた。今こそ先人の知恵を活かすときである。ダシのおいしさ。日本発の健康食を世界に発信すべきである。」(伏木亨「おいしさを科学する 先進諸国が飽食の時代に突入し、BSE問題を含め肉食文化への反省が生まれ、健康上油脂の取りすぎが問題とされる中で、魚食文化、醤油味噌、うま味、緑茶などの特徴を持つ日本食が世界的に見直されて、日本食ブームが起こっているが、これは人類が忘れていた古代の食文化を再発見する過程であるように思われる。シカゴの前衛黒人ジャズグループである Art Ensemble of Chicago は自らの音楽理念を"Ancient to the Future"という標語で示したが、私はこれが食文化にとどまらず日本文化が世界に貢献していく道だと思われてならない。 一般論として、日本が古代の習慣や文化を今に伝えている稀有な国であることを明らかにしているのは中尾佐助である。 例えば、日本の民家や仏教寺院は高床式建築であり、土間が基本の中国とは異なる。「雨の多い照葉樹林帯では、明らかに高床は合理的である。だから日本で、寺院が高床に変化したのかもしれない。それが中国の江南では華北文化の影響で土間に変わったが、日本は変わらずにそのままの形を保存してきたといってよいだろう。日本は古い文化要素を、そのままの形で、あるいはさらに洗練された形で残すことにかけては、実に世界にも稀な天才的能力を発揮している国である」(中尾佐助「現代文明ふたつの源流―照葉樹林文化・硬葉樹林文化 これは、やはり、日本が海で大陸から隔絶された環境にあり、陸続きの国々とは異なって、「中国の直接統治下には置かれず、その文明を強制されることがなかったため、中国文明を一つの体系としてまるごと受容するのではなく、文明を構成する要素に分解して、そのなかから自分たちの好む要素だけを選択的にとりいれることが可能であった」からだろう(石毛直道「日本の食文化史――旧石器時代から現代まで」岩波書店、2015年、p.57)。 古代以降の中世、近代と人類が自然や人間の本性に反する方向に堕落してきたとするなら古代を保存している日本の文化は、今後、世界に貢献できる余地が大きかろう。肉食や砂糖、油脂の過剰摂取は太古の農業以前時代を通じ採集植物食をベースに進化したヒトの生理には本来反するものである可能性がある。それらを摂取しないで満足を得られる工夫をした日本食が見直されるゆえんである。ことは食の分野に止まらない。精神態度においても、全知全能の唯一神信仰を深める方向ではなく、孔子に導かれ、「鬼神を敬して遠ざく」儒教的・世俗的な道徳心重視の方向をたどった東アジアの中でも、古来の「仁」の精神をもっとも現代まで保っているのが、仏教に対抗して精緻な理論化を進めた朱子学に影響されて個人の道徳的完成を目指すこととなった中国ではなく、むしろ、素朴な和の精神を最優先する気風を継続した日本だとすれば、種としてのヒトの本能や生理に無理のないこのような精神態度を育てた日本文化が将来的に人類の救世主になる可能性があるといえるだろう(図録8070参照)。 (2009年7月20日収録、2010年12月2日伏木(2006)よりの引用追加、2011年1月6日沖縄料理記述追加、2014年11月7日"Ancient to the Future"論補強、2015年3月30日伏木毎日新聞記事から(5)を挿入、2016年4月27日石毛直道引用、2017年4月23日伏木2017からの引用、2024年10月25日篠田統「舌ざわり後あじ」引用)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||