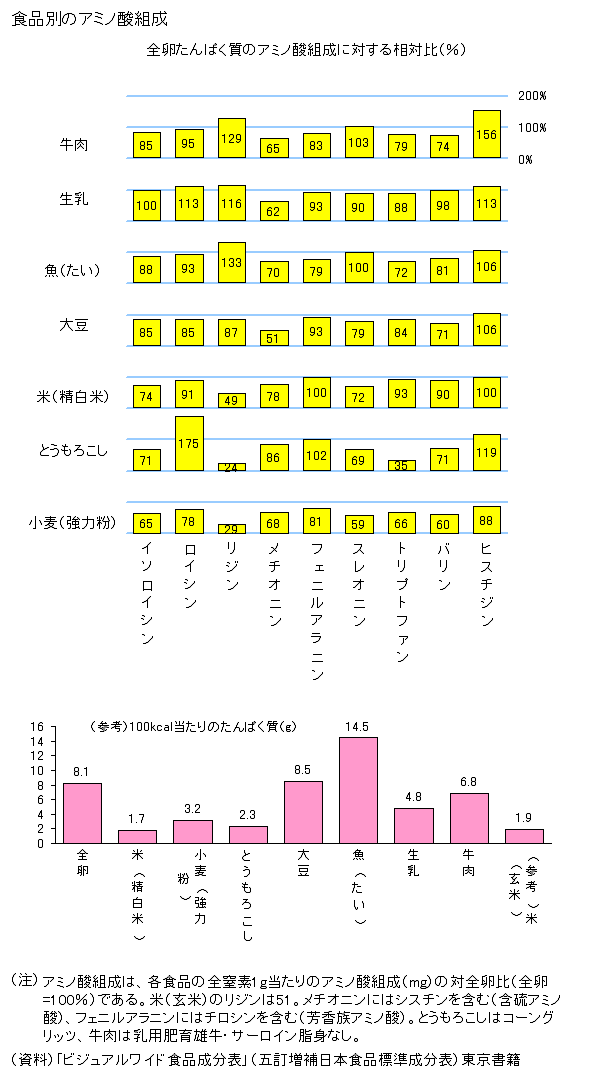
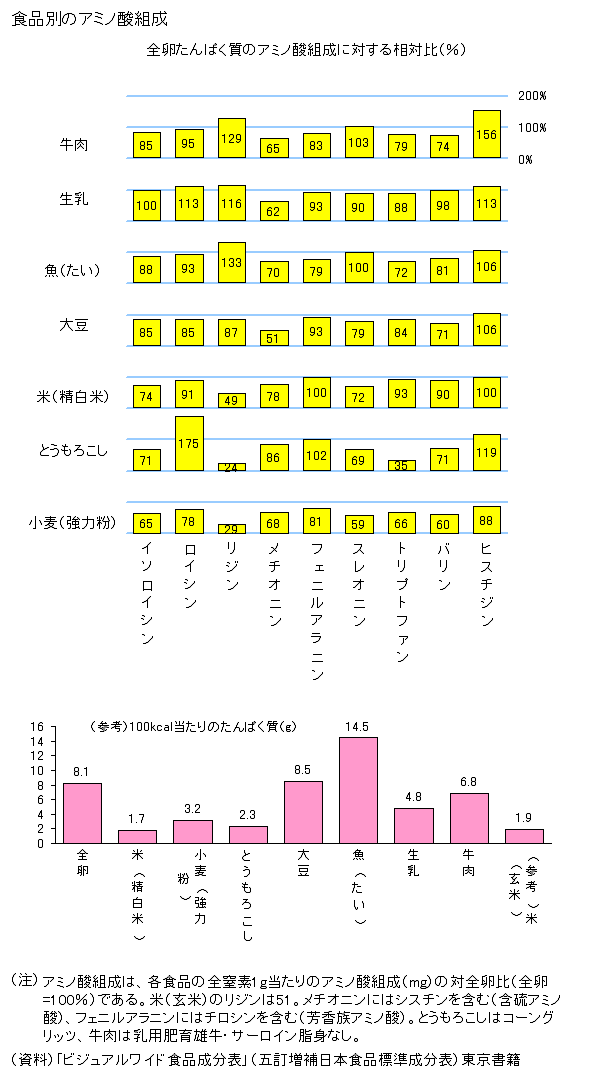
たんぱく(蛋白)質は、生命活動にとってもっとも重要な栄養素である。たんぱく質は各種のアミノ酸からなっているが、特に体内で合成できないため外部から摂取するしかないアミノ酸は必須アミノ酸と呼ばれる。 必須アミノ酸は、9種類、イソロイシン、ロイシン、リジン(リシン)、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジンである。ヒスチジンは体内で作られるが、急速な発育をする幼児の食事に欠かせないことから、1985年からこれも必要なアミノ酸として加わるようになった。これらのひとつでも欠乏すると他が十分であっても栄養不足と言うことになる。 たんぱく質食品として栄養の面から完全食品とされる全卵に対して、それぞれの必須アミノ酸が多いか少ないかを示したグラフを作成した。データは五訂増補日本食品標準成分表(2005)に基づく「ビジュアルワイド食品成分表」による。 これを見ると、動物性食品に比べ、穀物食品ではリジン不足に陥りやすいことが分かる。特に、米(49、玄米の場合は51)に比べとうもろこし(24)や小麦(29)はリジンが少ない。 植物学の中尾佐助によれば「コムギもトウモロコシも栄養学上からみると、蛋白価はコメに劣っているものである。米食ならば「1升めし」を食べれば、人間は「蛋白栄養」については、かろうじて生きられるが、コムギやトウモロコシでは、それだけを食べていくためには、「蛋白栄養」の上から、胃袋がパンクするほど食べなければならないので、不可能ということになる。だからコムギ食の場合は肉類や乳製品を加えなければ、人間の生命は維持しがたい。コムギ食の根底は、肉や乳製品が加わることが前提となって初めて人間の食生活の体系として完成できるものである」(「現代文明ふたつの源流―照葉樹林文化・硬葉樹林文化」朝日選書、1978年、p.44)。 一方、植物性食品の中でも根粒菌との共生により空気中からの窒素固定が可能な大豆など豆食品にはリジンを含めて比較的に豊富に必須アミノ酸が含まれている。このため、米食と豆の組み合わせで必要な栄養摂取が可能であり、米食民族に「主食」という概念が成立するゆえんとなった。欧米の場合は、小麦食を中心とするにしても肉食との組み合わせが必要であったのと大きく異なっている。戦前の日本人が米と大豆の組み合わせでたんぱく質を摂取していた状況については図録0280を参照。 ただし、参考に掲げた図に見るように、カロリー当たりのたんぱく質は米の場合多くないので、たんぱく質を量的に充足させようとすれば、沢山食べねばならない。 こうした点は食物学や栄養生理学では常識化している。例えば食物学の篠田統「舌ざわり後あじ」にはこうある。 「一般に小麦やその他の雑穀類は蛋白質の含量は高い(20%以上)が、その蛋白質はアミノ酸組成が悪く、それだけ食べていては特殊のアミノ酸(たとえばリジン)の不足をきたす。したがって、かならず優秀な蛋白質の副食物(鳥獣魚肉等)をとってその不足を補わなければならない」。これに対し米の「蛋白質は非常に優秀で、肉類のそれに近いから、その蛋白質だけで十分生理的需要を満たしうる。ただ、残念ながら、その含有量が雑穀類に比べて少ない(15〜6%)。それゆえ、米だけ食べても生きていけるが、そのかわりいちじるしく余分のデンプンを摂取することになる。高価な鳥獣魚肉が要らないから経済的ではあるが、胃の負担はぐんと重くなる。もちろん、油脂類を受けつける余裕もないし、第一、その必要もない。過剰のデンプンでカロリーは十分足りているのだから」(石毛・大塚・篠田「食物誌」中公新書、1975年、p.200〜2001)。 また、鳥居邦夫「栄養生理学・脳科学からみる嗜好の成立」(伏木亨編『味覚と嗜好 (食の文化フォーラム) 』ドメス出版、2006年)では次のように述べられている。 「穀物はエネルギー源および蛋白源として生体内で利用されるが、地域ごとに収穫できる作物の種類と生産性は気候風土により限定される。主要な穀物そして豆類にふくまれる蛋白質のアミノ酸組成は、動物性蛋白質である牛乳や畜肉とは大きく異なる。(中略)わが国をふくめ東アジアの地域では、主たる穀物の栽培は稲作である。小麦やコーンと異なり、コメは連作障害もなく単位面積当たりの収穫量も多いうえに、コメの蛋白質は小麦やコーンに比べリジン含量も多い。食事にはリジン含量の高い大豆等の豆類も広く利用されているので、穀物を家畜に与えて食肉や乳製品として利用する必要は少なく、蛋白質栄養の面から穀物中心の食生活が可能となり、結果として東および南アジアの稲作地帯では巨大な人口を支えることができるわけである。 わが国の具体的な例として、必須アミノ酸であるメチオニンは充分ふくまれるがリジンの少ない米飯に、メチオニンは少ないがリジンが充分含まれる大豆製品である納豆をかけて食べたり、大豆蛋白質である豆腐を副食として組み合わせて食べると、食事性蛋白質はほとんど牛肉並のバランスのとれたアミノ酸組成になるのである。 このような食事でもコメにふくまれる蛋白質が乾物でも10%程度と少なく蛋白質の生理的欲求に応えるには不足がちであるので、よく働いてコメの余分な炭水化物を活動エネルギーとして体外に放散し、蛋白質を体内で濃縮することにより蛋白栄養状態を良好に保ってきた。したがって、食事をすることはコメを多く食べることを意味し、「御飯(ごはん)」というふうによぶ習慣をもっていると考えられる」(図録2177の(注2)も参照)。 同じことを食の文化人類学の第一人者である石毛直道はこう要約している。「麦類にくらべて米にふくまれる必須アミノ酸のバランスは優れているので、米飯のどか食いをすれば、米をたんぱく質源として生きることも可能なのである。米を主食とする食生活においては、副食物は大量の飯を食べるための食欲増進剤としての機能が重視され、塩気とうま味のある少量のおかずさえあればよかった」(石毛「世界の食べもの――食の文化地理」講談社学術文庫、p.266)。塩分摂取量が米食アジア人で多い点については図録2174参照。 食物史家の篠田統も日本人は、米食でタンパク質の摂取が完結し、ただしそのためには余分のデンプンを食する必要から(つまりコメのドカ食い)、油脂類を受け付ける余裕もない食生活を長い間送ってきたため日本人の舌は「舌ざわりや後あじ」に敏感にならざるを得なかったのが日本の食文化の基本線だととらえている。「われわれはアユやウナギと、魚類までもその固有の香りを尊ぶ。それだけ、逆に、羊や山羊のような強い匂いはうけつけない。(中略)油脂の多用とあのどろどろのソースとは味を単調にする。本質的な味ではない、舌ざわりがである。中に入れる材料の三ツや四ツ入れかわっても、八宝菜は八宝菜、ブイアベースはブイアベース。多少の味の変化はあるにしても、舌の感触はかわらない。個々の材料の個性が消えてしまった、とも言えるが、原料の如何にかかわらず同じ味を出した、とも考えられる。(中略)舌ざわりといい、後あじといい、米だけにたよっている日本食を背景に考えねば意味をなさない」(篠田ら「食物誌」中公新書、1975年、p.202〜204)。 日本人の食の美意識の由来を「神韻」などでなく「物的背景」に求めた篠田に私は共感せざるを得ない。私の考えでは、日本人が肉食の忌避を長く続けられたのは石毛や篠田の言うように米食のおかげであり、肉や油脂を食べないことによる物足りなさから、ささいな味にも敏感となり、出汁や発酵食品を基調とする日本食を生み出すことができたのである(注)。 (注)枕草子を読むと、今でもそう感じられる日本人の美意識・感覚が古代から存続していることに気づかされる。例えば、「むつかしげなるもの ぬひ物の裏」(現代語訳:ごちゃごちゃして見たくないもの。刺繍の裏がわ)とあるが、確かにそうだなと思う。ところが、食べものに関しては、同じようになるほどなと思わせる所はなく、現代の感覚から見て「貧弱」あるいは「記述が少ない」と感じられる。これは日本の古代にはその後発達したみそ、しょうゆ、すしなどの発酵食品による豊かな味がそもそもまだ開発されていなかったためと考えられる。 コメのドカ食いの食習慣が外国料理の導入に当たってもキーポイントとなっていたことを料理研究家の稲田俊輔は「炭水化物問題」と呼んでいる。大量のパン食と組み合わされた日本の老舗のロシア料理店について「昭和の日本人は、少量のおかずで大量の米をかっ食らうのがあくまで基本だった。だから少量の肉や野菜と共に大量のパンが供されるようなコースも当時は普通に受け入れられていたのではないか」(「異国の味」集英社、p.80)。またイタリア料理やスペイン料理の「フランス料理に対するアドバンテージという意味では「炭水化物問題」が重要です。フランス料理はあくまで肉がメインで、炭水化物であるパンやじゃがいもは、添え物に過ぎません。これは多くの日本人にとっては結構つらい事実です。かつて日本人はフランス料理(や、イギリス料理)を、ご飯によく合うオカズとして魔改造した「洋食」によって、この問題を解決しました。しかし世の中の本場志向への流れの中で洋食が衰退していくと、そこで俄然優位性を持ったのが、パスタという極めて優れた炭水化物コンテンツを擁するイタリア料理でした。そしてスペイン料理にも、パスタに負けずとも劣らない炭水化物コンテンツがあります。そう、パエリアです」(同上、p.121)。 哲学者和辻哲郎の「風土」によれば、夏湿潤なモンスーン型のアジアでは夏草が繁茂するため雑草取りのハードな労働が不可欠であり、夏乾燥している「牧場型」のヨーロッパでは耕地に種子をまいておけばその成長を待つだけで済むのとは大違いである。これが欧米と比較して、働きづめに働くことを尊重する日本独自の勤労観を生んだとされた。 歴史人口学(数量経済史)の速水融は、人口の多い割に耕地の余裕のなかった江戸時代に、日本型の生産性向上に向け、それまでの畜力農業をやめ、人力依存の緑肥づくりや肥料購入のための副業を通じた多肥農業に傾斜したといういわゆる「勤勉革命」が働き者の日本人という特性を生んだと論じた(図録0207参照)。畜力を人力に代えれば飼料代の減が食費の増を上回り効率的だという理屈である。これも農業労働の特性から説いている点では和辻説を歴史的に捉え直した見方といえよう。 日本人の勤勉さの由来としてたびたび和辻説や速水説が引かれてきたが、ここでふれたアミノ酸バランス説の方がストレートである。 アミノ酸バランス説からすれば、日本人と同じく稲作民族である中国人、韓国人も肉食なしで済ませようと思えば済ませられたのであるが、仏教の影響が日本と異なり肉食に関しては減退し、日本人と異なり肉食を併用することとなった。あるいは稲作以前の狩猟採取段階では一般的であった肉食が維持され続けた(図録0214)。その結果、日本人だけが、明治以降欧米文化に感化され、戦後経済的に豊かになるまでは、純粋米食民族としての特異な歩みを続けたのであった。何か活動していないと気が済まないという東アジアに特有な民族性も蛋白質栄養の摂取方式に起源をもつという説は非常に興味深い。 米食を基本にして、野菜や肉(家畜と魚介類)などの多様な副食を適切に組み合わせた日本型食生活が推奨され、海外からも注目されているが、日本型食生活の由来というべき米食文化にはそれなりの風土上、歴史上の根拠があったと言えよう。 稲作はアジア・モンスーン気候特有の夏の高温多湿と適合的であるため、南アジアから東アジアで主作物となっている。気候については図録4335、作物マップについては図録0430参照。 図で取り上げた食品は、全卵、米(精白米)、小麦(強力粉)、とうもろこし、大豆、魚(たい)、生乳、牛肉、そして参考に米(玄米)である。 (2011年3月28日収録、2013年8月21日石毛引用、2014年9月29日中尾引用、2019年1月11日和辻説・速水説、2023年6月10日篠田引用、2024年3月15日稲田俊輔引用、10月25日篠田統油脂拒否由来引用、2026年2月19日枕草子引用)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||