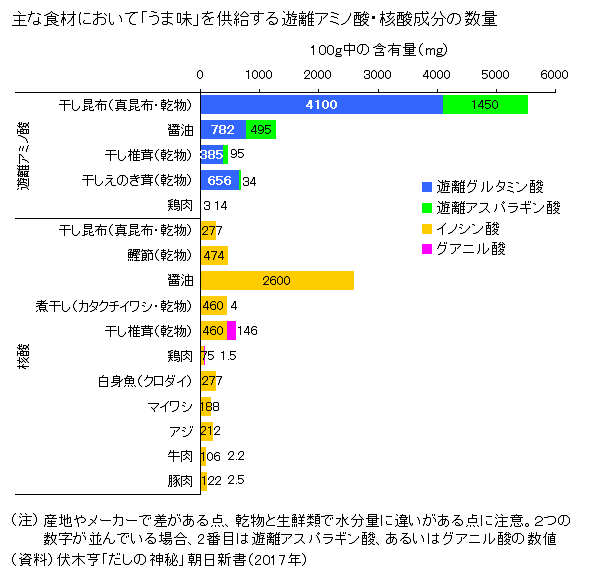
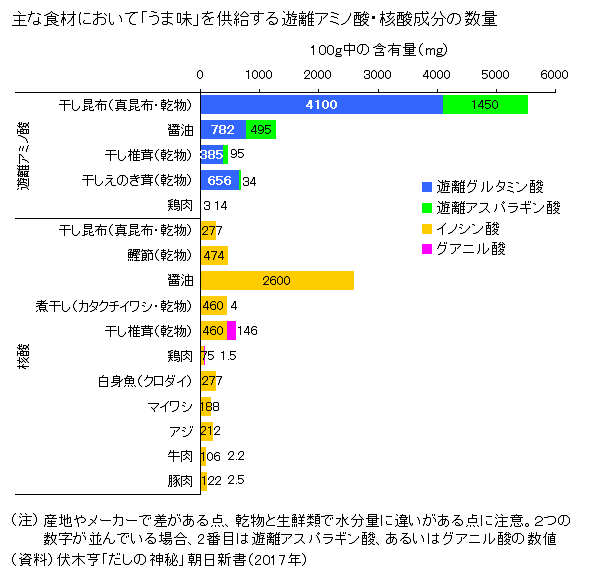
干し椎茸は禅宗などの精進料理に不可欠のだし(出汁)として古くから高価な食材であった。 安土桃山時代に農・乾物の一大集積地であった大阪は多湿な気候が乾物や昆布の旨味を熟成させたことから、江戸時代になると北前船海運の発達によって昆布が北海道から大量に運ばれるようになったため、昆布のダシを特徴とした食べ物が「大阪の食い倒れ」として有名になったという。 燻乾を経て水分を落としうま味を凝縮した乾物製品である鰹節は江戸時代に開発され、紀州漁民が開発したといわれるカツオの大量漁獲技術(撒き餌と水の音でパニックになったカツオの群れを疑似餌で一斉に釣り上げる一本釣り漁法)の発明によって鰹節の大量生産も可能となった(かつお節についてはコラム2参照)。 煮干しは手軽なだし材料として明治以降庶民に普及した。 現在では全国平準化が進んでいるが、「関西の昆布好き、関東の鰹好き」(梅棹忠夫)と言われていた(伏木下掲書。昆布消費の地域平準化については図録0668参照)。 図で明らかなとおり、昆布には遊離アミノ酸のグルタミン酸やアスパラギン酸、鰹節、煮干しには核酸のイノシン酸、干し椎茸には同じく核酸のグアニル酸が多く含まれている。醤油は遊離アミノ酸と核酸の両方が含まれる万能のうま味調味料である。 別の3資料では以下のように各食品にうま味成分が含まれているとしている。 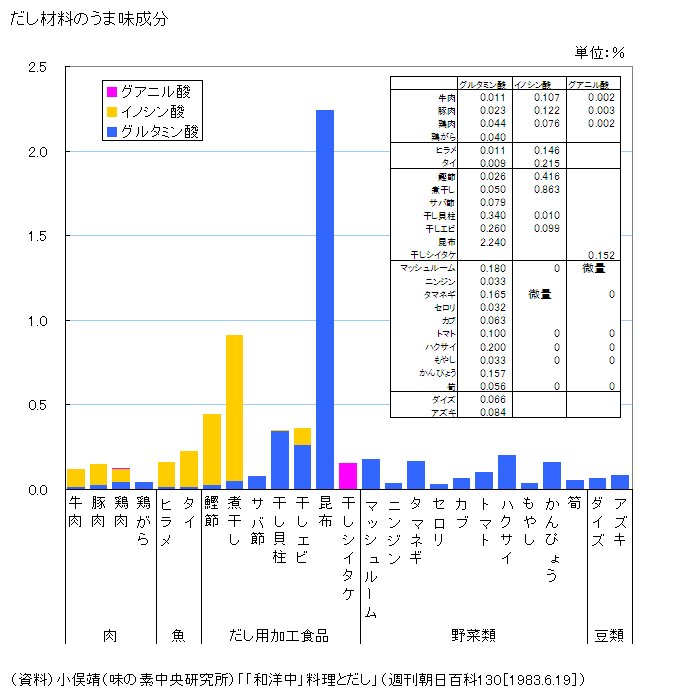  「うま味は種々の成分で構成されているが、その中のグルタミン酸(アミノ酸の一種)、イノシン酸、グアニル酸(核酸成分の一種)の3種がかなめである。グルタミン酸は植物性食品に、イノシン酸は動物性食品に多く含まれている。グアニル酸はシイタケなどキノコ類に多く含まれている」。日本における「うま味を求める伝統の影響か、うま味研究の面で大きな足跡を残してきたのは日本の学者たちである。池田菊苗博士が昆布のうま味の正体はグルタミン酸であることを発見した(1908年)話は有名だ。その5年後に池田の高弟小玉新太郎が、鰹節のうま味はイノシン酸であることをつきとめた。さらに1960年にはグアニル酸のうま味が、国中明博士によって解明されている」(小俣靖「「和洋中」料理とだし」(週刊朝日百科130[1983.6.19]))。
また、同じ国中博士が、こうしたうま味成分相互の相乗効果も発見し、日本料理において昆布と鰹節でだしをとることが、強いうま味を引き出す工夫であったことが明らかになった。伏木亨京大大学院教授によれば「昆布のグルタミン酸、カツオ節のイノシン酸は組み合わせることで相乗効果が出ます。昆布だし単独の場合に比べ、一番だしでは10倍以上のうま味になります。これが日本の伝統的なだしの特徴です」(毎日新聞2010.7.25)。 なおグルタミン酸がうま味成分として最初に発見された1908年、グルタミン酸ナトリウムが早くも鈴木三郎助・忠治兄弟によって調味料として商品化(商品名「味の素」)され発売された。やがてイノシン酸、グアニル酸も加わって、化学調味料、うま味調味料が日本から世界に広がっていった。 古来、中国では、五味(ごみ)として鹹甘酸苦辛(かんかんさんくしん)、すなわち塩味、甘味、酸味、苦み、辛さを味の要素と考えた。20世紀初め頃、世界の学界では、味覚神経を通じて感知される味として、五味のうち辛さを除く4基本味説が支配的であった。上記池田博士は、グルタミン酸の「うまい」と感じる独特な味を「うま味」(UMAMI)と名付け、5番目の基本味と主張した。その後、これが国際的にも認められるようになった(国際的にうま味が認められるまでの経緯は平坦なものではなかった点については巻末コラム参照)。 味覚は栄養摂取上のシグナルとなっている。「甘味」は、生命体の活動に即つながるエネルギー源の目印となっている。「塩味」は、原始の海から深化した陸上動物が、海の成分と似た自身の体液から汗や尿によって失われがちなミネラル、特にナトリウムを常に食べ物から摂取する必要から生じている。「酸味」は、食べ物が未熟、あるいは腐敗していないかを見分けるため、また「苦み」は毒性の高い食物であるかを見分けるために備わった味覚と考えられる(山口静子監修同上書、弓狩康三・鳥居邦夫「味の栄養学」(小石秀夫・鈴木継美編「栄養生態学―世界の食と栄養」恒和出版、1984年)。 一方、「うま味」は、身体にとって不可欠の栄養素であるたんぱく質摂取のシグナルととらえられる。 「タンパク質も重要な栄養物であるが、ごく少数の例外は別としてそれ自体には味がない。タンパク質は約20種のアミノ酸から構成されているが、タンパク質に組みこまれていない単独のアミノ酸(遊離アミノ酸)には味がある。タンパク質が存在するところには、遊離アミノ酸が存在するので、アミノ酸の味はタンパク質のありかを知らせるシグナルの役割をはたしている。グルタミン酸はタンパク質のなかでももっとも多く含まれるアミノ酸であり、グルタミン酸がもつうま味はタンパク質の代表的なシグナルである」(栗原堅三(1998)「味と香りの話」岩波新書)。 さらに核酸は、遊離アミノ酸からタンパク質をつくる遺伝情報を担っているのがDNAやRNAという遺伝子だが、これらの遺伝子は役目を終えるとイノシン酸などの核酸に分解される。つまり、「核酸成分のうま味も、タンパク質を探す手掛かりとなる」ので核酸にうま味があることになるのである(伏木亨(2017)「だしの神秘」朝日新書、p.23)。 また、「舌にうま味の受容体があることが明らかになっています」(伏木教授、毎日新聞2010.7.25)。この点については、脊椎動物の味蕾についてふれた図録4175参照。 動物によっては5つの基本味を感じる味覚のうちいくつかが進化の過程で失われることがある。例えば、南極のコウテイペンギンは、鳥になる段階で、甘みが失われ、その後、うまみ、苦みが失われ、今では、酸味と塩味しか感じられないという(図録4175参照)。 うま味が日本の科学者によって発見され、日本でうま味調味料の工業的な生産もはじまったのは偶然ではない。「うま味」調味に特別な重要性をおくようになった日本における食文化の発達の特殊性については図録0214参照。 なお、五基本味の性格を見るため濃度と味の強さの関係図を以下に掲げた。 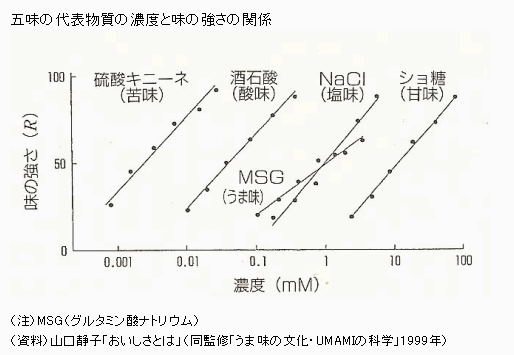 いずれもフェヒナーの法則に沿って味の強さは濃度の対数とともに直線的に増大する関係となっているととらえられる(山口前掲論文)。甘味、塩味、うま味といった栄養摂取と関連する物質は一定程度の量がないと味とならないが、避けるべき物質を示す酸味、特に苦みでは、微量でも味として感じる点が印象的である。また、グルタミン酸ナトリウムは、他の基本味と異なり、勾配がゆるやかであり、量を増やしても強烈にはならないおだやかな味である点に、ごく日常的に摂取する対象の味である特徴があらわれている。イノシン酸ナトリウムやグアニル酸ナトリウムはさらに勾配が小さいという。
なお、だしはうま味と香りからなっており、だしの香りは学習が必要だという。伏木教授によれば、「日本人でも子どものころにだしの香りを体験していなければ、おいしいと感じることができません。そのためにも小学校低学年までには、各家庭でだしを使った料理を食べ、体験しておく必要があります」(毎日新聞2010.7.25)。私が鰹節産地の食品メーカーから、鰹節には中毒性があり、一度食べれば止められなくなるときいたことがあるが、おなじことを言っているのかも知れない。
ここで、検索のため、取り上げた食品名を重複をいとわず列挙する。牛肉、豚肉、鶏肉、鶏がら、ヒラメ、タイ、鰹節、煮干し、サバ節、干し貝柱、干しエビ、昆布、干しシイタケ、マッシュルーム、ニンジン、タマネギ、セロリ、カブ、トマト、ハクサイ、もやし、かんぴょう、筍、ダイズ、アズキ、真昆布、羅臼昆布、パルメザンチーズ、のり、せん茶(茶葉)、トマト、シメジ、ホタテ貝、車エビ、白菜、アサリ、カツオ節、アジ、サンマ、鶏肉、豚肉、タイ、サバ、イワシ、煮干し、車エビ、牛肉、シイタケ(干し)、編みがさ茸(干し)、ホタテ貝、のり、ポルチーニ(干し)、ドライトマト、ズワイガニ、ウニ、シイタケ、コンブ、チーズ、一番茶、アサクサノリ、イワシ、スルメイカ、ホタテガイ、トマト、バフンウニ、ジャガイモ、白菜、煮干し、カツオブシ、シラス干し、カツオブシ、アジ、サンマ、タイ、サバ、イワシ、豚肉、牛肉、クルマエビ、ズワイガニ、乾しシイタケ、マツタケ、エノキダケ、生シイタケ、豚肉、牛肉。 (2009年7月20日収録、2010年7月26日別資料追加、2012年1月23日成分別資料、コラム追加、2014年12月17日コラム2追加、2017年伏木亨(2017)からのデータ等)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||