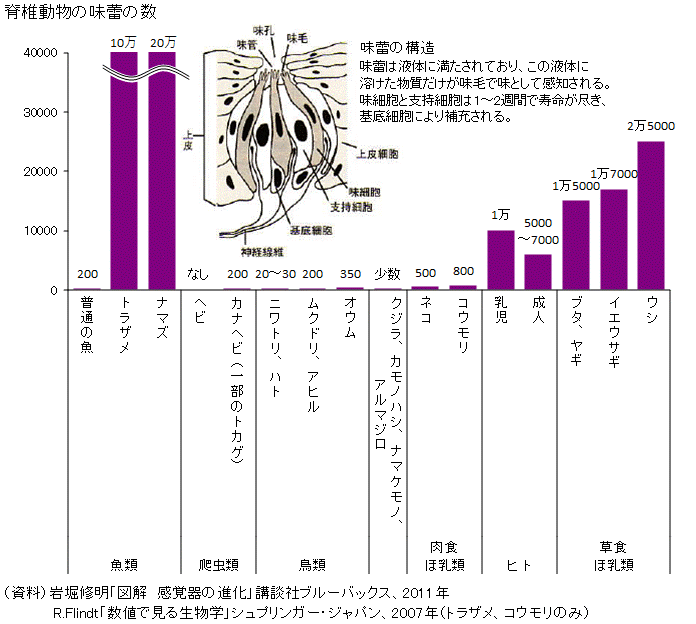
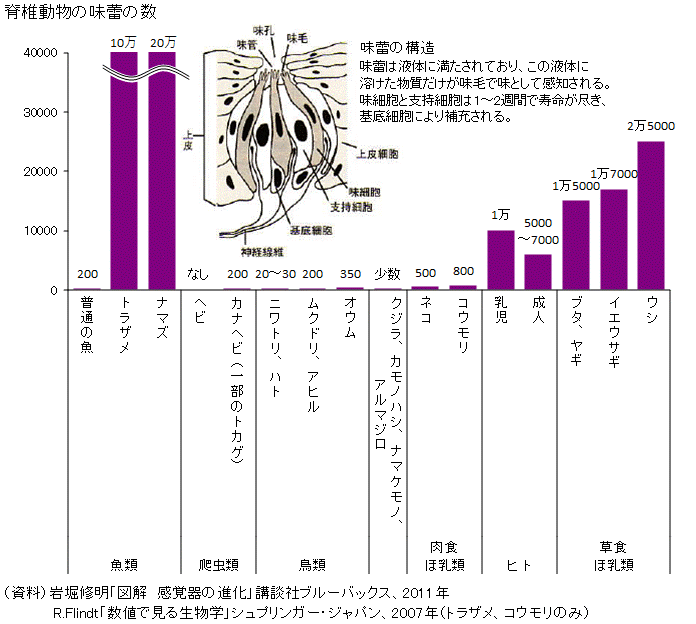
脊椎動物の味蕾は円口類の段階で発生した。原始的な段階からほ乳類までしくみは単純で大きな差はないが数は増えていく。 魚類は普通200ぐらいであるが、視覚のきかない濁水の中で生息するコイやナマズは、味蕾を体表全体に分布させ(特にヒゲに密集)、餌の小魚を全身で探知している特殊例である。漂ってくる「小魚の味が、ヒゲの味蕾と尾びれ近くにある味蕾のそれぞれに到達するまでの時間差を測ることによって、小魚のいる位置を正確に割り出すことさえできる」(岩堀2011)。 ヘビなどの爬虫類や鳥類は食べ物を噛まずに丸飲みしているので味を感知する必要がなく、味蕾もないか少ない(ヘビやトカゲは嗅覚器の一種の鋤鼻器で補っているという説もある)。 ほ乳類の中でもやはり丸飲みするクジラ、単孔類、貧歯類(ナマケモノなど)は味蕾が少ない。 肉食ほ乳類は生きている動物を食べるので毒味をする必要もない。腐っているかを判別する必要もないし、食する動物もだいたい決まっており毒もないことが分かっている。このため、味蕾が少なくなっている。 草食ほ乳類は、無数の見た目は違いのない草の中から毒になるものと身体に必要な栄養とを判別するために味蕾が非常に発達している。もっとも、草食動物は毒(植物二次化合物のアルカロイド、テルペンなど)をあらわす「苦み」に関してはそれほどこだわらないという説もある。「植物を食物対象とする草食動物は、かなり強い苦みも拒絶せず、味を手がかりとして食物を選択するというよりはむしろ、反芻胃や肝機能などによって摂取した二次化合物を代謝・分解してしまう。」(上野吉一「人類におけるグルメの成立」(伏木亨編『味覚と嗜好 (食の文化フォーラム)』 ドメス出版、2006年)) ヒトは肉食獣と草食獣の中間ぐらいの味蕾の数である。乳児期には舌だけでなく唇、口蓋、食道、あるいは内臓の一部にまで味蕾が広がっているが、成人では舌以外の味蕾は減っていく。子どもが大人より味の好き嫌いが多い理由といわれる(注)。老人はさらに全体に味蕾が著しく減少し、味に対する感度も低下する。高齢者が塩辛い味を好むのもこのためである。 (注)成人でも、30代以上と異なり、20代では男女ともに「好み」が食品選択の最重要項目である(図録0323参照)。 味は、食べ物の毒や腐敗を識別し、また優先的に摂取すべき栄養を探知する知覚である。20世紀初頭、ドイツの心理学者ヘニングが、すべての味は、甘味・酸味・塩味・苦味の4つの基本味を頂点とする正四面体の中のいずれかの点であらわせるという「味の正四面体説」を提唱したが、同時期に、日本の池田菊苗が「うま味」を加えた5基本味を発表し、いまでは、「うま味物質だけに反応する味神経線維や大脳皮質ニューロンが存在すること」(岩堀2011)などにより、5基本味が定説となっている。 マイナスの味、すなわち排斥すべき味のうち、苦味は、植物のアルカロイドをはじめ毒物の味であり、酸味は、腐敗したものの味である。 プラスの味、すなわち追い求めるべき味のうち、甘味はエネルギー源の糖分の味であり、塩味は食塩などミネラルの味である。うま味は、たんぱく質や核酸に富んだ細胞の原形質成分に多く含まれ、たんぱく質が豊富かを示す味である。 なお、カレーの辛味は、味覚器で感じる味ではなく、口腔粘膜の痛覚受容器を刺激しているため感じる「味」である。 どの味の受容体をもっているかは、動物によって異なり、例えば、ネコは砂糖に対する受容体がないため、砂糖を口に入れても何の味も感じないという。 塩分は、塩味を感じる味覚を通してだけでなく、甘さやうま味を感じる味覚が塩味によって敏感になることによっても摂取が促され、さらには麻薬的な効果によってなおさら塩分摂取が促進されるという。それほどまでに塩味を求める感覚が鋭敏になったのは、海から塩分を補給するのが容易だった長い間の水生動物としての生活から離れ、陸上動物へと進化し、生理上不可欠な塩分の補給が困難になった時期以降だと考えられる。さらに、農耕がはじまり、カリウムを多く含む穀物や野菜を摂取するようになると、腎臓が必要以上のカリウムとともにナトリウムを同時に排出してしまうため、ヒトは、なお一層塩分を追加補給せざるを得なくなった。そして、生産や流通の発達により食塩の入手が誰でも容易となった現代では、このようにして形成された食べもののおいしさを増す調味料としての威力の大きさから塩分を控えることは難しく、その結果、過剰摂取に陥ることになったのである(NHK「食の起源第2集 「塩」人類をとりこにする“本当の理由”」2019.12.15放映)。 苦味はその他の味より複雑な味覚であるようだ。「塩味、甘味、酸味、そしてうま味の受容体の種類は、それぞれ1種類か多くても2種類です。ところが苦味の受容体だけは25種類。受容体の種類が突出しています。なぜ苦味だけ、と不思議に思うかもしれませんが、これは人間が生きる上で必要なリスク管理能力なのです。苦いものは毒物だから吐き出さねばなりません。だから多様な苦味受容体が必要なのです」(伏木亨「だしの神秘」朝日新書、2017年、p.55〜56)。苦味を含んだ薬味やスパイスによる味つけが何ともいえない妙味なのはこのためかもしれない。 東大と理研の研究チームは味蕾に含まれる味細胞と周辺の細胞の違いをもたらす遺伝子の網羅的解析の結果、甘味、苦味、うま味を感じる細胞は、酸味を感じる細胞にはない共通のたんぱく質「Skn-1a」を有しており、このたんぱく質を作る遺伝子を欠くと酸味を感じるのみとなることから、両者は共通した前段階の細胞から分かれてできることが分かったという(毎日新聞2011.5.16夕刊)。生物における味覚の進化を知るきっかけとなる発見であると考えられ、興味深い(東京大学農学生命科学研究科プレスリリース2011.5.16参照)。 生物における味覚の進化には、退化もふくまれる。これまでのゲノム解読の研究によると、鳥類の多くが舌で「甘み」を感じるセンサーとなっている受容体たんぱく質の遺伝子を失ったされており、さらに南極に生息するコウテイペンギンやアデリーペンギンは、恐竜絶滅後の6000万年前頃に出現したペンギンの祖先から約2300万年前に種として分化するまでの間に、「苦み」や「うまみ」の受容遺伝子も働かなくなり、今では、5つの基本味のうち、「塩味」と「酸味」しか分らなくなったようである(毎日新聞2015年2月18日夕刊)。「甘みや苦み、うまみの信号を脳神経に伝えるのに必要なたんぱく質が極寒の環境では機能しなかったり、滑りやすい魚などの餌をとにかく捕らえて丸のみするようになったりしたことが原因の可能性がある」(同)。私が読んだ同じ新聞記事の埼玉版では、丸のみするようになったから味覚が失われたのか、味覚が失われたから丸のみするようになったのかは分らないという但し書きが付け加えられていた。 脊椎動物の進化の中で人類に至る系譜ではうま味や甘みを感じる遺伝子を退化させてきたらしい。「TASIR」という遺伝子の複数の組み合わせでうま味と甘味の味覚受容体が構成されるが、近畿大の西原秀典教授(ゲノム進化学)らによる33種の脊椎動物のゲノム解析によれば、「TASIR」遺伝子はこれまでの定説のようにヒトなどの脊椎動物共通で3種ではなく、種によって計11種あることが分かり、しかも魚類段階では9種と多かったのが人類に至る進化で退化したことも明らかとなった。 「味覚受容体は、生きものが必要な栄養源を取り入れる上で重要な仕組みです。たとえば、哺乳類より原始的な特徴を持つ魚類のポリプテルスやゾウギンザメは、哺乳類が感知できないアミノ酸を取り込むことができますが、それらはいずれも体内で作れない必須アミノ酸ばかりでした。生存していく上で重要だったと考えられます。 では、人を含む哺乳類はなぜこうした遺伝子を失ってしまったのでしょうか。西原さんはこう指摘します。「視覚や嗅覚の発達や、知能が発達して経験から口に入れる前に必要な栄養源を識別できるようになったのでは」。つまり、多数のうま味や甘味の受容体は進化の過程で不要になったということです」(東京新聞「フロンティア発」2024.1.14)。 作法や心意気を重視し味を軽視する関東の「食通」思想と味そのものを重視する関西の「美食」思想が対比されることがあるが(図録7840)、脊椎動物の進化の中で「美食」から「食通」へ変化してきたことになる。 もっとも、食べてみなくとも栄養の存在を流れてくる化学物質から味覚として察知できた水生動物だった頃とは異なり、陸上動物になると、食べてみないと分からなくなった味覚より、遠くからでも察知できる嗅覚の方が重要となり、味覚の方は衰えたと単純に考えた方がよいようにも思える。 人類、そして日本人の味覚について、また5基本味が定説となるまでの研究史については、図録0214、図録0216参照。 ここで取り上げている特定の動物種は、トラザメ、ナマズ、ヘビ、カナヘビ(一部のトカゲ)、ニワトリ、ハト、ムクドリ、アヒル、オウム、クジラ、カモノハシ、ナマケモノ、アルマジロ、ネコ、コウモリ、乳児、成人、ブタ、ヤギ、イエウサギ、ウシである。 (2011年2月14日収録、3月28日上野吉一引用追加、5月18日味細胞最新研究の紹介を追加、2015年2月19日ペンギンの味覚研究記事紹介、2017年4月19日伏木2017から引用、2019年11月3日トラザメ、コウモリ追加、12月15日塩味の魅力の由来、2024年1月14日「TASIR」遺伝子の退化)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||