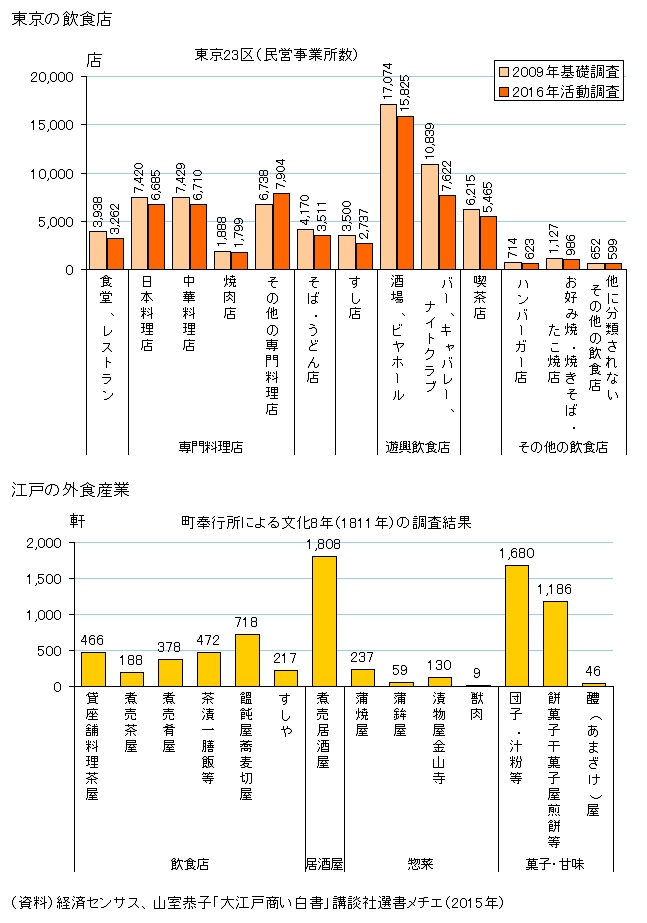
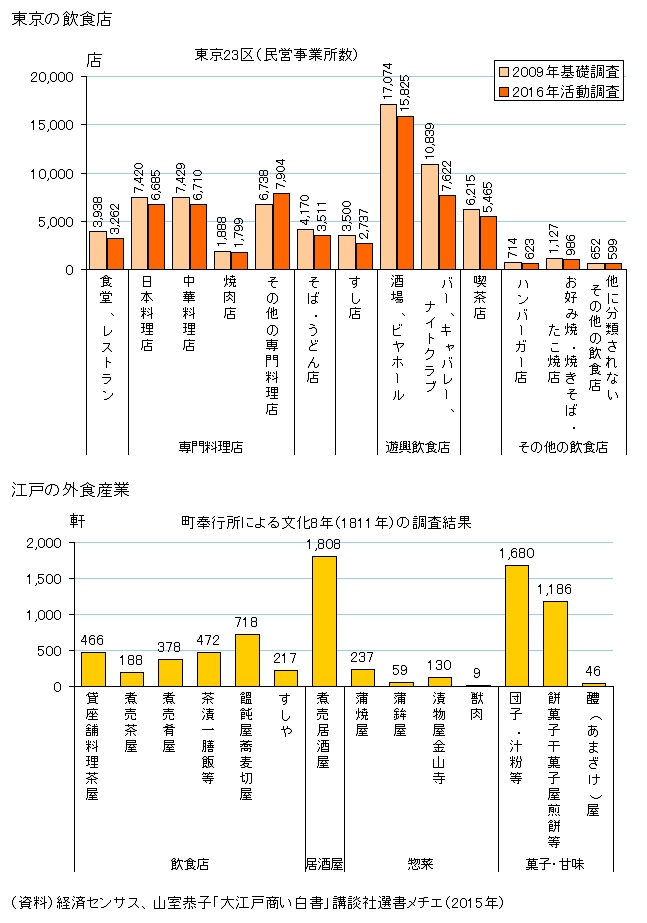
| 1.東京の飲食店 ここでは、経済センサスによる東京(23区のみ)の種類別の飲食店数、及び町奉行所調べの200年前の江戸における業種別の外食産業軒数を掲げた。 産業分類上、飲食店は、かつては食事の提供を中心とする「一般飲食店」と遊興あるいはアルコールの提供を中心とする「遊興飲食店」に区分されていた。現在の分類は下表に掲げた。図録5247でふれたように日本標準産業分類が改定となった。これに伴い、2008年度以降は料亭が遊興飲食店から専門料理店に区分が変わり、ラーメン店が中華料理店から独立し、朝鮮料理店が焼肉店でなくその他の専門料理店に仕分けられるといった変更が行われた。ただし、図に示した経済センサスの分類では、ラーメン店は中華料理店に、料亭はその他の専門料理店に含まれている。 なお、2006〜19年の7年間に全般的に飲食店数が減少しており、例外は種々のエスニック料理店を含む「その他の専門料理店」だけである。昔ながらの個人経営店が高齢化で引退し、チェーン店が増えているのと在京外国人が増加している影響だと考えられる。
東京の飲食店のうちいわゆる飲み屋(呑み屋)と呼ばれる酒場、ビヤホール、バー、スナックなどが2万3千店(2016年、以下同様)と非常に多く立地しているのに、まず、驚く。大衆酒場、ビヤホールでは料理も大きな位置を占めているほか、焼鳥屋やおでん屋がお酒が欠かせないということで酒場、ビヤホールに分類されている点は注目される。
一般料理店の中で最も多いのは中華料理店6,710店であり、自国料理の日本料理店の6,685店とほぼ同じ数である。西洋料理店や朝鮮・韓国系、インド料理などその他エスニックを合計すると日本料理店は少数派ともいうべき存在であり、自国料理店が多くを占める海外諸国と比較して日本の大きな特色となっている(ソウルの料理店の内訳を参考のため下に示した。朝倉敏夫「世界の食文化〈1〉韓国 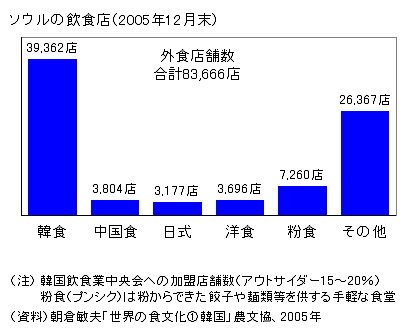 もっともすし店やそば・うどん店も多く、これらは日本料理店の一部ともいえる。そこで日本料理系と海外料理系の合計を算出すると以下の通りである(カッコ内は2009年)。
ただし、家庭料理でも同様の状況であり、これをもって「日本料理は負けている」という見方もあるだろう。例えば、これが、世界の食べ物に精通している関西系の学者が参加した論集・対談集の石毛直道編「世界の食事文化 中華料理店には日本化したラーメン店が多く含まれており、即席ラーメンを日本が開発し、またカレーもいまやおふくろの味となっていることにもあらわれているように、海外料理系の多くが日本料理となっている点から日本料理は海外料理を同化して発展しているのだという観点もありうるだろうが、料理体系としてはやはり日本料理が劣勢にあることは確かであろう。 また、近年、海外ですしや魚食など和食ブームが巻き起こっており、外国での見直しの影響で日本料理が復活するきざしもある。 海外料理系の進出が本格化したのは明治以降である。それ以前の江戸時代に日本の料理店はどんな分布を示していたかを示し、参考にするとしよう。 2.江戸の外食産業 江戸の飲食店数(1811年)
19世紀前半の江戸はおそらく当時の世界で最も飲食店が密集していた都市だったろうと食文化人類学の石毛直道は言っている。その際の根拠資料がここで掲げた江戸の飲食店数データである。肩を並べるのは北京ぐらいだっただろうが北京の飲食店数については資料が見つからないというのだ。19世紀中葉、京都や大阪ではひとかどの者は行楽などの際に必ず弁当をもって出掛ける気風を持っていた(京都では家でつくった弁当、大阪では料理屋につくらせた弁当)。これに対して江戸ではあらゆる階層の者が手ぶらで出掛けて外食すると言われていた。このことからも江戸の外食都市ぶりがうかがえるという(石毛直道「日本の食文化史―旧石器時代から現代まで 江戸の町において急増した飲食店など食物商いの店舗数を新規参入禁止により抑制する方針を1804(文化元)年に打ち出した町奉行所は、その理由として奢侈禁止をあげているが、おそらく防火上の懸念も大きかったのではないかと考えられる。奉行所は、このため、文化・文政期(1804〜30年)に6000軒以下に抑えるという目標をたてるとともに、裏づけとして町年寄を通じた実態調査を毎年のように行った。外食産業の内訳が分かる文化8年(1811年)の調査結果から業種別の軒数をグラフにした(飯野亮一「居酒屋の誕生: 江戸の呑みだおれ文化 一番軒数が多いのは、現代と同じように、居酒屋の1,808軒であるが、団子・汁粉などの菓子・甘味屋の多さも目立っている。 居酒屋の展開
煮売居酒屋は、飲酒(居酒といった)をさせる酒屋、また江戸中期にそれが本業化して出現した居酒屋が酒の肴を充実させたため、明暦大火(1657年)後にできた煮売茶屋(下にもふれるような煮物を中心に簡単な食事と湯茶・酒を提供する茶店)と提供サービスが類似してきて、ひとつのものと考えられるようになった外食産業業種である(飯野(2014)、松下幸子氏による書評)。 一説に居酒屋のルーツは鎌倉から来た材木商たちが家康の江戸築城に使う建築部材を取り仕切っていた鎌倉河岸で1596(慶長元)年に酒屋兼量り売りの一杯飲み屋をはじめた「豊島屋本店」(現在も酒問屋兼地酒屋として存続)といわれる(図録5407参照)。飯野(2014)によれば、豊島屋がブレークしたのは1736(元文元)年に清酒と豆腐田楽を原価で安く提供し、その結果生じた空樽を売って利益とする新商売が当ってからであり、この頃に、酒屋が居酒屋的となったとされる。 下図は江戸時代の豊島屋本店がひな祭り前に売り出した白酒が女性の間でヒットし列をなした様子を描いた江戸名所図会(毎日小学生新聞記事2021.2.23より)。 当時の江戸の町人人口(約50万人、図録7850参照)から人口千人当たりの居酒屋数を計算してみると3.6店となる。現代の東京23区の昼間人口は1,171万人(2010年国調)なので、人口千人当たりの酒場・ビアホールの数は1.5店ということになる。居酒屋密度は現代より倍以上高い計算である。現代の呑み屋の方が収容人数は多かろうから不思議ではないが、それにしても人口比では現代以上に呑む所が多かったというのは驚きである。 飯野(2014)は19世紀前半頃の江戸市民の清酒の消費量を一日155mlと計算し、現代の東京都民のビールを含む酒消費量一日301mlと比較して摂取アルコール量だとほぼ同等と考えている。量ははっきりしないが清酒とは別に飲まれていた濁り酒(どぶろく)も加えればなおさらであるともしている。もっとも江戸人の飲酒好きは有名だったようなのでこれは日本全体の状況とはいえないらしい。大阪に住む狂歌師筆彦が撰した咄本『軽口筆彦咄』(1796(寛政7)年)によると「江戸の呑みだをれ京の着だをれ。大坂はくひだをれ」と三都が比較されているのでとりわけ江戸には居酒屋が多かったのであろう(飯野前掲書、p.99〜100)。 こうした江戸の飲食店の多さは、手軽にはじめられる商売だった側面が大きいという。「江戸町触集成」の資料によれば、「大火の後に類焼で焼け出された町民のことを考えるとヘタに飲食店を禁じると商人たちが飢えてしまう」という記述があることからもその点がうかがわれるのである(山室前掲書、p.157)。 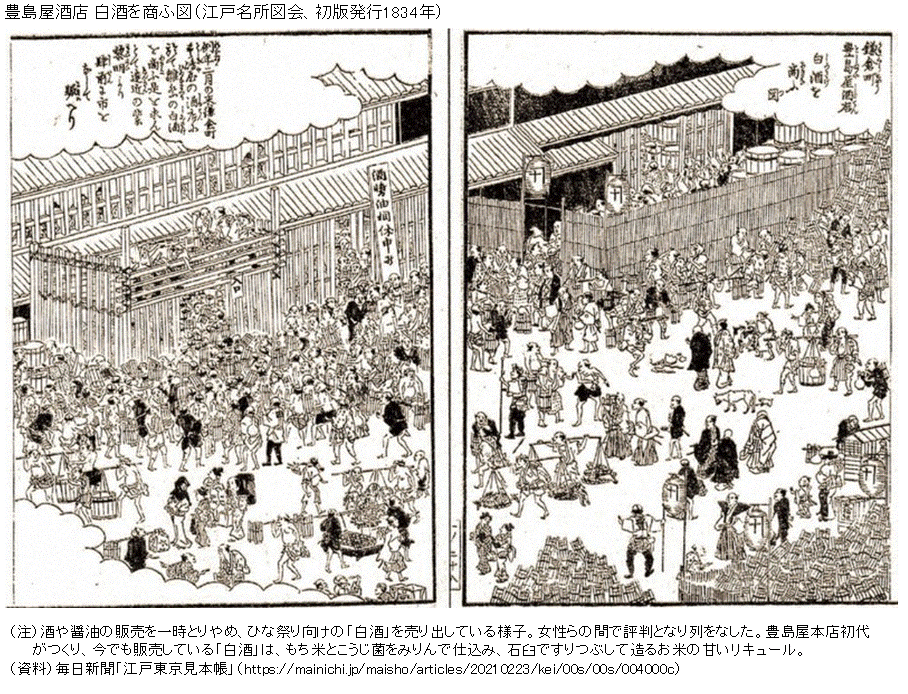 外食店の多様な展開
江戸の外食店は、当初の振り売り、惣菜屋に食堂、居酒屋が加わり、専門料理店やレストランも生れていった。この過程について、要点を記しておこう。 原田信男「江戸の食生活 煮売店は近世後期にかけてさまざまな形態の店が増えたようである。幕末の風俗誌である「守貞謾稿」(1853(嘉永6)年、1867(慶応3)年までの追記あり)は、江戸にあって京阪にない生業の1つとして、「菜屋」(さいや)をあげ、これについて次のように述べている。 「江戸諸所往々これあり。生あわび・するめ・刻するめ・焼豆腐・こんにゃく・くわい・蓮根・牛蒡・刻牛蒡等の類を醤油の煮染(にしめ)となして、大丼鉢に盛り、見世棚にならべこれを売る。煮豆を兼ねたるもあり。」(「近世風俗志―守貞謾稿 (1) 」 岩波文庫、p.187) これは、今でいえば惣菜店にあたるものであるが、一方で、茶店が酒や煮物などを出すようになって、料理店がはじまる。「守貞謾稿」では、「茶漬屋」の紹介の中でそうした経緯が語られている。 「『事跡合考』に曰く、明暦の大火後、浅草金竜山(今の待乳山を云ふ)の門前の茶屋に始めて茶飯・豆腐汁・煮染・煮豆等を調へ、奈良茶と号せしを、江戸中端々よりも、金竜山のならちゃくひに往かんとて、ことのほか珍しきことに興ぜり。それより追々、さまざまの善き膳店出来しより、いつしかかの聖天の山下の奈良茶衰微に及べり、云々。右の奈良茶、皇国食店の鼻祖とも言ふべし。」(同上、p.198) 料理としては、湯豆腐、あんこう汁、ねぎま(まぐろと葱を煮て食べる料理)、まぐろの刺身、ふぐ汁、がん鍋、しゃも鍋などが人気メニューとしてヒットし、煮売茶屋や居酒屋のメニューとして取り入れられていった。危険を恐れながらもふぐ汁を賞味する人が増えた点については文明批評の対象ともなった。平賀源内は次のように嘆いているという(飯野前掲書、p.255〜256)。 「惣じてむかしは、人間も質朴にありし故、毒といふものは喰はぬ事と心得、河豚を恐るる事蛇蝎(じゃかつ、へびとさそり)のごとくなりしが、次第に人の心放蕩になりゆき、毒と知ってこれを食す。人に君たる方(お上)、これを憂ひ給いて、河豚を喰ふて死じたる者は、そお家断絶とまで律(きまり)をたて」たが、その効果はなく、今や、「ふぐや、ふぐや大道を売り歩行き、煮売店にも公(おほやけ)に出し置く事、上をかろんずるの甚だしき」(『根南志具佐(ねなしぐさ)』1763(宝暦13)年) こうした煮物茶屋、茶漬屋、煮売居酒屋などとともに、屋台から発展した鰻蒲焼屋、うどん・蕎麦屋、すし屋、天ぷら屋などが加わり、現代につながる多様な飲食店が江戸に増えていった。 大阪生まれで30歳で江戸に移った喜田川守貞が著した「守貞謾稿」は京阪と江戸との対比がちりばめられているのが特徴だが、幕末の段階の江戸における飲食店の多さを次のように印象深く記している。「江戸は京阪より諸小賈多く、特に鮨・蕎麦の二店大略毎坊これあり。湯屋・髪結床も大略毎坊これあり。この四戸なき所を稀とす。すし・そば店に次いで餅・菓子店多し。」(同上、p.294)ここで賈(こ)とは商売・商人のことである。まさに冒頭の図のデータを裏打ちしている記述である。 ただし、煮売茶屋が188軒とやや少ない印象がある。飯野(2014)は、煮売茶屋の多くが煮売居酒屋にシフトし、ここでの煮売茶屋は酒を置いていないか、テイクアウト専門の店のみがカウントされていると見ている。また、図では蕎麦とすしの比較ではすしが相対的に少ないが、これは調査年である1811年以降に、新たに握り鮨が登場して、すし店も増えたからと考えられる。江戸では「もとは京阪のごとく箱鮨。近年はこれを廃して握り鮨のみ」(同上、p.293)。図録7762 【コラム3】「江戸末期における東西のすし」参照。 なお、18世紀中葉には、本格的レストランというべき存在として、座敷や庭を備えた料理茶屋(貸座敷とも)が登場した(原田2003)。そして江戸では、京阪にはないコース料理システムが新しいビジネスモデルとして生み出された。 「守貞謾稿」では、料理茶屋についても東西比較し、京阪は客の人数の多少にかかわらず肴を多く出して金を使わせるのに対して江戸では「会席風」と名付けられた人数に応じたリーズナブルな価額の料理提供を行うとしている。会席のコースは名のある料理茶屋では以下の通りであり、このスタイルが現在にまで受け継がれていることが分かる。 「肴数は減ぜず。ただ京阪のごとく各肴を多くせず、まづ第一みそ吸物、次に口取肴、次に二つ物(甘煮と切焼肴等各一鉢)、次に刺身、次にすまし吸物あるひは茶碗もの、以上酒肴備はり、次に一汁一菜の飯あるひは一汁二菜の飯なり。(中略)前後とも上々の煎茶に上製の口取菓子を添へ、また需めに応じて美なる浴室にて浴させ、余肴は笹折に納めて客の携へ帰るに備へ、夜に至れば、用ひ捨ての小田原提灯を出す。これ皆、一人大略銀十匁以下の費中なり。京阪は前後の茶に菓子を出さず、浴事なく、余肴は竹皮に包み、提灯は得意の客にあらざれば貸さず。また用ひ捨てにあらず。次の日取りに巡る。しかも一人分価銀二、三十匁なり。(中略)天保初め比以来、会席料理と云ふこと流布す。」(同上、p.207、209) さらに興味深いことに、割り箸を用いるかどうかで一般料理店と高級料理店が見分けられることが「守貞謾稿」の「鰻飯」の項で紹介されている。 (鰻飯屋では)「必ず引き裂き箸を添ふるなり。この箸、文政(1818〜29年)以来比より、三都ともに初め用ふ。杉の角箸半を割りたり。食するに臨んで裂け分けて、これを用ふ。これを再用せず。浄きを証すなり。しかれどもこの箸、また箸工に返し、丸箸に削ると云ふなり。鰻飯のみにあらず、三都諸食店往々これを用ふ。かへって名ある貸食店には用ひず。これ元より浄きが故なり。」(同上、p.212) 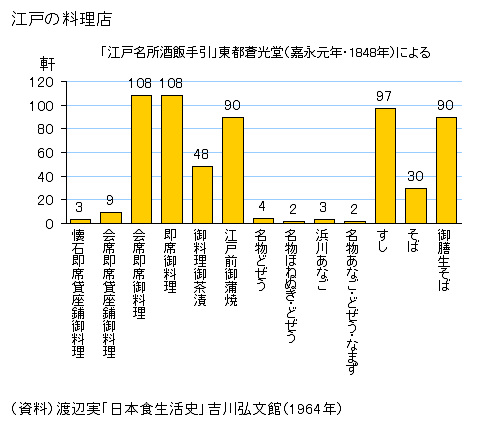 江戸の料理店については、さらに、別資料による種類別のデータを掲げた(渡辺実「日本食生活史
これは、江戸末期に出版されたレストランガイドである「江戸名所酒飯手引草」で紹介されている料理店の軒数である。ミシュランガイドが刊行される一世紀以上前から江戸ではこうした案内書で美食を楽しんでいたのである(石毛直道2015)。諸国から来た不案内の者へのガイドとしてつくられた冊子なので必ずしも上記のデータとは異なり、総ての料理店を尽くしたものではないが、どんな料理店が多かったかの概観は得られる。 中級料理ともいうべき会席即席料理と即席料理が約3分の1、大衆料理ともいうべきすし、そばの店が約3分の1を占めていた。この他、鰻の蒲焼きやドジョウ料理といった専門店もかなりあった。なお、会席料理はコース料理、即席料理は一品料理のことをいう。 うなぎの蒲焼店については「別の資料から、当時の江戸市街では約1000軒のウナギ料理店が営業していたことがわかる。そのなかから、おすすめの90軒を選択しているのである」(石毛直道2015、p.157)。 そば屋は合計120軒、すし屋は97軒であり、現在のそば・うどん店とすし店の相対比率と同じぐらいであった点も興味深い。冒頭の1811年データと比較すると、蕎麦屋とすし屋の対比ですし屋が多くなっており、上記の通り、この間に、大きくすし店が増えたのではないかと思われる。 上記の外食産業沿革の記述とダブル面もあるが、江戸の料理店に関する文献を要領よくまとめている国会図書館の資料を以下に引用することとする。
(2010年1月21日収録、1月30日ソウル飲食店グラフ追加、2014年6月24日更新、2015年8月7日江戸の外食産業軒数新データ掲載、旧資料「江戸の料理店」も参考資料として継続掲載、8月9日補訂、8月17日煮売居酒屋のおこりコメント追加、9月1日守貞謾稿などにより外食産業沿革の記述追加、9月3日補訂、9月7・9日補訂、10月25日豊島屋コメント追加、2016年4月24日石毛直道引用、2019年1月13日経済センサス更新、2024年1月7日豊島屋本店江戸名所図会)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||