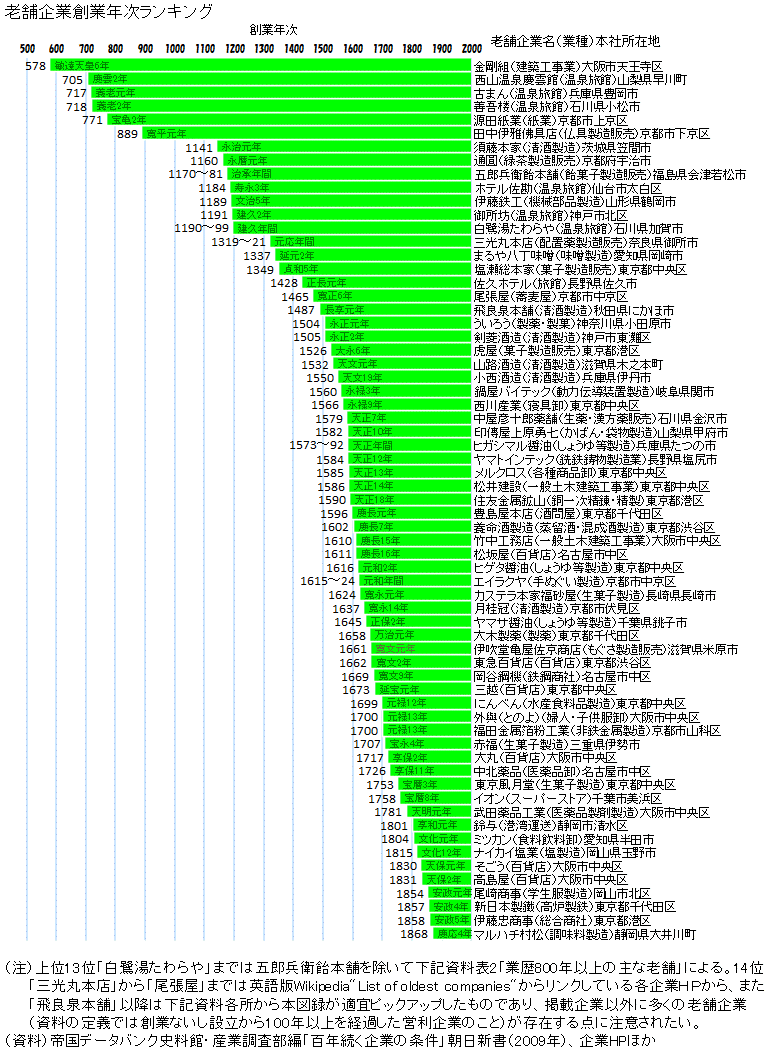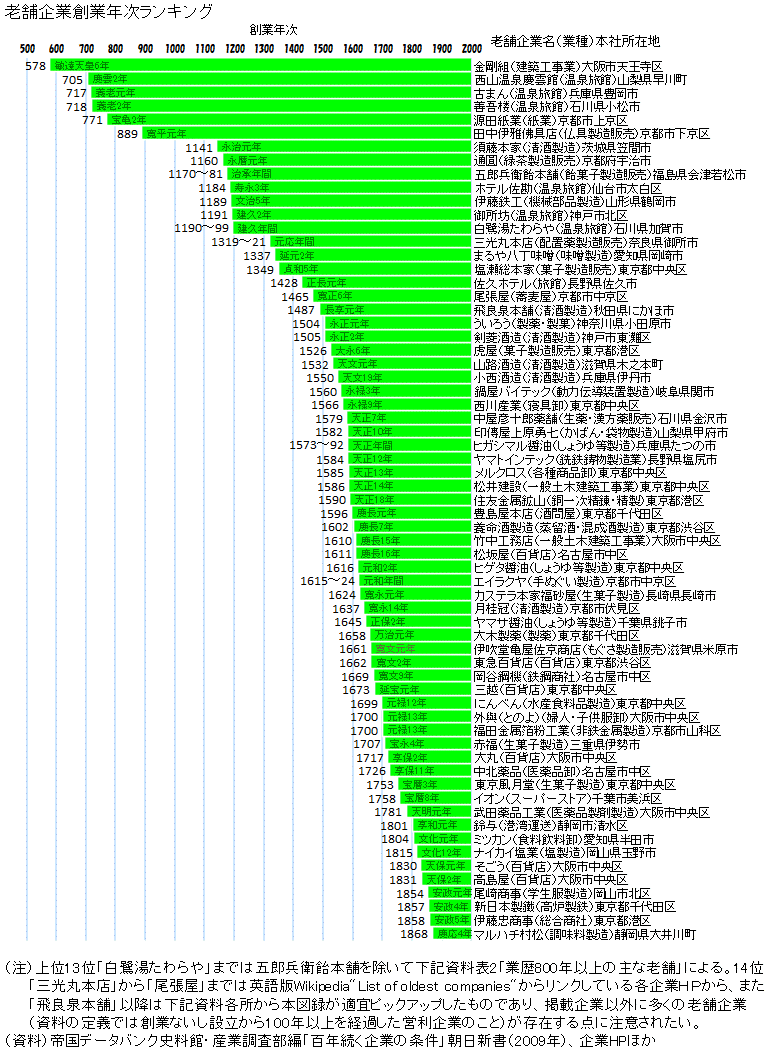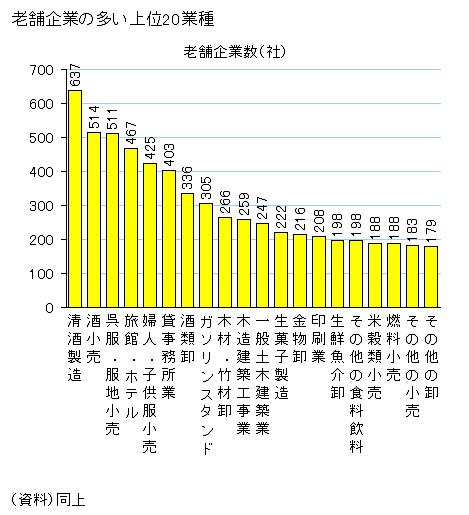| 創業年 |
企業名 |
所在地 |
業種 |
備考 |
| 578 |
金剛組 |
大阪市天王寺区 |
建築工事業 |
聖徳太子に百済から招かれた宮大工初代金剛重光が四天王寺を建立して以来、寺院建築に携わる。2006年の経営危機で新しい金剛組が営業権の譲渡を受け、宮大工も引受けて発足し、企業存続 |
| 705 |
西山温泉慶雲館 |
山梨県早川町 |
温泉旅館 |
武田信玄や徳川家康の「隠し湯」といわれる |
| 717 |
古まん |
兵庫県豊岡市 |
温泉旅館 |
兵庫県城崎温泉「千年の湯 古まん」経営。湯治場として創業 |
| 718 |
善吾楼 |
石川県小松市 |
温泉旅館 |
石川県粟津温泉「法師」経営。湯治場として創業 |
| 771 |
源田紙業 |
京都市上京区 |
紙業 |
戦前まで水引を製造。現在祝儀用品、紙製品を取り扱い |
| 889 |
田中伊雅佛具店 |
京都市下京区 |
仏具製造販売 |
主に真言宗寺院向け仏像、華鬘、厨子、灯籠などを製造販売 |
| 1141 |
須藤本家 |
茨城県笠間市 |
清酒製造 |
現在日本で最も古い酒蔵。「郷の誉」ブランド |
| 1160 |
通圓 |
京都府宇治市 |
緑茶製造販売 |
初代は現在も本店がある宇治橋のたもとで茶を供したといわれる |
1170
~81 |
五郎兵衛飴本舗 |
福島県会津若松市 |
飴菓子製造販売 |
前九年の役に八幡太郎義家に従い下向し土着したという長谷川家は変わらぬ味と製法を守り現在38代目。家には文治4(1189)源義経公が平泉落ちの途中に立ち寄り飴を所望した際の代金の借証文(武蔵坊弁慶自筆)が残る |
| 1184 |
ホテル佐勘 |
仙台市太白区 |
温泉旅館 |
仙台市秋保温泉「ホテル佐勘」経営。伊達家湯浴み御殿として栄える |
| 1189 |
伊藤鉄工 |
山形県鶴岡市 |
機械部品製造 |
鋳物師として創業。現在は空調機器用の特殊バルブなどを製造 |
| 1191 |
御所坊 |
神戸市北区 |
温泉旅館 |
神戸市有馬温泉で「陶泉 御所坊」経営 |
1190
~99 |
白鷺湯たわらや |
石川県加賀市 |
温泉旅館 |
平安~鎌倉時代に再興された石川県山中温泉「白鷺湯 たわらや」経営 |
1319
~21 |
三光丸本店 |
奈良県御所市 |
配置薬製造販売 |
三光丸の前身「紫微垣丸」と名付けられた薬つくられる。1336年、後醍醐天皇から「三光丸」の名を賜り、「紫微垣丸」の名に代えて使用しはじめ、越智氏の中で米田家が三光丸を継承して現在に至る |
| 1337 |
まるや八丁味噌 |
愛知県岡崎市 |
味噌製造 |
太田弥治右エ門が元岡崎市八帖町で味噌製造をはじめる |
| 1349 |
塩瀬総本家 |
東京都中央区 |
菓子製造販売 |
初代林浄因が中国より来日、奈良に住し日本で初めて餡入りの饅頭を作り売り出す |
| 1428 |
佐久ホテル |
長野県佐久市 |
旅館 |
紀伊国造三十八代末裔の望月城の望月河内守滋野朝臣光尚が現在の佐久ホテルの場所で領主として宿泊や料理を提供(当館の祖)とされる |
| 1465 |
尾張屋 |
京都市中京区 |
蕎麦屋 |
菓子司として始まり次第に、そば処としても、京の町衆に親しまれるようになった |
| 1487 |
飛良泉本舗 |
秋田県にかほ市 |
清酒製造 |
「飛良泉」ブランド |
| 1504 |
ういろう |
神奈川県小田原市 |
製薬・製菓 |
始祖である帰化中国人陳延祐が元官職名から陳外郎と称したことから家名が生じた。足利義満の招きで京都に移った二代目が両方ともに「ういろう」と呼ばれるようになったくすりとお菓子を作り出し、これらが1504年に分家し、北条早雲の招きで小田原に移った小田原外郎家により受け継がれている。お菓子のういろうと同様の蒸し菓子が名古屋、京都、山口など各地で名産品となっている。二代目市川團十郎の自作自演でヒットした「外郎売」は去痰をはじめとして万能薬として知られたくすりのういろうの効能を言い立てる演目 |
| 1505 |
剣菱酒造 |
神戸市東灘区 |
清酒製造 |
「剣菱」ブランド |
| 1526 |
虎屋 |
東京都港区 |
菓子製造販売 |
京都の御所御用菓子商人として創業、遷都とともに東京へ
■虎屋の歩み(朝日新聞(2017年1月9日)
| 室町時代後期 |
京都で創業 |
| 1695年 |
現存する虎屋最古の菓子見本帳を作成 |
| 1805年 |
9代当主の光利が「掟書」をまとめる |
| 1869年 |
遷都にともなって東京に進出 |
| 1924年 |
店頭での販売を開始 |
| 1962年 |
東武百貨店池袋本店に出店 |
| 1980年 |
パリに出店 |
| 1991年 |
17代当主、黒川光博氏が社長就任 |
| 1992年 |
社員自己啓発支援制度「Egg21」を導入 |
| 2003年 |
トラヤカフェ |
| 2007年 |
とらや東京ミッドタウン店開店。静岡県御殿場市にとらや工房を開設 |
| 2016年 |
トラヤカフェ・あんスタンドを出店 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1532 |
山路酒造 |
滋賀県木之本町 |
清酒製造 |
「北國街道」ブランド |
| 1548 |
吉乃川 |
新潟県長岡市 |
清酒製造 |
「吉乃川」ブランド(2016.3.29に図からは削減) |
| 1550 |
小西酒造 |
兵庫県伊丹市 |
清酒製造 |
「白雪」ブランド |
| 1560 |
鍋屋バイテック |
岐阜県関市 |
動力伝導装置製造 |
岐阜市にて鋳造業として創業。本家ナベヤ(鋳物、精密治具)と同根企業 |
| 1566 |
西川産業 |
東京都中央区 |
寝具卸 |
近江商人西川仁右衛門が創業。近江の蚊帳を商って以来「睡眠」にこだわり |
| 1579 |
中屋彦十郎薬舗 |
石川県金沢市 |
生薬・漢方薬販売 |
山城から金沢に移った中屋家の二代目創業の薬種商に由来する。江戸時代には家伝薬混元丹が広く常備薬として使われたのに加え、前田家伝来の加賀三味薬といわれる紫雪、烏犀円、耆婆万病円の製造販売を許可された。中屋家の旧商家は市に寄付され金沢市老舗記念館となっている |
| 1582 |
印傳屋上原勇七 |
山梨県甲府市 |
かばん・袋物製造 |
鹿革の伝統工芸品「甲州印伝」最古参企業 |
1573
~92 |
ヒガシマル醤油 |
兵庫県たつの市 |
しょうゆ等製造 |
播磨国守護大名赤松一族の家臣片岡治兵衛が、龍野で幾久屋の屋号で醸造を始める。1666年、龍野でうすくち醤油誕生 |
| 1584 |
ヤマトインテック |
長野県塩尻市 |
銑鉄鋳物製造業 |
初代濱伊右衛門清賢が松本領主により相模から招かれ鋳物師として創業。戦後もエクステリア製品、さらにターボチャージャー部品へと転身 |
| 1585 |
メルクロス |
東京都中央区 |
各種商品卸 |
近江商人初代西川勘衛門数吉が滋賀県近江八幡で農産品を商い始めたのが原点。西川商店から改名 |
| 1586 |
松井建設 |
東京都中央区 |
一般土木建築工事業 |
初代松井角右衛門が越中守山城(富山県高岡市)の普請に従事したのが始まり、社寺建築に長い実績 |
| 1590 |
住友金属鉱山 |
東京都港区 |
銅一次精錬・精製 |
住友家の業祖、蘇我理右衛門、京都において銅製錬・銅細工を開業。1691(元禄4年)別子銅山(新居浜市)の稼行開始から住友グループ形成へ |
| 1596 |
豊島屋本店 |
東京都千代田区 |
酒問屋 |
初代が鎌倉河岸(千代田区神田橋付近)で酒屋兼量り売りの一杯飲み屋をはじめたのが「居酒屋」のルーツとされる(図録7840)。当初は上方からの下り酒と豆腐の田楽を売っており、同じく初代が考案したひな祭りの白酒とともに江戸で絶大な人気を博した。明治中期に自社の酒を手掛け、昭和初期の「金婚」、最近の純米吟醸「羽田」など東京の地酒として人気を集める(東京新聞「ジモトのFood」2015.10.23)。 |
| 1602 |
養命酒製造 |
東京都渋谷区 |
蒸留酒・混成酒製造 |
信州塩沢家が開発製造、1603年家康から日本初のブランドともいわれる「飛龍」の印の使用許可を得る。1923年信州の株式會社天龍舘が設立され、塩沢家より養命酒の事業を継承 |
| 1610 |
竹中工務店 |
大阪市中央区 |
一般土木建築工事業 |
織田信長の元家臣、初代竹中藤兵衛正高が名古屋で創業。神社仏閣の造営を業とする。1899年 14代竹中藤右衛門神戸に進出、創立第1年とされる |
| 1611 |
松坂屋 |
名古屋市中区 |
百貨店 |
元織田家の小姓の子孫である伊藤蘭丸祐道が名古屋本町ではじめた呉服小間物商いが最初 |
| 1616 |
ヒゲタ醤油 |
東京都中央区 |
しょうゆ等製造 |
田中玄蕃が千葉県銚子にて溜り醤油の製造販売を始めたのが嚆矢 |
1615
~24 |
エイラクヤ |
京都市中京区 |
手ぬぐい製造 |
麻や綿の着物を扱う太物問屋として創業した永楽屋細辻伊兵衛商店の名称の由来は戦国時代、織田信長から命をうけ先祖が出陣した際、直垂に永楽通寳の紋が入っていたことからといわれる |
| 1624 |
カステラ本家福砂屋 |
長崎県長崎市 |
生菓子製造 |
中国「福」州の「砂」糖などを扱う福砂屋がポルトガル人よりカステラ製造を伝授される |
| 1637 |
月桂冠 |
京都市伏見区 |
清酒製造 |
京都伏見の代表的蔵元。清酒業界2位 |
| 1645 |
ヤマサ醤油 |
千葉県銚子市 |
しょうゆ等製造 |
初代・濱口儀兵衛が「山笠にキ」の暖簾を考えるが、紀州徳川家の船印と同じだったため、キを横向きにした所、サと読めることからヤマサとした |
| 1650 |
タカサゴ |
東京都千代田区竹橋 |
洋食 |
神田三河町にて一膳飯屋・高瀬屋七兵衛として創業、明治に入って高砂屋に屋号変更、1966年パレスサイドビル開業時に移転、カレー屋タカサゴに変更(実際は洋食屋)、現在に至る(神田学会HP)。 |
| 1658 |
大木製薬 |
東京都千代田区 |
製薬 |
近江商人大木口哲が江戸両国に創業し滋養強壮薬「大木五臓圓」を売り出したのが大木製薬などからなる健康産業の大木グループのルーツ |
| 1661 |
伊吹堂亀屋佐京商店 |
滋賀県米原市 |
もぐさ製造販売 |
近江商人松浦七兵衛創業の艾(もぐさ)専門店としてそのまま存続。広重の木曽海街道六拾九次之内柏原に店頭風景。福助人形発祥の店。司馬遼太郎「街道をゆく/近江道散歩」に記述。 |
| 1662 |
東急百貨店 |
東京都渋谷区 |
百貨店 |
日本橋呉服店・百貨店白木屋が1958年電鉄系東横百貨店と合併し現在に至る |
| 1669 |
岡谷鋼機 |
名古屋市中区 |
鉄鋼商社 |
金物商として創業。現在中部地方最大の独立系鉄鋼商社 |
| 1673 |
三越 |
東京都中央区 |
百貨店 |
1683年店頭現金掛け値なし(正札販売)方式をはじめて採用、庶民層まで顧客層を広げる |
| 1699 |
にんべん |
東京都中央区 |
水産食料品製造 |
初代高津伊兵衛が日本橋で、戸板を並べて鰹節と塩干類の商いを始めた年を創業年としている |
| 1700 |
外與(とのよ) |
大阪市中央区 |
婦人・子供服卸 |
近江商人外村与左衛門が創業。当初、麻を商う |
| 1700 |
福田金属箔粉工業 |
京都市山科区 |
非鉄金属製造 |
俳諧師の福田鞭石が京都室町で金銀箔粉商井筒屋を創業 |
| 1707 |
赤福 |
三重県伊勢市 |
生菓子製造 |
伊勢神宮参拝者向けに「赤福餅」を販売 |
| 1717 |
大丸 |
大阪市中央区 |
百貨店 |
下村彦右衛門正啓が京都で呉服商を出発点として両替商を兼営 |
| 1721 |
ホワイトローズ |
東京都台東区 |
ビニール傘製造 |
甲州武田家の血を引く初代武田勝政が江戸に出て「武田長五郎商店」として刻みたばこ卸を創業。4代目から使っていた油紙を使い武士向けカッパの雨具商に進出。油紙と同じ用途として戦後取り組んだビニール製傘カバー製造から1958年頃ビニール傘開発。1964東京五輪の際に米国バイヤーが持ち帰りビニール傘が世界的普及。50社あった国内ビニール傘メーカーは撤退、現在唯一の国産ビニール傘製造メーカー |
| 1726 |
中北薬品 |
名古屋市中区 |
医薬品卸 |
初代中北伊助により創業 |
| 1753 |
東京風月堂 |
東京都中央区 |
生菓子製造 |
初代大住喜右衛門が“大阪屋”を屋号として菓子屋を営んだのがはじまり |
| 1758 |
イオン |
千葉市美浜区 |
スーパーストア |
初代岡田惣左衛門が太物・小間物商「篠原屋」を開業、岡田屋、ジャスコを経て現在へ |
| 1781 |
武田薬品工業 |
大阪市中央区 |
医薬品製剤製造 |
道修町に出てきた長兵衛が薬種仲買商の近江屋喜助の下で奉公したあと「のれん分け」によって独立し薬種商「近江屋」を開いたのが始まり |
| 1801 |
鈴与 |
静岡市清水区 |
港湾運送 |
初代鈴木與平(現社名はこの名前が由来)が駿河国清水湊で船舶を利用した物流業「播磨屋」を創業 |
| 1804 |
ミツカン |
愛知県半田市 |
食料飲料卸 |
中野又左衛門により尾張国半田村で酒造業としてはじまる。創業年は分家して新たな家業として酢の醸造を始めた年。酒かすを使った酢が評判になり、江戸で流行していた握りずしの店に供給するようになった(毎日新聞「もとをたどれば」2016.12.4)。図録0354(すしの歴史)参照。 |
| 1815 |
ナイカイ塩業 |
岡山県玉野市 |
塩製造 |
創業者野﨑武左衛門が倉敷市児島において塩田事業を始めたのが発祥。もと内海塩業 |
| 1830 |
そごう |
大阪市中央区 |
百貨店 |
十合伊兵衛が、大阪の坐摩神社(陶器神社)近くに古手屋(古着屋)「大和屋」を開業。1877年大阪の心斎橋筋に大和屋を移転。十合呉服店と名付けたのがはじまり。 |
| 1831 |
高島屋 |
大阪市中央区 |
百貨店 |
近江の飯田新七が創業。商号は、創業者本家出身地の高島郡(現在の高島市)から |
| 1854 |
尾崎商事 |
岡山市北区 |
学生服製造 |
綿糸卸として創業。1923年に学生服・作業服の大量生産を開始 |
| 1857 |
新日本製鐵 |
東京都千代田区 |
高炉製鉄 |
釜石で、日本初の洋式溶鉱炉の出銑に成功したのがはじまり |
| 1858 |
伊藤忠商事 |
東京都港区 |
総合商社 |
近江商人伊藤忠兵衛が創業。麻布の持ち下りから |
| 1868 |
マルハチ村松 |
静岡県大井川町 |
調味料製造 |
村松善八商店が発足し鰹節製造法の改良に専念したのがはじまり |
| (注)(資料)グラフと同じ |