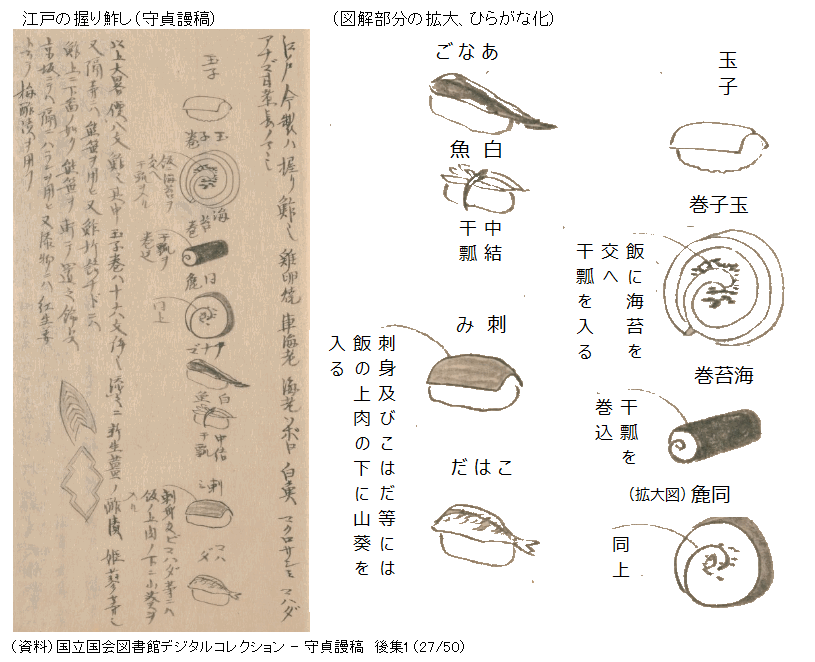
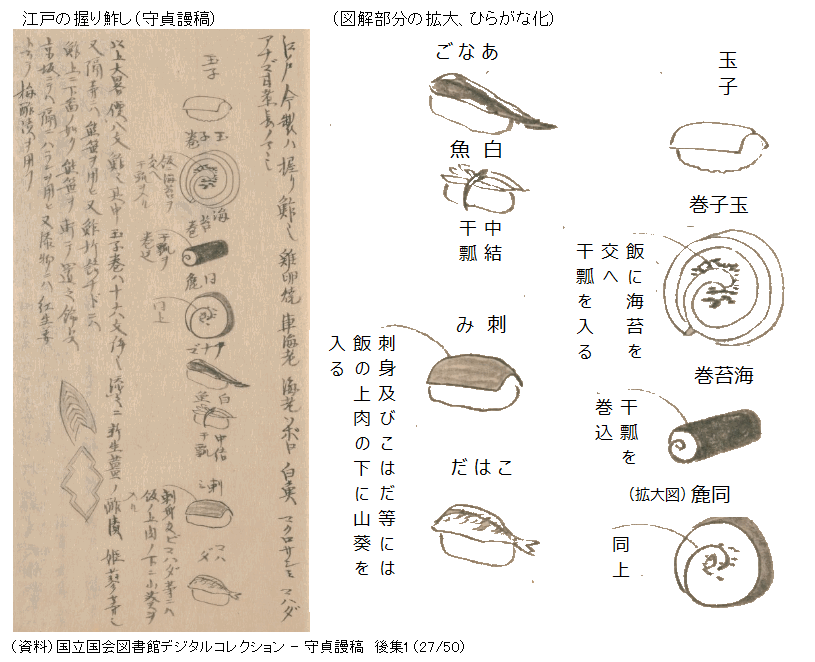
(資料)喜田川守貞『守貞謾稿』、宇佐美英機校訂「近世風俗志」(五)岩波文庫、P109
江戸前の新鮮な魚を使ったとされる江戸前寿司は、そもそも、どんなものだったかを知るため、幕末の風俗百科事典ともいうべき「守貞謾稿」における「握り寿司」の紹介図を掲げた(原図は国立国会図書館デジタルコレクション)。 握り寿司は下の写真のように屋台売りが多かった。江戸前寿司については「守貞謾稿」の別の箇所を引用した図録7762コラムや下の写真を掲載している「江戸前寿司と醤油」サイトも参照。また、江戸前の魚の魚種については図録7838参照。  「地の文」を読みながらこれを見ると、当時の江戸前寿司は、ワサビのはさみかたや甘煮のあなごなど、現在の「握りずし」とほぼ同様のものであったことがうかがわれる。 もっとも、最初に魚の握りずしに先立って玉子寿司や玉子巻、海苔巻(現在のかんぴょう巻き)といった巻寿司が掲げられており、これらが現在のように脇役ではなく主役に近い存在だったということが分かる。また、海苔巻が現在のかんぴょう巻きであるばかりでなく、玉子巻きや白魚の握りにも使われるなど干瓢という食材の役割が大きかったことがうかがえる。 天麩羅は、当時、握りずしと同様に屋台で売られるヒット商品だった。現在、握りずしといえばもっぱら魚介類、そして、天麩羅といえば具は魚介類に限らないが、江戸時代には、にぎり寿司でも魚介類とは限らず、逆に、天麩羅は魚介類だけだった。「守貞謾稿」によれば、「江戸の天麩羅は、あなご・芝ゑび・こはだ・貝の柱・するめ。右の類、惣じて魚類に温飩粉(うどんこ)をゆるくときて、ころもとなし、しかる后に油揚げにしたるを云ふ。菜蔬の油揚げは江戸にてもてんぷらと云はず、あげものと云ふなり」(後集・巻乃一)とある(飯野亮一「すし 天ぷら 蕎麦 うなぎ」ちくま学芸文庫、2016年、p.245、p.270)。 玉子巻、海苔巻は現在普通に売られているものと異なり、「の」の字に巻かれている。「図説江戸時代食生活事典」(1978年)の「海苔巻」の項を担当した「吉野鮨」三代目の吉野曻雄氏は「昔から、東京の海苔巻は細い太いにかかわらず「の」の字に巻くのが原則とされているだけに、芯にした具が一緒くたにならないように巻きあげるのを本筋の技術とした」といっており、図はもともとの姿を示しているといえる。 なお、同項には、関東で幕末以降に、鉄火場のやくざのように身をもちくずしたという意味の「鉄火ずし」として芝エビ鮨が生まれ、それがマグロの鉄火巻に適用され(図録7838)、関西では、明治末期に細巻として「こうこ巻」(たくわん巻)がつくられ、ここからさらにかっぱ巻(具が漬物のキュウリから生のキュウリに変化)が生まれるというかんぴょう巻以降の海苔巻の展開経緯が記載されている。 発祥が名古屋とも江戸ともいわれる稲荷寿司は玉子や海苔の巻寿司のように油揚で巻いた寿司として生まれ、稲荷信仰とからみ、また油っぽいので独自の屋台や振り売りで売られ、わさび醤油で食された。油揚げをキツネが好むとされたことから「お稲荷さん」、「篠田鮨」の名がついた。守貞謾稿での言及は図録0354コラム参照。 いなり寿司(稲荷寿司)については、現在の形が東日本で四角、東日本で三角となった点を含め、図録7839d参照。 篠田統氏は「図説江戸時代食生活事典」の「稲荷鮨」の項で「もとは魚味の代用として油揚を使ったと思われる」と言っている。腐りやすい魚の保存手段として東南アジアで生まれた「すし」は、歴史的、地理的に次々と原型から離れた「似て非なる」新食品として生まれ変わって来たが(図録0354参照)、稲荷寿司は、ついに、魚介類からも完全に離れ、それでもやはり「すし」である点に「究極の寿司」の姿をうかがうことができよう。干瓢巻きも魚の食感を干瓢で代替した点ではかなり大胆な変転だといえるが、まだ、海苔という海産物をまとっている分、原型を保っているのと比べるとその感を強くする。 (2018年7月6日・7日収録、2019年1月27日天麩羅コメント、2021年2月11日いなり寿司の部分が図録7839dとして分離独立)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||