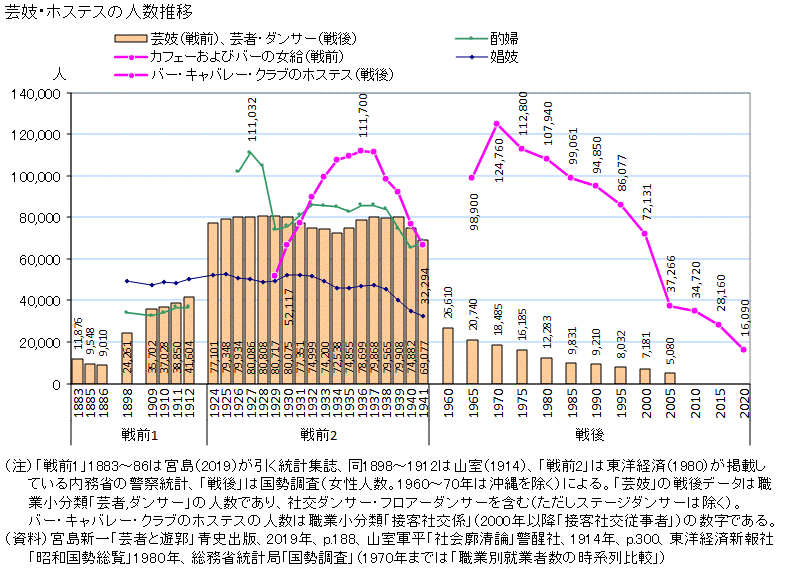
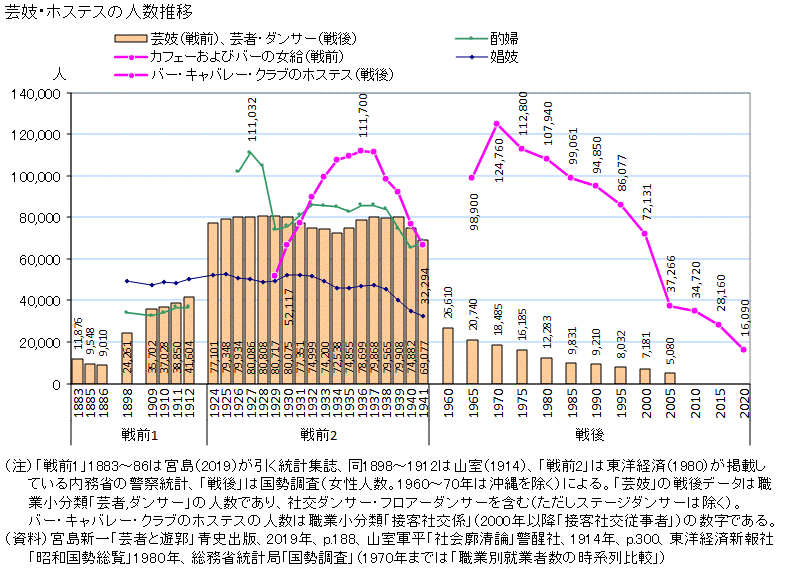
ここでは、芸妓と娼妓、あるいは関連職種の人数推移を戦前は基本的に警察統計により、戦後は国勢調査で追った。 明治期の東京花街の芸妓数は図録7845d参照。昭和戦前期の全国花街の芸妓数は図録7846、図録7847参照。最近の主要花街の芸妓数は図録7845参照。 芸妓は戦前期、明治から大正にかけて大きく増加した。廃娼運動家の山室軍平は「社会廓清論」(1914年)の中で、上図の数字を引き、近年、娼妓と比較して芸妓が驚くほど増加したため、世界漫遊家の間で「日本に往きて芸者を見ざるは、エジプトに往きて三角塔を見ざるが如し」が普通の諺になり、「既に「吉原」を以て世界の噂にのぼって居る日本は、更に「芸者ガール」を以て万国に評判せらるることとなった」(同p.300)と嘆いている。 上図では1912年と1924年との間で系列が途切れており人数推移を確認できない。下に連続したデータが得られる戦前期東京の芸妓数推移を掲げた(1911年時点の各花街の芸妓数は図録7845d)。これを見ると大正年間にほぼ一定のペースで芸妓数が倍増するに至ったことが分かる(1923年の落ち込みは関東大震災の影響と思われる)。なお、京都でも1895年、1913年、1925年に芸妓数はそれぞれ772人、1,423人、1,929人と急増したとするデータもあり(図録7845)、この時期の増加は全国的だったと考えられる。 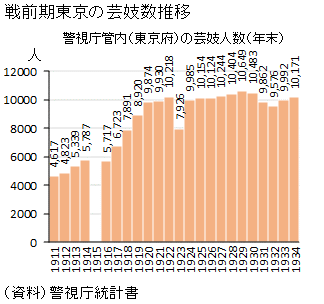 何故、この時期に芸妓数が急増したのかに関する論考には出会っていない。日本では1914(大正3)年に勃発した第一次世界大戦による特需で都市文化が勃興し、1914〜19年の5年間に全国のビール生産量は2.7倍に成長したというが、花柳界においても大正期に入って宴会文化が花開いたため芸妓人数も急増するに至ったのであろう。 経済の進展、社会の近代化とともに拡大した遊興ニーズの受け皿として、さしあたって、花街という指定地制度(二業地、三業地)が活用されるに至った事情もあろう。 明治期後半から芝浦、大森海岸といった海岸部の風光明媚な行楽地や尾久、森ケ崎といった鉱泉レクリエーション地、大正に入って大塚、蒲田など鉄道開通などによる新開地が生まれ、各地で地域振興を目指して花街が誘致された。 また、明治半ば以降、白山、麻布といった新開地や芝神明、葭町、渋谷、浅草といった花街との隣接・混在地において、矢場や銘酒屋の形をとって私娼窟が蔓延しはじめた。これに対して、明治末から大正にかけ、地域における風紀をただす動きや当局が進めた私娼撲滅運動(1916〜17)のなかで、花街としての指定や指定地域拡大が進められた(西村亮彦・内藤廣・中井祐「近代東京における花街の成立」2008年)。 旧来からの花街の繁昌に加え、こうした動きで生まれた新花街や花街域拡大によって芸妓の鑑札を受ける芸者の人数も急速に増えていったものと考えられる。 昭和に入ると芸妓数はほぼ8万人台で横ばいで推移し、鑑札不要の新興勢力である「カフェーの女給」に職域を侵されるようになった(注)。 (注)芸者と女給の違いについて、永井荷風はお歌という芸者の前借金を返済してやった例をあげながらこう言っている。「カッフェーの女給仕人と芸者とを比較するに芸者の方まだしもその心掛まじめなるものあり。如何なる理由にや同じ泥水家業なれど、両者の差別はこれを譬ふれば新派の壮士役者と歌舞伎役者との如きものなるべし」(「断腸亭日乗」1927年9月17日)。 両者に対する警察の取締状況は、銀座のカフェーの女給君江を主人公にした永井荷風「つゆのあとさき」(1931年)の次のような記述を見るとはっきり分かる。仲間の「京子が知合いの待合や結婚媒介所を歩き廻って、結局何不自由もなく日を送っているのを、傍で見ている君江もいつかこれをよい事にしてその仲間にはいった。しかし何分にもその筋の検挙がおそろしいので、京子はもとの芸者になろうと言出す。君江もともども芸者はどんなものか一度はなって見たいと思いながら、鑑札を受ける時所轄の警察署から実家へ問合せの手続きをする規定のある事を知って、やむことをえず女給になった」(岩波文庫、P.12)。 1910年代以降、当時の繁華街だった東京・銀座を中心に喫茶店(カフェー)文化が発展し始めた。当初は文化人たちが交流するサロンのような場所だったが、1923(大正12)の関東大震災後、女給(食事や飲物をサーブするウェイトレス)が客の隣に座り色っぽい接待をする店が急増したため、1929(昭和4)年頃から警察は取り締まりを強化し、1933(昭和8)年にはカフェーを対象とする「特殊飲食店営業取締規制」が出された。そして、酒類を出さず女給による接待サービスを行わない店は「純喫茶」と呼ばれるようになった。 現代においてとかく話題となる女性職業人は「女子アナ」であるが(図録5660)、明治から大正、昭和にかけては、人びとの関心の的が「芸者」、「演劇女優」、「映画女優」、「カフェーの女給」と移り変わっていったと永井荷風は述べている。 「わたくしは教師をやめると大分気が楽になって、遠慮気兼をする事がなくなったので、おのずから花柳小説『腕くらべ』のようなものを書きはじめた。当時を顧ると、時世の好みは追々芸者を離れて演劇女優に移りかけていたので、わたくしは芸者の流行を明治年間の遺習を見なして、その生活風俗を描写して置こうと思ったのである。カッフェーの女給はその頃にはなお女ボーイとよばれ鳥料理屋の女中と同等に見られていたが、大正十年前後から俄に勃興して一世を風靡し、映画女優と並んで遂に演劇女優の流行を奪い去るに至った。しかし震災後早くも十年を過ぎた今日では女給の流行もまた既に盛を越したようである。これがわたくしの近著『つゆのあとさき』の出来た所以である」(「正宗谷崎両氏の批評に答う」(昭和7年)『荷風随筆集(下)』p.205)。 花街の芸妓やカフェーの女給とは別種の存在として私娼窟に非公認の娼婦がいた(非公認なので人数は不明)。 銘酒屋と称した私娼窟は、樋口一葉の「にごりえ」の舞台となった白山のほか、芝神明などでも明治中頃から盛んとなったが、特に東京一の盛り場だった浅草はその本拠地となり、警視庁の撲滅運動後も命脈を保ち、関東大震災(1923年)の前には、再度隆盛を迎え、凌雲閣辺の「12階下の女」として有名になっていた。 しかし、震災による消失の後に警察は取り締まりを強化して再興を許さず、銘酒屋は新たな地を求め、隅田川を越えた亀戸と玉の井へと移転していった(玉の井の一部はのちに鳩の街に再移転)。公認されていた花街や遊郭とは異なり、非公認のこうした低級で悪臭漂う悪徳の私娼窟に哀愁と憩いを見出して好んで通うものも多く、そうした一人である永井荷風は玉の井を舞台に「墨東綺譚」という代表作を書いている。亀戸の私娼窟は日露戦後に生まれた城東花街の隣接地に形成されたが、玉の井は純然たる私娼窟なので芸妓はいない(注)。 (注)公認されているかどうかは税金が制度として課され得るかという違いにもあらわれる。戦時下には私娼の客からも税金に近いものを取り立てようとしたらしい。「人の話に玉の井亀戸の銘酒屋にてはお客に一円の少額債券を買わせる由。これは色町にては芸者娼妓の如く揚代に遊興税を附加すること能わざるを以て政府はその代りとして一円債権を売付けることにせしなりといふ。窮状憫むべし」(永井荷風「断腸亭日乗」昭和17年1月19日)。 1938〜39年頃から、女給、酌婦、娼妓が減少に転じた一因は、彼女らが彼女らに対するニーズが急拡大していた外地に向かったためである。宮島新一「芸者と遊郭」青史出版(2019年)によれば、酌婦は「「国家総動員法」が成立した13年に10万人を切ってからは激減していく。だが、単純に減ったわけでなく、彼女らが海外植民地に向かった可能性が考えられる。同じ昭和13年のことであるが、先の『世態調査資料第4号』に山梨県下での酌婦の不足を語る中で、「最近神戸港から朝鮮、満州、支那に一日平均200人ぐらい渡航し、50人ぐらいは帰るそうです」とある」(同書、p.195)。 永井荷風は日記の中で、資金は出すと軍部に言われ、若き士官を相手にする売春婦を募集し北京に送り、料理屋兼旅館で働かせるやりくりをしていた水天宮裏の待合の女将の言を引用し論評を加えている。「主婦はなほ売春婦を送る事につき、軍部と内地警察署との聯絡その他の事を語りぬ。世の中は不思議なり。軍人政府はやがて内地全国の舞踏場を閉鎖すべきと言ひながら戦地には盛に娼婦を送り出さんとす。軍人輩の為すことほど勝手次第なるはなし」(昭和13年8月8日、「摘録断腸亭日乗」下、岩波文庫、p.58)。なお実際に北京を訪れたこの女将は北支の気候が余りに厳しいのでこの話を辞退したそうだ。 芸妓についても外地に活躍の場を移すものが多かった。この点については外地における芸妓数を示した図録7847d参照。 戦後は娼妓が売春禁止法(1956年)で公的には存在しなくなったし、芸妓も営業自由となったので、両方とも警察統計からは消えた。戦後については、国勢調査の職業別就業者数で芸者・ダンサーと接客社交係の推移を掲げた。娼妓(売春婦)の統計は不在となった。 GHQによる公娼廃止指令(1946年)から、売春防止法の施行(1958年)までの間には、いわゆる赤線と呼ばれた地域で半ば公認で売春が行われていたので、それまでは事実上娼妓は存在した。1955年の国勢調査によると「芸妓、ダンサー、接客婦」という職業に119,671人が従事という結果となっている。これは1941年の警察統計による芸妓と娼妓の合計人数10万人とほぼ同等の人数である。 売春防止法直前の状況としては以下のような数字がある。ここで洋娼とはいわゆるパンパンのことである。
戦後を通じて芸妓数は和風の宴会文化が衰退するとともに減少の一途をたどった。バー・キャバレー・クラブのホステスも1970年をピークに減少に転じ、特に、バブル崩壊後の2000年以降は急減した。カラオケ文化の勃興が大きく影響しているといわれる。
(2021年5月22日収録、5月23日永井荷風(注)、5月25日戦前期東京の芸妓数推移、6月9日荷風引用、6月17日大正期の急増理由補訂、6月23日亀戸・玉の井、7月2日1956年状況、7月7日税に関する断腸亭日乗引用、7月31日女給・芸者に関する断腸亭日乗引用、2024年2月16日国調データ更新、2025年7月8日コラム)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||