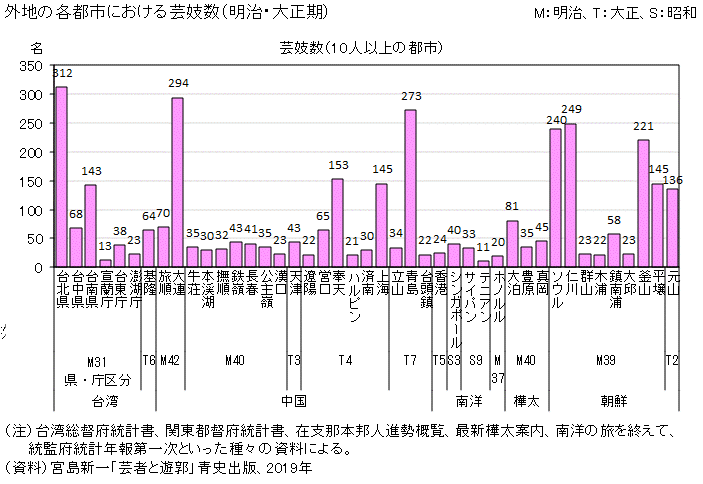
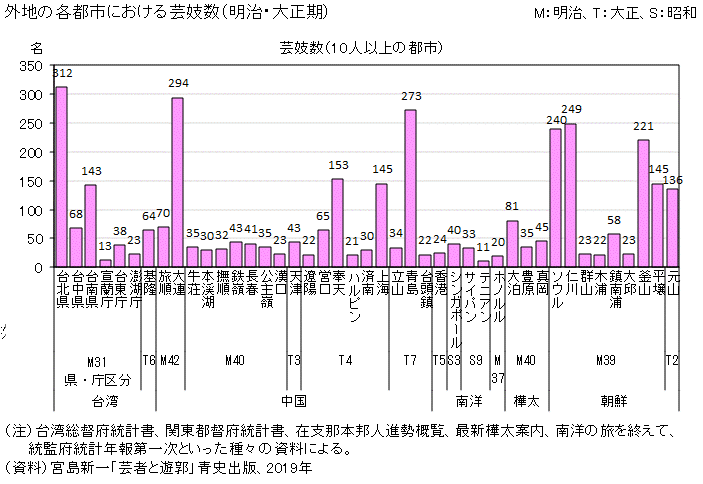
ここでは、明治末期から大正期(一部昭和初期)における外地の各都市における芸妓数(10人以上)を図示した。 台湾は、主に、当時の行政区分である県・庁区分で示した。基隆は台北県、嘉義は台中県に含まれていた。 台湾の芸者はレベルが高かったという。宮島新一(2019)「芸者と遊郭」青史出版によれば、「井東憲氏は『台湾案内』(植民事情研究所、1935)に、「どこの植民地でもそうであるが、驚くほど設備がととのっているのは、花街と享楽地である」と、記している。性格上、好意的な記述が多いが、「嘉義の芸者、台北の芸者、台南の芸者などは、大阪新町あたりの芸者や、東京赤坂あたりの芸者にくらべても、決してひけはとらない、...嘉義は台湾芸者の本場である、嘉義の花街は各精糖会社の発展の線に沿って繁栄していたところで、金融の中心等があるので、いろいろな意味でちょうど大阪の南地といった風に盛大になったものである」と記している。(中略)関西の実業家だった林安繁氏も随筆『柿の蔕(へた)』(モダン日本社、1940)で、台北芸者があなどれない存在だったことにふれている。そこには「芸者にいたりては新来の客みだりに論ずべきにあらざるなり。いわんや西川の名取あり、毎年東京に出て師匠に猛訓練を頼む老妓あるにおいてや、鏡獅子を舞う、北州を舞う、相当のものなり、舞台度胸あり、台北を田舎なりと考えるのは謬りである。いわんや15歳にして台湾に渡り、51歳の今日まで30有余年花柳界に馳駆する老妓あるにおいてや」とある。井東氏の感想は率直なもので、とくに迎合的だったわけではなかった。外地でこれほど高い評価を得ているのは台湾以外にはない」(p.367〜368)。 中国本土では、もう少し質が落ちてくる。同書によると「田山花袋が『満鮮の行楽』(1924)に大連芸者についてちょっとした感想を残している。「概してお客にあまやかされている。客が満鉄の金持ちか、貿易商か、軍人かであるためわるくはしゃぐことばかりをやって、...お座付き(唄)というものをちゃんとつけたのを見たことはなかった。あれがあるから座がしまってくるのである。また舞踊、あれがあるので客の心が浮き立ってくるのである」と述べている。彼が理想とした吉原仲の町や柳橋のお座敷に出る芸者と比較されては、大連芸者も立つ瀬がない。彼女らにしてみれば宴を賑わすのが仕事なのだから土地柄を考えてほしい、と言いたかったであろう」(p.371〜372)。 外地でももっと場末になってくると芸妓と酌婦の区別もつかないようなどんちゃん騒ぎが常態となっていたようだ。「高島高文氏は『蛮人の奇習』(京文社、1928)に、欧州戦争による好景気によってジョホールの州都グダンには「数人の真似芸者しかなかったものが、香港や大連、天津から流れてきた者...驚くなかれ40有余人」として、彼女らのすさまじい稼ぎっぷりを書き残している。新聞記者だった梶原保人の『図南遊記』(1913)には、ハノイで大正元年の年末を飲み明かし、「硬派の宴なれば芸者も硬派たらざるべからず」などと記されている」(P.378)。 国内でも同様であるが、外地でも場所柄や客層によって、芸者の質や遊興法に大きな落差があったことがうかがわれる。 昭和期に入り、外地で戦火が広がると、女給、酌婦、娼妓などとともに、芸妓も、こうした地域でさらに増加していったと思われる(図録5690参照)。 (2021年5月25日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||