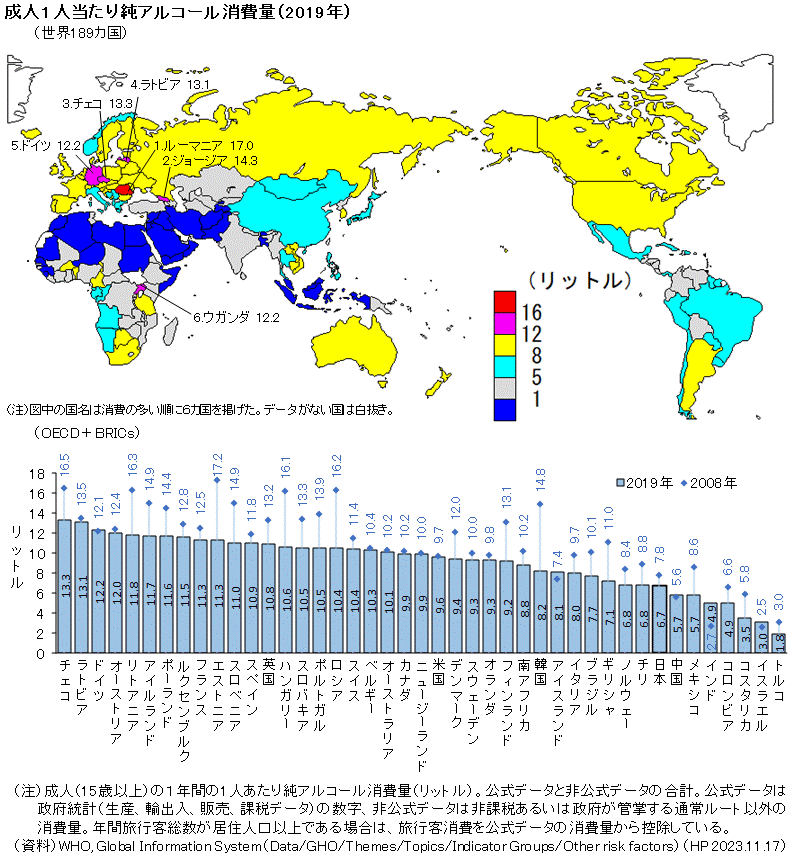
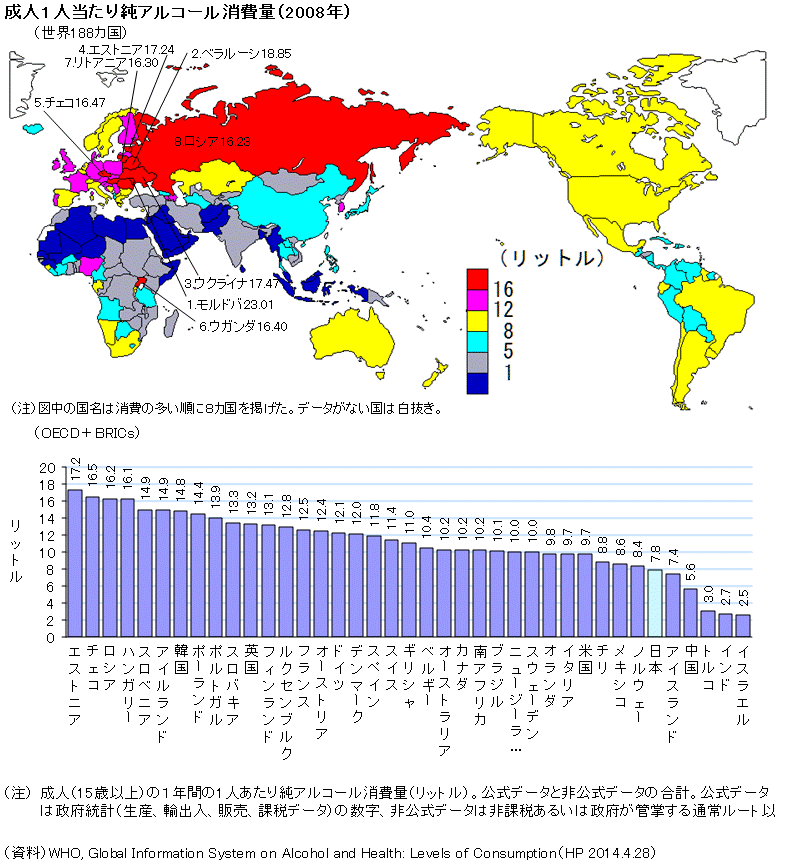
【クリックで図表選択】
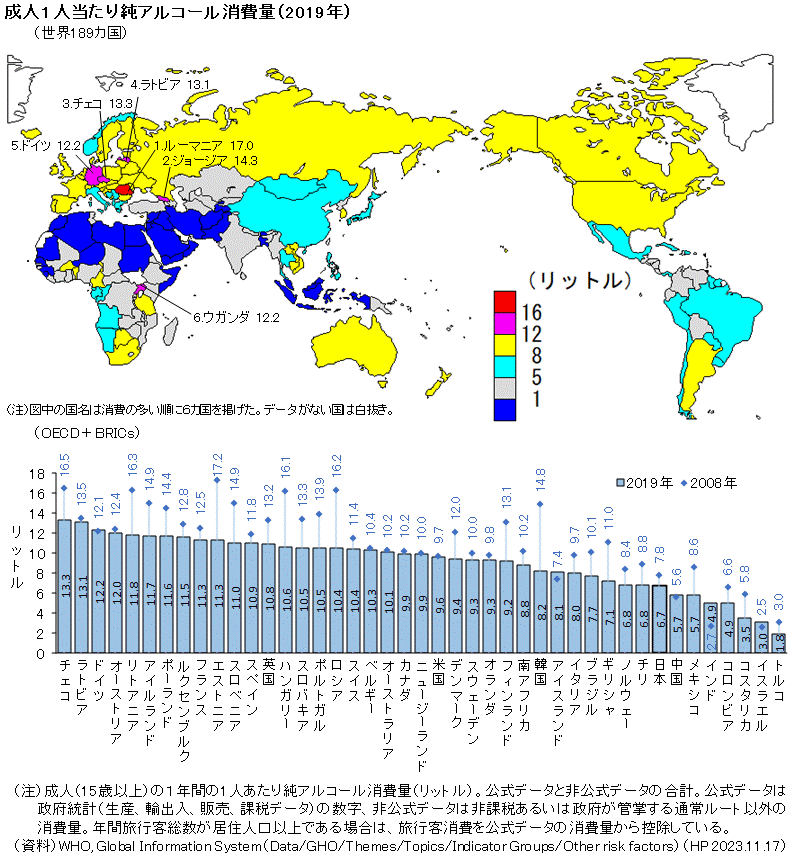 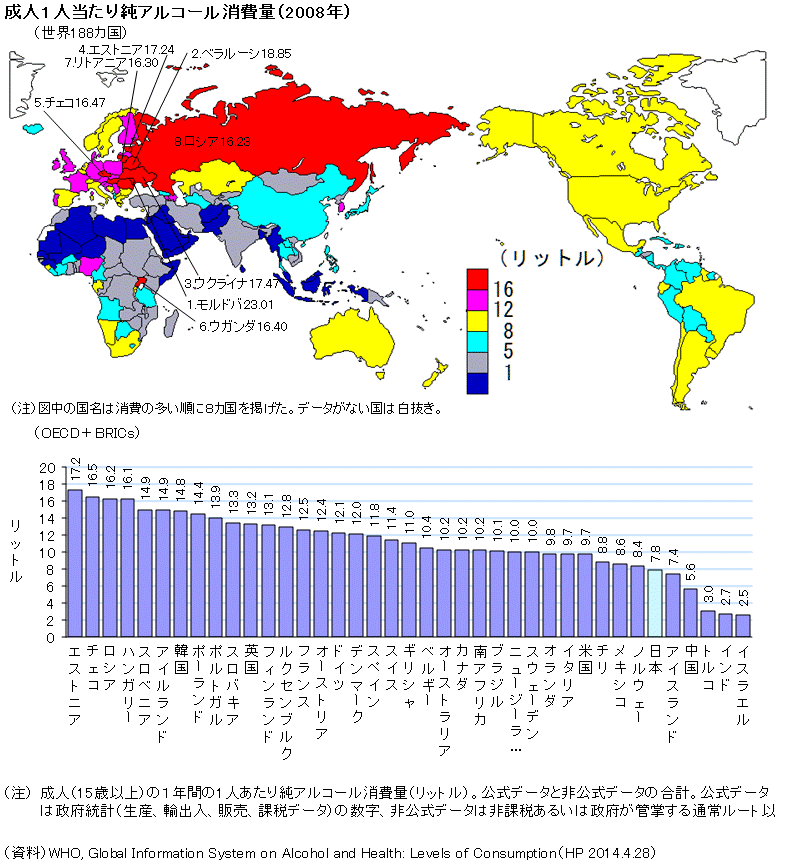 |
アルコールの内訳の1つであるビールの消費量については図録0434参照。ワインの消費量については図録0435参照。 OECD諸国とBRICsの対象国では、アルコール消費量の多い順にチェコ、ラトビア、ドイツ、オーストリア、リトアニア、アイルランド、ポーランド、ルクセンブルク、フランス、エストニア、スロベニア、スペイン、英国、ハンガリー、スロバキア、ポルトガル、ロシア、スイス、ベルギー、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、米国、デンマーク、スウェーデン、オランダ、フィンランド、南アフリカ、韓国、アイスランド、イタリア、ブラジル、ギリシャ、ノルウェー、チリ、日本、中国、メキシコ、インド、コロンビア、コスタリカ、イスラエル、トルコとなっている。 2019年と約10年前の2008年を比較するとほとんどの国でアルコール消費量が少なくなっていることが分かる。特に、ロシア、エストニア、リトアニアなど旧ソ連圏諸国での低下が目立っている。社会の安定化によるものと考えられる。韓国の消費量もかなり落ちており、飲酒習慣の変化がうかがわれる。 OECD諸国の中では多消費国のラトビア、ドイツ、オーストリアの消費量がほとんど変わっていないのがかえって目立つような状況である。ラトビア人の飲酒好きについては佐藤優(2023)「それからの帝国」(小説宝石連載時題名「酒を飲まなきゃ始まらない」)にも詳しい。 それ以外の地域的な特徴は以下のコメントで記した通りである。 (2008年データによるコメント) 世界の中ではウガンダは例外として、モルドバ、ベラルーシ、ウクライナ、エストニア、リトアニア、ロシアなど旧ソ連諸国がもっとも多い。これらの国は飲酒好きだから多いというより、アルコール中毒が社会問題となっている点が特徴となっている。 ロシアのアルコール依存はなお深刻であり、2016年12月には、東シベリアのイルクーツクで、エタノールの代わりにメタノールを使った入浴剤の偽物を酒代わりに飲んで70人以上が死亡する事件までが起こっている。 事件を報じた朝日新聞(2016.12.28)は酒代わりに飲んだのは入浴剤でなくローションとしていたが、同紙によると「日本でも終戦直後、工業用アルコールなどを使った「バクダン」と呼ばれる酒が出回っていた。ロシアでは旧ソ連時代から、酒の入手が難しい時は工業用アルコールのほかオーデコロンや洗浄液も飲まれていた。靴墨をパンに塗り、アルコール分を染みこませて食べる人さえいた。特に1985年、ペレストロイカ(改革)の一環で節酒令が布告され、酒が大幅に値上がりした。タクシー運転手は「困って代用品を飲んだら大丈夫だった。安心して広まった」と振り返る。最近では酒の入手に困ることはない。それでも、低所得者層や若者に人気がある」。 東京新聞(2016.12.29)によると「入浴剤には飲用禁止の表示はあったが、75〜90%のアルコールを含んでおり、事実上の代用酒として流通していたとみられる。(中略)ロシアではソ連時代からアルコールの過剰摂取が深刻な社会問題。プーチン政権発足後もアルコール度数の高いウオッカなどへの課税強化や、夜間の酒類販売規制といった措置をとってきた。しかし、ロシアのシンクタンクは、2000万人以上が密造酒や化粧品など法規制の枠外のアルコールを飲んでいると推計する」。 つまり日本でもビールへの課税を回避できるため安価で流通するビール風アルコール飲料が人気となったように、課税逃れの代用酒として入浴剤など種々の商品が売られていたということなのだろう。朝日新聞の報じ方は間違っていたことになる。ロシアの平均寿命が社会に蔓延するアルコール中毒で低くなった点については、図録8985や図録2774参照。 ロシアなど旧ソ連諸国に次いで、東欧・西欧諸国の消費量が大きい。ビールの本場チェコ、チェコに影響されたドイツ、ワインのフランスなどビールやワインの本場ではやはりアルコールの消費も多くなっている。ロシアでは最近では健康的なライフスタイルが広がり飲酒量は独仏を下回ったという(図録2774参照)。 欧米の中で、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど英語圏諸国はそれほど消費量が多くはない(英国はやや多い)。 逆に、アルコール消費量の少ない地域は、イスラム圏の諸国、あるいは低所得地域である。アルコール消費を補うかのようにイスラム国の中にはお茶の消費量が多い国がかなりある(図録0476参照)。 アジアは、概して、アルコール消費は少ない。これはコラムに紹介したようにモンゴロイド系の民族はアルコールに弱いからという側面も無視できない。アジアの中では、韓国が14.82リットルと最も消費量が多くなっているのが目立っている。 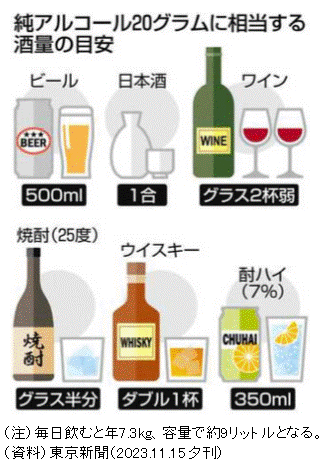
(2006年2月14日収録、2014年4月28日更新、コラム追加、2016年12月28日ロシアの偽ローションを飲んだ事にによる集団死亡事件、2020年2月3日コラム2にNHKスペシャルの内容紹介、2023年11月16日純アルコール20グラムに相当する酒量の目安、11月17日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||