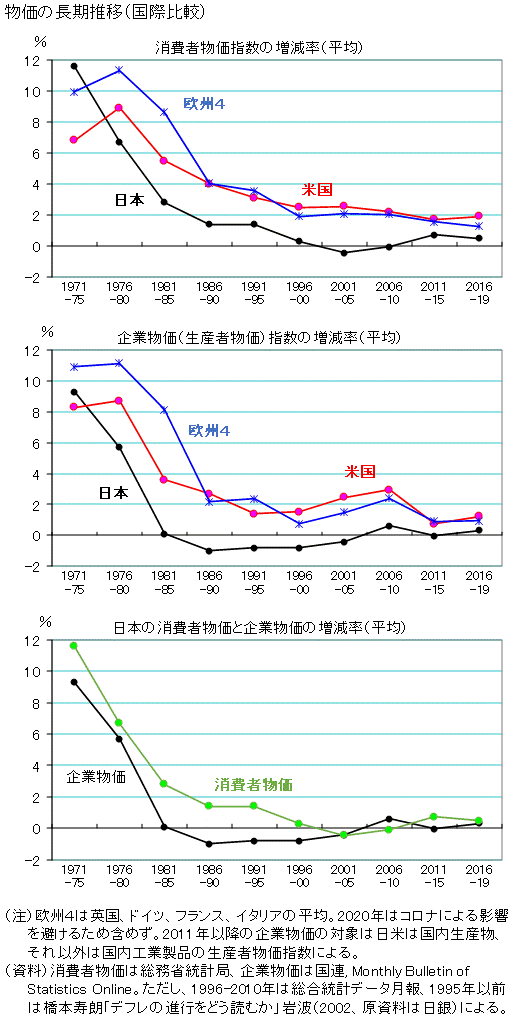
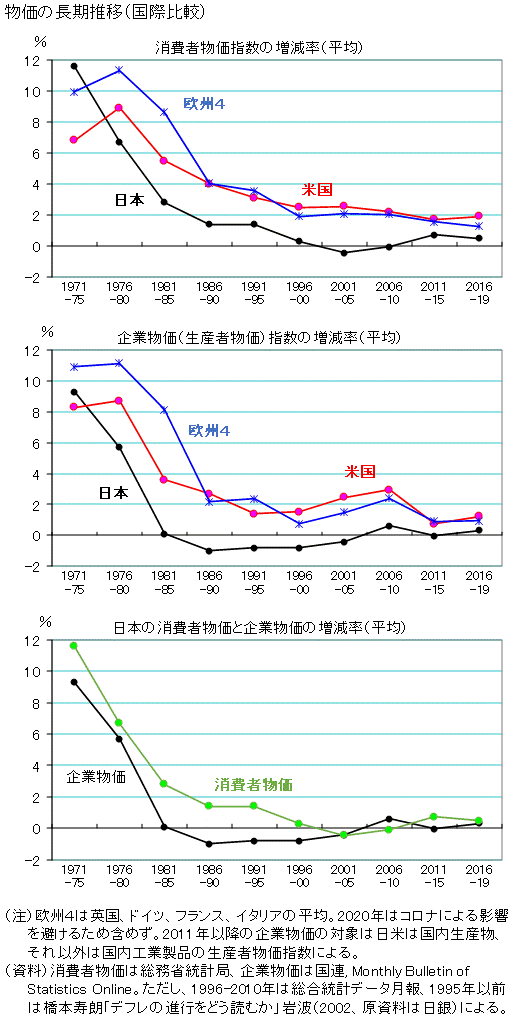
消費者物価は財とサービスの両方を含むBtoC価格であるのに対して、企業物価は財のみのBtoB価格である。 推移を見ると、先進国では、1970年代には10%前後であった物価上昇率が1990年代以降は-2〜2%程度の水準と変化し、全体として、1980年代前半を移行期間として、インフレ経済からディス・インフレ経済(インフレでない経済)、あるいはデフレ経済に大きく変化したことがうかがえる。 日本も欧米と同様の推移であるが、物価上昇率の低下が欧米より著しく、また物価上昇率の水準がつねに欧米を下回っているという特徴が見て取れる。 欧米では5年平均で物価がマイナスになったことはないが、日本では消費者物価では2000年代前半〜同後半に、企業物価では1980年代後半〜2000年代前半にマイナスにまで至っている点が目立っている。 物価の長期低落化傾向については、日本の場合は経済成長率のペースダウンと平行的な現象であるので、まさに物価推移は成長率鈍化によってもたらされているようにみえる。しかし、欧米では日本のような目立った経済成長率のペースダウンはおきておらず、それにもかかわらず物価推移には際立った変化が生じているので、物価推移の基調変化の主要因を成長率にもとめることはできないように考えられる。橋本(2002)はこうした変化を「価格革命」と呼んでいる。 ともあれ、インフレ時代には可能であった賃上げ率のチューニングによる生産性向上に合わせた労働コストの調整、あるいは税率を据え置いても累進直接税との組み合わせで可能となる増税がデフレ時代には難しくなる。これまでと同じ状態を維持するために、特に日本では、賃金カットや税率引き上げという抵抗の多い手段を行わねばならない事態となったのである。 物価上昇率が日本の場合、欧米に比べて低かった理由としては、やはり、日本においてはインフレを回避することを重視する政策が根強かったからといえよう。 2013年以降のアベノミクス期には、デフレ克服するためにインフレターゲットが設定され、これが達成されるまでとして、従来の日銀のスタンスでは考えられないような大胆な量的金融緩和政策を講じた。物価上昇率の対欧米格差が2010年代前半から縮まったのはその成果とも考えられよう。 消費者物価と企業物価の推移を比べると、20世紀の間はほぼパラレルに(平行して)前者が後者を上回るかたちで推移していたが、2000年代以降は両者の水準が近接するかたちで推移するように変貌した。 20世紀中に消費者物価が長らく企業物価を上回る水準で推移していたのは、財の価格より相対的に上昇する傾向をもつサービスの価格が消費者物価に方にだけ含まれているため、サービス経済化の進展にともなって、ますます両者の差が広がるからであるといえよう(財の価格とサービスの価格の上昇格差については図録4700参照)。 21世紀に入って、2006-10年期には、消費者物価上昇率と企業物価上昇率とが逆転しているのが目立っている。下に掲げたように、米国や欧州でも同じタイミングで両者の逆転現象が見られる。原油・鉱物資源や穀物など資源価格の高騰が消費者物価に反映されにくい新しい状況とも見えるが、いずれにせよ、新しい経済の構造変化を示しているといえよう。 その後、2011-15年にはいったん元のパターンに戻るかに思えたが、2010-19年には再度逆転の方にぶれている。これには、消費者物価により大きく反映される賃金上昇率の低さが影響しているという説もある。 日本における毎年の消費者物価上昇率については図録4719参照。最近の主要国の消費者物価指数の動きは図録4722参照。 (参考文献)
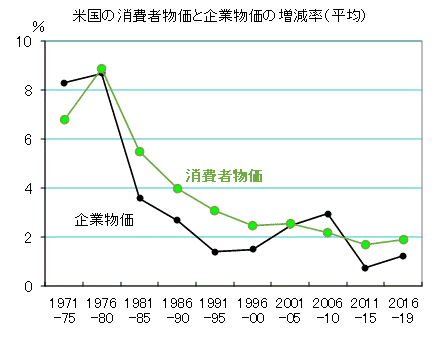 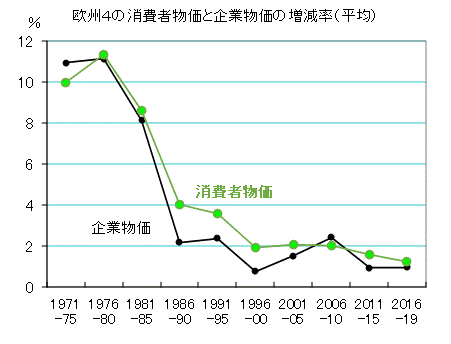 なお、下には、日本人が社会経済対策の中で物価安定に関しては例外的に政府の責任であると強く考える傾向がある点を示すデータを掲げた(図録5184のデータ)。過去にインフレーションによって非常に痛い目にあったことにより、アベノミクスまでは、物価安定が日銀の最優先課題となってきた背景を物語るデータであるといえよう。これが大きな要因となって図録に示したような日本の物価上昇率の相対的な低さを招いていたのではなかろうか。
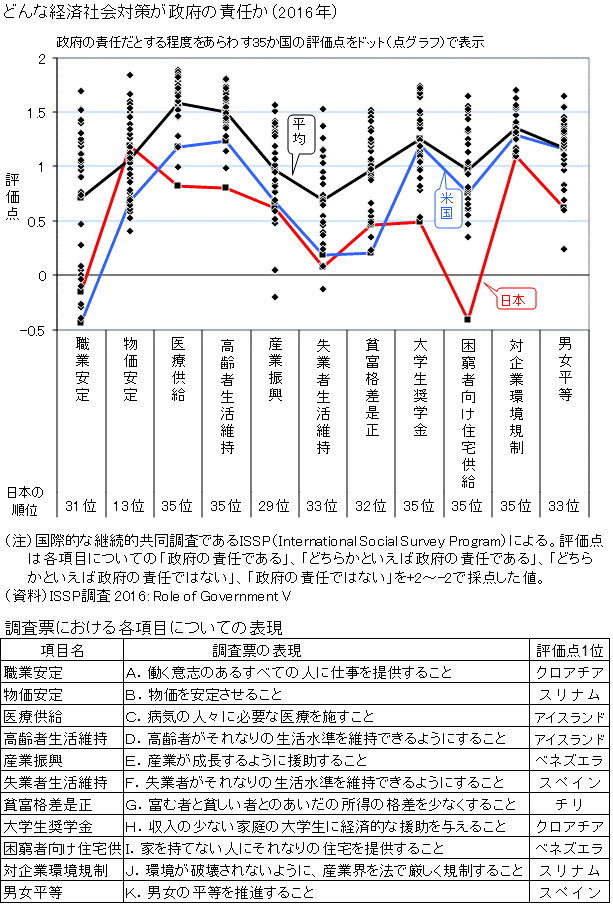 (2004年5月18日収録、2008年6月3日更新、2011年3月11日更新、2015年12月9日ISSP調査結果、2016年4月4・5日インフレ率OECD内順位表、2023年7月22日更新、コメント改訂、インフレ率OECD内順位表削除)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||