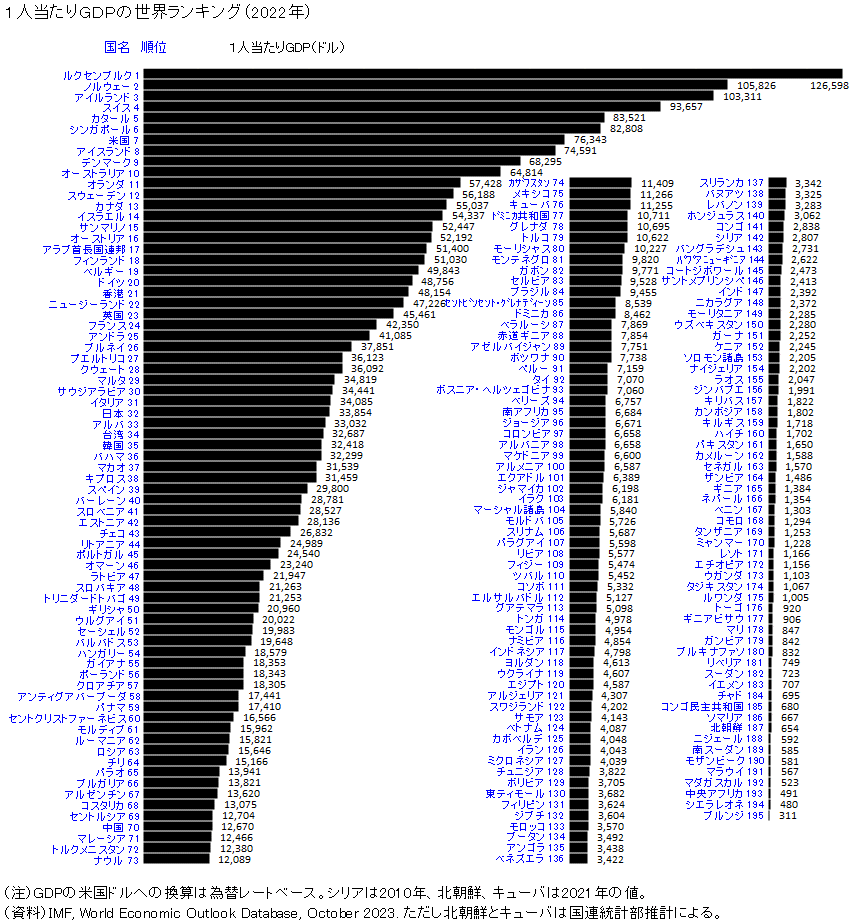
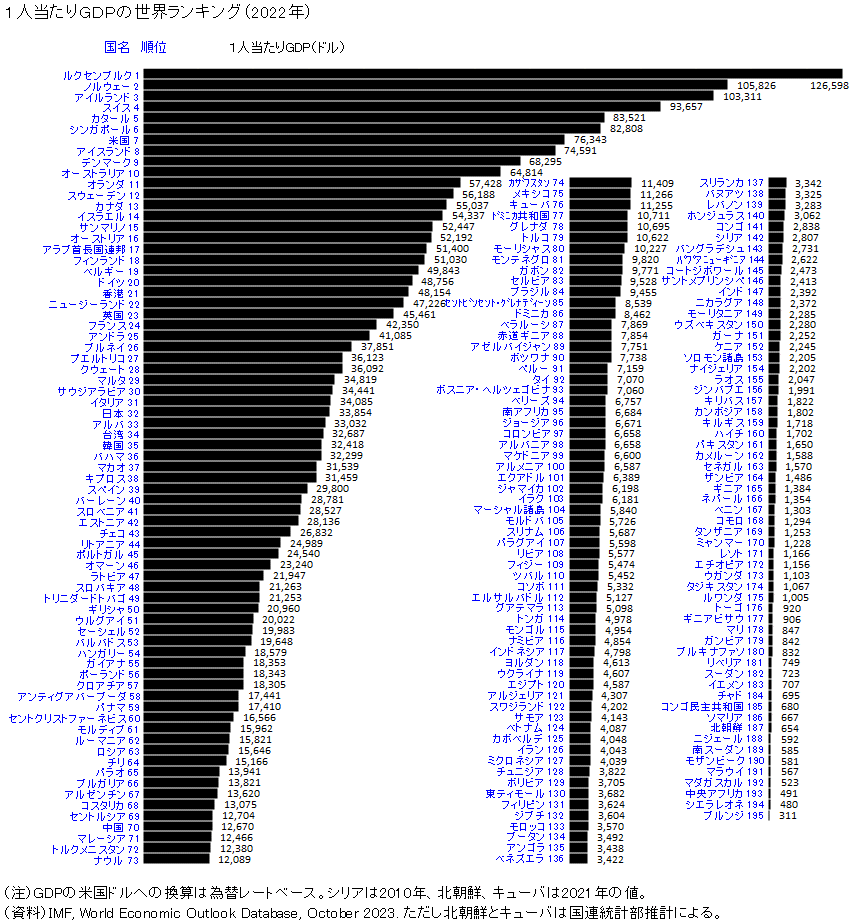
| PPPベースはこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1人当たりのGDPの指標には、現地通貨ベースのGDPをその時の為替レートで米国ドルに換算したものと、購買力平価(PPP)、すなわち一定の種類と量の財・サービスを購買するために各国の通貨がどのくらい必要かのレートで換算したものとがある。単純に経済力を測るためには前者が用いられるが、国民にとっての豊かさや富の量を実質比較するときは後者がしばしば用いられる。ここでは、前者を用いた。(後者を使った例としては平均寿命との相関を図録1620で、また貧富の格差との相関を図録4650で示した。) 1人当たりGDPの世界1位はルクセンブルク、第2位以下はノルウェー、アイルランド、スイス、カタール、シンガポール、米国、アイスランド、デンマーク、オーストラリアと続いている。米国は7位、日本は32位である。カタール、アラブ首長国連邦といった産油国が5位、17位と上位に入っている。 2023年、英国からの独立50年を迎えるカリブ海のバハマは1人当たりGDPが世界36位と32位の日本とそれほど違わない(2022年)。面積は福島県程度、黒人が90%をしめる人口は約40万人のバハマは米国からも近く観光と金融が2大産業であり、所得水準はカリブ海諸国でトップの地位にある。もっとも国民の5人に1人が銀行口座をもっていないといった格差を背景に犯罪も多発しているという。 バハマではコロナ対策で観光客の入国を22年夏まで2年近く制限し、20年のGDP成長率はマイナス16.3%という大打撃を受けた。また、タックスヘイブンとして誘致してきた金融業では、バハマに本拠を置いた暗号資産(仮想通貨)の大手交換所FTXトレーディングが22年11月に破綻しバハマのイメージに傷が付く恐れがあるとともに地元経済に悪影響を及ぼしているという。こうした事情により20年以降の1人当たりGDPのランキングは大きく低下しているものと思われる(東京新聞2023.1.18夕刊)。 日本をはじめ先進国の1980年以降の順位の変化については図録4542を参照されたい。 ルクセンブルクの1人当たりGDPランキングには過大評価の側面がある点については下のコラムを参照されたい。ノルウェーは北海油田からの石油・天然ガスの輸入収入が大きく貢献している。 1人当たりGDPが1万ドル以上の国はモーリシャスまでの80カ国である。2010年の中国のGDP規模が日本を追い抜いて世界第2位に躍進した(図録j006)。しかし、上図のように70位である中国の1人当たりGDPの水準は、なお、日本の0.37倍である。 1人当たりGDPが456ドル以下は1日1.25ドル以下の貧困国であるが、ブルンジ1カ国がこれに当たっている。 GDPに計上されないシャドーエコノミーを考慮するとこのランキングはかなり変更を迫られる。例えばロシアやタイはシャドー率が50%以上なので1人当たりGDPも2倍以上ということとなる(図録4570参照)。
取り上げている195カ国は、具体的には、1人当たりGDPの大きい順に、ルクセンブルク、ノルウェー、アイルランド、スイス、カタール、シンガポール、米国、アイスランド、デンマーク、オーストラリア、オランダ、スウェーデン、カナダ、イスラエル、サンマリノ、オーストリア、アラブ首長国連邦、フィンランド、ベルギー、ドイツ、香港、ニュージーランド、英国、フランス、アンドラ、ブルネイ、プエルトリコ、クウェート、マルタ、サウジアラビア、イタリア、日本、アルバ、台湾、韓国、バハマ、マカオ、キプロス、スペイン、バーレーン、スロベニア、エストニア、チェコ、リトアニア、ポルトガル、オマーン、ラトビア、スロバキア、トリニダードトバゴ、ギリシャ、ウルグアイ、セーシェル、バルバドス、ハンガリー、ガイアナ、ポーランド、クロアチア、アンティグアバーブーダ、パナマ、セントクリストファーネビス、モルディブ、ルーマニア、ロシア、チリ、パラオ、ブルガリア、アルゼンチン、コスタリカ、セントルシア、中国、マレーシア、トルクメニスタン、ナウル、カザフスタン、メキシコ、キューバ、ドミニカ共和国、グレナダ、トルコ、モーリシャス、モンテネグロ、ガボン、セルビア、ブラジル、セントビンセント・グレナディーン、ドミニカ、ベラルーシ、赤道ギニア、アゼルバイジャン、ボツワナ、ペルー、タイ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ベリーズ、南アフリカ、ジョージア、コロンビア、アルバニア、マケドニア、アルメニア、エクアドル、ジャマイカ、イラク、マーシャル諸島、モルドバ、スリナム、パラグアイ、リビア、フィジー、ツバル、コソボ、エルサルバドル、グアテマラ、トンガ、モンゴル、ナミビア、インドネシア、ヨルダン、ウクライナ、エジプト、アルジェリア、スワジランド、サモア、ベトナム、カボベルデ、イラン、ミクロネシア、チュニジア、ボリビア、東ティモール、フィリピン、ジブチ、モロッコ、ブータン、アンゴラ、ベネズエラ、スリランカ、バヌアツ、レバノン、ホンジュラス、コンゴ、シリア、バングラデシュ、パプアニューギニア、コートジボワール、サントメプリンシペ、インド、ニカラグア、モーリタニア、ウズベキスタン、ガーナ、ケニア、ソロモン諸島、ナイジェリア、ラオス、ジンバブエ、キリバス、カンボジア、キルギス、ハイチ、パキスタン、カメルーン、セネガル、ザンビア、ギニア、ネパール、ベニン、コモロ、タンザニア、ミャンマー、レソト、エチオピア、ウガンダ、タジキスタン、ルワンダ、トーゴ、ギニアビサウ、マリ、ガンビア、ブルキナファソ、リベリア、スーダン、イエメン、チャド、コンゴ民主共和国、ソマリア、北朝鮮、ニジェール、南スーダン、モザンビーク、マラウイ、マダガスカル、中央アフリカ、シエラレオネ、ブルンジである。 (2006年12月4日収録、2008年10月29日更新、2011年1月22日更新、データ出所を世界銀行からIMFに変更、2011年10月7日更新、12月30日順位表彰を下から上に、2012年4月6日対数つづら折れ図から非対数棒グラフに変更、7月18日キューバ追加、11月28日更新、2013年3月23日コラム追加、3月27日同コラムOECDは高所得国のみである点を明確化、10月9日更新、2014年10月8日更新、2015年10月14日更新、2022年12月25日更新、2023年1月19日バハマのコメント、4月29日2〜3段目上部国名ミス修正、2024年1月16日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||