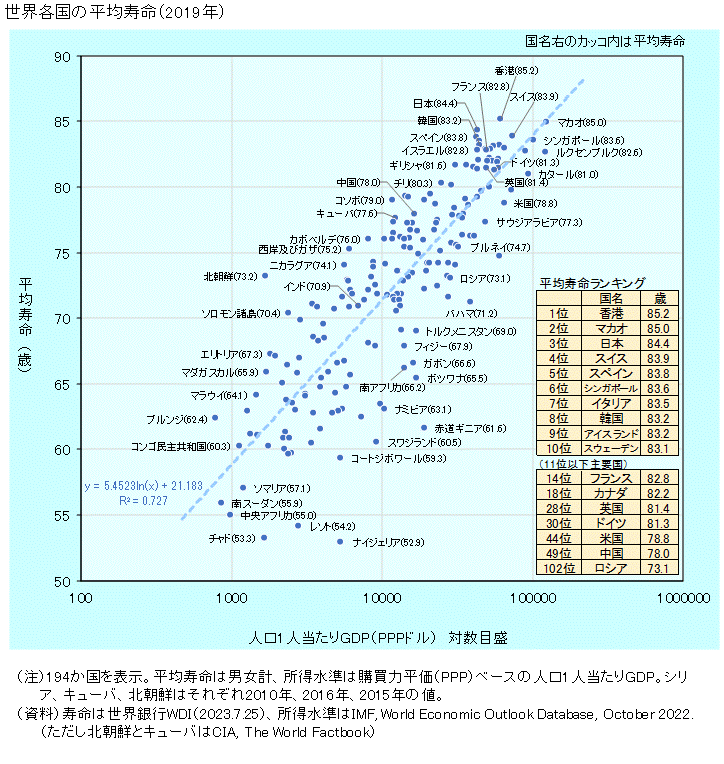
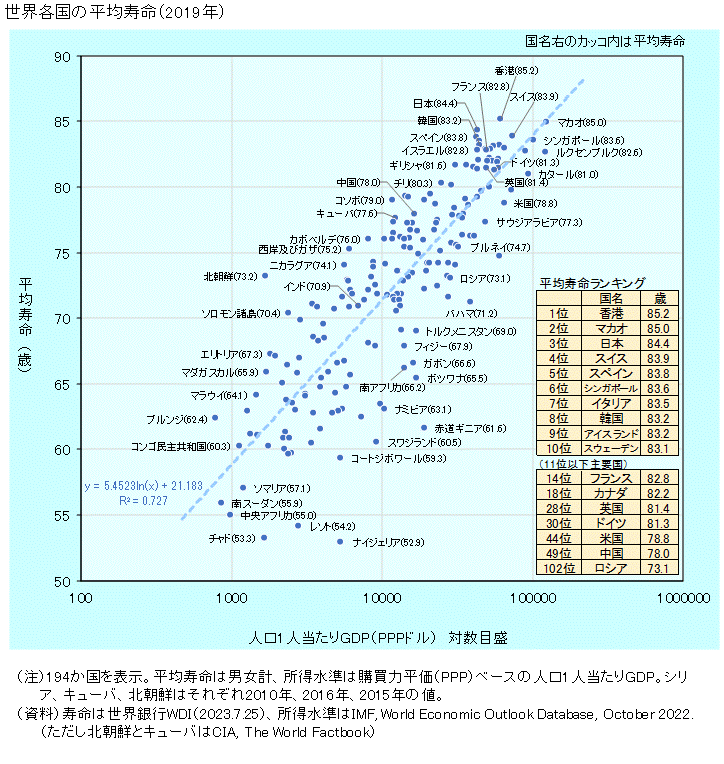
図の中で最も所得水準が高いのはマカオ(125,002ドル)であり、最も所得水準が低いのは、アフリカのブルンジ(783ドル)である。格差は160倍にもなっている。一方、平均寿命の最も高い国は香港(85.2歳)であり、最も低い国はアフリカのナイジェリアの52.9歳である。差は32.3歳もある。 日本の所得は43,459ドルで32位、平均寿命は84.4歳で3位である。 図を見れば、高所得国ほど平均寿命が長く、低所得国ほど平均寿命が短いという一般傾向、正の相関が認められる。高所得国ほど医療水準が高く、衛生状態、食生活水準もよいため、こうした相関が生じることは明らかであり、双方には因果関係があるといえよう。 (経済発展度の割に平均寿命の長い国) 日本は主要国の中では世界一平均寿命が高い国である。人口1億人の大国としては立派であり、このような相関図の中に位置づけると、日本は平均寿命の点では世界から尊敬を受けて然るべき地位にあるということが実感される。 実際、世界中の人々は日本がどうして人類の夢に最も近づくことができたのかに注目している。こうした日本で、チェルノブイリ以来の大きな原発事故が起こっただけに世界は強烈なショックを受けている。それだけ注目されているのだから、私は、人類の未来を切り拓くリーダーとしての自覚を、日本人はもっと持つべきだと考えている。 他方、平均寿命が50歳代と非常に短い国がサハラ以南のアフリカに多く見られる。図では、平均寿命と経済発展度(所得水準)の相関とともに、経済発展度が低い割に平均寿命の長い国と高い割に平均寿命の短い国があるという点も明確に分かる。 右上がりの傾向線より左上にある国、すなわち日本の他、コソボ、キューバ、ニカラグアといった国は、経済発展度の割には平均寿命は長くなっているがひと頃と比べると目立たなくなった。経済より健康優先というのが新自由主義が主流となった時代に合わなくなってきたせいかも知れない。 (経済発展度の割に平均寿命の短い国) 逆に右上がりの傾向線より右下にある国、すなわち所得水準の割には平均寿命の短い国としては、ルクセンブルク、米国、カタール、ブルネイ、ボツアナ、赤道ギニア、ナイジェリアなどがあげられる。産油国や資源国が多く含まれる。米国は、1人あたりの所得では南米チリの2.6倍の水準となっているが、平均寿命は78.8歳とチリの80.3歳を下回っている。医療制度の問題、貧富の差や薬物依存の問題などが背景にあると考えられる。 サハラ以南アフリカで平均寿命が短いのは、経済発展が遅れているせいだが、資源開発等による所得向上が保健衛生の向上に結びつきにくい国内事情も要因のひとつである。 アフリカで人口や経済規模が最大で「アフリカの巨人」とも呼ばれるナイジェリアは、平均寿命は世界最低となっている。同国は、国家歳入の約7割、総輸出額の約8割を原油に依存している資源国でもあるが、広大な国だけに地域毎に歴史と地理、宗教と部族、石油資源賦存と収入配分などに大きな差異があり、政治的な不安定性や地域間の対立が醸成され易く、ボコハラムのテロ、牧畜民と農民の争いなどもある。こうした複雑な国情もあって所得水準に見合った平均寿命の伸びを実現することが難しいのだと理解できる。 (その他) なお、世界銀行の世界開発報告2006に、上図と同様のテーマの図が掲載されており、良くできた図なので、下に掲げておく。ヨコ軸が対数目盛でない点、国のプロットに人口規模が合わせ表現されている点に上図との違いがある。 更新前の2010年のグラフと比較するとサハラ以南アフリカでも平均寿命40歳台の国がなくなったし、2002年グラフと比較するとサハラ以南アフリカでも平均寿命30歳台の国がなくなった。一方、欧米で平均寿命80歳台の国がかなり増加している。 (関連図録) (参考図) 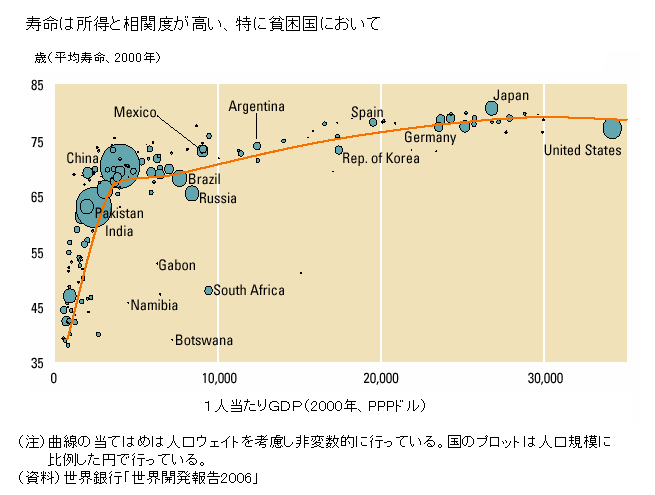 (2004年8月12日収録、データ修正、2006年3月10日参考図追加、2008年4月6日更新、2009年6月4日平均寿命ランキング表の第5位をオーストリアから正しいオーストラリアに訂正、2010年6月23日図中国名(フランス、ドイツ、英国、ガボン、ナミビア、赤道ギニア追加、2012年6月13日更新、2023年10月2日更新、10月4日図中にランキング表付加)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||