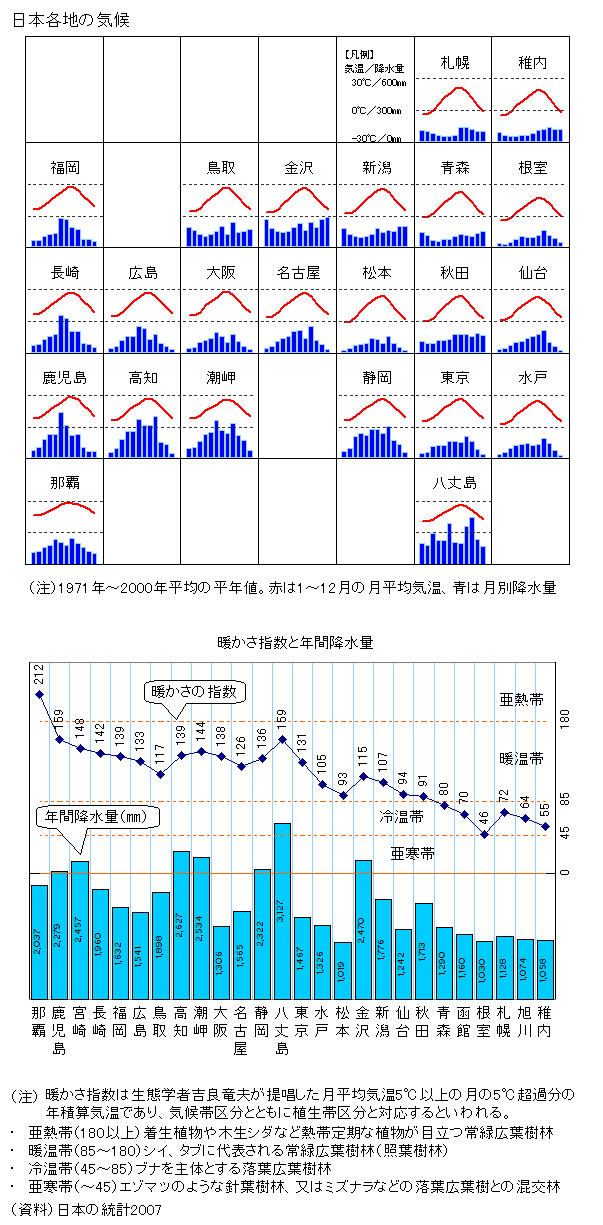
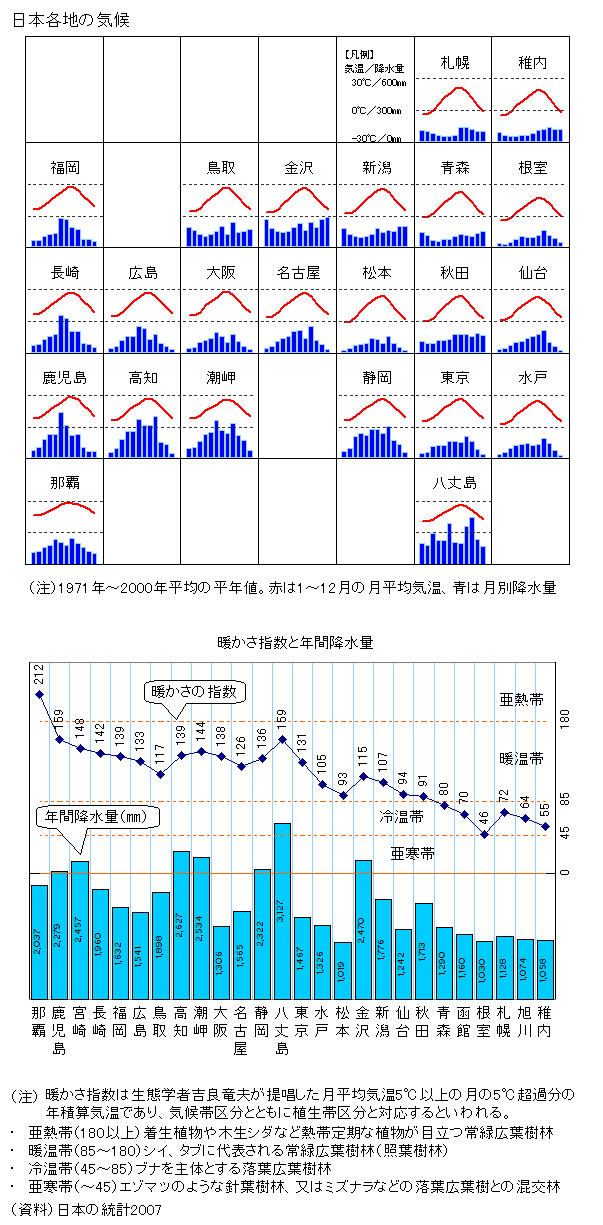
| �@ | �@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@���{�e�n�̋C��ł܂��ڗ��̂͊��g�̍��ł���B��k�ɍג������{�ł́A�����̔N���ϋC����6.1���A�ߔe��22.7���Ƃ��Ȃ�̕�������B �@�A���̊�����5���ȏ�ł͂��܂�A���x�ɍ��킹�Ċ��������邱�Ƃ���A�����Ƃ�5���ȏ�̐ώZ���x�i�g�����̎w���j�ɂ���ċC��т��敪����Ɠ��{�͈����т��爟�M�т̋C��Ƃ���ɑΉ������A����L���Ă���i�}�^4340�Q�Ɓj�B �@�g�����w���͐��Ԋw�ҋg�Ǘ��v�����������ϋC��5���ȏ�̌���5�����ߕ��̔N�ώZ�C���ł���A�C��ы敪�ƂƂ��ɐA���ы敪�ƑΉ�����Ƃ�����B
�@�����������g�̑傫�ȍ������{�̎��R�̑��l���A�L������ł���B���g�̍������łȂ��A�C�Ɉ͂܂�Ă��邱�Ƃ����Ԏj�I�Ɏ��R�̖L�����̗��R�ƂȂ��Ă���B �@�����ɓ��{�̐X�ю��킪���[���b�p��k�ĂƔ�r���ĖL���ł���_��X�͊��ɂ����̂ڂ邻�̗��R���L���Ă������A���E�e�n�̐������l���ɂӂꂽ�}�^4176d�Ɉړ������B��������Q�Ƃ��ꂽ���B �Q�D�~�� �@�~��̃��[���V�A�嗤����C��������{�C��������o���Ɠ��{�C��ŋz��������������C�����{�̐җ��R���̐����ɐ���~�点�A���̌��ʁA�����ɂ͍D�V�������炷�B�X�m�[�x���g�̓��{�C���ƃT���x���g�̑����m�����������ΏƂ������̂ł���B��}�ŋ���A�V���ȂǓ~��̍~���ʂ������n�悪�X�m�[�x���g�ɑ����Ă���i�}�^4338�Q�Ɓj�B �@���{�ɍ���Ƃ��Ă��قǐႪ�����~��悤�ɂȂ����̂�1���N�قǑO�A�Ō�̕X�͊����I����Ă���Ƃ�����iNHK�X�y�V����2011�j�B�X�͊��ɂ͍����C�ʂ������ƒႭ���A���N�����Ƃ̊Ԃ̑Δn�C���͋����Ȃ��Ă��āA�����̕����ł���g�����Δn�C�������{�C�ɗ��ꍞ��ł��Ȃ������̂ŁA���{�C�S�̂����Γ���t���A�V�x���A����̋C���͓��{�C�Ő������z�������ɂ��̂܂ܓ��{�ɐ����t���Ă����B�Δn�C������������̐��݂̐e�Ȃ̂��B �R�D���˓��C��A�y�ъC�m���C��E�������C�� �@��}�̍L���A���́A�~�̉J�����Ȃ��A�Ă��~���ʂ����Ȃ����˓��C��̒n��ł���B �@���{�͍ג����A�S�y���C�m���C��ł��邪�A���{�̂悤�ɋC���̔N�r�����傫���A�~���ʂ̏��Ȃ��������C��̑��ʂ������n�������B �S�D�~�J �@�k�C���������ē��{�ɂ�6�`7���ɑ����̍~�J�ʂ�����n�悪�������A����͒��N�����암�A�����̉ؓ��ؒ��̉��C���A����ё�p�ȂǁA���A�W�A�̍L�͈͂ɂ����Ă݂�����L�̋C�ۂł���~�J���ۂɂ��i�}�^4347�Q�Ɓj�B�~�J�̓A�W�A�E�����X�[���̈ꕔ�ł���A�q�}�����E�`�x�b�g���������邽�ߔ�������Ƃ����i�}�^4335�Q�Ɓj�B �i�Q�l�����j
�i���f�[�^�j
�i�����j���{�̓��v2007 �i2007�N9��18�����^�A2011�N3��9���R�����g���M�A2023�N12��16���ŏI�X���}�A12��17���ꕔ��}�^4176d�Ɉړ��j
�m �{�}�^�Ɗ֘A����R���e���c �n |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@