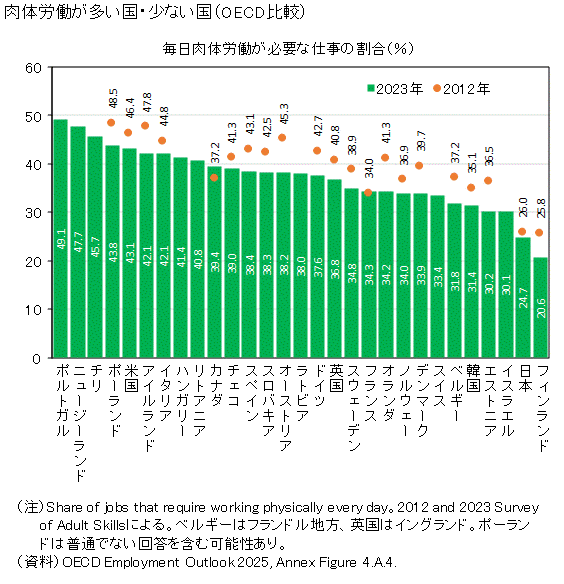
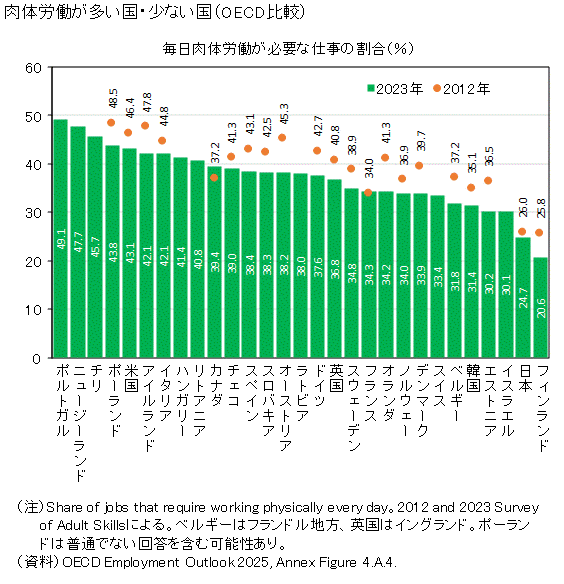
エネルギー多消費型の行動や労働が減っているから世界でも珍しく日本人のカロリー摂取量は減っているのではないかと考えていたが(図録0120、図録0202)、この点と関連して、エネルギー多消費型の肉体労働の比率の国際比較データが見つかったので掲載する。 データは、OECDのSurvey of Adult Skills(成人スキル調査)によるものであり、図録3570には、どんな職業で肉体労働比率が高いかのランキングを掲げたので参照されたい。 対象となっているOECD29か国の中で、日本は肉体労働比率が24.7%とフィンランドの20.6%に次いで低くなっている。 この2か国に続いて肉体労働比率が低いのは、イスラエル、エストニア、韓国、ベルギーの順である。 これらの国についてぱっと思い当たるような共通点はない(日本と韓国が東アジアという点を除き)。 逆に、対象国中、もっとも肉体労働比率が高いのはポルトガルの49.1%であり、ニュージーランド、チリ、ポーランド、そして米国がこれに続いている。米国の肉体労働比率43.1%は、主要先進国(G7諸国)の中では最も高くなっている。 29か国中21か国で2012年と2023年の21年間の変化を知ることができるが、肉体労働比率が上昇しているのはカナダとフランスのみであり、世界的傾向として、肉体労働は減りつつつあることが分かる。日本の変化は余り大きくなく、すでに20年前から肉体労働は少なくなっていたようだ。 日本の肉体労働比率の低さが、日本の産業社会の構造に起因しているのか、あるいはロボット化・機械化によるものなのか、それとも高齢化に伴う労働力不足で肉体労働の職場が嫌われ、成立しにくくなっているためか(そしてそれを埋め合わせる外国人労働も少ない)、さらに探る必要があろう。 高齢化が進んだ国の中でも日本は肉体労働比率が低いが、イタリアでは逆に高くなっているのは、外国人労働者が多いせいかもしれない。 対象となった国は、図の順に、ポルトガル、ニュージーランド、チリ、ポーランド、米国、アイルランド、イタリア、ハンガリー、リトアニア、カナダ、チェコ、スペイン、スロバキア、オーストリア、ラトビア、ドイツ、英国、スウェーデン、フランス、オランダ、ノルウェー、デンマーク、スイス、ベルギー、韓国、エストニア、イスラエル、日本、フィンランドである。 (2025年9月2日収録)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||