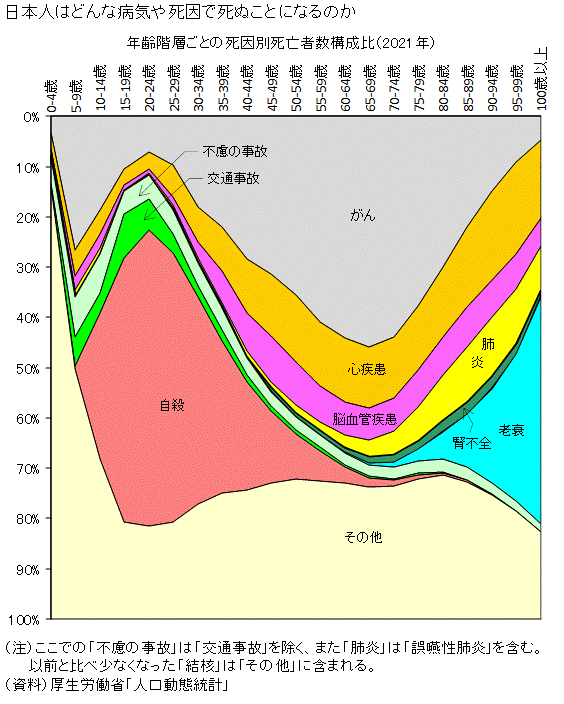
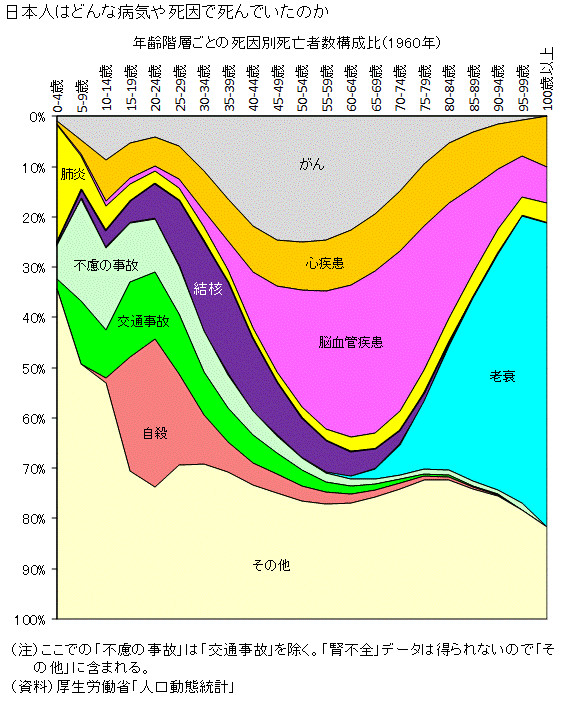
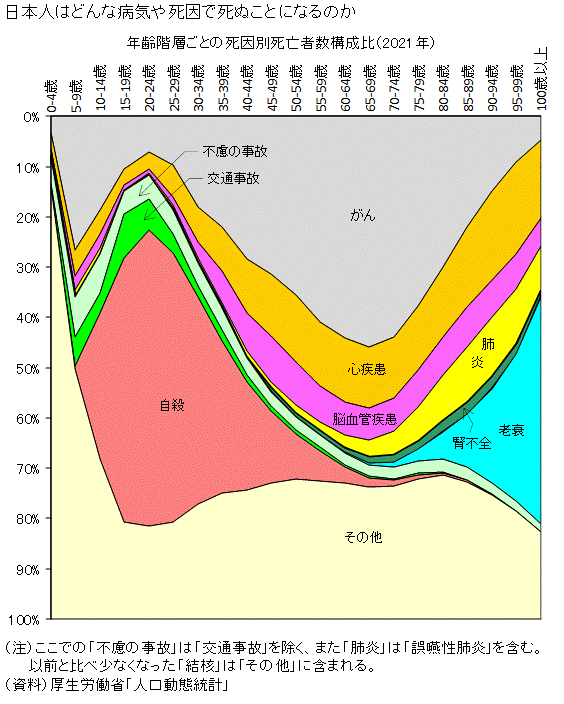
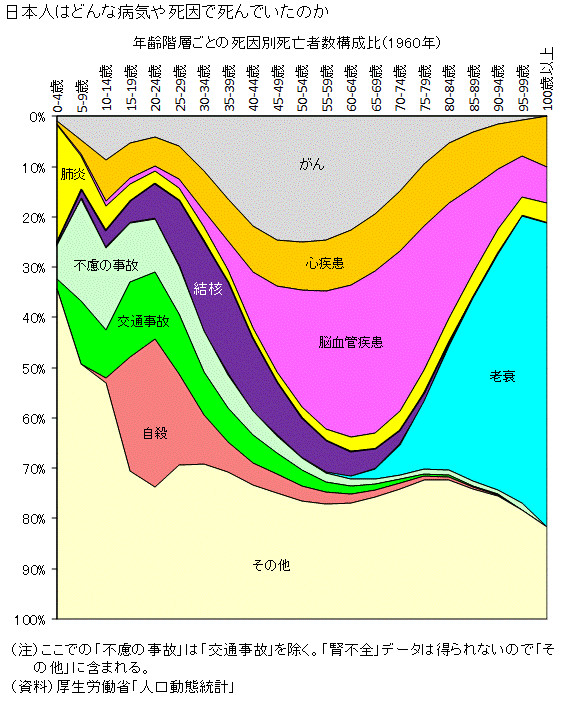
図録は、年齢階層ごとに死因別の死亡者数構成比をグラフにあらわしたものである。母数となる死亡者数の規模が年齢で大きく異なることを知った上で死因割合を理解する必要がある。下図に対象としている両年の年齢別死亡者数を示した(年齢別の死亡者数の推移については図録1555で詳細をふれた)。 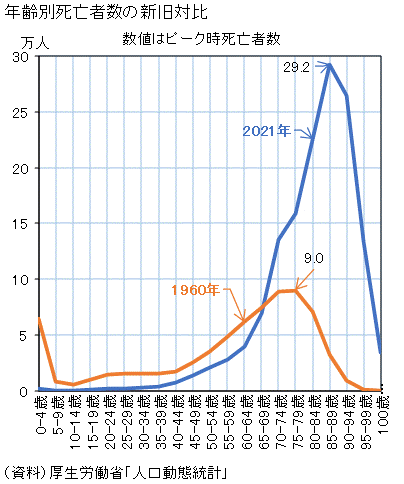 現代では少なくなった幼児期の死は小児がんや種々の小児疾患が多い。また、やはりかつてと比べて非常に少なくなった青年期の死亡の死因としては自殺が多くなっている。 中高年期に入ると年とともに、がん、心疾患、脳血管疾患という三大成人病と呼ばれる病気によって死ぬ者が増えていく。 ところが、65〜69歳の時期を境に、心疾患や脳血管疾患は相変わらず多いままであるのに対して、がんの割合は減少に転じる。その一方で、肺炎(誤嚥性肺炎を含む)や老衰が年齢とともに増加する。 一番死亡数が多い85〜89歳以降は、これらのいずれかで死ぬ確率がほぼ同等に近づく。また、これらほどではないが腎不全や転倒などの不慮の事故で死ぬ場合も一定程度ある(死亡者数のピーク年齢については図録1557参照)。 参考までに、若い世代でも死亡数が多かった1960年頃の年齢階層別死亡者数構成比のグラフを掲載した。 こちらを見ると、幼児期から青年期にかけて、今ほど自殺の割合は高くなく、肺炎や結核といった感染症による死亡が戦後直後ほどではないがなお多く、また川遊びで溺れ死ぬといった不慮の事故、あるいは無茶な運転による交通事故死などがかなり多かった。自殺の割合は現代ほど圧倒的ではなかった。 中高年から高齢期には、今よりがんの割合は小さく、心疾患や特に脳血管疾患の割合が大きかったのが1960年頃の実態である(日本ではかつて脳血管疾患による死亡が世界の中でも特に多かった点については図録2090参照)。 老衰死については、現代よりずっと多かったことが分かる。死因が不詳の死が老衰と判断されることが今より多かったためであろう。従って、主要死因別死亡率の長期推移で老衰が最近顕著に増えているのは(図録2080)、単に、老衰死が多い後期高齢者の割合が激増しているからにすぎないことが分かる。 このように何歳ぐらいで死ぬかだけでなく、年齢ごとにどんな病気や死因で死ぬことになるかについても時代の変遷とともに大きく変貌をとげてきているのである。 また、こうした観察を行うと、若者の自殺死因の多さを過剰に社会問題として憂慮したり、65歳前後の時期ならともかく後期高齢者に近づいた人が、心筋梗塞や脳梗塞・脳出血といった血管系の疾患や肺炎などよりがんの方ばかりを心配するのは余り合理的でないと示唆されるのではないだろうか。 (2022年10月14日収録、2023年7月18・19日年齢別死亡者数参考図)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||