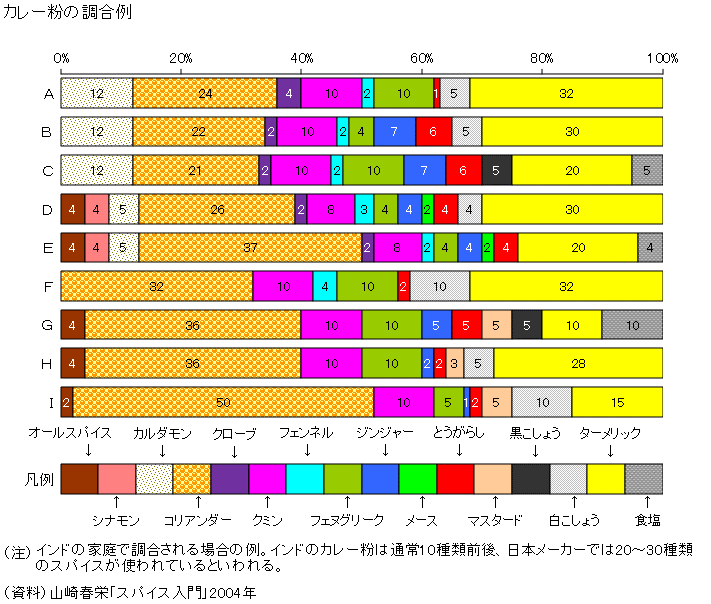
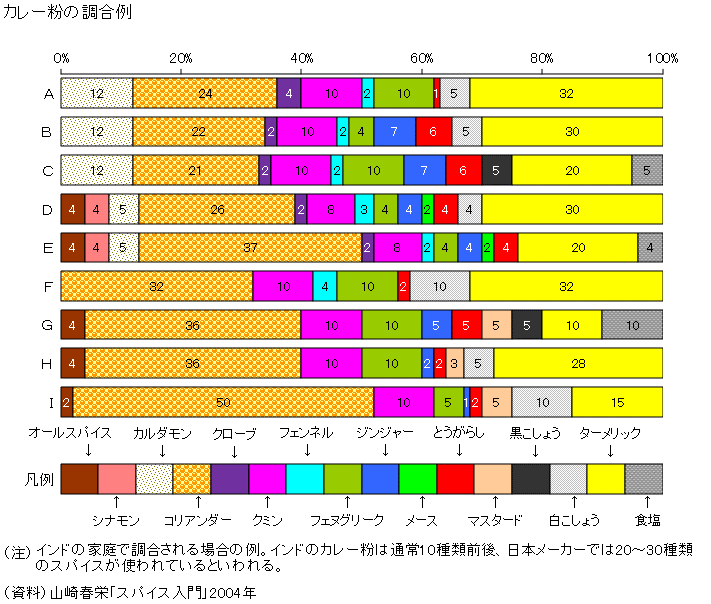
インドにおけるのカレーの作り方は、日本のように市販のカレー粉やカレールウを使って調理するのではなく、常備している何十種類ものスパイス(香辛料)の中から10種類前後を自在に組み合わせてその日毎のカレー料理に仕上げていくといわれる。調合傾向は家庭により異なり、地域や宗教、民族、カーストによって異なる。例えば、ヒマラヤの近くの北部では温和な調合が多く、インド南部ではヒリヒリ辛い調合が好まれるといわれる。水とこね合わせてペースト状にして使用する。やはり家庭で作られる1カ月など作り置きの乾燥混合スパイスはガラムマサラと呼ばれる(山崎春栄「スパイス入門」日本食糧新聞社、2004年、森枝卓士「カレーライスと日本人」講談社現代新書、1989年)。 ここではそうしたカレー料理に使用するインド家庭でのスパイスの調合例を示した(各スパイスの使用頻度については図録0214参照)。 A〜Iの9種類のカレー粉に必須となっているスパイスは、コリアンダー、クミン、フェヌグリーク、とうがらし(トウガラシ)、こしょう(黒又は白)、ターメリックの6種類である。また、フェンネルとジンジャーは6種類で、オールスパイスとカルダモンは5種類で使われており、これらに次いでよく使用されるスパイスであるといえよう。 こしょうばかりでなく、コリアンダーやクミンも日本人にとってなじみ深い香辛料になりつつある。ターメリックはウコン(鬱金)ともいい、ショウガ科に属する植物の根茎を利用し、インド料理では香りづけや黄色の色づけとして多用される。インド料理では「ほとんど全部に多少なりともウコンが入っているので、日本人が味わうと、どれもこれもカレー煮のように感じる」(中尾佐助「栽培植物の世界 (自然選書) 」中央公論、1976年)。中尾はフェヌグリークもインドでは一般的だと報告している。「インドで市場を散歩してみると、非常に多種類の香辛料を売っており、それを鑑別するのはなかなか面白い仕事である。そのなかであんがい多い印象を受けたものにコロハ(胡廬巴、フェヌグリーク)がある。コロハはマメ科の低草で、種子に微香と微苦味があるが、多量の粘液を出す特色のほうがいちじるしい。インドでは蔬菜の漬物に加えたり、カレーに和したりしている」(同上)。 これらのスパイスの他、図にあるように、シナモン、クローブ、メース、マスタード、食塩が組み合わされる。図には登場しないが、ナツメグ、スターアニス、リカリス、アニス、ディル、キャラウェー、ローレル、サボリー、オレガノ、ローズマリー、セージ、マジョラム、タイム、バジル、マンダリン、ガーリック、パプリカ、サフランなど、要するにほとんどすべてのスパイスが使用される。 英米で販売されているカレー粉に含まれているスパイスについては以下の調査結果が報告されている。
英米のカレー粉の主要成分はインドのカレー粉と共通である。ただし、インドと異なり、ガーリック(ニンニク)がかなり使われる一方でトウガラシとコショウは案外入らないことも多いようだ。 辛島昇・辛島貴子「カレー学入門」河出文庫(1998)によれば、9世紀の南インドのタミル語刻文資料には、カレーの元祖と思われるクーットゥと呼ばれるヨーグルト(タイル)とカーヤムという調味料で作る野菜料理が神様への供え物として記されており、その調味料の組成はミラフ(胡椒)、マンジャル(ターメリック)、ジーラハ(クミン)、シル・カドゥフ(マスタード)、コーッタンバリ(コリアンダー)の5点とされているという。現地インド人が指摘する重要スパイスと照らし合わせても、17世紀に新大陸からもたらされたトウガラシを別にすると、この5つの香辛料がカレーの必須要素だとしている。なお同書によれば、カレーの食文化はスパイスの豊富な南インド、ドラヴィダ民族の間に古代に成立し、それが北インドに広がり、逆に北インド、アーリア民族のもとで成立したギーやヨーグルトといったミルクを主体とする食文化が南インドに広がり、両者が16世紀ムガル朝宮廷料理の中で結合し現代インド料理が創り出されたとされる。 図の必須スパイスとの違いとしては古代文献のマスタードが必ずしも必要でない点があげられるが、多分、新大陸からもたらされたとうがらしが代替した面があるということなのであろう(図録0460参照)。ノーベル賞を受賞したインド人の経済学者アマルティア・センは、偏狭な文化排外主義が国民の対外文化導入能力を過小評価する傾向のおろかしさについて、次のように巧みに表現している。「「国の伝統」という言葉は、様々な異なる伝統に対する影響の歴史を隠してしまうことができる。例えば、われわれが理解する限りは、唐辛子はインド料理の中心的な部分(人によってはインド料理の「主題曲」とさえ見る)かもしれない。しかし唐辛子はポルトガル人がわずか数世紀前に持ってくるまではインドでは知られていなかったのが事実なのである(古代のインド料理法では唐辛子でなく胡椒を使った)。だからといって、今日のインドカレーがその分だけ「インド的」でないということにはならない。」(アマルティア・セン「自由と経済開発」日本経済新聞社、原著1999年) カレーの起源については、上記のドラヴィダ民族をさらにさかのぼるインダス文明(盛期BC2600〜1900年)に求められるという見解もある。「総合地球環境学研究所でインダス文明プロジェクトを率いた言語学者の長田俊樹は、ガッガル河流域のファルマーナー遺跡の人骨に残った歯石の分析から、ターメリックやジンジャーなど、カレーにつきものの香辛料を使った料理を食べていたとの興味深い研究成果を紹介している。カレーの原型がインダス文明にあったことになる」(山下博司「古代インドの思想: 自然・文明・宗教」ちくま新書、2014年)。 以下にインドのカレーと日本のカレーの対比を掲げた。日本式カレーは、インドから直輸入ではなく、まず、ベンガルから英国に入ったのち市販カレー粉と小麦粉を使う料理に進化し、これが洋食の1つとして明治日本に伝来し、これがさらに大正時代までにニンジン、ジャガイモを使う日本式に生まれ変わり軍隊食などを通じ家庭料理としても普及したものである。戦後、カレールウが普及し、国民食として確立した。インド式カレーも戦前中村屋がはじめて発売したが、最近はインド料理店が増えてめずらしいものではなくなった。エスニックブームでタイ式カレーなど東南アジアのカレー店も多くなっている。 インド起源のものが他国に入って独自に展開し、さらに日本に導入されて日本独自の発展をとげたという点では、カレー料理は、大乗仏教として中国・韓国に入り、さらに日本に導入されて独自の発展をとげた仏教と似ているといえる。仏教の場合、仏像や漢訳経典が歴史上カレー粉のような位置づけとなる。
(2008年1月31日収録、2月21日辛島夫妻資料による追加、2010年11月9日カレー年表項目追加、2011年4月2日ターメリック、フェヌグリークのコメント追加、2013年9月20日アマルティア・セン引用追加、2014年11月18日インダス文明起源説紹介、2016年4月15日カレー南蛮起源説の(注)追加、2019年12月7日英米カレー粉成分表、2019年12月15日日本式カレー年表追加)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||