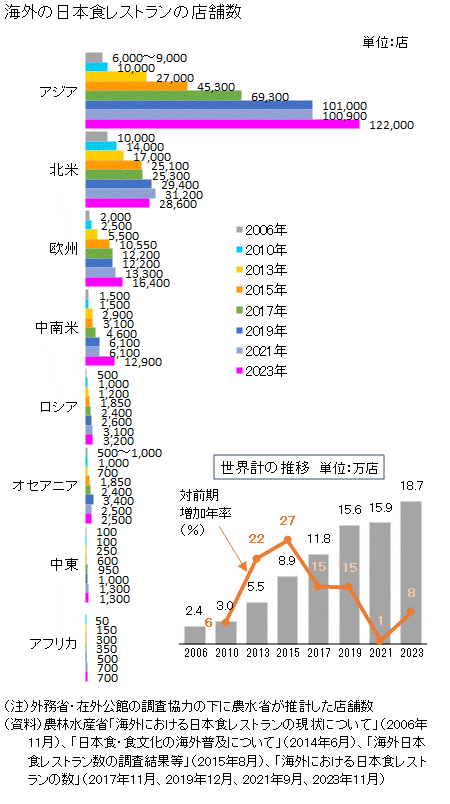
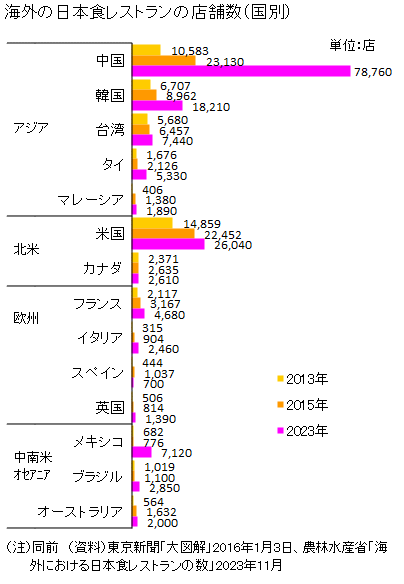
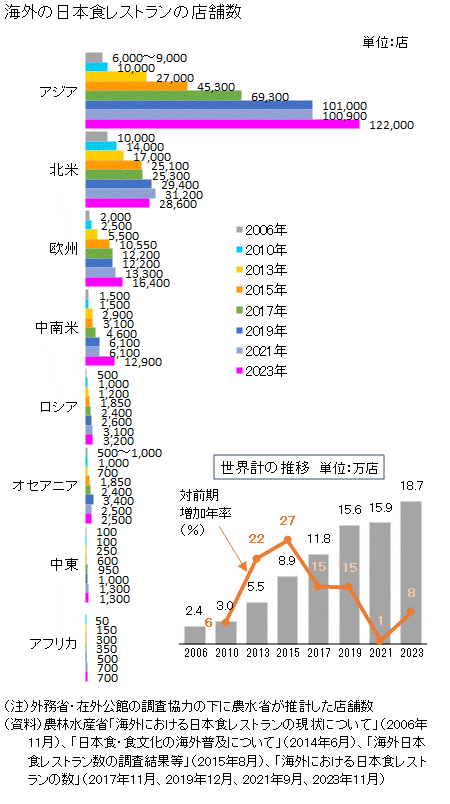
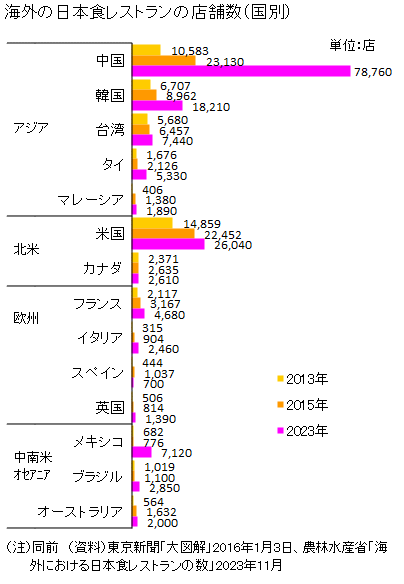
日本食レストランは2023年には世界で18.7万店となっており、2006年の2.4万店から17年間に7.8倍に増えている。 地域別には、アジアが12.2万店と約3分の2を占め最も多くなっており、北米の2.9万店、欧州の1.6万店、中南米の1.3万店と続いている。国別では中国(香港、マカオを含まず)が7.9万店と最大の集積を誇っている。米国が2.6万店、韓国が1.8万店でこれに次いでいる。 増加率の推移をみると2010年代前半には年率20%以上の急拡大であったが、近年は落ち着いた伸びとなっている。ただし2021年には新型コロナの影響で伸びがゼロに近かった。 前期2021年との対比では、北米が新型コロナの影響もあって約1割減となっているのに対して、アジア、欧州はいずれも約2割の増加となっている。中南米の増加が2倍以上と特に目立っているが、「メキシコやアルゼンチンで「ONE PIECE(ワンピース)」や「鬼滅の刃」などのアニメが人気で、日本食の需要拡大につながった可能性がある」(東京新聞2023.11.11夕刊)とされている。 海外に活路を見出そうとする外食大手の動きも進んでおり、2013年には天丼チェーン「天丼てんや」がタイに進出し、現在は中国、香港、フィリピン、シンガポールを加えた5か国・地域に計30店舗余りを展開している。「タイでは現地の定番料理に欠かせないガバオソースによる味付けや、ナマズの天ぷらといった地元の味覚に合わせたメニューも提供する」(同上)。 (2021年段階のコメント) ここで「日本食レストラン」とは、海外で日本料理の看板を掲げ、料理を出しているレストランのことを指す。厳密な日本料理ではなく、海外の食文化と融合した広い意味での日本料理を提供している場合があり、日本食ブームに便乗して中国料理などからの看板の掛け替えなどにより、本来の日本料理とはかけ離れたものを出している店も含まれるという(東京新聞大図解「海外へ広がる日本食」2016年1月2日)。 海外における日本食ブームのおこりは、1970年代末に米国のニューヨークとロスアンジェルスを拠点におこったスシ・ブームであるとされる。変化が起きている時には、そのさなかに現地調査をしないと時機を逸すると考えた石毛直道らは1980年に現地の50軒ほどの日本料理店を訪れてインタビューとアンケート調査を行った。結論的には、「米国の一部地域で、高所得層がまず在米日本人向けの店ですしを食べ、すしは健康食という評価が広まってブームが起きた。それが世界中に波及していったのである」(石毛直道「私の履歴書」(21)日経新聞、2017年11月22日)。 地域別の日本食レストラン数は2010年までは北米が最も多く、2013年以降にアジアが北米を上回るに至った。こうした点にもブームの発祥が米国にあることがうかがわれる。 タイでは日本食レストランがバンコクだけでなく地方にまで出店が増え、下図のように右肩上がりの増加を見ている。2013年のビザ緩和も一助となって訪日の機会が増え、日本の味を知る人が増えたのもこうした増加の一因という。 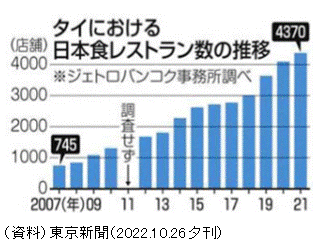 (2016年段階のコメント) 最新データでは、地域別には、アジアに6割近くの6.9万店、これに続いて、北米に2.5万店、欧州に1.2万店となっている(2017年)。国別は、2013年のデータだが、中国の2.3万店、米国の2.2万店が多く、これに、韓国、台湾が続いている。欧州では、フランスが3千店と最も多く、イタリア、スペイン、英国の3倍以上となっている。欧州ではフランスの日本食人気の高さがうかがわれる。 2015年から17年にかけての世界の増加店舗数は2.9万店だったが、そのうち2.4万店はアジア、1.8万店は中国が占めており、中国における日本食ブームが大きなインパクトを与えている。 毎日新聞(2017.12.30)によれば、「中国で日本食レストランが急増している。この2年で店舗数は約2倍になり、刺し身、天ぷらといった日本の味が定着しつつある。安全、ヘルシーという日本料理の印象の良さに加え、訪日旅行客の急増で本場の味に触れた経験が日本食レストランの人気を支えているようだ。(中略)在中国日本公館の調査によると、中国の日本食レストラン数は17年時点で約4万800店。15年調査で約2万3100店、13年調査では約1万600店にとどまっており、2年で約1.8倍、4年で約3.9倍という急増ぶりだ。農水省の推計では海外の日本食レストラン数は約11万8000店(17年時点)。約3分の1が中国に集中している計算だ。以前は北京、上海といった大都市が中心だったが、江西省の増加率が2年で約9.1倍、河南省が約5.8倍になるなど最近は中国内陸部への浸透ぶりが際立つ。沿岸部より人件費の安い内陸部は近年、成長率が高まっている。中国メディアは、個人所得の向上に伴い「安全・安心」な食を求める消費者が増えたことが日本食人気につながっていると分析。訪日旅行客の増加で日本食に触れる機会が多くなったことも背景にあるとみられる」。 世界的な日本食ブームの背景としては、和食が2013年にユネスコ(国連教育科学文化機関)の無形文化遺産に登録された点、世界中でブームの日本のアニメでカレーライスや弁当などの食事シーンから日本食に興味をもつ人が増えている点、そして上述のように中国で日本食がブームになっている点などがあげられる。 私の考えでは、肉食を忌避してきた長い日本の歴史から、日本人は食事が基本的に味気なかったので、だしの開発や寿司の持続的革新などいろいろと独自な工夫を積み重ねながら肉食以外の要素でおいしさを追求してきたが、こうした蓄積が、今になって、期せずして、肉によるうま味追求に飽きた文明の成熟や肥満に陥らないための世界的な健康ブーム、脱肉食嗜好に応えることになったため日本食ブームが起きたと捉えられる(図録0214参照、寿司の歴史は図録7762参照)。そして日本食は日本文化が独自に世界に貢献しうるひとつの重要要素に過ぎないと考えられる(図録9463参照)。 国別で取り上げたのは中国、韓国、台湾、タイ、マレーシア、米国、カナダ、フランス、イタリア、スペイン、英国、メキシコ、ブラジル、オーストラリアである。 (2016年1月3日収録、図録0209から独立、1月4日補訂、2018年1月1日更新、6月4日2006年値追加と石毛引用、2021年8月4日更新、2022年10月26日更新、タイでの増加、2023年11月11日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||