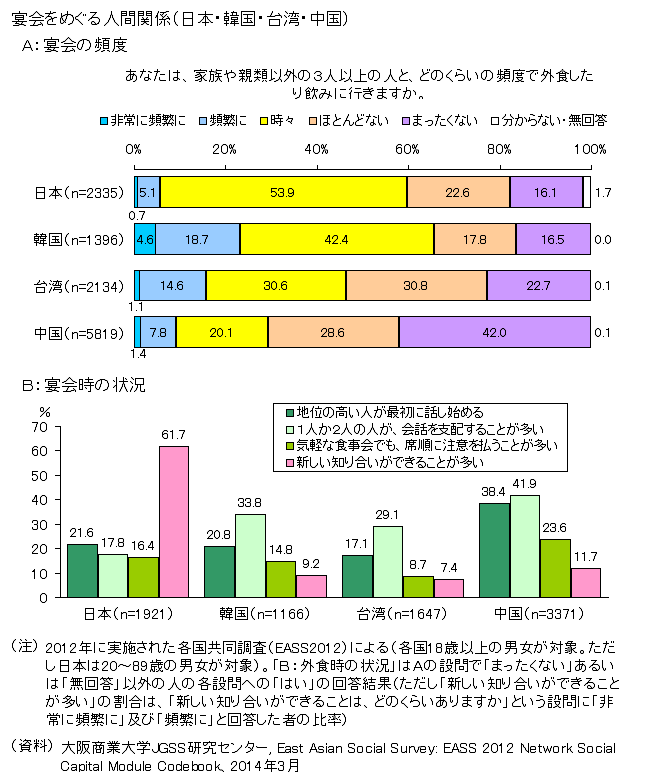
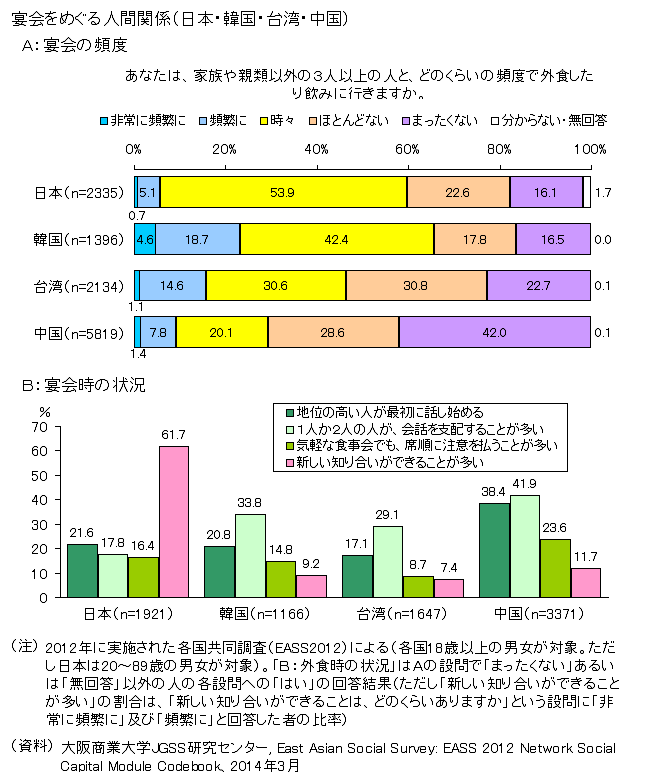
宴会の頻度では、「非常に頻繁に」と「頻繁に」を足した割合で見ると、もっとも頻繁に宴会が行われているのは韓国であり、台湾、中国がこれに続いている。宴会は「まったくない」人が多い中国でも頻繁に宴会する者は日本より多いのである。これに対して日本は「頻繁」は少なく、むしろ「時々」の値が最も多くなっている。 宴会時の状況を見ると、日本では「新しい知り合いができることが多い」とする者が6割以上となっており、韓国、台湾、中国が1割前後と少ないのと対照的な値となっている。 中国では最初の発声者が地位の高い人である点や1〜2人が会話を支配する割合の高さから、地位の高い人や主要人物が宴席を主導している点が目立っている。韓国や台湾でも最初の発声者は中国ほど限定されていないが、1〜2人が会話を支配する割合は中国に次いで高い。 日本は最初の発声者や席順を気にする点では中国に次いでいるが、会話は韓国や台湾より自由に行われている。 以上を総合すると、日本では、宴会が、既存集団の結束を図るため以外に、人間関係の輪を広げたり、新しく結成された集団の結束を図ったりするための常套手段として活用されているのに対して、それ以外の国では、むしろ、宴会は職場や取引先などとの既存の人間関係を固めることに努力が傾けられているように見える。 酒盛りの習慣から日本人が飲み会好きであることを指摘する論者が多い。「どこの国でも男の人たちはお酒が好きです。しかしその中でも日本人は酒好きではないかと思います。これは神のまつりには必ずお酒を供え、そのあとで、みんながわけ合って飲むならわしがあったからです」(宮本常一著作集〈24〉食生活雑考 (1977年) 柳田国男は日本人が皆で一緒に酒を飲むこうした習慣を「群飲制度」と呼び、懇親の手段としての根強さを強調した。古くは村人同士の意気投合に役立った。「祭礼その他の晴れの日の式というものは、それ自身が昂奮の力をもっていたのだけれども、なお一時に多数の人の気持を揃えさせるべく、酒によってある種の異常心理を作り出す恒例となっていた」(柳田国男「明治大正史 世相篇 明治以降になると、群飲制度は、あらたな集団形成の手段となった。「知らぬ人に逢う機会、それも晴れがましい心構えをもって、近づきになるべき場合が急に増加して、得たり賢しとこの古くからの方式を利用しはじめたのである。明治の社交は気の置ける異郷人と、明日からすぐにもともに働かねばならぬような社交であった。(中略)根本は人が互いに知り、速やかに全国感覚の統一を図ろうという志にあったので、いわば世間知識の授業料の覚悟をもって、この第三生活費の膨張を厭わなかったのである」(同217〜218)現代における男女の集団見合いともいうべき「合コン」もこうした宴会パターンの派生形態と位置づけられよう。 柳田国男は、酒宴の機能が村人の結束を図る役割から転じて、明治以降、見知らぬ日本人同士の懇親手段として国民統合に役立てられたと論じている訳であるが、図録のデータは、こうした見解と整合的である。 中国の宴会作法についてはが西澤治彦「中国食事文化の研究―食をめぐる家族と社会の歴史人類学 中国では、日本のように各人の食器に料理が盛られていないので、作法は、各人の食器から口の段階だけでなく、その前の共同食器から各人の食器に取り分ける段階にも及ぶ。「中国人は、子どもの頃から家庭での食事を通して、取り分けて食べる際の他者への気遣いというものをしつけられる」。客や子供はおかずばかり食べず、ご飯を多く食べること(「少喫菜、多喫飯」)が適切とされる。「ところで、中国人のこの社交性というのは、日本人が考えるものとは多少異なるようである。中国人が相手の立場を考えるというのは、一方で自分の立場を守る為におこなうことである。食事の場合を例に言うと、同席者に人よりも食べ過ぎていると思われない範囲内で、いかに多く取るか、というゲームをしているとも言える」。 中国人にとって、既存集団の結束を図るため、宴会は重要である。招く主人と招かれる主客が明確であり、友人同士でも割り勘はない(言葉もない)。「中国人にしてみれば、その席で誰が払うかということは大体決まっており、通常は誘った人が払う。この時、ご馳走になった人はお礼を言うことをしない。」また「食卓内での平等性・共同性と、食卓外への無関心」が顕著であり「中国人の家庭内での結束の強さ、及び他者に対する無関心については、従来よりよく指摘されてきた通りである」。 西澤治彦氏は、また、中華料理店で必ず見られる回転テーブル(ターンテーブル)を主客座順にこだわる中国人がつくった筈がないと考え、それが、日本人の発明だとする説を確かめるため目黒雅叙園に訪問調査を行っている。「回転テーブルは、昭和7(1932)年前後に、目黒雅叙園の創業社長である細川力蔵氏が考案して作らせたもの(中略)目黒雅叙園に来る客層は資産家などに限られ、また大皿料理という性格上、女性らは箸をのばすスタイルに遠慮がちであり、なかなか多くの人に楽しんでもらうには至らなかった。そこで、料理に手を伸ばしやすいよう、回転テーブルを載せたらどうかと細川氏が考案したという」(注)。 (注)回転テーブルには雅叙園以前の導入説もある。1931年1月発売のグルメ本「東京食べある記」(松崎天民著)では日本橋浜町「濱の家」にあると紹介されており、同年11月には松坂屋が「開化食卓」という名で売り出したとする新聞記事もあるという(東京新聞「東京トリビア」2014.10.1)。西澤治彦氏によれば「ただ細川氏が金物師に作らせたのはこれらとは違い、回転部分がパイプを組み合わせた一本軸の構造。後に職人が「特許を取っておけば良かった」と話した記録があり「細川氏がアイデアを参考にした可能性があるが、現在の形のルーツは雅叙園にあるのでは」と話す。華僑の人々が日本で見て、戦後本国に持ち帰ったと考えられるという(同記事)。 さらに、これらをさかのぼる1915年に上海で活動するペナン生まれの中国人医師・衛生学者の伍聯徳が、専門医学雑誌で、従来のように自らの匙や箸を共通の大皿につけて他者に感染させずに、回転台に置かれた各皿の料理に別々の取り分け匙を準備する方式が衛生上好ましいと考え、「衛生食卓」と命名した回転テーブルを提唱していた。料理史家の岩間一弘は「近代の日本人は、おもに上海から中国料理を受容していたので、最新の中国料理と同様に、回転テーブルも、上海で見聞した誰かが日本に伝えたと考えるのが自然」としている(「中国料理の世界史」慶應義塾大学出版会、2021年、p.517)。そして回転テーブルの日本発祥説は文化ナショナリズムと批判している。ただし、日本より前に回転テーブルが上海の料理店で中国の接待習慣より衛生を優先して実際に提供されていた証拠を挙げていない点が弱点の説と言えよう。 今日では香港、台湾、中国本土でも大きなレストランなどでは円卓と合わせて回転テーブルが普及したが、元はと言えば、主客、新参者、男女が入り乱れての宴会もまたよしとする近代日本の新気風から生まれ、同様の必要が生じた東アジアに広く普及していったものなのである。 卑弥呼の時代の倭の国について古代の中国人は「魏志倭人伝」の中でこう伝えている。「その集会や居住の坐位には、父子男女の区別はなく、人々は性来酒が好きである。支配身分の人に尊敬を示す作法は、ただ拍手をして、中国の跪拝の礼にあてているようだ」(弥生ミュージアムサイトから)。古代の中国人にとっても日本の宴会のこだわりのなさは意外だったようだ。日本人の宴会パターンは太古から余り変っていないようだ。 図録を見ると、こうした中国や日本の宴会パターンの構図や推移が現代のデータに反映していると考えられ、まことに興味深い。 最後に、もう1つ、知っておいたほうが良い日本と中国との食卓作法の違いにふれておこう。それは宴会の食事を残す方がよいのか残さない方がよいのかという点についての正反対の考え方についてである。「食事に招かれた際に、客が全部平らげてしまうと、接待側は量が足りないと判断し、家庭であればさらに料理をつくったり、レストランであれば追加注文することがよくある。日本では食べ残すと、料理が口に合わなかったと思われるため、残さず食べるのが作法であるが、中国では逆である」(西澤2009)。テレビなどで中国人の宴会の後を見ると、食べかすを机の上に残すだけでなく、食べ残しが多く、日本人にとっては、全体にいかにもきたならしいという印象をもつが、それなりの作法の結果という側面があるのである。 (2014年9月12日収録、10月4日回転テーブルの雅叙園以外の導入説を追加、2016年3月17日魏志倭人伝引用、2022年1月6日回転テーブル中国発祥説)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||