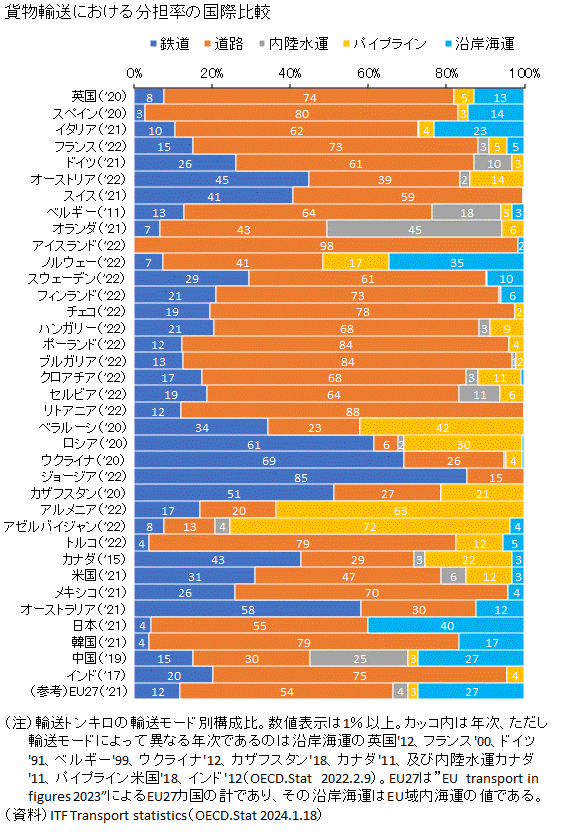
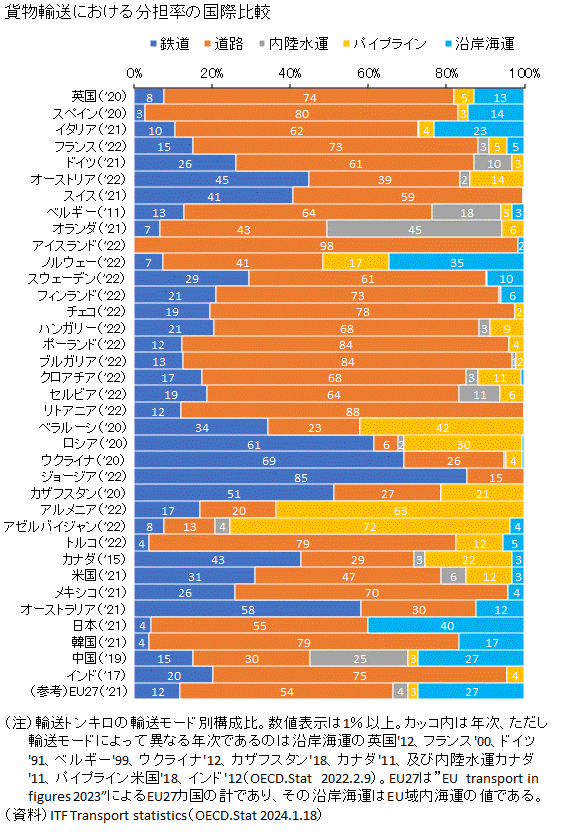
図には、ITF(International Transport Forum:国際交通フォーラム、OECDの下部組織)が公表しているデータを使って、主要な加盟国の輸送モード別の貨物輸送分担率をあらわした。 同じデータを使って主要国の輸送モード別の輸送量推移を図録6400に、またロシア・ウクライナの同推移を図録6403に掲げているので参照されたい。 36か国の比較図を俯瞰的に眺めると、鉄道先進国だった西欧諸国では今や道路輸送が大勢を占めるようになっている点(オーストリア、スイスは例外)、旧共産圏の中でも旧ソ連諸国では鉄道輸送が非常に高いシェアを占めている点、また米国、カナダ、オーストラリアといった西欧の旧海外植民地ではやはり鉄道のシェアがなお高い点などが目立っている。 ロシアを中心とする旧ソ連、さらに米国、カナダを含め、東西の交通路が基軸となる大陸国では鉄道の地位がなお高くなっているといえる。 同じ大陸国でも古来より東西方向の大河や南北方向の運河による大動脈が大きな役割を果たしていた中国では鉄道の地位はそれほど高くなく、むしろ内陸水運のシェアが高いという特徴がある。 それでも、鉄道輸送量の実数を各国比較すると大陸国での輸送量の大きさが目立っている(下図)。 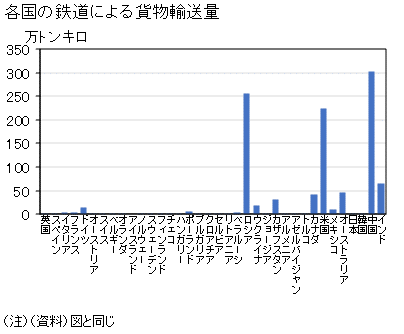 なお、中国以上に内陸水運が目立っているのは、運河の国とも言うべきオランダであり、内陸水運の分担率は45%と最大となっている。お隣のベルギーも似たところがある。 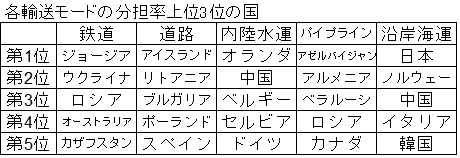 日本については沿岸海運のシェアが40%と36か国中もっとも高い点が目立っているが、同じ島国の英国や半島国のスペイン、イタリア、ノルウェー、韓国などでも、やはり、沿岸海運の地位が大きくなっている。また、中国も沿海部での経済発展の著しいこともあって内陸水運だけでなく沿岸海運の分担率がかなり高くなっている。 西欧諸国の沿岸海運の分担率はノルウェー、イタリアなどを除いてそれほど高くないが、これはデータがそれぞれの国の国内輸送に限定されているからである。EU域内海運を沿岸海運として含めたEU全体の分担率を参考までに図に示したが、これで見ると沿岸海運の分担率は27%と中国並みに大きいことが分かる。 ロシアやベラルーシ、アルメニア、アゼルバイジャンではパイプライン輸送のシェアが大きい点が目立っているが、石油や天然ガスといった資源の生産と輸出が多いせいであるが、鉄道とあわせ、かつての計画経済とマッチしていたという側面もあろう。 ロシアの物流構造の特徴は、鉄道、パイプラインといった装置型輸送路のシェアが高い点にある。道路輸送は6%と図の36か国の中で最少となっている。背景としては、国土が広く(またシベリアもあるため)道路整備が一部の地域に集中し、網羅的に発達しなかったことによるものとされている。 日本をはじめ欧米先進国では、重厚長大から軽薄短小への産業構造の転換、またジャストインタイム生産方式やドアツードア輸送に対応するきめ細かな配送需要の高まりに伴って高速道路を含む道路ネットワークのインフラ整備が進み、道路輸送のシェアが大きく拡大する傾向にあるが、ロシアはこうした動きに決定的に乗り遅れていると言わざるをえない。 ウクライナの輸送構造もロシアより道路輸送が多く、パイプライン輸送が少ないという違いはあるが、鉄道輸送の分担率はロシアより高く、なお、ロシアとの共通性が高いと考えられる。ジョージアもウクライナと同様の輸送構造をもっている。 取り上げた36か国は図の順に、英国、スペイン、イタリア、フランス、ドイツ、オーストリア、スイス、ベルギー、オランダ、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、チェコ、ハンガリー、ポーランド、ブルガリア、クロアチア、セルビア、リトアニア、ベラルーシ、ロシア、ウクライナ、ジョージア、カザフスタン、アルメニア、アゼルバイジャン、トルコ、カナダ、米国、メキシコ、オーストラリア、日本、韓国、中国、インドである。 (2022年3月26日収録、2024年1月18日更新、1月20日EU27データ)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||