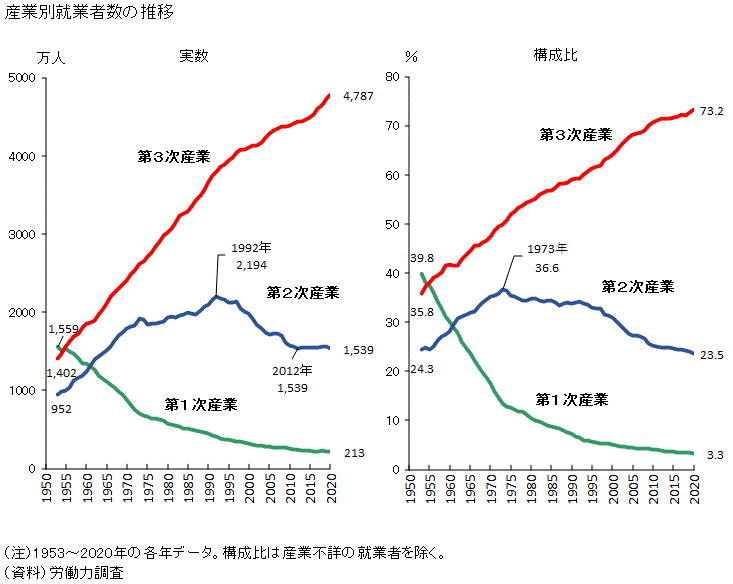
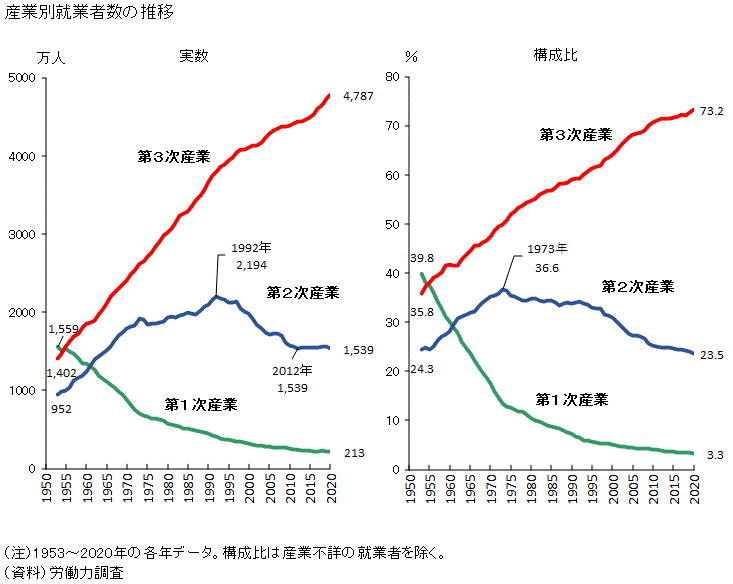
第1次産業就業者は、1953年には1,559万人と最も数が多かったが、2025年には187万人にまで減少している。構成比では同じ期間に 39.8%から2.8%にまで縮小している。また、1973年までの高度経済成長期にそれ以降と比べ減少のスピードが高かったことが図からうかがえる。 第2次産業就業者数も第1次産業の減少幅が大きかった時期に952万人から2,000万人近くまで2倍以上へと大きく増加した。その後も実数では増加を続けたが、構成比では1973年の36.6%をピークにして縮小に転じている点が目立っている。実数でもバブル崩壊後の1992年に2,194万人のピークを記した後、公共工事抑制等による建設業の低迷、円高に伴う海外への製造業シフトなどの影響で減少に転じ、2012年には1,539万人にまで低下した。しかし、その後円安による海外進出からの復帰などで横ばいに転じ2025年には1,513万人となっている。ただし、構成比は減少傾向を続け、2025年に22.8%となっている。 一方、第3次産業は、実数、構成比ともに安定的かつ一貫した増加を続けており、第1次産業や第2次産業とは対照的な推移となっている。 こうした産業構造の変化の実態を知っておくことも重要であるが、同時に、その理由を理解しておくことも大切である。こうした変化の要因としては、需要要因、輸出入要因、生産性格差要因の3つをあげることが出来る。 まずは、需要要因であるが、各産業の生産する財・サービスへの需要の伸びの差をあげることができる。所得が2倍になっても食料の消費は2倍にならない。すなわち、エンゲル係数は低下する。そこで第1次産業の需要は、他産業に比して伸びない。従って第1次産業の構成比は基本的には低下する。また、所得がさらに伸びてくるとモノよりサービスへの需要が高まる。特に高齢化が進むとモノの消費より医療・介護といったサービスへの需要が増加することは容易に想像できるであろう。従って、第2次産業より第3次産業の生産物のシェアが高まり、これが産業構造の変化にむすびつく。 第2に、輸出入要因である。第1次産業や第2次産業は貿易が可能な財を生産している。9割以上であった食料自給率は、2018年度速報では37%と低下している(カロリーベース)(図録0310参照)。自給率が低下しなければ第1次産業の就業者数はもっと多かったと考えられる。第2次産業についても、アジアにおける加工貿易基地として独占的な地位を築いた高度成長期には第2次産業の中心を占める製造業就業者数が増加したが、近年では、アジアの加工貿易拠点が、アセアン、韓国、台湾、そして中国へと多様化し、それらの地域へ工場も海外シフトした結果、第2次産業就業者数は減少するに至っているのである。 第3に、これが、最も重要な要因ともいえるのであるが、生産性格差要因、正確には生産性の伸びの格差要因である。図録4700の「傘と床屋の価格推移」で見たように、財と比較してサービスはどうしても労働生産性の伸びが低い宿命にある。自動車であれば、同じ性能の商品をより少ない工数(延べ労働時間)で生産することが可能であるが、より少ない先生の数で同じ教育内容を生徒に提供することは難しいのである。医療、介護など社会にとって重要なサービスは同様の性格をもっている。従って、需要要因、輸出入要因が不変であったとしても、この要因により、第3次産業就業者数は相対的に拡大せざるを得ないのである。社会が必要とする自動車の数と医療サービスの量とが同じであっても、自動車産業従事者数より医療産業従事者数の方がより多くなるのは当然なのである。 このように考えると、衰退産業と成長産業という言い方も気をつけなくてはならない。第1の需要要因によって影響されている限りは確かに、衰退産業と成長産業の区分けは分かりやすいが、第3の生産性格差要因によれば、生産性の伸びの高い成功している産業ほどシェア的には衰退するのである。農業も製造業も第1と第2の要因から縮小している面の他、生産性の伸びが高いためにシェア的には縮小している側面もあることを忘れるべきではなかろう。 サービス経済化が産業の地域分布を平準化させている点については図録7490参照。 (2004年6月2日収録、2008年3月24日更新、2011年8月9日更新、2013年5月16日更新、2015年1月30日更新、2017年2月17日更新、2019年2月15日更新、12月13日構成比を近年拡大している産業不詳を除く数値に変更、2021年10月14日更新、2026年1月30日更新)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||