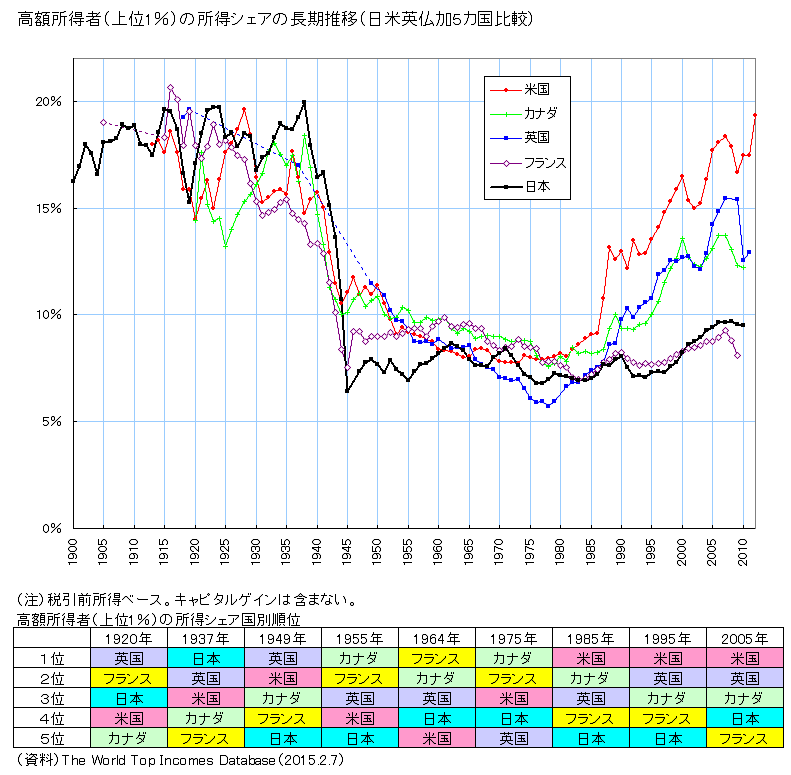
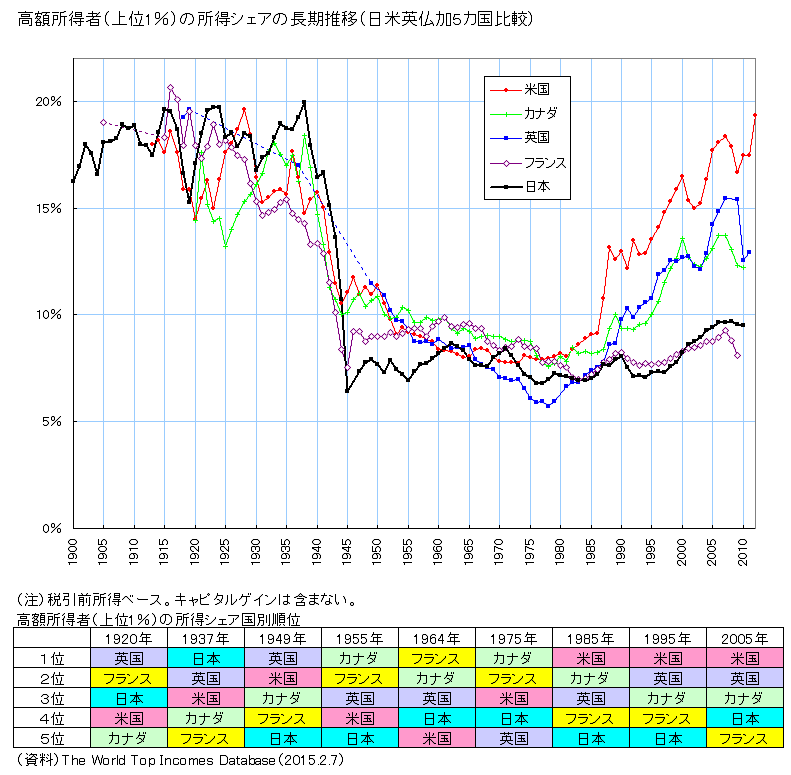
欧米でも格差問題が関心を呼び、ピケティなど高額所得者の所得シェアのデータベースを作成する研究者が出てきている。こうしたデータベースはThe World Top Incomes Databaseサイトに集大成されており、ここには主要国の高額所得者(所得上位1%層や10%層など)の所得シェアを戦前から追ったデータが掲載されている。ここでは所得上位1%層について日本、フランス、米国、英国、カナダの推移をグラフにした。 もっと多くのOECD諸国のデータ(ただし2時点比較のみ)は図録4656参照。また、所得格差ではなく資産格差の長期推移については図録4640参照。 まず、興味を引くのは、近年における動向である。1980年代後半から、米国、そしてカナダ、英国といった英語圏の諸国では、上位1%の高額所得者の所得が占めるシェアが大きく拡大している。一方、フランスと日本は、対照的に、戦後の推移は20世紀中はほとんど横ばいと言っていい動きを示しており、21世紀に入って英語圏諸国ほどではないがやや上昇傾向にある。 日本の場合、1980年代後半のバブル経済の時期に高額所得者シェアは上昇したが、バブル崩壊とともに1990年代前半には再度元の水準に戻った。しかし、1990年後半以降はバブル期を上回って高額所得者シェアが高まりつつある。 日本をはじめ先進国では、近年、所得格差が拡大傾向にあることは、図録4660で見た通りである。しかし、日本の場合は、米国等とは異なって、一部の高額所得者の所得シェアの拡大の影響はそれほど無いと言って良かろう。ホリエモンや村上ファンドなどヒルズ族の高額所得が話題になったが、米国の巨大企業の経営者やマクロソフトのビル・ゲイツなどとは異なって、社会全体における影響度はそう大きくないのである。 この他、この図は、いくつか興味深い点を明らかにしている。 どの国でも、戦前と戦後で高額所得者の所得シェアはまるで水準が異なっている点が目立っている。日本に関して、戦前の所得格差が著しかったことを図録4660に示したが、欧米各国も、戦前は、今とは比べものにならないくらい、高額所得差の所得の大きさが目立っていた。そして、米国だけが最近戦前の状況に近づきつつある。 もうひとつ目立っているのは、図の5カ国のいずれもが、高額所得者の所得シェアが、他国に比べ最大の時があったし、また最小の時もあったという点である。 高額所得者の所得シェアの面からは、日本は、1930年代には世界最大の所得格差国であったが、戦後は、世界最小の所得格差国となり、現在もフランスとともにほぼそうである。 現在、世界最大の所得格差国である米国も、第1次世界大戦後、及び1960年代前半は、世界最小の所得格差国であった。この他、英国、カナダ、フランス、いずれの国も所得格差最大と最小を経験している。 少なくとも活力のある国においては、経済というものはダイナミックな変転を遂げるものなのであろう。 ところで、「21世紀の資本」が世界的ベストセラーとなり、日本語版が出版されたのをキッカケに2015年の年初には来日し、講演会やテレビ出演など、あちこちでひっぱりだことなったピケティ教授が日本の格差拡大の証拠として示したのは上の所得上位1%の推移グラフでなく、下に示した所得上位10%の推移グラフであった(東京新聞「ピケティ教授に聞く」2015年2月8日、同じソースの図が示されているが国や時期範囲がやや異なる)。上の所得上位1%の推移と異なり、日本の格差は英国やカナダ並であり、大陸欧州より大きい(ここで示していないがドイツはフランスと日本の中間の水準)。日本にも格差拡大の世界的傾向が同じように当てはまっていると主張するには好都合なデータであろう。しかし、日本の場合は、高齢化により年金収入のみの層が他国と比較できないほど増大しており、所得上位10%には、所得上位1%よりも、年齢間格差による影響が大きく現れているといえるので、これをもって米英並に貧富の差の拡大が進んでいるとするのは少し無理があろう。なお、この点については末尾のコラム参照。 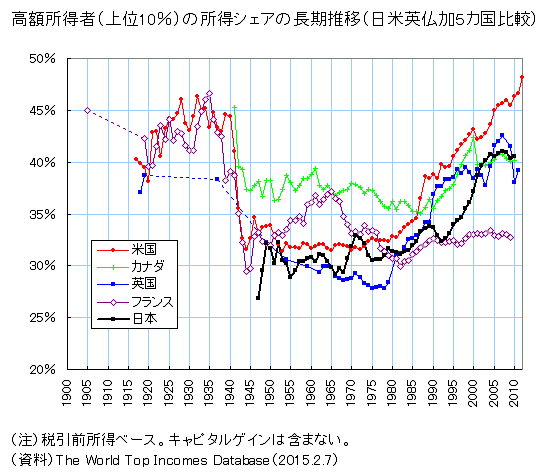
(2006年7月16日収録、2012年8月15日高額所得者データをThomas Piketty & Emmanuel Saezによる上位0.1%データからOECD報告書の上位1%データに変更、2015年2月8日ソースをOECD報告書からThe World Top Incomes Databaseに変更して更新、上位10%のグラフを追加、2月23日コラム追加)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||