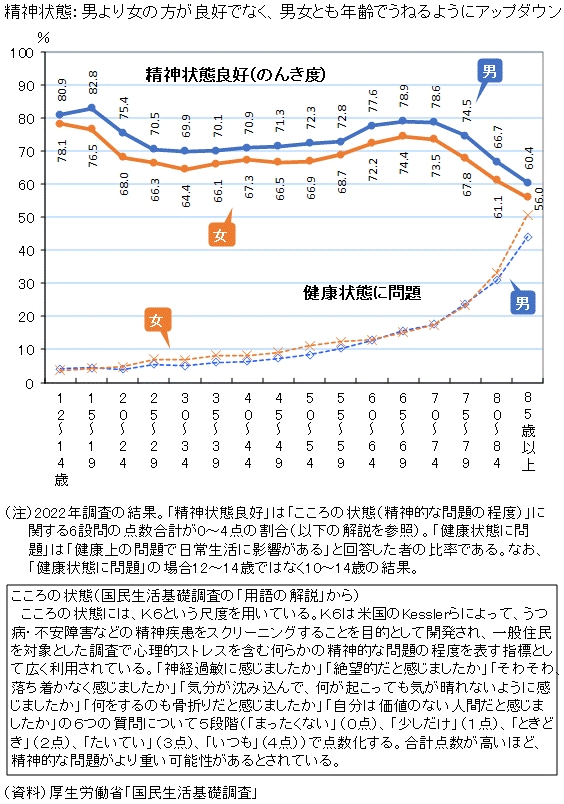
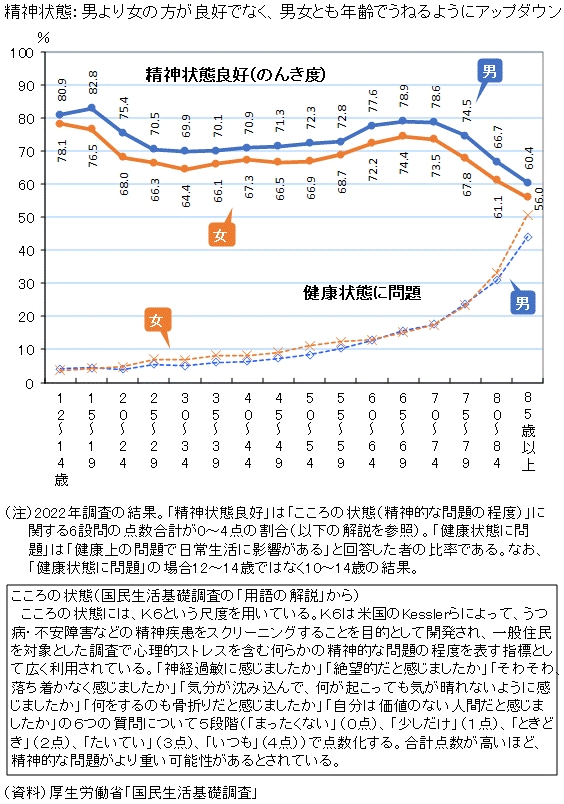
|
図に結果を掲げたが、精神状態が良好な人の割合(以下、「のんき度」と呼ぶことにする)は、5歳刻みのいずれの年齢でも、女性は男性を下回っている点が目立っている(設問の内容については図の(注)を参照、原設問文)。しかも、男女差は各年齢ともにほぼ一定である。 これは、うつ症状に陥るケースが男性より女性に多いことと整合的な結果である(図録2150参照、これが世界共通である点は図録2142参照)。 のんき度について、年齢ごとの状況を見ると、まず、10代では男女ともに8割前後だったのんき度が大学に進学したり社会に出たりする20代以上になると7割前後に低下する。両親に守られ悩みも少なかった子どもが、成人して、大人の世界の風雨にさらされることになるのだといえよう。 その後、青壮年期を通じてのんき度に余り大きな変化がなく、次の転機として、男女ともに、50代後半から60代前半にかけてのんき度がかなり高まる。子どもが独立したり、自分や配偶者が定年を迎えることにより、子育てなど生活上の問題や仕事上の問題に関する悩みやストレスから、ある程度、解放されるからだと思われる。 ところが、男女ともに65〜69歳をピークにのんき度は下降に転じるのが次なるもう1つの目立った特徴である。75歳を境に前期高齢者と後期高齢者とに分ける場合があるが、両者には、のんき度に関して50代までの人生とは異なる大きな落差が生じるといってよい。 その理由が健康上の問題であることはまず間違いがない。国民生活基礎調査の健康票では、こころの状態と並んで、日常生活に影響するような健康問題を抱えているかを聞いているが、図に示したように60代後半以降、特に70代後半以降に「健康問題あり」の人は加速度的に増えていくのであり、これと反比例で精神状態の良好さも失われるのである。健康寿命が大きな課題となるゆえんである。 もっとも、高齢となると悩ませられる疾病や老衰が、むしろ、深刻な精神的危機に陥るのを救っている面もあると、「生活の落伍者」、「敗残の東京人」だという批評を甘んじて受け入れていた永井荷風は記している。 「さればいかなる場合にも、わたくしは、有島、芥川の二氏の如く決然自殺をするような熱情家ではあるまい。数年来わたくしは宿痾に苦しめられて筆硯(ひつけん)を廃することもたびたびである。そして疾病と耄碌とはかえって人生の苦を救う方便だと思っている。自殺の勇断なき者を救う道はこの二者より外はない。老と病とは人生に倦みつかれた卑怯者を徐々に死の門に至らしめる平坦な道であろう。天地自然の理法は頗(すこぶる)妙である」(「正宗谷崎両氏の批評に答う」(昭和7年)『荷風随筆集(下)』p.207〜208)。 男女差はほぼ一定で推移すると上に述べたが、12〜14歳では男女差が若干小さいという傾向が認められる。50代前半で女性の健康状態が前後の年齢と比べてやや低下し、その結果、男女差の乖離もこの時期大きくなるが、これは、女性の更年期障害の影響と思われる。 同じ指標を使って、県民ののんき度を調べた結果は、図録7304参照。 最後に、性・年齢別のんき度の時系列変化を見ておこう(末尾図参照)。 2013〜19年について、全体としては、働き盛りの年齢では、精神状態良好度は低迷しているのに対して、10代、あるいは高齢層では精神状態の改善が見られる。 2019〜22年にはコロナ禍で世の中が大揺れした時期であるが、各年齢層を通じてのんき度はかえって上昇している点が非常に興味深い。2022年調査はこのデータが属する健康票については6月に実施されているが、6波と7波の間で感染者数が大きく減り、コロナ禍への慣れもあって感染不安はかなり低下した時期にあたる(図録1951p)。最悪の事態を何とかやり過ごしてほっとした感情がのんき度の上昇にむすびついたと解されよう。 2013年から2022年にかけての9年間の長期推移を男女・年齢別に見ると、男女ともに、10代〜20代前半と45〜54歳と70代の3つの山で上昇幅が大きく。それらをはさむ2つの谷と80歳以上とで上昇幅が小さくなっている。中でも、小さな子どもがいる女性の30代前半と心身の衰えがもっとも顕著な男性の85歳以上では変化幅がほぼゼロという点で他の階層と比べた時に、その精神状態の厳しさが目立っている。 逆に、大いに「のんき度」が増した層として目立っているのは、20代前半までの若年層男性と70代男女である。70代男女の「のんき度」アップは、体力アップ(若返り)や健康上の改善が理由と考えられるか、若年層男性の「のんき度」アップは、あくまで仮説であるが、男子はこうあらねばならないという精神的呪縛から若者男子が解放されつつあるからではなかろうか。 「のんき度」アップの男女比較(下図)では、女性の12〜24歳、30〜34歳、75〜84歳が男性と比較してアップ度が小さい点が目立っている。大学進学率が女性で特に上昇していることなどで12〜24歳女性は受験や進学の悩みでなかなかのんきになれない。また30〜34歳女性は子育てと仕事の両立で、75〜84歳女性は介護の負担で、男性と比較してなかなかのんきになれないのではなかろうか。 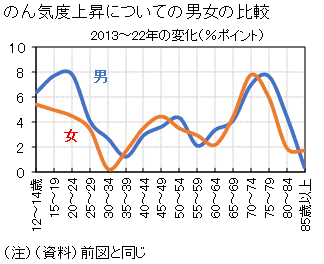 若者男子ののんき度上昇の理由を探るため、同じ国民生活基礎調査健康票の悩みとストレスの原因に関する設問について15〜24歳(およびうち15〜19歳)の結果の推移を示した図を参考までに以下に掲げた。2013〜2022年について、特定の悩みというより全体的に若者男子の悩みは低減しているようなので、やはり、のんき度上昇は、どんなことにもこだわらなくなったことによるのではなかろうか(男女・年齢別の悩みとストレスの現状については図録2720参照)。 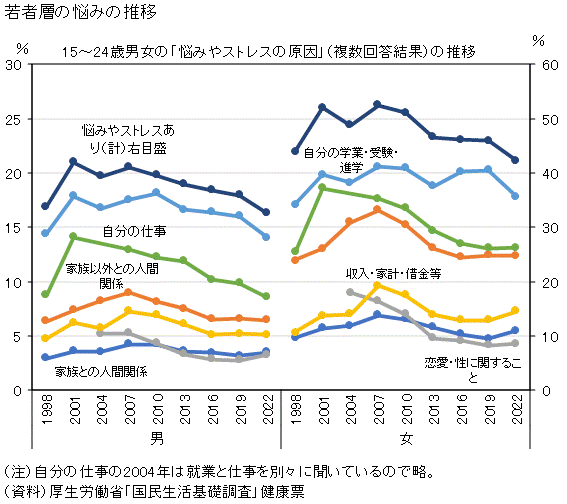 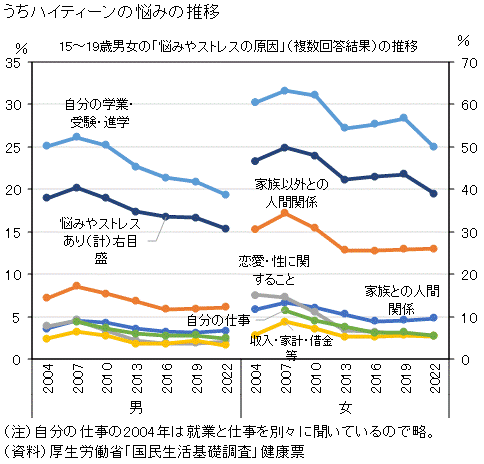 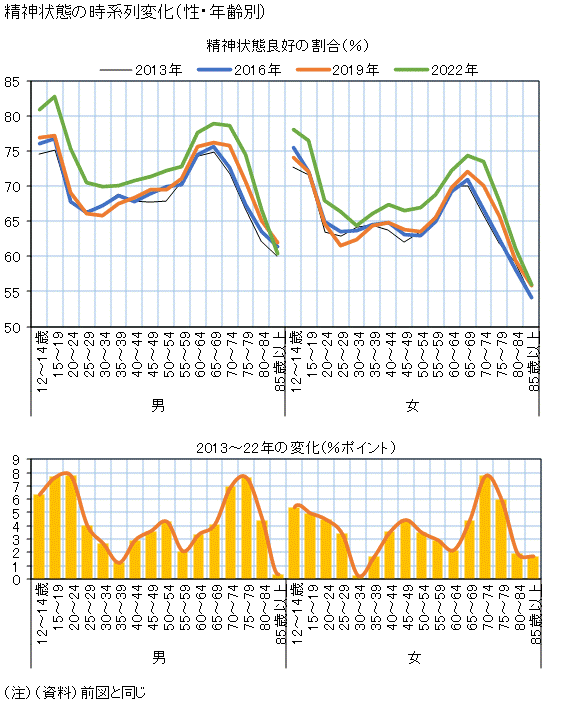 (2021年4月11日収録、6月9日荷風引用、2023年9月4日・6日更新、9月7日若者男子の悩み推移、11月17日同左ハイティーンのみの図追加、2025年3月1日のん気度上昇についての男女の比較)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||