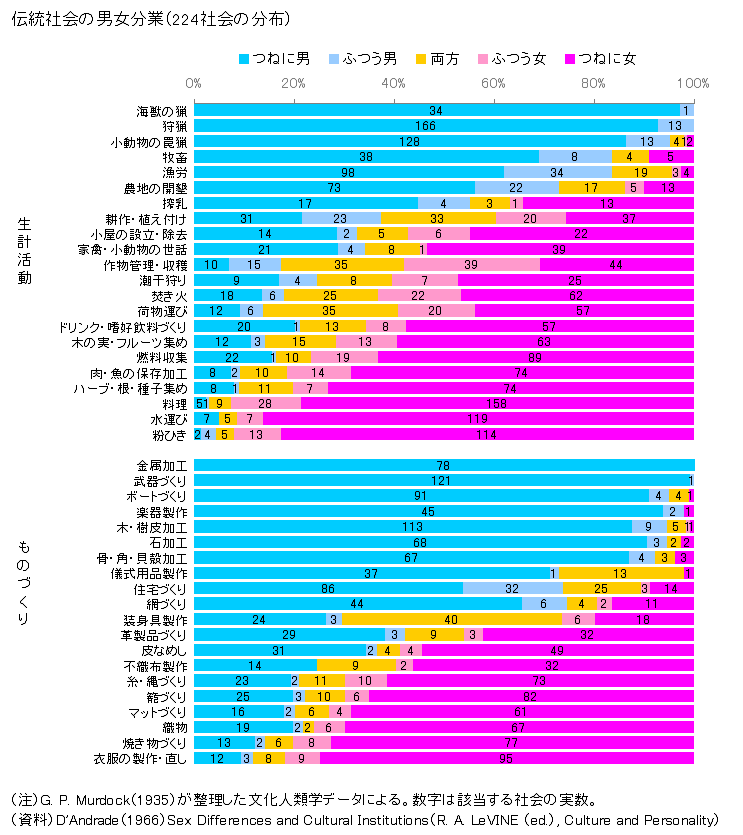
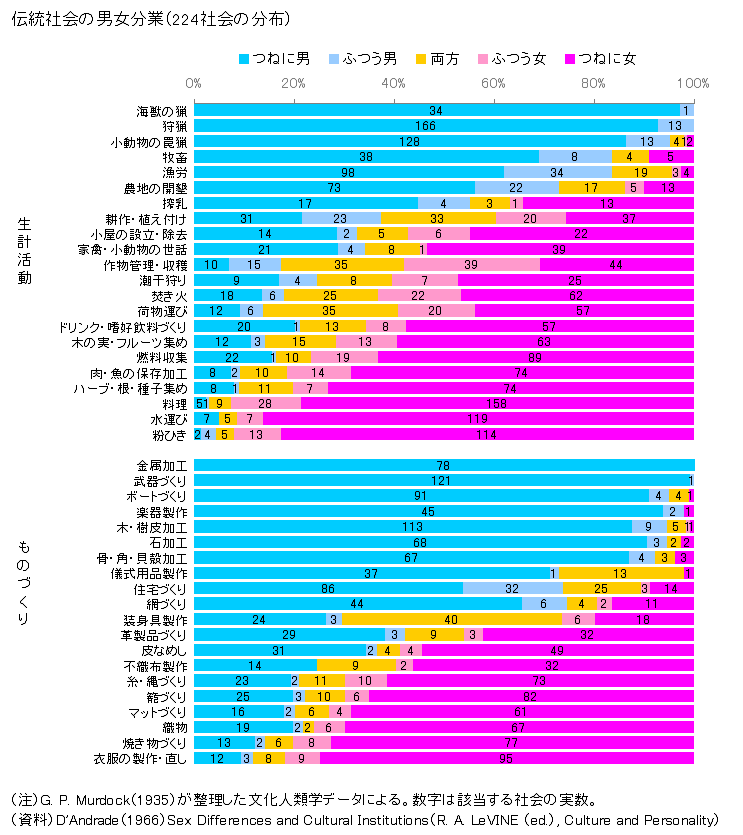
|
文化人類学者が広く集めた伝統社会(未開社会)の男女分業の分布を帯グラフで示した。ただし、数字は、該当する社会の数である(現代における職業別の男女比率については図録2705参照)。 まず、食料調達などの生計活動にせよ、ものづくりにせよ、作業の種類によって、男が中心のものと女が中心のものとに分かれていることが明確である。 どのような作業が男中心であり、どのような作業が女中心であるかについては、身体的な男女差にもとづく要因、および、それに起因する男女固有の作業のためのものづくりという間接的な要因の2つがあると考えられる。 身体的な男女差にもとづく分業については、男の活動が、①力を要する、②協働的である、③長期の旅程を要するものなりがちであるのに対して、女の活動は、①身体的に容易、②孤立的に可能、③移動的でないものとなりがちであるとされる(D'Andrade 1966)。 西田利貞(1999)は同じマードック・データについて、こうまとめている。「男の仕事は、高い移動性、瞬発力や筋力を要するだけでなく、部族の縄張に関する詳しい知識を要するような作業が多い。一方、女の仕事は食物採集を除いて、いずれも炉と赤ん坊の近くで実行できる。子育てとの両立可能性が最も重要な要素である。」(p.124) ものづくりについては、必ずしもこうした身体的差異が影響しないものが多いが、男女の分業がひろく成立している。これは、生計活動などで男固有、または女固有となった作業に関連するものづくりは、やはり男、または女の分担となるからだと考えられる。例えば、戦いは男の分担なので武器づくりも男が行い、片や、料理が女の分担なので焼き物づくりも女の仕事になるという訳である。従って、これは、身体的差異の間接的な影響の結果だともみなせる(同)。 進化的な観点からは、身体的な男女差が男女の分業を生んだという見方では充分ではないだろう。むしろ、男女の分業が身体的な差異に影響を与えるいう側面が無視できないからである。 授乳期間には動き回るのが容易でないメスが営巣地周辺で生活し、オスがメスの出来ない遠出作業を行うという分担が、男女分業のはじまりで、その後、営巣地周辺で採れるイモの加熱料理が食料革命を生み、それを担当したメスが調理品を奪われないよう、特定のオスを用心棒にしたことから家族がはじまったのではなかろうか(図録0207参照)。 狩猟が可能にした肉食で脳の大型化を実現するエネルギーを得たのがヒトがヒトになる要因とするダーウィン説は、狩猟採集民族のエネルギー源が採集植物を主としているという調査結果から説得力を持たないようになった。そうすると、男女の分業も、男の作業を女が補完したのではなく、女の作業を男が補完したという考え方に変わってくる。男の頑健な身体が時代遅れとなったのは、まず第1に、このイモ革命以降であり、現代の機械革命は、第2のステップだとも言えることになる。ゴリラ、オランウータン、チンパンジー、ヒトの体重性差(オス/メス)は、それぞれ、2.00、1.90、1.32、1.24である(西田1999、p.131)。技術進歩が性差を小さくしたのであろう。 図においては、採集を指す「ハーブ・根・種子集め」や「木の実・フルーツ集め」、及びそれを加工する「料理」に加えて、料理と関連する「焚き火」や「燃料収集」も女が担うことが多くなっている。栄養の根本は女性が牛耳っていたと考えられる。 狩猟採集時代をへて、農耕や畜産の時代に入ると、農耕においては、力の要る「農地の開墾」、「耕作・植え付け」までの前工程は男も役割を果たすが、後工程である「作物管理・収穫」、「粉ひき」などは女の担当となり、畜産に属する「牧畜」、「搾乳」は、狩猟採集時代からの習慣で遠出や動物知識が得意な男が主に担当ということになっている。 「水運び」や「料理(カマド作業)」が開発途上国の女性問題として関心をもたれている状況については図録1020、図録1022参照。現代の夫婦の家事分担の国際比較は図録2323参照。 女が担う料理
195文化を取り上げた1973年マードック論文の料理の分業についてふれたランガム(2009)は、男女がほぼ同等に料理をするか、男性が大部分の料理をする社会は、わずか4つであり、そのうち、1つは誤り、残る3つの社会は南太平洋(サモア諸島、マルケサス諸島、トラック諸島)にあったと述べている。そこでは、「女性がする家族のための料理と、男性がする共同体のための料理」を区別していた。主食の果実パンノキの料理は、親族の男たちによって女人禁制の建物で何日もかかかって共同で行われる。皮をむいて切り分け、大きな火と焚いて蒸し、汗まみれになって果肉を叩きつぶすと、どろどろになった果肉を葉に包んで完成。料理に不参加の男たちにも余った分を分け、「自宅に帰ったときには、料理したパンノキの果肉を妻に渡した。妻がそれに豚か魚のソースと野菜を加えて夕飯を作る。パンノキがないときには、タロイモの根など、ほかの澱粉質の食物を料理する。男性は気が向いたときに主食を料理するが、女性は責任をもってほかのあらゆる料理と家族の食事の世話をしていた」(p.148)つまり、料理の分業に関しては、男性が担当とされていても見かけ上の場合が多いと言える。従って、上のグラフで見る以上に、料理は女性の担当の性格が強いのである。 こうした伝統社会(未開社会)の傾向は、文明社会においても共通であり、例えば、英語の"lady"の語源は「パン生地をこねる人」、"lord"の語源は「パンを守る人」なのだという。 文明社会と同様に、伝統社会(未開社会)でも、男が料理をする社会があってもよさそうなのに、まず、そうした社会はないということは、女が料理をすることがヒトがヒトである根本にかかわることだと示しているようにも見える。料理が人類と結婚の起源とするランガム仮説はコラム参照。 台所が女性にとってかけがえのない場であり、嫁姑の問題も台所を共有する無理から生じていることを社会人類学者の中根千枝が指摘している。 「成人した女性にとって、台所はなによりも大切な自分の場です。とくに夫や子どもをもつ女性にとっては、欠くことのできない大切な場所です。そこには、その女性の好みとかシステムが刻印されているものです。こうした重要な場所を二人以上の女性が共有するということは、心理的にきわめて無理なことです。アフリカの多くの社会では、結婚しても、専用の台所が用意されていないと、新妻は怒って生家に帰ってしまうということです。インドでは、妻たちがけんかしたり、不和になったりすると、まず台所をわけることにしています。同じ家に住んでいても、台所をそれぞれの妻にわけると、まず問題は解決するようです」(中根千枝1977、p.133~134)。ここではアフリカの一夫多妻家族、インドの結婚したきょうだいが同居する大家族が想定されている。 料理から発して栄養管理も女性の役割となっている現代的な状況は、東京新聞コラム「つれあいにモノ申す」の以下の「専属栄養士」と題された記事(2024.3.15)からもうかがえる。 他人から見たら、お出掛けはいつも仲良く、おしどり夫婦。その実態は…食事療法が必要な後期高齢者と、その外食メニューに目を光らす専属栄養士です。(老老介護は嫌よ・72歳)
(参考文献) ・D'Andrade(1966)Sex Differences and Cultural Institutions(R. A. LeVINE (ed.), Culture and Personality: Contemporary Readings ・リチャード・ランガム(2009)「火の賜物―ヒトは料理で進化した」日本版、NTT出版、2010年 ・西田利貞(1999)「人間性はどこから来たか―サル学からのアプローチ」京都大学学術出版会 ・中根千枝(1977)「家族を中心とした人間関係」講談社学術文庫 (2013年11月19日・20日収録、2018年2月3日中根千枝引用、2024年3月15日「つれあいにモノ申す」引用)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||