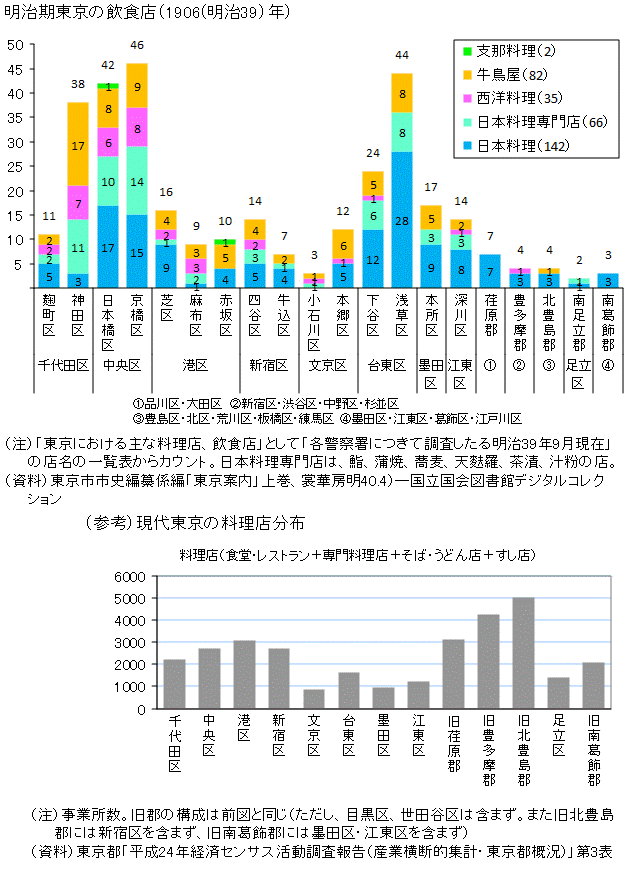
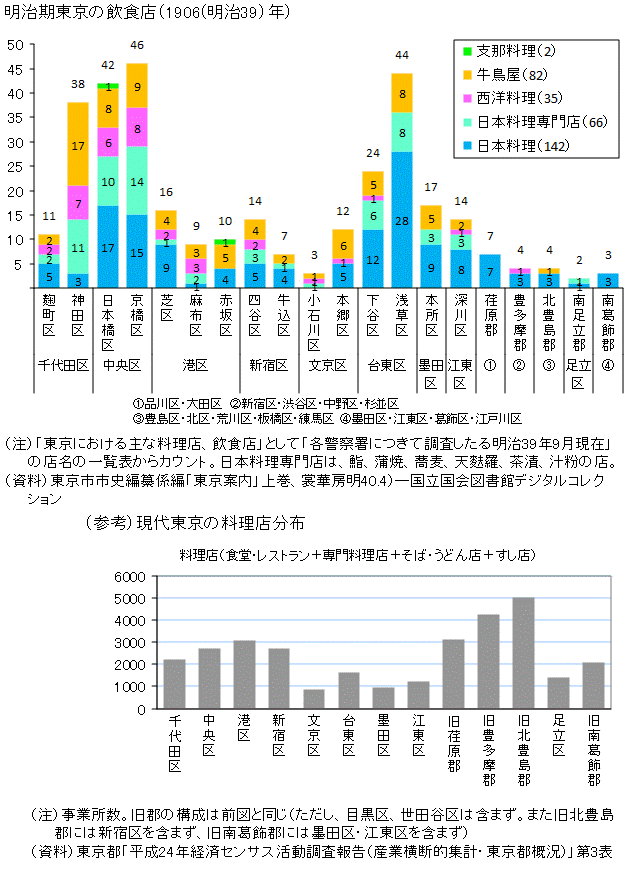
当初、データは下記の宮本常一の論考から引いたが、宮本が引いた原資料である東京市編「東京案内」を直接ネット上で見ることができる環境となったので(ここ)、宮本論考の誤りを正し(年次を明治30年頃から明治39年に訂正、及び支那料理店などのカウントを修正)、改めて掲載した。 料理店分布については、神田から日本橋、京橋にかけての一帯と浅草地域という2つの中心地をもっていたことが分かる。これは江戸時代からの立地分布を受け継いだものであろう。参考に掲げた現代の料理店分布と比べると、港区や新宿区、あるいは旧郡部に属していた新宿・池袋・渋谷・品川といったターミナル駅周辺や郊外住宅地など、その後の増加地域における料理店密度はなお低かったことがうかがえる。 また、明治期には西洋料理店は限られた存在だったことが分かる。 「西洋料理店も牛鳥屋も下町の中央部、神田、日本橋、京橋に集まっており、周辺に至るに従って少なくなる。大衆の町浅草には36の料理屋を見るが、西洋料理店は1軒もない。したがって西洋料理をたべる大衆と言っても、それはまだこの頃になっても一部の人々に限られていたことを知る」(宮本常一(1955)「近代の飲食と生活」(『宮本常一著作集 24 食生活雑考 西洋料理店のはじまりは横浜の西洋人相手の開陽亭(明治3〜4年)であった。ついで築地の外国人居留地のそばに精養軒ができて(明治6年)、明治9年には上野にその支店が設けられたという。「日本人の客は政府の要路者とハイカラ連に限られたという(『日本人の生活史』)」(宮本常一、上掲資料) なお、洋食が最初に普及してもおかしくなかった東京など大都市においても、米飯を主食とする食生活は根強く、そうした和食に適した新鮮な食材が大都市に集まるようになって、「洋食の素材となるような高価な蔬菜類の生産をいそいで促進せしめるほどのことはなかった」(上掲資料)。このため、本格的な西洋料理はなかなか一般化せず、カレーライスやオムレツ、カツレツといった単品料理系の洋食がむしろ大衆的に広がっていったとされる。 なお、図では牛鳥屋にカウントしたが、馬肉料理店としては、唯一、「馬肉、鳥」を出す小林支店(四谷区永住町17)が掲載されている。コラムにふれた馬肉飯と比べずっと上等な料理を出していたのであろう。また、支那料理店2店のうち、日本橋区の店は「偕楽園」(亀島町1ノ29)、もう1店は、赤坂区の「もみぢ」(田町3ノ13)である。 下には、料理店とはいえないような下等飲食店(飯屋、居酒屋)の明治期における状況を松原岩五郎「最暗黒の東京」(1893年)から引用した。下等料理店の所在地も上の料理店とかなり重なっていることが分かる。
検索が容易になるよう、図中の地域名を掲げておくと以下である。麹町区、神田区、日本橋区、京橋区、芝区、麻布区、赤坂区、四谷区、牛込区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所区、深川区、荏原郡、豊多摩郡、北豊島郡、南足立郡、南葛飾郡 (2015年8月8日収録、2021年4月26日【コラム】明治期の下等飲食店、4月28日「東京案内」を元に再掲載、2023年10月3日福翁自伝)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
|||||||||||||||||||