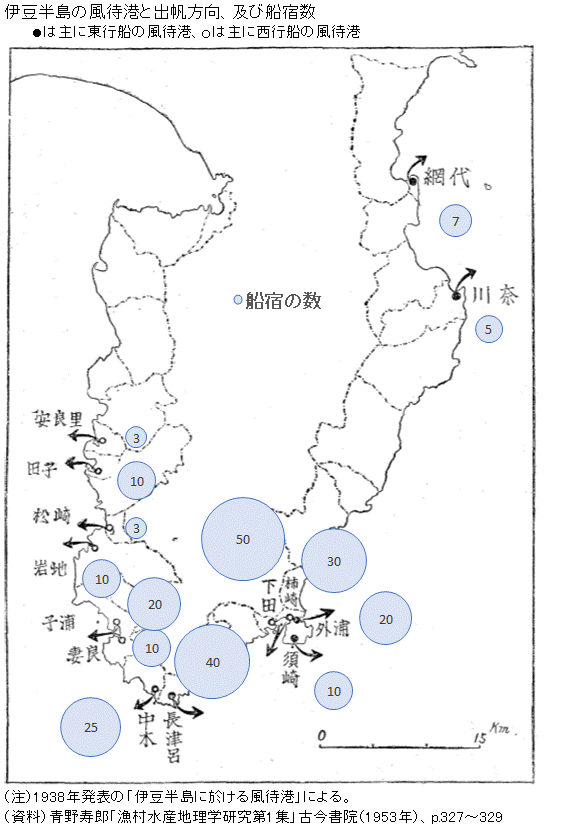
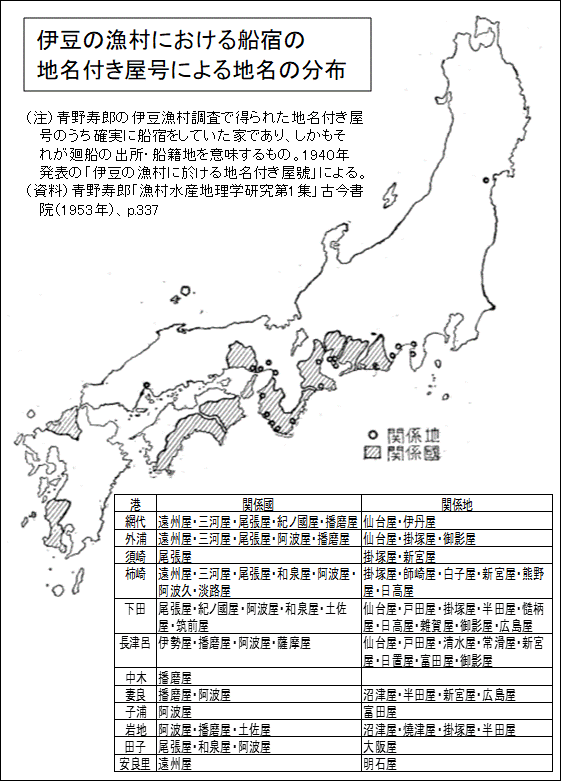
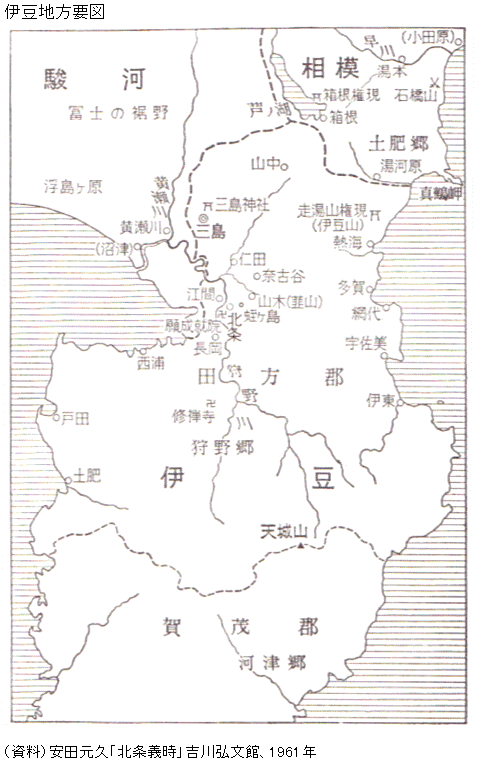
【クリックで図表選択】
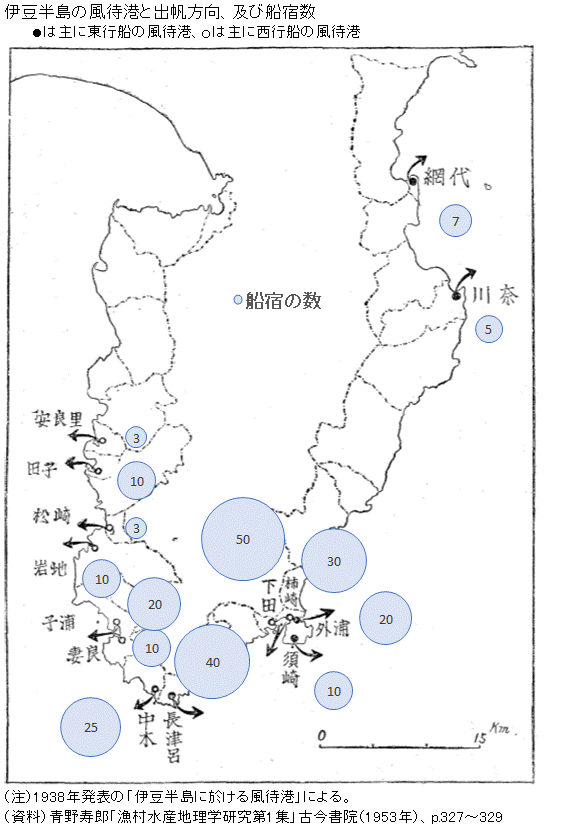 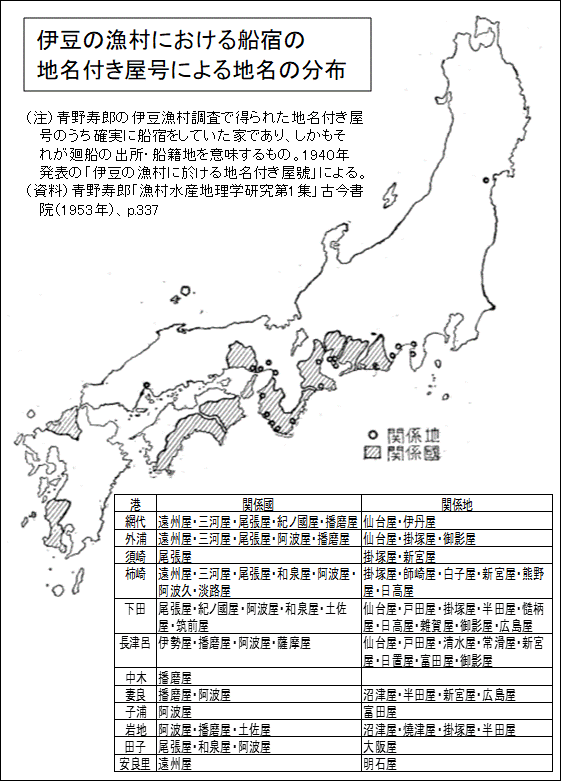 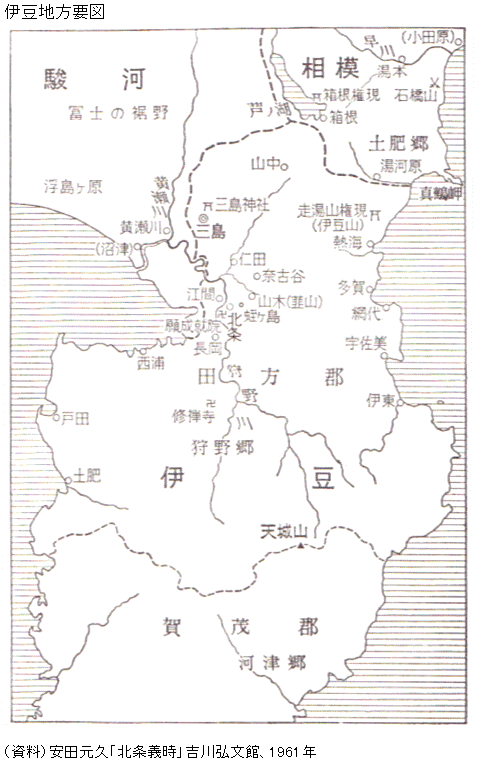
|
天城より北の田方郡を「口伊豆」、南の賀茂郡を「奥伊豆」と称する場合があるが、これは東海道筋から伊豆の温泉場を訪れる時の感覚である。伊豆、特に南伊豆が日本型帆船による東西物流の大動脈の中継地だった時代には、むしろ南伊豆が「表伊豆」、北伊豆が「裏伊豆」でもいうべき位置づけだったことは、房総半島で、「上総」が半島南部、「下総」が半島北部に位置していたのと同様である。 海運がさかんだった江戸時代から明治初年にかけて伊豆が半島だからこそ繁栄していた点を長期人口動向から図録7814及び図録7859で探ったが、ここでは、南伊豆の船宿数の分布などからその点を明らかにしよう。 伊豆半島沿岸の港は明治中期以前には関西、関東をむすぶ主要貨物運送路における風待ち港の役割を演じており、港湾関連の造船、船宿、遊興業、中継商業などの産業が集積し経済的に繁栄していた。 資料とした青野寿郎(1953)「漁村水産地理学研究第1集」(古今書院)は、こうした伊豆半島、特に南伊豆における繁栄の背景を以下のように記述している。 「周知の如く東海道の街道交通は人の往来が主で、馬背による貨物の輸送は比較的少なく、特に重量の大きなものや容積の嵩張るものは、輸送能力が極めて低かった。而して江戸=東京は消費人口の一大集団地であったので経済の中心大阪及び関西の各種生活必需品の生産地より多くの物資を仰がねばならなかった。それがため、必然的に海路がその輸送路として利用されたのである。現在においても陸上交通の不便な臨海地域では沿岸航路が重要な役割を演じている例は甚だ多いのである。而して当時の輸送機関の日本型帆船はその特徴として風向・風力に決定的に支配されたため風待港を必要とするに至ったものである。 関西・関東を結ぶ所謂南海路には、紀伊半島と伊豆半島との突出がある。そこで航路は当然この両半島を迂回せざるを得ない。紀伊半島沿岸のことは暫く措き、志摩半島より東京湾に至る間に突出するのが伊豆半島である。若しこの半島がなければ遠州の御前崎より三浦半島突端部まで直線的に航海することができるのである。従って伊豆半島の突出している自然性が風待港を存在せしめた1つの自然的条件となる。併し単に突出陸地があてもそこに何等の寄航に適する湾入海面が存しなければ勿論風待港はできない。然るに幸にも伊豆半島沿岸には好錨地が甚だ多い。従ってこの好錨地が帆船の寄航地となったのは極めて自然の成行と言わねばならない。又何等寄航地のない遠州灘50里の航海は当時の航海者にとり相当怖れられていたので、この半島の好錨地は一層心理的にも彼等に好感を持たれたようである。下田に番所が置かれた100余年間は、風の状況がいかによくとも寄航せざるを得なかったのであるが、その番所が浦賀へ移ってもこの心理は依然として続いたのである。又東行の場合鳥羽を出帆する際は西風を利用したのであるが、その風が東京湾口に達するまで続くとは限らないので一度途中で寄航し更に風の模様を見定めて出帆する必要があったことも伊豆沿岸に風待港を生ぜしめた1つの自然的条件である。西行の場合も亦同様で、一度東風を利用して出帆しても志摩半島に到着する前に西風に逢えば、仮令志摩・伊勢の山々を望み得る所まで航海していても又この半島に帰らねばならなかったと言うことであるから、風向・風力及びその継続時間等が当時の航海者の最大関心事であったのである。又仙台船が伊豆の風待港を利用したことは顕著な事実であるが、これは全く当時の船舶の運航が風のみを頼っていたことを物語るもので、外房沿岸を航しそのままの風を利用して伊豆東岸に至ることは極めて自然で、ここで更にこれと反対の風向である順風を待って東京湾口へ向け出帆したのである」(p.325〜326)。 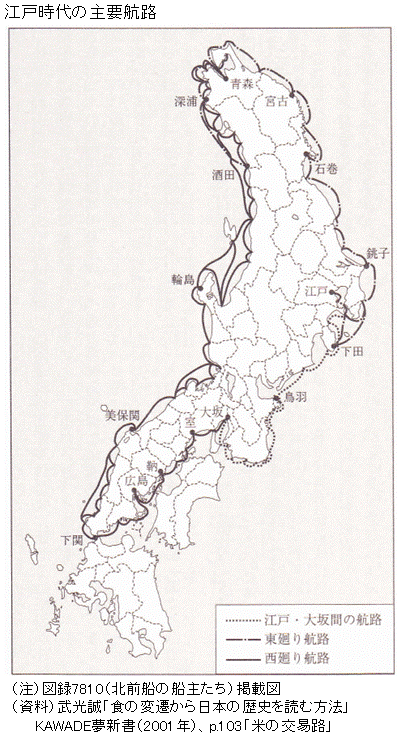 伊豆半島の風待港としての性格や仙台からの航路でも下田港が重要な役割を果たしていた点は上図からもうかがえる。下田は江戸・大坂間の航路の経由地であるとともに、東廻り航路も下田を経由することが多かった点が見て取れる。 表示選択の既定図である港・船宿分布図に見られる通り、港には主として東行船の風待港となっていた港と西行船の入った港があった。各港湾の外海への開口方向がこの区別を生じた。 青野寿郎(1953)が碇泊廻船数・船宿数・遊興機関の状況などから判断したところでは、「下田が最重要港で、柿崎これに次ぎ、以下子浦・長津呂・中木等が続き、総じて南海岸の諸港が有力で、此等の各地は港集落として栄えていた」(p.334)。なお、東海道線の開通などによる交通機関の進歩により風待港としての機能が失われると南海岸におけるこうした主要港が最も経済的打撃を受けたことが同論考では戸数の増減率から明らかにされている。 廻船の乗組員は1艘当たり平均12人ぐらいだったので碇泊廻船数から最多時の滞在乗務員数は柿崎2,160人、下田1,440人、子浦1,200人、網代840人などと計算されており、現地の人口よりも多い場合もあった。風の状況によれば碇泊日数も極端な場合には3カ月に及ぶこともあり、1カ月ぐらいの滞留はしばしばだったというから、それぞれの地にもたらした賑わいと経済的な利益は相当大きかった。 「船宿には普通大宿・小宿の別があり、大宿は船頭の宿、小宿は水夫の宿とされていたが、実際は現在の宿屋の役割をなしたというよりも彼等の休養所であり、飲食物の供給、貨物売買の仲継、病人の看病等あらゆることを世話したものである。又廻船の各港における船宿は一定し且つ船宿は船籍地の地名を屋号名としていたものが多かった」(p.329〜330)。 表示選択の2番目の地図にはこの屋号名から推察される廻船の出身地の分布を示した。「国名で最も普通なものは阿波屋・尾張屋・播磨屋・遠州屋で、反対に淡路屋・筑前屋・薩摩屋は共に1件宛しかない。(中略)関係地の全部が殆ど表日本に限られていることは裏日本の廻船が直接伊豆半島に廻送されなかったことを示すものと考えられる」(p.337)。仙台屋が網代、外浦、長津呂など東行船の港にあるのは上記引用に示された事情による。 青壮年の男子乗組員が長く滞在することから船着場には歓楽街も発達する。「唐人お吉」(注)で知られる下田だけでなく各港にも遊興機関が存在した。「各地に亙って調査するに、下田が最も多かったようであるが、網代・長津呂・中木・子浦及び妻良等にもあったようで、その他には専門的なものはなかったようである。現在の下田の特殊地域はその当時の名残りで、他では最早見られなくなった。遊興機関の程度も下田が第一位を占めていたことは明らかで、他の5港は大なる差異はなかったようである」(p.330)。 (注)愛知から下田に移住した舟大工市兵衛の娘斎藤きちは、船頭相手の洗濯女・酌婦をしていたが、安政4(1857)年下田奉行の命で玉泉寺に滞在中の米国駐日総領事ハリスの看護婦名目の侍妾(そばめ)となるが腫物を理由に3夜で解雇された。以後「唐人お吉」と差別され、不遇の晩年を送り、稲生沢川で投身自殺した。 今では鄙びた漁村と温泉保養地のイメージしかない網代のかつての賑わいを「網代村誌」はこう記載しているという。 「往時港には帆檣林立して黄金の波を漂はし巷には楼櫛比して嬌艶の春色を竝ぶ。此処に百貨輻輳して商買繁盛を極め彼処に人馬来往して市井殷賑を加ふ。里人傲語して曰「京・大阪に江戸・網代」と。猶俗謡あり「四国・西国巡りて見ても兎角網代は好い所」と。栄華の面影躍如として眼前に見るが如し」(p.331)。 ウィキペディアでも網代は、廻船滞在中に船荷を売るときはその斡旋の口銭があったほか、航海中に濡れて上納できなくなった「濡米」が流通し、活気に満ちた港町であったとある。 上で登場した各港が所属する現在の市町村は半島を右回りに記すと次の通り。熱海市(網代)、伊東市(川奈)、下田市(外浦、須崎、柿崎、下田)、南伊豆町(長津呂、中木、妻良、子浦)、松崎町(岩地、松崎)、西伊豆町(田子、安良里)。 (2022年12月9日収録、2023年9月5日江戸時代の航路図)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||