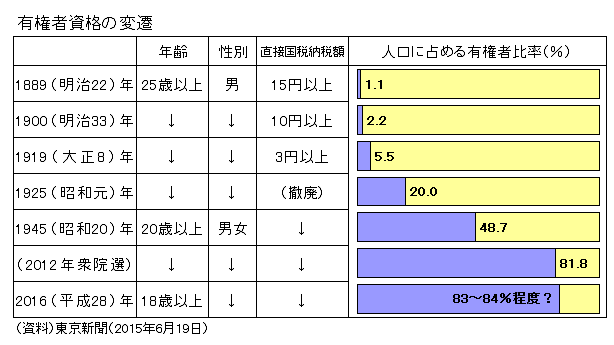
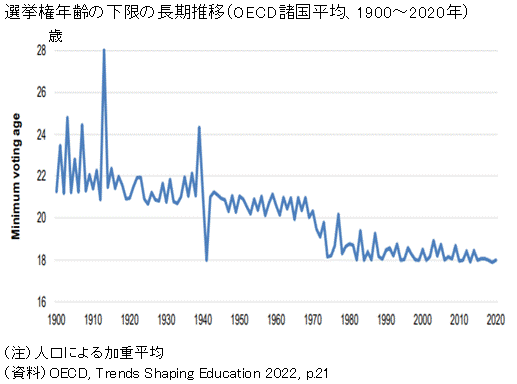
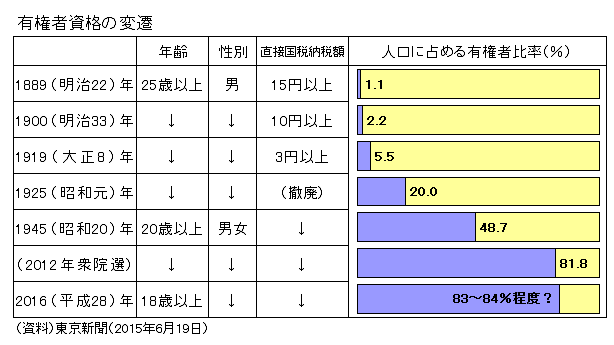
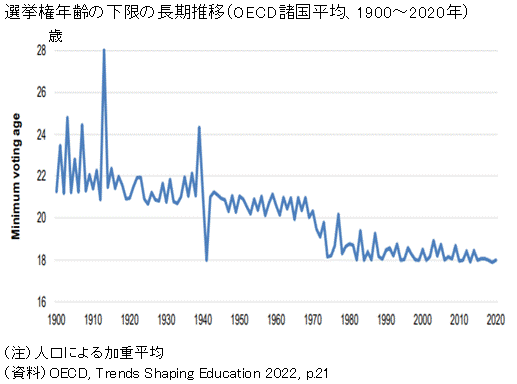
|
ここでは、わが国における男女、納税額、年齢の有権者資格の変遷をまとめた。参考にOECD諸国平均の下限年齢の長期推移図を掲げた。 選挙制度は旧憲法が発布された1889年に創設されたが、当初は、25歳以上、男性のみ、直接国税15円以上納税者に限定されており、人口に占める有権者比率は1.1%に過ぎなかった。 普通選挙運動が進み、納税額の制限は1925年に撤廃されたが、戦前はなお女性には選挙権が認められていなかった。 戦後の民主化で1945年に女性に選挙権が与えられたことで有権者は一気に拡大、人口の約半数を占めるに至った。当時はなお20歳未満の人口比が大きかったので有権者の対人口比率はそれほど高くなかったが、その後、人口ピラミッドは大きく変貌して、少子高齢化が進み、有権者の比率が8割以上となるとともに、有権者の高齢者比率も高まった。今回の法改正で18〜19歳人口が有権者に加わるとはいえ、該当人口じたいそれほど大きくないため、プラス約2%の増に止まる。 OECD諸国平均の選挙年齢下限の長期推移は、第二次世界大戦前は21〜23歳と20歳を超えていたが、戦後は20歳に近づき、1970年代には20歳レベルから18歳レベルに下がっている。ただ、下限は18歳で止まり、それ以上の若年化の動きは見られない。 表の通り、海外では選挙権年齢は、「18歳以上」が主流。「国立国会図書館の調査(2014年)では、197の国・地域のうち、8割以上が日本の衆院にあたる下院の選挙権を18歳以上としている。特に主要8か国(G8)では、日本以外の7か国が18歳以上と決めている」(読売新聞2014.12.1)。
このように世界的には18歳で選挙権を得る国が主流で、欧米は1970年代に18歳以上に引き下げた。すなわち、今回の選挙権年齢の引き下げは、世界の大勢に応じたかっこうの法改正であるが、直接的には、2014年に成立した改正国民投票法で憲法改正の国民投票ができる年齢を「2018年に18歳以上」にするとしたのを受けた措置である。国民投票法は選挙権年齢や民法の成人年齢の引き下げについて「速やかに検討」するとしていた。若い世代が加われば、自分たちに有利と考える野党に、憲法改正に道を開きたい与党・自民党が余り積極的にではなく譲って実現した引き下げであり、18〜19歳の学生層が積極的に運動して得られた成果ではない。今回の有権者資格の拡大は、これまでの普通選挙、女性参政権のように志の高い運動の結果ではない点が特徴といえよう。 選挙権と対になる被選挙権の年齢については、衆議院議員、都道府県・市区町村議員、市区町村長は25歳、参議院議員、都道府県知事は30歳である。下表の通り、これについても世界では日本より若い傾向にある。
なお、以下に選挙権年齢の引下げにともなって、実際に投票率がどう変化したかの事例をあげた。個々の選挙の事情が様々なので単純に比較できないが、概ね、投票率は下がっている場合が多い。これは若い層の方が投票率が低い傾向があるためだと考えられる(図録5230e参照)。 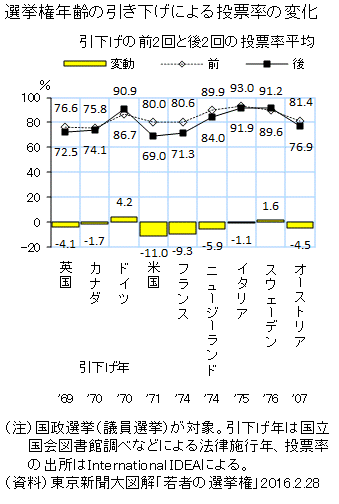 (2015年8月6日収録、2016年2月28日選挙権年齢引下げによる投票率変化の図、被選挙権年齢表の追加、2022年2月12日OECD平均の選挙年齢下限の長期推移、2025年1月5日2016年有権者比率算出)
[ 本図録と関連するコンテンツ ] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||